(岩内)
(ビクトリー1号)
(導入2号)
(ビクトリー1号牧草混)

土
良
肥
量
用
(3,058)
(3,058)
(5,427)
(4,045)
【普及参考事項】
|
岩見沢空知丘陵畑作地帯における有畜営農確立に関する経営試験 北海道中央農業試験場 |
Ⅰ.研究の目的と経過概要
1.研究の目的と意義
本研究の目的は、空知丘陵畑作地帯における有畜営農確立に関する研究の一環として行っているもので、本稿は昭和33年より昭和38年迄の6年間岩見沢市に設置した有畜営農試験地の試験成績を纏めたものである。
空知丘陵畑作地帯とは本道中央の南部に位置し石狩川を中央に挟み両側に展開する傾斜度5~10度を有する波状性緩傾斜地帯を称する。その大部分は重粘強酸性の不良土壌で各種作物の土地生産性が低く、穀菽経営が支配的であるが経済的に有利な作物がなく一般的に技術水準も低位で農業経営は停滞不振であった。叉一方昭和24年の旱害ならびに昭和29粘、31年の冷害により農家負債が累増し、この儘推移するならば本地帯の農か経済の窮迫は尚一層の度を加えるものと憂慮されていた。これらの問題を解決する手段として、土壌が重粘加過湿酸性土壌であるため有機物の投入を考慮し、有畜化による経営確立を企図し、営農試験地を設置したのである。
2.研究方法と経過概要
岩見沢営農試験地は岩見沢市街より東方薬4kmの孫別にあり、技術改善農家2戸で構成されている。この農家の剪定は、耕地規模4乃至6haを指標として本地区を代表し得る農家を現地指導機関と協議決定した。担当農家はいづれも穀菽経営が支配的であり且土地生産性も低かったが、耕土改良を施行し土地基盤を整備しつつ一方有畜化を推進し経営組織を展開発展せしめたのである。
本地帯の土性区は石狩北部段丘亜系に属し、その面積は農牧適地も含めて約5万haあり、空知、北竜、浦臼の3地区に区分され各地区は更に16の所属統に分けられているが、そのうち空知地区の桜山統は約5割と大半を占め、関係市町村は数カ所に及んでいる。岩見沢営農試験地の候補地はおこの桜山統地区に選定したものである。
Ⅱ 営農試験地における問題点と改善目標
1.営農試験地の問題点
(1) 土壌は酸性重粘土で且つ過湿な不良耕地であるにも拘わらず土地改良が進捗せず土壌改良に重要な意義をもつ堆廐肥の生産も少ない。
(2) 経営面積は比較的広いが、耕地率が低く、且つ穀菽経営が行われているが経営経済の基幹となるべき有利な作物がない。
(3) 農用地内に傾斜地、沢地などの未利用地が相当面積を占めているが、平坦で水利の便のある沢地が若干水田として利用されている程度で土地の合理的且集約的な利用がなされていない。
(4) 技術改善農家は穀菽経営より有蓄経営への組織転換に苦慮しており関係機関もこれを奨励しているが、これを実現すべき技術体系、経営形態については確たる見通しが得られず暗中模索の状態であった。
2.営農試験地の改善目標
(1) 経営形態は従来の穀菽経営をあらため有蓄経営とする。有蓄化への推進については、本営農試験地の設置当初は技術改善農家が穀菽経営が支配的であったとはいえ、乳牛を1頭宛飼育していたので有蓄化への組織転換を乳牛部門の拡大に求めた。しかし、これが実現に展開するとなると乳牛部門の強化に伴い主たる収入源であった穀菽作物を漸次減少し、飼料作物を作付けする訳であるが、乳牛部門からの収入を獲得するまで時間差が生ずる。この打開策として(A)農家は一時的に養鶏部門を併置し、乳牛部門の強化にともなって漸次養鶏規模を縮小する様に配慮した。叉(B)農家の有蓄化は本地域の耕地規模が概して狭少なのに鑑み、乳牛のみに現定せず、養豚部門をも兼営せしめた。
(2) 飼料基盤の強化を図るため、能うる限り草地化をすすめ且、地力の増進と労働の合理化を主眼とした輪作方式を策定し、土地利用の集約化を計る。
(3) 土地生産性の向上を計るため(イ)暗渠排水、(ロ)酸性矯正、(ハ)深耕・心土耕(トラクター)、(ニ)有機物の多施等の一連の土地改良を施行する。
(4) 草地化により、有蓄経営転換に伴う飼育管理労力をうみ出し、労働の合理化を計る。
Ⅲ 営農試験地における改善技術の施行経過
改善技術の実施事項は別に定めた基本計画に従って施行したが基幹的な改善技術の施行経過は大要次の通りである。
1.耕土改良基盤の確立
土地生産性向上対策としての耕土改良即ち、暗渠排水、酸性矯正、深耕、心土耕の実施状況を示すと、第1表の通りであり、土管による暗渠排水は、各農家とも耕地の9割内外を実施し、心土耕は(A)農家は8割強(B)農家は昭和32年以前をも含めて耕地を2.5回宛施行し、深耕は(A)農家は100%完了した。
叉、酸性矯正は各農家とも10a当石灰0.3tを2回に分けて投入した。
第1表 耕土改良の実施状況
| 項 目 | 昭和32 以前 |
昭33 | 昭34 | 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | 延面積 (差引実面積) |
耕地面積に 対する割合 |
|
| 暗渠排水 | (A)農家 | ha - |
0.45 | 3.2 | 0.9 | - | - | - | ha 4.55 |
% 88 |
| (B)農家 | - | 3.1 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | 4.90 | 94 | |
| 心土耕 | (A)農家 | ha 0.3 |
1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 4.4ha (2.8) |
86% (54%) |
| (B)農家 | 5.2 | - | - | - | - | 1.0 | 0.6 | 12.2 (4.9) |
242 (100) |
|
| 深 耕 | (A)農家 | - | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 5.5ha (4.4ha) |
100% (108%) |
| 酸性矯正 | (A)農家 | -ha (-t) |
7.7 (30.0) |
1.4 (1.4) |
0.95 (03.0) |
- | - | - | 10.05ha (39.0t) |
196% (10a当0.38t) |
| (B)農家 | - (-) |
5.3 (15.0) |
2.1 (12.0) |
1.7 (6.2) |
0.2 (0.4) |
- | 06. (0.9) |
9.9 (34.5t) |
195 (〃0.35t) |
|
2.有畜経営基盤の確立
有蓄かの推進については、飼料基盤の整備に伴い乳牛部門は漸次拡大され(A)農家は昭和33年は作乳牛1頭、育成牛2頭であったが、昭和38年には作乳牛10頭と試験開始年次と比較すると成牛換算で約8培増となった。叉(B)農家は昭和34年に家族の不慮の事故にあい労働力の不足をきたし乳牛を手放さざるを得ない状態となり、昭和35年より再出発したが昭和38年には作乳牛5頭、育成牛4頭となり2農家とも乳牛の飼養頭数は当初の計画を上回った。この乳牛頭数増加の方法は、自家増殖によらず出来うる限り成牛の購入による導入を基本とした。即ち、乳牛頭数の動態については第2表に示した。
尚(B)農家は昭和36年より繁殖豚♂1頭、♀5頭の導入を行い養豚部門の設置をみた(第2表)。叉(A)農家の養鶏部門は乳牛部門の拡大に伴い漸次減少せしめ昭和38年には自家用にとどめた。
養畜施設の整備については第3表に示す如く、両農家とも穀菽経営を行っていたので家畜導入にさいしての畜舎は納屋の内部を過剰投資にならぬ様配慮しつつ内部改修を行った。但し、(B)農家の豚舎は労働力の省略管理を考えて、デンマーク式豚舎96m21棟の新設をみた。
第2表 乳牛部門の動態(昭和35~38年)
| 項 目 | (A) 農 家 | (B) 農 家 | |||||||||||||||||||
| 33年 度始 |
導入 | 生産 | 売却 | 死亡 | 38年 度末 |
33年 度始 |
導入 | 生産 | 売却 | 死亡 | 38年 度末 |
||||||||||
|
1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | |||||||||
| - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | ||||||||||
| - | 1 | 11 | 6 | - | 3 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | ||||||||||
| 1 | 9 | 26 | 19 | 1 | 13 | 2 | 5 | 14 | 9 | - | 9 | ||||||||||
第3表 養畜施設の整備
| 項 目 | 昭 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| (A)農家 | 畜舎1棟 92.6m2 (納屋と兼用) 鶏舎1棟 33m2 |
同左 | 畜舎の内部改修 (成牛5収納) 同左 |
サイロ新設 1基 22t入 |
畜舎の内部改修 (成牛10収納) |
畜舎内部の改修 |
| (B)農家 | 畜舎1棟 79.3m2 (納屋と兼用) 尿溜 1基 サイロ 1基 (1.8×1.8m) |
同左 | 同左 | デンマーク式豚舎 1棟 69m2 サイロ 1基 6t入 尿溜 1基 |
畜舎の内部改修 (成牛 5収納) |
同左 |
Ⅳ 有畜経営の組織展開に関する考察
1.飼料基盤の整備に関する考察
(1) 耕土改良に関する考察
低位生産地における重粘強酸性土壌の改善技術対策は、原則的には土地生産性の(1)増進技術対策と(2)維持管理対策に二大別される。この地力増進技術対策は、物理的対策としての(イ)暗渠排水(ロ)深耕・心土耕と化学的対策としての(ハ)酸性矯正、(ニ)有機物多施が基幹技術と考えられる。これらの基幹技術について、既存のの資料を整理し、時間的要素を加え重粘強酸性土壌の改善技術の導入順序を考察し模式化すると、土壌の熟畑化の程度により3段階に分けられる。即ち、未風化のA段階では、排水、心土破砕等を行い、土壌の風化作用を促進し、同時に酸性矯正をも施行する。次いで、土壌容量が増加するに伴い次第に深耕を行い、有機物をも施用しB段階へと発展し、最終的にはC段階に至り、化学肥料を増肥し収量の増加を計るのである。かくすることによって、粘質且堅密な土壌のため、農機具に附着し、耕起の作業を困難にし、作土が土塊を作って整地、播種、施肥の一連の管理作業に多くの浪費を要していた土壌が次第に風化し、その結果耕種作業が容易になり且土壌容量が大きくなり、保水性も増大し作物の生育が良好となるのである。但し、固定費(暗渠排水・心土耕)はA段階よりB段階へと順次増額し、変動費(肥料費)は熟畑化の程度に応じて収量反応が異なるものである。
本営農試験地で施行した耕土改良は前記第1表の如くであり、輪作式は基本的には各農家とも、
| 燕麦-牧草-牧草-玉蜀黍 - 馬鈴薯 | ||||||||
| (牧草混) | デントコーン | 甜菜 | ||||||
| ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
| ( | 心土破砕 トラクター |
) | ( | 普通耕 堆肥・石灰 |
) | ( | 深耕・トラクター 堆肥 |
) |
第4表 (A)農家の土壌断面
| 年 次 | 昭32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| 作付順序 | 秋蒔菜種 (岩内) |
燕麦 (ビクトリー1号) |
甜菜 (導入2号) |
燕麦 (ビクトリー1号牧草混) |
牧草 | 牧草 | 牧草 | |
| 土壌断面 |  |
|||||||
| 耕 土 |
暗渠排水 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心土耕 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 改 良 |
深 耕 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 酸性矯正 | - | 石灰210㎏ | 石灰450㎏ | - | - | - | - | |
| 堆厩肥 | - | - | 3.0t | - | - | - | - | |
| 施 肥 量 |
N | 11.2㎏ | 4.0 | 9.6 | 3.5 | 1.6 | 3.1 | 3.1 |
| P2O5 | 4.3㎏ | 7.1 | 8.9 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
| K2O | -㎏ | 0.7 | 10.8 | 6.6 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 費 用 |
固定費 | -円 | 349 | 1,558 (3,058) |
1,558 (3,058) |
1,558 | 1,558 | 1,548 |
| 変動費 | 1,555円 | 803 | 2,369 | 987 | 592 | 820 | 820 | |
| 計 | 1,559円 | 1,152 | 3,927 (5,427) |
2,545 (4,045) |
2,144 | 2,378 | 2,368 | |
| 収 量 | 子実 78㎏ | 子実 232㎏ | 根 25t | 子実 300kg | 茎稈4.0t | 〃5.7t | 〃6.2t | |
第5表 耕土改良による理化学性の変化
| 層 序 |
耕土改良前(昭32) | 耕土改良後(昭38) | ||||||||||
| PH | 置換 酸度 |
置換性石灰 (mg/100) |
腐植 | 燐酸吸 収係数 |
PH | 置換 酸度 |
置換性石灰 (mg/100) |
腐植 | 燐酸吸 収係数 |
|||
| H2O | KCL | H2O | KCL | |||||||||
| 1 | 5.1 | 3.9 | 0.2 | 74 | 2.5 | 1,146 | 6.2 | 5.0 | 0.5 | 204 | 3.0 | 474 |
| 2 | 4.5 | 3.8 | 30.2 | 67 | 0.2 | 1,146 | 5.1 | 23.8 | 23.8 | 84 | 1.2 | - |
| 3 | 4.2 | 3.5 | 75.5 | 61 | 0.2 | 1,298 | 4.8 | 47.3 | 47.3 | 78 | 1.3 | - |
第6表 耕土三相分布成績
| 試 料 | 現地土壌重量 (g) | 容 積 量 (g) | 直 比 重 | 気 相 | 固 相 | 液 相 | 孔 隙 率 | |
| 耕土改良前 | 層序1 | 151.4 | 114.8 | 2.50 | 17.5 | 45.9 | 36.6 | 54.1 |
| 〃 2 | 166.1 | 134.3 | 2.60 | 16.5 | 51.6 | 31.9 | 48.4 | |
| 行動改良後 | 層序1 | 145.6 | 117.6 | 2.58 | 26.4 | 45.6 | 28.0 | 54.4 |
| 〃 2 | 136.6 | 108.4 | 2.60 | 30.1 | 41.7 | 28.2 | 58.3 | |
第7表 団粒分析成績(湿土:%)
| 試 料 | 2.0mm以上 | 2.0~1.0mm | 1.0~0.5mm | 0.5~0.25mm | 0.25~0.1mm | 計 | |
| 耕土改良前 | 層序1 | 12.27 | 10.59 | 7.17 | 10.04 | 4.50 | 44.57 |
| 〃 2 | 10.97 | 9.28 | 7.74 | 8.57 | 4.39 | 40.93 | |
| 耕土改良後 | 層序1 | 16.51 | 13.79 | 10.42 | 12.03 | 4.21 | 56.96 |
| 〃 2 | 14.53 | 12.36 | 11.97 | 11.88 | 4.52 | 55.26 | |
次ぎに、土地生産性について見ると、耕土改良の結果、土地基盤が確立し土地生産性の向上が認められた。
即ち、燕麦、玉蜀黍、馬鈴薯について土地生産性を見ると第8表の如く、燕麦の圃場は暗渠排水を昭和34年、心土耕は35、36年深耕は昭和33年に実施し、有機物は前作甜菜に堆肥を約3t施用し、その結果燕麦は昭和33年に比較し昭和36年は55%増の9.0俵となった。叉玉蜀黍の圃場は暗渠排水を昭和35年、心土耕は31年、深耕は36年に実施し且牧草跡地を利用し玉蜀黍40%増の7.0俵となり、馬鈴薯の圃場は暗渠排水を昭和34年、心土耕は27、32年に実施し有機物は堆肥を昭和33年に対し約30%増の2.5tを投入し、馬鈴薯は40%の49.0俵となった。以上の如く各作物は暗渠排水を基幹とする一連の耕土改良技術の滲透による増収が認められている。
第8表 主要作物の収量(10a当)
| 項 目 | 燕 麦 | 玉 蜀 黍 | 馬 鈴 薯 | |||||||
| 昭 33 | 昭 36 | 昭 33 | 昭 36 | 昭 33 | 昭 36 | |||||
| 収 量 (比率) |
5.8俵 (100%) |
9.0俵 (155) |
5.0俵 (100%) |
7.0俵 (140) |
35.0俵 (100%) |
49.0俵 (140) |
||||
| 耕 種 技 術 |
暗渠排水 | - | ○昭34 | - | ○昭35 | - | ○昭34 | |||
| 心土耕 | ○昭33 | 昭35 ○〃36 |
- | ○昭31 | ○昭30 | 昭27 ○〃32 |
||||
| 深 耕 | - | 昭33 | - | 昭36 | - | - | ||||
| 品 種 | ビクトリー1号 | ビクトリー1号 | 在来種 | 複文5号 | 農林1号 | 農林1号 | ||||
| 播種量 | 8.0㎏ | 7.5㎏ | 3.5㎏ | 3.9㎏ | 170㎏ | 170㎏ | ||||
| 栽植密度 | 45×-㎝ | 45×- | 85×45㎝ | 66×30 | 75×20㎝ | 72×20 | ||||
| 施 肥 量 |
堆 肥 | 1,875㎏ | 前作甜菜に 堆肥施用 |
1,500㎏ | (牧草跡地) | 1,900㎏ | 2,500㎏ | |||
| 要 素 量 |
N | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | |||
| P2O5 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 10.5 | 12.3 | 9.9 | ||||
| K2O | 4.4 | 5.9 | 2.0 | 5.4 | 10.1 | 8.1 | ||||
| 病中害防除 | - | - | ハリガネムシ 防除 |
〃 | オオニジウヤ ホシテントウ ムシ、疫病 |
〃 〃 |
||||
| 生 育 期 間 |
播種期 | 5月9日 | 5月3日 | 5月11日 | 5月11日 | 5月4日 | 5月3日 | |||
| 収穫期 | 8月4日 | 8月1日 | 10月29日 | 10月13日 | 9月12日 | 9月15日 | ||||
| 育成日数 | 88日 | 91日 | 176日 | 160日 | 132日 | 132日 | ||||
| 積算温度 | 1,441.2C | 1,524.3 | 2,851.8 | 2,784.2 | 2,241.8 | 2,455.2 | ||||
| 降水量 | 366.4㎜ | 480.7 | 685.4 | 761.5 | 534.4 | 621.3 | ||||
第8表の耕種管理のうち、耕土改良(固定費)と投入肥料(変動費)に要した費用のみを整理すると、第9表の如く、耕土改良の結果は、固定費の増加により耕地単位当り投下資本の集約化が認められる。この資本集約化により土地生産性は認められはするが、部令書の如く変動費である肥料費が減少しても尚収量が増加する理由は、変動費は、固定費の大きさに応じて収量反応が異なる為めであろうと推論する。この耕土改良費と肥料費ならびに収量とに関する課題は、別途研究する予定である。
第9表 耕土改良費と肥料費(10a)
| 項 目 | 燕 麦 | 玉 蜀 黍 | 馬 鈴 薯 | |||
| 昭35 | 昭36 | 昭33 | 昭36 | 昭33 | 昭36 | |
| 固 定 費 | 1,217円 (60.8%) |
2,547 (71.2) |
750 (42.1) |
2,080 (52.0) |
1,230 (28.6) |
2,590 (56.7) |
| 変 動 費 | 832 (39.2) |
958 (28.8) |
1,029 (57.9) |
1,923 (48.0) |
2,923 (71.4) |
1,928 (43.3) |
| 計 | 2,049 (100.0) |
3,505 (100.0) |
1,779 (100.0) |
4,003 (100.0) |
4,156 (100.0) |
4,518 (100.0) |
| 土地生産性 | 5.8俵 (100%) |
90. (115) |
5.0 (100) |
7.0 (140) |
35.0 (100%) |
49.0 (140) |
耕土改良に要した投入総額は有機物を除き(A)農家は76.5万円、(B)農家は84.5万円で、その内訳は第10表に示す如く、暗渠排水が全体の6割を占めている。叉10a当耕土改良費は1.6~1.7万円であり、原価償却費を定額法で求めると年間経費は(A)農家が1,442円、(B)農家が1,158円となった。
第10表 耕土改良費(昭和33~昭38)
| 項 目 | (A)農家 | (B)農家 |
| 暗 渠 排 水 | 520,975円 (68.1%) | 561,050円 (66.3%) |
| 心 土 耕 | 61,600 (8.0) | 170,800 (20.0) |
| 深 耕 | 54,000 (7.1) | - (-) |
| 酸 性 矯 正 | 128,700 (16.8) | 113,850 (13.5) |
| 計 | 765,275 (100.0) | 845,700 (100.0) |
| 耕土改良面積 10a当耕土改良費 |
4.55ha 16,819円 |
4.90 17,252 |
| 10a当年間経費 | 1,442円 | 1,158 |
(2)作付体系の整備に関する考察
第11表 耕地面積(昭38)
| 項 目 | 所有地面積 (ha) |
耕 地 | 耕地率 (%) |
畑作率 (%) |
||
| 畑(ha) | 水田(ha) | 計(ha) | ||||
| (A)農家 | 9.20 | 4.10 | 0.60 | 4.70 | 51.2 | 87.2 |
| (B)農家 | 5.90 | 4.75 | 0.30 | 5.05 | 85.6 | 94.1 |
所有地面積は(A)農家は9.2ha、(B)農家は5.9haでそのうち耕地は(A)農家は耕地率51.2%の4.7ha、(B)農家は85.6%の5.05haである。経営試験の開始に当りmqあず、土地利用の検討を行い、各農家とも1区60aとし5年輪作方式とした輪作区を設置し、圃場の生理を行った。作付状況について試験開始の昭和33年と圃場整理後の昭和38年とを対比すると、作付作物数は第12表の如く、(A)農家は昭和33年は12作物12筆であったが、昭和38年は4作物8筆に整理し、(B)農家は調査圃場が0.5㎞多くなっているが、14作物21筆が6作物11筆へと整理した。この結果1筆面積も(A)農家は32aから40%増の46a、(B)農家は16aから120%増の35aと各々拡大され、叉作付面積規模も1筆面積以20a以下の比率が昭和33年には(A)農家は4割、(B)農家は8割を占めていたが、(A)農家は40~60aが6割、(B)農家は20~40aが5割40~60aが3割へと拡大し、その1筆面積規模の構成に変化をもたらした。
叉、圃場の作付を整理し、且飼料作物の如き労働の粗放な作物の作付を拡大するにともない、畑作部内に投下された耕種管理労働は減少した。即ち(A)農家は3,258時間より72%減の919時間、(B)農家は2,744時間から31%減の1,901時間へと減少し、且10a当耕種管理労働時間も併せて減少の傾向をとり、特に(A)農家は減少が著しく、昭和33年の10a当56.6時間に対して61%減の22.4時間となり、(B)農家は極端な減少は認められなかったが40時間となった。(第13表)
第12表 作付面積規模
| 項 目 | (A) 農家 | (B) 農家 | ||||||||
| 昭33 | 昭38 | 昭33 | 昭38 | |||||||
| 調査圃場面積 (ha) | 3.84 | 3.70 | 3.35 | 3.80 | ||||||
| 分 散 数 (筆) | 12 | 8 | 21 | 11 | ||||||
| 1 筆 面 積 (a) | 32 | 46 | 16 | 35 | ||||||
|
41.7 | 12.5 | 81.0 | 18.2 | ||||||
| 25.0 | 25.0 | 9.5 | 54.5 | |||||||
| 33.3 | 62.5 | 9.5 | 27.3 | |||||||
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
第13表 畑作部門耕種管理投下労働
| 項 目 | (A) 農家 | (B) 農家 | ||
| 昭33 | 昭38 | 昭33 | 昭38 | |
| 耕種管理労働 (時間) | 3,258.7 (100%) |
919.5 (28.2) |
2,744.5 (100) |
1,903.5 (69.3) |
| 10a当〃 (時間) | 56.6 (100%) |
22.4 (39.6) |
47.5 (100) |
40.0 (84.2) |
作付体系の整備に伴い、畑作部門の作付構成を示すと、第14表の如くである。牧草も含めた飼料作物の作付率をみると昭和38年には(A)農家は95.1%、(B)農家は68.5%を占めるに至った。叉、飼料作物の総生産量をみると、第15表の如く、牧草は昭和33年に対比し昭和38年は(A)農家は12.2tの約10倍の130.2t、(B)農家は28.7tの約3.3培の96.3tと増大し、デントコーンも叉、(A)農家11.3tの約38倍の44.0t、(B)農家は180tの約2.2倍の40.0tが生産されるようになった。これは、飼料面積の拡大、且単位当り収量の増加に伴う総生産量の増大であり、この結果飼料基盤の確立が認められ、有畜化が推進されたのである。
第14表 畑作部内作付構成(%)
| 種類/農家番号 | (A)農家 | (B)農家 | ||
| 昭33 | 38 | 昭33 | 38 | |
| 燕 麦 | 16.3 | - | 15.4 | 12.6 |
| 麦 類 | 5.4 | - | 2.2 | 21 |
| 玉 蜀 黍 | 9.0 | - | 2.2 | - |
| 豆 類 | 18.8 | - | 18.7 | - |
| 亜 麻 | 12.6 | - | 13.2 | 6.3 |
| 秋 蒔 菜 種 | 7.3 | - | 6.6 | - |
| 甜 菜 | 3.6 | - | 2.2 | - |
| 馬 鈴 薯 | 3.6 | - | 5.5 | 12.6 |
| 牧 草 | 8.4 | 51.3 | 19.8 | 36.9 |
| デントコーン | 5.4 | 26.8 | 6.6 | 16.9 |
| その他飼料作物 | 5.4 | 17.0 | 3.3 | 2.1 |
| 蔬菜その他 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 10.5 |
| 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 牧草及飼料作物 | 19.2 | 95.1 | 29.7 | 68.5 |
第15表 飼料作物の総生産量と面積
| 項 目 | (A)農家 | (B)農家 | |||
| 昭33 | 38 | 昭33 | 38 | ||
| 牧 草 | 総生産量 (比率) |
12.2t (100%) |
130.2 (1067) |
28.7 (100) |
96.3 (335) |
| 面積 (比率) |
47t (100%) |
210 (446) |
90 (100) |
175 (194) |
|
| 10a当収量 | 2.6t | 6.2 | 3.2 | 5.5 | |
| デントコーン | 総生産量 (比率) |
11.3t (100%) |
44.0 (389) |
18.0 (100) |
40.0 (222) |
| 面積 (比率) |
30a (100%) |
110 (366) |
30 (100) |
80 (266) |
|
| 10a当収量 | 3.8t | 4.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 馬 鈴 薯 | 総生産量 (比率) |
30.0 (100.0%) |
- (-) |
88.0 (100) |
300.0 (340) |
| 面積 (比率) |
20a (100%) |
- (-) |
25 (100) |
60 (240) |
|
| 10a当収量 | 15.0 | - | 35.0 | 50.0 | |
2.有畜化組織展開に関する考察
(1) 乳牛部門展開に関する考察
酪農経営における多頭飼育の優位性は、土地、資本、労働を経済的に有効に利用するということであるが、自給飼料作物の比重を高めようとする飼養形態では経営規模に限界があり、それをさらに発展しようとすると外延的拡大、即ち共同化への方向をとらざるを得なくなる。しかし、個別経営において多頭飼育の方向で内延的拡大を求めるならば飼料を外部より購入し自給率を低めざるを得なくなるが、この傾向は年近郊での搾乳専営に多い。本営農試験地の(A)農家は後者の立場から考察したものである。
(A)農家の乳牛の年次別動態は、昭和33年に対比し昭和38年の年度末では家畜単位で11.5頭と約7.6倍である。乳牛1頭当りの飼料給与量を示すと第16表の如くであり、試験開始当初は、FU、DTPいずれも、基準量よりも給与量が多い傾向であったが、昭和36年以降はほぼ均衡が保持される様になった。この飼料給与量のうち、自給に要した乳牛1頭当りの飼料面積をみると第17表の如く、昭和33年の143aに対し38年は23a(83.8%減)で頭数増加にともない、第1図に示す如く、1頭当りの作付面積が減少の傾向をとる。これは耕土改良の結果土地生産性が向上したことにもよるが、耕地規模が4haと北海道の畑作地帯としてはあまり大きくなく、とくに都市近郊(市乳圏内)にあるため多頭化に伴って飼料の自給率が昭和33年に対比し昭和38年にはFUは90.4%が58.3%、DTPは78.3%が26.8%と低下したことによるのである。
第16表 乳牛1頭当飼料給与量((A)農家、搾乳牛)
| 種類/年次 | 昭33 | 昭38 | |
| 飼料名 | 配合飼料 | 532㎏ | 1,000 |
| 燕 麦 | 1,038 | 12 | |
| 麩 | - | 11 | |
| 玉蜀黍 | 1,356 | - | |
| 大 豆 | 140 | - | |
| 大豆粕 | - | 14 | |
| ビートパルプ | - | 96 | |
| 牧草(生) | 4,035 | 5,520 | |
| 〃 (乾) | 443 | 330 | |
| デントコーン | 4,590 | 1,220 | |
| 家畜根葉類 | 1,122 | 217 | |
| 甜菜茎葉 | - | 518 | |
| サイレージ | 2,822 | 2,215 | |
| 茎稈類 | 1,190 | 1,164 | |
| 野草(生) | - | - | |
| 〃 (乾) | - | - | |
| FU | 基準量(A) | 2,856 | 2,853 |
| 給与量(B) | 5,925 | 2,963 | |
| 差引(A-B) | (+)3,069 | (+)110 | |
| 自給率 | 90.4% | 58.3 | |
| DTP | 基準量(A) | 302㎏ | 314 |
| 給与量(B) | 458㎏ | 334 | |
| 差引(A-B) | (+)156㎏ | (+)20 | |
| 自給率 | 78.3% | 26.8 | |
第17表 乳牛1頭当自給飼料面積((A)農家、搾乳牛)
| 種類 / 年次 | 昭33 | 昭38 | |||
| 濃厚飼料 | 燕 麦 | 49a | (31.4)% | 1 | (4.3) |
| 大 豆 | 8 | (5.5( | - | - | |
| 玉蜀黍 | 45 | (13.4) | - | - | |
| 小 計</TD> | 102 | (71.3) | 1 | (4.3) | |
| 粗飼料 | 牧 草 | 20 | (13.3) | 11 | (48.2) |
| デントコーン | 13 | (9.8) | 10 | (43.2) | |
| 家畜根菜類 | 8 | (5.6) | 1 | (4.3) | |
| 甜菜茎葉 | - | - | (13) | - | |
| 茎稈類 | (45) | - | (45) | - | |
| 小 計 | 41 | (28.7) | 22 | (95.7) | |
| 合 計 | 143 | (100.0) | 23 | (100.0) | |

第1図 乳牛飼養頭数と飼料面積
更に多頭化の一手段である自給率の低下の問題について検討をする。
即ち、成牛体重550㎏の粗飼料を日量標準夏基幹は牧草(生)65㎏、牧草(乾)2㎏、(乾物量14.7㎏、Fu13.8、DTP13.8㎏)、冬期間は牧草(乾)8㎏、サイレージ25㎏、根菜類20㎏(乾物量15.8㎏、Fu7.7、DTP0.50㎏)を給与すると土地生産性が牧草、デントコーンが4~5tの段階では、1頭当り必要面積が65aとなり試算の結果6.2頭しか飼養できないことになる。この場合成牛1頭当りの粗収益を約12~14万円としても約80万円前後である。そしてさらに経営規模拡大を計画するときには土地生産性の増大に期待することとなるが、牧草およびデントコーンの昭和33~37年の過去5ヶ年の実績を基礎とした単純予測とした収量の回帰線を求める。
牧草 y'=0.57+0.83x (単位:t、x:年次)
デントコーン y'=3.66+0.06x
となり、牧草の10a当り8tの生産量をあげるのは昭和41年頃となり、デントコーンは約4tが限界となる。このようにデントコーンの生産性の増加があまり期待できないとすれば、牧草単一の土地利用方式に変更する必要性が生じる。
耕地の4haの飼料作物部門の投下労働量での試算では第18表に示す如く、牧草(2ha)デントコーン(1ha)、根菜類(1ha)の作付に要する総労働量は1,250時間であるが、全面牧草方式は600時間であって約1/2量に減少する。叉、投入肥料費も尿散布の実施によってかなり節減する可能性をもっている。
第18表 4.0haにおける乳牛基礎飼料代替試
| 項 目 | 土地利用法 | 畑作投下労働 | 肥 料 費 | ||||||
| 試算(1) | 〃(2) | 〃(3) | 試算(1) | 〃(2) | 〃(3) | 試算(1) | 〃(2) | 〃(3) | |
| 牧 草 | ha 2.0 |
3.0 |
4.0 |
時間 300 |
時間 450 |
時間 600 |
円 15,100 |
円 22,650 |
円 30,200 |
| デントコーン | 1.0 | - | - | 450 | - | - | 8,850 | - | - |
| 根 菜 類 | 1.0 | 1.0 | - | 500 | 500 | - | 8,330 | 8,330 | - |
| 計 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1,250 (100%) |
950 (76) |
600 (48) |
32,280 (100) |
30,980 (96) |
30,200 (94) |
乳牛の飼料構造は、維持飼料(a)と生産飼料(b)よりなり、この給与量飼料の養分自給率を常に100%にすると、搾乳日数の経過と共に搾乳量が減じ(b)も次第に減少の傾向をとる。
(A)農家のように、穀菽経営より酪農経営へと組織転換を行う場合、経営体としてある大きさの乳牛規模を必要とするこの必要規模に達する手段としては、土地生産性を高めることには意義があるが、自給率をも高めなければならないということには疑問が生ずる。即ち、乳牛規模の拡大対策の一つとして維持飼料を乾燥10㎏(Fu4.0、DTP413g)配合飼料は牛乳3㎏(脂肪率3.25%、Fu1.0、DTP140g)に対し約1㎏の割合で給与するときには、この(A)農家のように耕地4haといえども試算によると12頭の飼育が可能となり、実績でも自給率の低下により昭和38年は搾乳牛10頭、育成牛3頭、家畜換算計11.5頭の飼育を行い搾乳量も41.3tの生産が認められたのである。(第19表)
第19表 産乳量((A)農家)
| 項 目 | 昭33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 総 量 (比 率) |
4,200.0㎏ (100%) |
3,739.3 (89) |
8,686.5 (207) |
14,460.0 (345) |
22,477.5 (533) |
41,345.0 (985) |
| 年間搾乳述べ日数 (頭 数) |
366日 (1.2頭) |
219 (1.0) |
915 (3.1) |
1,109 (3.8) |
1,738 (5.8) |
2,213 (7.4) |
| 1頭1日当産乳量 | 11.5㎏ | 12.8 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 18.6 |
2.養豚部門導入に関する考察
有畜化への促進を計る為、(B)農家は昭和36年より養豚部門の新設をみた。豚舎はデンマーク式豚舎を採用し、同年6月に1棟69m2(総工事費42万円)を設置した。
豚頭数の動態を整理すると第20表の如くなる。併し(B)農家の豚舎はデンマーク方式を採用し1豚房約10m2で6豚房あるが、繁殖豚による仔豚生産を経営方針とするときその基礎豚数と豚房数の決定には理論的根拠がない。今、繁殖豚と豚房数の関係について図面上で検討の結果は次式に求めることが出来た。即ち、
(イ)繁殖豚数より豚房数を決定する式
(N/2+n)=x (n:繁殖豚数)
(ロ)豚房数より繁殖豚数を決定する式
(2/3x=n) (x:豚房数)
上記の(ロ)の式より(B)農家の場合はxが6であるので、nが4即ち繁殖豚4頭が最適であると推定した。
第20表 養豚部門の動態 ((B)農家)
| 項 目 | 年度始 | 生産 | 売却 | 死亡 | 年度末 | ||||||||
| 昭36 |
|
- | (1) | - | - | 1 | |||||||
| - | (5) | - | - | 5 | |||||||||
| - | (16) | 6 | - | 10 | |||||||||
| 計 | - | (22) | 6 | - | 16 | ||||||||
| 昭37 |
|
1 | - | 1 | - | - | |||||||
| 5 | - | - | - | 5 | |||||||||
| 10 | 68 | 27 | 2 | 49 | |||||||||
| 計 | 16 | 68 | 28 | 2 | 54 | ||||||||
| 昭38 |
|
0 | 1 | - | - | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 2 | - | 6 | |||||||||
| 54 | - | 68 | 23 | 31 | |||||||||
| 計 | 54 | 2 | 70 | 23 | 38 | ||||||||
繁殖豚および肥育豚の1頭当りの飼料給与量の実績を示すと第21表の如くであり、自給率は乾物量で繁殖豚39.8%、肥育豚で45.3%であった。叉自給作物は牧草、馬鈴薯、家畜南瓜で繁殖豚は7a、肥育豚は3aを必要とした。
第21表 繁殖豚と肥育豚の1頭当給与量 ((B)農家:昭37)
| 飼料名 | 繁殖豚(365日) | 肥育豚(227日) | ||||
| 給与量 | Fu | DTP | 給与量 | Fu | DTP | |
| 配合飼料 | ㎏ 499.0 |
453.6 |
㎏ 64.0 |
㎏ 128.2 |
116.5 |
㎏ 16.4 |
| 小 米 | 10.2 | 10.2 | 0.6 | 8.0 | 8.0 | 0.5 |
| 馬鈴薯 | 333.0 | 74.0 | 1.9 | 240.0 | 53.3 | 1.3 |
| 南 瓜 | 177.0 | 18.2 | 1.5 | 165.4 | 17.1 | 1.5 |
| 澱粉粕 | 1,090.0 | 72.7 | 1.1 | 120.0 | 8.0 | 0.1 |
| サイレージ | 573.2 | 249.2 | 5.0 | 356.8 | 155.1 | 3.1 |
| 牧草(生) | 263.0 | 37.6 | 4.5 | 27.8 | 4.0 | 0.5 |
| 母 乳 | - | - | - | (400.0) | - | - |
| 合 計 | - | 915.5 | 78.6 | - | 362.2 | 23.4 |
叉、肥育豚の生体重をも昭和36年に調査した。飼育管理は標準的な6ヶ月肥育を計画したが7ヶ月間を要し肥育豚1頭当りFu211.8、DTP24.1㎏を給与した。肥育豚の6体の平均(加重)生体重は第22表に示す如である。即ち1体当平均80㎏で、枝肉は46㎏、精肉は40㎏であり、枝肉歩合は48%、精肉歩合は枝肉100に対して83%であった。
この枝肉歩合は北海道標準と対比すると約5%減であり、枝肉歩合を高めることが今後の課題である。叉脂肪については肉眼観察にとどまったが、稍々多すぎた感があり、これが叉枝肉歩合を低めた原因とも考えられた。
第22表 肥育豚の生体重(昭36)
| 項 目 | 体重 (㎏) |
歩留 (%) | 標準 (%) | ||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
| 生体重 | 80 | 100 | - | 100 | - |
| 枝 肉 | 48 | 60 | 100 | 65 | 100 |
| 精 肉 | 40 | - | 83 | - | 83 |
以上の養豚飼料の給与飼料の給与計画は養豚の理論的技術体系にもとづき設計した。しかし繁殖豚の従来の飼料給与計画で実際に給与するとなると繁殖豚と哺乳期、離乳交配、妊娠前後期との組合せにより配合飼料と馬鈴薯サイレージの給与量が各々異り、その給与労働が繁雑すぎた。故にこの修正の基本的な考え方として繁殖豚の理論栄養量のFu、DTPから先ず自給飼料を平均的に日量を削減し、残量を配合飼料で給与し、しかも配合飼料は出来るだけ長期的に給与量を変更しない方法を採用し第2図の如く修正した。即ち、自給飼料は夏季(5月~9月、日量Fu1.7、DTP86g)と冬期(10月~4月、日量Fu1.3~1.7、DTP72~86g)とに分け、配合飼料は哺乳期を2期、交配期を1期、妊娠前期を3期、妊娠後期を1期と計7期に整理した。これは前飼料給与計画の20期と対比すると約1/3減の繁雑から解除されたものである。
A 自給飼料(日量)

B 配合飼料(日量)
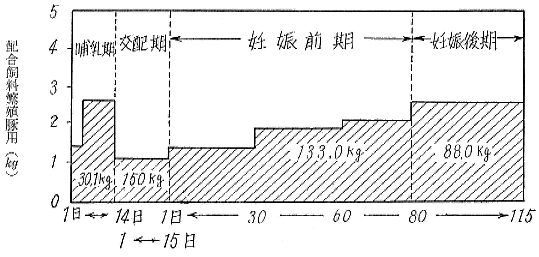
第2図 繁殖豚の飼料給与の修正計画
次ぎに肥育豚の飼料給与計画は当初購入飼料と自給作物を馬鈴薯に求めた。試算によると肥育豚の1頭当馬鈴薯サイレージ350㎏を必要とするが、馬鈴薯(生)で換算すると約10俵である。即ち肥育豚20頭を飼育するには馬鈴薯を約200俵必要とし、約40aの飼料面積を要する。換言するならば20aの馬鈴薯の栽培管理労働は約240時間を要する。問題となるのは都市近郊における作物栽培において240時間の労働時間を経済性の低い馬鈴薯を栽培することに意義ありや否やの点である。試算の結果によると馬鈴薯1俵当り400円以下でなければ養豚経営の飼料としては採算にあわず、若し、1俵400円以上の価格であるならば馬鈴薯を販売し、配合飼料を購入した方が労働の点からも価格の点からも有利ではあると考えられた。
以上の理由によって、特に都市近郊においては肥育豚は完全飼料給与式を採用するのが望ましいと推論した。
叉、繁殖豚より生産仔豚を早期離乳する利点は種々あるが、昭和37年は人工哺乳より早期離乳法を実施し、哺乳期間を15日に減少出来たばかりでなく、且母豚の健康状況も良好であった。
この人工哺乳は繁殖豚の配合飼料を約2/5に減少する可能性をもっている。叉人工哺乳法のもう一つのねらいは、哺乳期間の短縮による分娩率の向上を期待するのであるが、この点を検討したのが第23表である。
即ち、労賃を除外した仔豚費についてみると2回分娩の場合は1頭当3,033円となり、2.5回分娩の場合は2,522円と17%の減価が認められるが本道の場合2.5回の分娩をなす場合には冬期間も考慮し保温施設を設けなければならず、この経費を加えると2回分娩とほぼ同類の育成費となる。故に、北海道における2.5回の分娩については今後の課題である。
第23表 仔豚育成費試算
| 項 目 | 1回分娩 | 2回分娩 | 2.5回分娩 |
| 配合飼料 | 487㎏ | 609㎏ | 655㎏ |
| 馬 鈴 薯(生) | 245 | 245 | 245 |
| 馬鈴薯サイレージ | 840 | 840 | 840 |
| 牧 草(生) | 920 | 920 | 920 |
| 牧草サイレージ | 530 | 530 | 530 |
| 飼 料(A) | 25,110円 | 29,380 | 31,340 |
| 仔豚生産数(B) | 8-10頭(9) | 16-20(18) | 24-30(27) |
| A/B仔豚1頭当 (平均 C) |
3,138-2,511円 (2,790円) |
1,836-1,469 (1,632) |
1,305-1,044 (1,160) |
| C+仔豚飼料費(D) (D)+種付料(E) |
3,850円 4,073 |
2,692円 2,915 |
2,220円 2,443 |
| 建物減価/B 仔豚1頭当 (F) |
237円 | 118円 | 79円 |
| 仔 豚 費 | 4,310円 | 3,033円 | 2,522円 |
肥育豚の飼養管理を完全配合飼料で給与した場合の枝肉価格と1頭当価格換算を試算すると年2回分娩で枝肉価格が1㎏200~260円以上、1回分娩で220円~280円以上でなければ採算が合わない。この様な試算で検討すると豚肉価格の暴落した昭和37年度の前半は枝肉価格が高値でさえ200円前後であり、10月以降にはもちなおしたが、1年間の25%のみが採算のあった期間といえた。
以上の如く、従来の副業的な養豚技術から部門としての養豚技術を考察するとき、本経営試験では期間が短く問題提起にとどまったものが多い。
3.農業投下労働に関する考察
穀菽経営より有畜経営へ組織転換による部門別労働時間の変化を昭和33年と対比すると第24表の如くである。即ち(A)農家は8千時間内外と大差が認められないが、手伝、雇傭労働時間が12.4%から8%へと約1/2に減少し、(B)農家は逆に昭和33年に対比し38%増の6.4千時間と投下労働が拡大している。併し、部門別労働時間をみると耕種労働は(A)農家は54.4%から17.6%、(B)農家は67.0%から38.2%へと縮小し、叉養畜労働は(A)農家は38.3%から81.0%、(B)農家は31.3%から56.0%へと増大し部門間の質的労働の変化が認められている。
叉年間旬別労働配分をみると昭和33年は各農家とも労働ピークの形成が認められていた。即ち(A)農家は特に8月上旬は燕麦、亜麻の収穫に労働集中が認められ叉、(B)農家は6月下旬、7月下旬より8月上旬にかけての2回の労働ピークが認められていた。前者は水稲、小豆、デントコーンの中耕除草、後者は燕麦、亜麻、菜種の収穫ならびに菜種の脱穀調整であった。いずれにしても穀菽作物の肥培管理に投入された労働によるものであるが、昭和38年は家畜部門の強化により労働のピークがくずれ、むしろ、労働が月別に稍均等に配分されその結果冬期間の労働の燃焼が認められている。
作付体系の整備に伴い耕種部門に投下した労働時間の減少傾向については前述した如くであるが、尚、作業別投下労働時間についてみると、第25表の如く、その比率は昭和33年に対比し昭和37年は各農家とも大差が認められなかった。主要作業別労働投下の推移をみると第26表の如く、(A)農家は91.5%が穀菽作物より粗放な飼料作物に作付変更を行い、その結果、堆肥・運搬より始まる整地、耕起、播種迄の農作業と追肥、中耕除草、収穫脱穀調整、収納の農作業に分類され、前者は労働投下減少が2~3割、後者は2/5~1/2の減少が認められた。但し、(B)農家は飼料作物の作付率が68.5%と低く、且その飼料作物の内容も養豚部門へ給与する馬鈴薯を作付しているので、(A)農家の如き傾向は認められなかった。
第24表 部門別労働時間(単位:時間、( )割合)
| 農番/年次/部門別 | 耕 種 | 養 畜 | 経営一般 | 合 計 | 内 訳 | ||
| 自家労働 時 間 |
手伝、雇傭 労働時間 |
||||||
| (A)農家 | 昭33 | 4,474.6 (54.4) |
3.149.0 (38.0) |
599.5 (7.3) |
8,223.1 (100) |
7,021.7 (87.6) |
1,021.4 (12.4) |
| 昭38 | 1,456.0 (17.6) |
6,695.0 (81.0) |
117.0 (1.4) |
8,268.0 (100) |
7,600.5 (91.9) |
667.5 (8.1) |
|
| (B)農家 | 昭33 | 3,341.5 (67.0) |
1,564.5 (31.3) |
89.0 (1.7) |
4,995.0 (100) |
4,695.5 (94.2) |
294.5 (5.8) |
| 昭38 | 2,534.5 (38.2) |
3,711.5 (56.0) |
382.5 (5.8) |
6,628.5 (100) |
6,488.5 (97.9) |
140.0 (2.1) |
|
第25表 耕種作業別畑作投下労働時間
| 年次/項目 | 堆 肥 | 耕鋤整地 | 播種 (準備も含む) |
迫肥管理 | 中耕除草 | 収 穫 | 脱調収納 | 雑 | 計 | ||
| (A)農家 | 昭33 | 実数 比率 |
時間 38.6 1.2% |
127.5 3.9 |
288.5 8.9 |
170.7 5.2 |
857.9 26.3 |
1,331.0 40.8 |
359.0 11.0 |
86.5 2.7 |
3,259.7 100.0 |
| 昭37 | 実数 比率 |
時間 33.0 2.2% |
106.0 7.0 |
213.0 14.1 |
30.0 2.0 |
372.5 24.6 |
608.0 40.2 |
138.0 9.1 |
13.0 0.8 |
1,513.5 100.0 |
|
| (B)農家 | 昭33 | 実数 比率 |
時間 31.0 1.1% |
237.7 8.6 |
224.3 8.1 |
85.5 3.1 |
564.5 20.4 |
1,148.5 41.5 |
454.0 16.4 |
22.0 0.8 |
2,767.5 100.0 |
| 昭37 | 実数 比率 |
時間 100.0 5.1% |
177.0 8.9 |
296.5 15.1 |
104.0 5.3 |
342.0 17.4 |
850.0 43.1 |
55.0 2.8 |
45.0 2.3 |
1,969.5 100.0 |
|
第26表 主要作業別労働投下の推移
| 作 業 別 | (A)農家 | (B)農家 |
| 堆 肥 運 搬 | 85.5% | 332.6% |
| 耕 鋤 整 地 | 83.1 | 74.5 |
| 播 種 | 73.8 | 132.2 |
| 追 肥 | 17.6 | 121.6 |
| 中 耕 除 草 | 43.4 | 60.6 |
| 収穫・脱調・収納 | 44.1 | 56.5 |
次ぎに、養畜部門別投下労働についてみると、第27表の如く、総計は、各農家とも昭和33年と対比すると昭和38年は約3倍となった。即ち、(A)農家は6.6千時間、(B)農家は3.5千時間である。
尚、乳牛管理労働(飼育+搾乳)を(A)農家について昭和33年より昭和38年までの6ヶ年間について乳牛頭数と総投下労働でみると乳牛頭数の増加に伴い、投下労働は増加はするが、特に乳牛6頭以上は比例的な傾向をとる、換言するならば乳牛頭数と乳牛1頭当管理労働との関係は第3図の如く、乳牛規模が小さい場合には1頭当管理労働は多くかかる傾向にあるが、6頭以上は約500時間とほぼ一定となる。この事は、将来多頭化の方向をとり、稼働力に限界がある際には乳牛頭数が規制される結果となる。故に(A)農家の如き、稼働力に限界があり、若し乳牛規模をより以上拡大するとするならば、乳牛管理労働を減少せしむる技術の導入が必要となってくるであろうと推論した。
4.農業の収益性に関する考察
穀菽経営より飼料基盤を整備しつつ、有畜経営へ組織展開し、農業粗収益が如何に変化したかを示したのが第28表である。即ち、農業粗収益を昭和35年と昭和38年と対比すると、(A)農家は193万円(B)農家は172万と4ヶ年間に漁農家とも約3.7倍の増額が認められている。総額に対する現金割合は、有畜化が進んでいない昭和35年は(A)農家は90.6%が現金による収入であったが、昭和38年には77.2%、(B)農家は70.7%から58.8%へと現金比率が低くなっているがこれは、家畜の個体増加によるものが多い。叉、耕地10a当農業粗収益は昭和38年は(A)農家は41.2千円、(B)農家は33.2千円と昭和35年と対比し、約3倍弱の増額となった。
農業粗収益の年次別内訳をみると第29表の如く、農業粗収益に対する殖産部門の占める割合は、各農家とも年次毎に減少し昭和38年には20%になり且、作物の種類も水稲、蔬菜、馬鈴薯と整理されるに至った。それに反し、畜産部門は次第にその比率を高めたがその内容は(A)(B)農家によって異なるものである。即ち(A)農家は昭和35年には乳牛が21.1%であったが、昭和36ねんには50%と急激な伸をみ、昭和37年61.8%、昭和38年74.1%と次第に比率が高まっていった。叉、養鶏部門は、10.1%を占めていたが乳牛部門の強化に伴って4.5%へと減少したものである。叉、(B)農家は昭和36年より養豚部門の併置をみ、昭和38年には乳牛39%養豚が33%を占めるに至っている。
第27表 養畜部門別投下労働
| 項 目 | 乳 牛 | 搾 乳 | 豚 | 鶏 | 飼 料 | 販 売 | 計 | ||
| (A)農家 | 昭33 | 実数 (比率) |
時間 677.5 (27.2%) |
412.5 (16.5) |
61.5 (2.5) |
754.5 (30.2) |
329.0 (13.2) |
258.5 (10.4) |
2,493.5 (100.0) |
| 昭38 | 実数 (比率) |
3,300 (49.3) |
2,325.5 (34.7) |
- - |
251.0 (3.8) |
314.0 (4.7) |
504.5 (7.5) |
6,695.0 (100.0) |
|
| (B)農家 | 昭33 | 実数 (比率) |
548.0 (47.4) |
264.5 (22.9) |
- - |
- - |
70.0 (6.0) |
272.5 (23.6) |
1,155.0 (100.0) |
| 昭38 | 実数 (比率) |
1,077.0 (30.8) |
657.5 (18.8) |
1,209.0 (34.5) |
- - |
263.5 (7.5) |
294.0 (8.4) |
3,501.0 (100.0) |
|

第3図 乳牛頭数と乳牛1頭当管理労働((A)農家)
第28表 農業粗収益
| 項目/農家番号 | (A) 農 家 | (B) 農 家 | ||||||
| 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | |
| 植 産 部 門 | 千円 487.9 |
401.3 |
404.4 |
398.4 |
545.5 |
472.6 |
501.6 |
460.8 |
| 畜 産 部 門 | 221.5 | 688.2 | 1,015.5 | 1,541.2 | 105.9 | 451.2 | 931.8 | 1,268.9 |
| 計 | 709.4 | 1,089.6 | 1,419.9 | 1,939.6 | 651.5 | 923.8 | 1,433.5 | 1,729.8 |
| (比 率) | (100.0%) | (153.6) | (200.1) | (365.7) | (100.0) | (141.8) | (220.0) | (376.3) |
| 内 現 金 (総額に対する割合) |
千円 642.9 (90.6%) |
755.7 (69.4) |
1,074.1 (76.2) |
1,487.1 (77.2) |
460.8 (70.7) |
554.6 (60.0) |
749.3 (52.3) |
1,049.3 (58.8) |
| 耕 地 10a 当 農 業 粗 収 益 |
千円 14.6 (100%) |
25.1 (172.0) |
32.6 (223.0) |
41.2 (282.1) |
12.5 (100.0) |
19.3 (155.3) |
28.2 (224.0) |
33.2 (265.5) |
第29表 農業粗収益の内訳(%)
| 項目/農家番号 | (A) 農 家 | (B) 農 家 | |||||||
| 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | ||
| 植産部門 | 水 稲 | 21.2 | 17.6 | 13.0 | 11.3 | 15.7 | 10.7 | 6.4 | 6.0 |
| 燕 麦 | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 10.6 | 7.0 | 2.1 | 3.6 | |
| 豆 類 | 1.2 | 0.4 | - | - | 9.1 | 1.0 | - | - | |
| 亜 麻 | 3.5 | - | - | - | 7.8 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | |
| 秋蒔菜種 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | - | 3.0 | 4.8 | 1.2 | - | |
| 甜 菜 | 7.7 | 3.4 | 3.1 | - | 0.4 | - | - | - | |
| 馬鈴薯 | 4.7 | 0.3 | - | - | 18.4 | 9.9 | 11.3 | 6.5 | |
| 蔬菜、その他 | 18.7 | 7.2 | 9.3 | 9.1 | 18.7 | 15.9 | 12.2 | 9.4 | |
| 小 計 | 68.8 | 36.9 | 28.5 | 20.5 | 83.7 | 52.4 | 35.0 | 26.6 | |
| 畜産部門 | 乳 牛 | 21.1 | 50.0 | 61.8 | 74.1 | 15.5 | 20.8 | 31.3 | 39.0 |
| 養 豚 | - | - | - | - | - | 12.1 | 31.7 | 33.0 | |
| 養 鶏 | 10.1 | 12.8 | 9.6 | 4.5 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | |
| その他 | - | 0.3 | 0.1 | 0.9 | - | 12.3 | 0.5 | 0.1 | |
| 小 計 | 31.2 | 63.1 | 71.5 | 79.5 | 16.3 | 47.6 | 65.0 | 73.4 | |
| 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
農業粗収益が増加するに伴って叉農業経営費も支出増となった。即ち、第30表に示如く、昭和38年は昭和35年と対比し(A)農家は2.4倍の92.5万円、(B)農家は3倍の89.1万円と増額した。そのうち、総額に対する現金の占める比率は60%から80%へと増大し、現金の占める比率は農業粗収益とは逆の傾向を示している。この農業経営費の現金比率が昭和35年には低いのは、土地改良費、家畜費の減価が総額に対して相対的に大きいが、有畜化の推進により購入飼料費が増加し、現金の占める比率が大きくなったものである。叉耕地10a当農業経営費は昭和38年は(A)農家は19.6千円、(B)農家は17.6千円と昭和35年に対比すると(A)農家2.4倍、(B)農家3.2倍となった。
第30表 農業経営費
| 項目 | (A)農家 | (B)農家 | ||||||
| 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | |
| 総額 (比率) |
382.0千円 (100.0%) |
516.3 (135.1) |
758.6 (198.5) |
925.5 (242.2) |
288.2 (100.0) |
439.6 (152.5) |
766.4 (269.3) |
891.0 (309.1) |
| 内現金 (総額に対する割合) |
246.5千円 (24.8%) |
415.7 (80.5) |
675.4 (89.2) |
817.8 (88.3) |
185.6 (65.6) |
320.6 (72.9) |
629.5 (80.9) |
739.0 (82.9) |
| 耕地10a当 農業経営費 |
7.8千円 (100.0%) |
11.9 (152.5) |
17.4 (223.0) |
19.6 (249.0) |
5.5 (100.0) |
9.2 (167.2) |
11.1 (204.0) |
17.6 (321.0) |
農業経営費の内訳をみると、第31表の如く各農家とも土地改良費は昭和35年には11%であったが昭和38年には4%内外となり、叉家畜、飼料および飼育費は60%を占めるに至った。
第31表 農業経営の内訳(%)
| 項目/農家番号 | (A) 農 家 | (B) 農 家 | ||||||
| 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | |
| 土 地 改 良 費 | 11.2 | 9.6 | 5.8 | 3.6 | 11.5 | 8.8 | 4.8 | 4.8 |
| 建 物 費 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 5.3 | 5.7 | 3.2 | 3.2 |
| 農 具 費 | 13.2 | 11.4 | 7.9 | 4.2 | 20.3 | 17.6 | 10.0 | 9.7 |
| 種 苗 費 | 2.9 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 1.2 |
| 肥 料 費 | 16.3 | 10.1 | 8.7 | 4.9 | 19.7 | 16.3 | 9.9 | 8.2 |
| 家畜、飼料、飼育費 | 36.5 | 48.1 | 57.3 | 68.2 | 7.6 | 32.6 | 59.1 | 64.5 |
| 消耗品、光熱薬剤費 | 9.5 | 8.2 | 5.8 | 5.8 | 10.2 | 8.9 | 1.2 | 1.3 |
| 雇 入 労 賃 | 2.1 | 4.2 | 7.9 | 7.2 | 18.1 | 0.7 | 2.1 | 0.8 |
| 租税、公課、保険費 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 5.1 | 6.4 | 4.7 | 2.6 |
| 販売、運搬、雑費 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 3.7 |
| 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
有畜化の推進による農業の収益性を農業粗収益から農業経営費を差引いた農業所得でみると第32表の如く、(A)農家は昭和35年32.7万円から約3倍の101.4万円、(B)農家は36.3万円から約2.3倍の83.8万円と農業所得の増加が認められている。併し、(B)農家の伸びは(A)農家より低いものである。この原因について、考察するに生産に参加している乳牛、豚、鶏の家畜単位と農業所得との関係をみると、第4図の如く、(A)農家は家畜単位が増大するに伴い、農業所得も拡大されているが、(B)農家は家畜単位11頭前後で停滞をしている。これは昭和37、38年にあたるのであるが、(B)農家は乳牛部門に養豚部門が併置され、この養豚部門に影響されているからである。即ち、昭和37年は豚肉価格が暴落し、昭和38年は養豚技術が未熟の為肥育豚が23頭冬期肥育に失敗しそれらの原因によって(A)農家の農業所得より低くなり、昭和35年と対比するとき(B)農家は2.3倍増の伸にとどまったのである。故に、単位当り農業所得は(B)農家は耕地10a当16.6千円、農従者1人当41.9万円であるが、豚肉価格の安定した昭和38年は、養豚技術さえ修得していたならば、(A)農家の如く、耕地10a当21.1千円、叉農従者1人当50.7万円の農業所得を増す可能性を有していたものと推論する。
本営農試験地は昭和33年に設置したものであるが、農業収益性については昭和35年より考察した。これは(B)農家の農業従事者が昭和34年に交通事故による不慮の災難にあい病院に入院をしたので考察から除外したが、昭和33、34両年は未だ耕土改良も施行されず土地生産性も低く昭和33年と対比するときには尚、経営の成果が認められているものである。
以上の如く重粘強酸性の不良土壌といえども、計画的な耕土改良を施行し、経済性を考慮しつつ経営組織の転換を行えば、経営不安定の農家と云えども本営農試験地の如く、経営が安定することの可能なことが実証されたのである。
第32表 農業の収益性
| 項 目 | (A) 農 家 | (B) 農 家 | ||||||
| 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 | |
| 農業粗収益 ┌植産 ┤畜産 └計 |
709.4千円 ┌68.8% ┤31.2 └100.0 |
1,089.6 ┌36.9 ┤63.1 └100.0 |
1,419.9 ┌28.5 ┤71.5 └100.0 |
1,939.6 ┌20.5 ┤79.5 └100.0 |
651.5 ┌83.7 ┤16.3 └100.0 |
923.8 ┌52.4 ┤47.6 └100.0 |
1,433.5 ┌35.0 ┤65.0 └100.0 |
1,729.8 ┌26.6 ┤73.4 └100.0 |
| 農 業 経 営 費 | 382.0千円 | 516.3 | 758.6 | 925.5 | 288.2 | 439.6 | 629.5 | 891.0 |
| 農 業 所 得 | 327.3千円 | 573.3 | 661.3 | 1,014.1 | 363.2 | 484.2 | 803.9 | 838.7 |
| 農 業 所 得 率 | 46.1% | 52.6 | 466.6 | 52.3 | 55.8 | 52.4 | 56.1 | 48.5 |
| 単位当たり農業所得 ┌耕地10a当 ┤ └農従者1人当 |
┌6.7千円 ┤ └9.4万円 |
┌13.2 ┤ └16.4 |
┌15.0 ┤ └33.5 |
┌21.5 ┤ └50.7 |
┌7.2 ┤ └18.7 |
┌10.1 ┤ └24.2 |
┌15.8 ┤ └40.2 |
┌16.6 ┤ └41.9 |
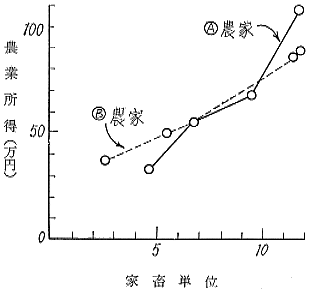
第4図 家畜単位と農業所得
Ⅴ要約
1)本稿は空知急流畑作地帯における有畜営農確立に関する研究の一環として行っているもので、岩見沢営農試験地の昭和33年から昭和38年までの6年間の試験成績を纏めたものである。
2)空知丘陵畑作地帯とは本道中央の南部に位置し、石狩川を中央に挟み両側に展開する傾斜度5~10度を有する波状性緩傾斜地帯を称する。その大部分は穀菽経営が支配的であるが経済的に有利な作物がなく一般的に技術水準も低位で農業経営は停滞不振であった。ここにおいてこれらの問題を解決する一手段として、有機物の投入を考慮し有畜化により解決せんとして営農試験地を岩見沢市に設置した。
3)営農試験担当農家は既存の農家より二戸選択し、所有地面積は(A)農家9.2ha(B)農家は5.9haで、耕地率は(A)農家は51.2%、(B)農家は85.6%である。経営状態は従来の穀菽経営をあらため、有畜経営とし、(A)農家は乳牛専営、(B)農家は乳牛部門と養豚部門とを併置せしめた。
4)低位生産地における重粘強酸性土壌の改善技術対策は原則的には土地生産性の(1)増進技術対策と(2)維持管理対策に二大別される。改善技術対策は土壌の熟畑化の程度により、A、B、Cの3段階に分けそれに応じて対策も異る。即ち、未風化のA段階では排水、心土破砕を行い、土壌の風化作用を促進し、同時に酸性矯正をも施行する。次いで土壌容量が増加するに伴い次第に深耕をしながら有機物を施用し、B段階へと発展し最終的にはC段階に至り、化学肥料を増肥し収量の増加を計るのである。固定費(暗渠排水・心土耕)はA段階へと順次増額し、変動費(肥料費)は熟畑化の程度に応じて収量反応が異る。
5)本営農試験地で施行した耕土改良は(A)農家は暗渠排水が延面積4.55ha、心土耕4.4ha(差引実面積2.8ha)、深耕4.0ha、酸性矯正10.05ha(4.55ha)、石灰39t、有機物は堆肥を140t投入した。叉、(B)農家は暗渠排水は4.9ha、心土耕12.2ha(4.9ha)、酸性矯正9.9ha(3.6ha)、石灰34.5t、堆肥160tを投入した。その結果、土壌断面も深くなり(第1層18㎝から22㎝)酸性矯正の効果が認められ(PH5.1から6.2)置換性石灰も多くなり(74㎎/100から204㎎/100)、腐植も増加し(2.5%から3.0%)、更に燐酸吸収係数も半減し(1,146から474)化学性の改良の効果が認められた。叉物理性も良好となり且土地生産性の向上も確認された。
尚、耕土改良に要した投入総額は有機物を除き(A)農家76.5万円、(B)農家84.5万円であり、10a当耕土改良費は1.6~1.7万円であった。年間減価償却費は1.1~1.4千円である。
6)土地利用は各農家とも飼料作物を基準とした5粘輪作方式を採用し、作付体系の進展に伴って1筆当りの面積も拡大し、且作付構成も牧草を含めた飼料作物の作付率は(A)農家は95.1%、(B)農家は68.5%となり飼料作物の基盤が整備された。
7)酪農経営における多頭飼育の優位性は、土地、資本、労働を経済的に有効に利用することであるが、自給率を高めると経営規模に限界があり、それを更に発展する際には外延的拡大即ち、協同化への方向をとる。個別経営において多頭飼育の方向で内延的拡大を求めるならば、飼料を外部より購入し自給率を低めざるを得なくなり、この傾向は都市近郊での搾乳専営に多い。(A)農家は後者の方法を採用した。その結果耕地4.0haといえども搾乳牛10頭、育成牛3頭の飼育の可能性が実証された。
8)養豚部門は(B)農家に併置し、昭和36年にデンマーク式豚舎を1棟60m2新設したが、従来の副業的な養豚技術から部門としての養豚技術を考察するとき、本経営試験では繁殖豚数と豚房数との関係、繁殖豚および肥育豚の省略労働を加味した飼料給与方式、仔豚育成等に監視問題提起にとどまった。
9)穀菽経営より有畜経営へ組織転換による農業総投下労働は、(A)農家は8専時間内外と大差が認められなかったが、(B)農家は4割増の6.4千時間と増大している。併し、部門別投下労働は畑作部門から有畜部門の労働の質的変化が認められている。叉(A)農家の乳牛頭数と1頭当乳牛管理労働(飼育+搾乳)との関係をみると、乳牛規模が小さい場合には、1頭当管理労働は多くかかる傾向にあるが、6頭以上は約500時間とほぼ一定である。この事は将来多頭化の方向をとり、稼働力に限界がある際には乳牛頭数が規制される原因となる。
10)有畜化の推進による農業の収益性を農業粗収益から農業経営費を差引いた農業所得でみると、(A)農家は昭和35年の32.7万円から約3倍の101.4万円、(B)農家は36.3万円から約2.3倍の83.8万円と農業所得の増加が認められ、重粘強酸性の不良土壌といえども耕土改良を施行し飼料基盤を整備しつつ、有畜化を推進するならば、本営農試験地の如く、経営が不安定な農家と云えども安定せしめることが可能な事が実証された。