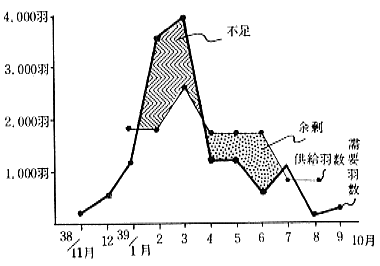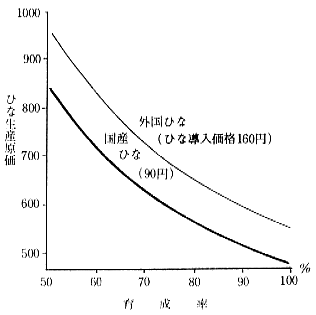【指導参考事項】
Ⅰ 共同育すう成立とその背景
1. 地域農業の概要
農家数1.280戸、水田面積3.29ヘクタ-ル、水田の作付割合85%の純農村である。1戸当りの耕地面積は約3.0ヘクタ-ルで、専業農家の適正面積を4.0ヘクタ-ル以上と見なせば、この階層に属する農家群は全戸の約25%を占め、残りの75%は何らかの形で補完を必要とする農家群である。
家畜の使用状況は、38年の統計によると馬約600頭(普及率46%)、鶏約38.000羽ア8普及率52%)の他は見るべきものはない。鶏は年々増加し、飼育農家1戸当り63羽で全道平均2.0倍に達し、今後、水田養鶏の形態で養鶏主産地として発展を期待し得る所である。
2. 共同育すう事業の理由と計画
上述の如く当町の水田経営規模は充分でなく、3.0ヘクタ-ル以下の過小経営農家層が50%を占めているが今後耕地拡大の余地がないこと、水田省力栽培技術の進歩により将来農家の余剰労力がますます多くなることと、冬の農閑期の遊休労力の活用を積極的に考えること等の理由から、養鶏を大幅に採り入れる方針が決定された。
この養鶏主産地形成の最重点事業として共同育すうを採り上げた。この制度により、農家個々の育すうによる従来の弊害を取り除き、農家が手軽に安心して養鶏に取り組める体制を確立するのがねらいである。38年農業構造改善事業の発足により、次表の如き12万羽の養鶏団地育成を目指して共同育すう計画が立てられた。
第1表 年次別増羽と共同育すう予定
| 年度別/区別 |
38年 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
摘 要 |
| 養鶏羽数(羽) |
38.500 |
50.000 |
80.000 |
100.000 |
112.000 |
120.000 |
|
共同育すう施設
供給羽数 |
|
33.000 |
66.000 |
88.000 |
90.500 |
100.000 |
120日令まで育成 |
| 共同育すう施設 |
1棟 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
内5棟は構造改善事業補助 |
Ⅱ 共同育すう事業の運営
1. 規模の決定
共同育すう事業の規格は、それ事態独立採算のとれる大きさであると同時に、5年後の完成時に毎年10万羽の若ひなを供給する機能を持つことが必要である。
規模の決定は第1表の増羽計画が順調に進むことを前提として施設を拡充して行くことが必要である。この際に必要な育成もひなの羽数は、ア)既存鶏の現状維持に必要な補充ひな、イ)増羽計画に伴うひなに分けられるこの際問題となるのは、卵価の下落等により農家の養鶏に対する熱意が薄らぎ、イ)に属するひなの需要が急に減少する危険が考えられ、育成ひなの売れ残り、あるいは、施設の遊休という経済的な打撃を被ることになる。
また全く逆な現象として卵価の好調等により、ひなの需要に応じきれない場合も起こり得る。このようなひな需給の異常に際しては、育成日数の120日を加減せざるを得ない。
2. 技術指導体制
この超大規模の共同育すう事業を円滑に進めるためには、技術的な背景が裏付けされることが絶対条件で、これが伴わないために大規模畜産が失敗している事例が甚だ多い。
共同育すうの直接の担当機関である農協では、つとにこの点を重視し、試験機関と十分な連絡をとり担当職員や中核農家の養鶏訓練を依託し、事業当初において技術者の養成に務めた。
またこの事業設計に際しては、畜産試験場を中心として地元関係機関からなる技術顧問団を組織し、特に重要な技術課題について指導をいける体制をとった。更に農家に対する一般指導については、農協の営農部を充実し、養鶏経営の基準を設け、養鶏記録を励行せしめている。然し水田と養鶏とを緊密に結びつけた水田養鶏の確立に必要な営農類型の作定等の経営指導の分野になると未開発のままである。
3. 事業運営
事業発足後、運営面で共通的に問題となるのは、経済的にはひなの配付価格、ひなの需要と供給の調整、技術的にひなの育成率、ひなの品種の選定、最終的には配付ひなの良否についての農家側の批評等である。
(1) 品種と孵卵場の選定
はじめは道内の4~6孵卵場から導入した。品種は色レグが主体で1部に一代雑種をとり入れた。然し外国ひなの成果が一般に明式されるにつれ、40年以降は全面的に外国ひなに切り換えられた。それ以前は第2表にに示す如く、育成率が不振で道産ひなでは大規模育成には不向きであることが判明した。
外国ひな、国産ひなに係わらず、一端導入したひなは、単に育成率のみならず、産卵後の成績についても、導入群別に実決をよく調べ的確な資料のもとに孵卵場、品種、系統を選別する努力が必要である。単なる評判によって選定する態度でおわってはならない。
(2) ひなの配付価格
原価計算にもとづき、更に業者の相場等を参考にして決定している。然し一般物価の値上がり外国ひなの導入により配付価格を次のように引き上げている。
第2表 配付価格
| |
60日令 |
120日令 |
摘 要 |
| 39年 |
国産 |
270円 |
500円 |
育成率やや不良 |
| 40年 |
〃 |
なし |
620円 |
|
| 40年 |
外国 |
なし |
670円 |
育成率が良いため
比較的安い |
有同育すうは独立採算の基盤に立つ事業でなければ永続しないが、創業当時からこの確信を持つことは容易でなく、導入ひなの育成率が予想より低下したことが、配付単価を割高にしている。
(3) ひなの需要と供給
ひなの配付を計画的に進める上に最も苦心する点である。すなわち、次図の如くひなの水平的供給能力に対して、農家の需要は春ひなに集中し、需給の均衝がとれずにこれの調整に困惑する。
第1図 ひなの需給の季節変動
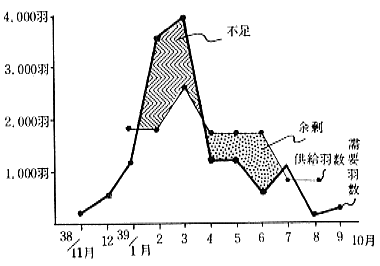
すなわち、副業養鶏が大部分を占めている現状では春ひな中心の需要になるのは止むを得ない。もしこの農家のの希望にそうには限られた施設で密飼することになり、その結果は配付ひなの品質低下となり農家の信頼を失うことになる。この毎年繰り返される共同育すうの悩みを解決するには、受入側の副業養鶏を速やかに近代化するため規模を拡大し、年間ひなの補充を必要とする養鶏農家群を育てあげなけらばならない。
この共同育すうでは、構造改善事業により第1表の如く40年の現在では5棟を整備したので、年間の配付能力は4万羽に達している。一方農家の養鶏飼育羽数は第1表の予想より50%下回る4万羽に留まっているので、施設は余剰気味になっている。この際、隣接町村の需要にも答え施設の十分な活用を考える必要がある。
4. 育すう実績と経営収支
(1) 育すう成績
第3表の如くで、39年の配付羽数は約12.000羽で、その育成率は120日令で75.3%、計画当初の89%を大きく下回っている。これは密飼が主因であり、連続育ひなによる消毒の不徹底や、道産ひなの抗病性にも関係があるようだ。然し40年以降は外国ひなに転換し、飼育方式もクル-イン、オ-ルアウト式に改めひな舎の徹底的消毒を図った所、育成率は国産ひなでは5.3%向上し日、120令の比較では10%もよくなっている。また外国ひなと国産ひなの比較では8%の差がある。
第3表 育すうの実績
| |
導入羽数 |
配付羽数 |
育成率(120日令 |
摘 要 |
回数
(回) |
総計
(羽) |
60日令
(羽) |
120日令
(羽) |
計
(羽) |
国産ひな
(%) |
外国ひな |
39年
(1~12月) |
17 |
15.191 |
4.432 |
7.787 |
12.219 |
75.3 |
なし |
60日令を含めた総体の育成率80.4% |
40年
(1~6月) |
11 |
28.531 |
0 |
24.082 |
24.082 |
80.6 |
87.8 |
総体育成率86.6% |
(2) 経営収支
ア)育すう施設投下資本
40年までの投下資本は23.542千円で育すう舎の坪当単価は約40.000円で、1ヵ年の配付羽数を4万羽とすれば、羽当の投資額は約600円となる。これを経済的投資額の坪当( )円、1羽当( )円に比較すると大幅な過剰投資とされる。
第4表 育すう施設に対する資本投資
| |
数 量 |
単 価 |
金 額 |
摘 要 |
| 育すう舎 |
1棟 79m2 (24坪) |
9.800円(32.700円) |
784.390円 |
|
| 大すう舎 |
5棟2.030m2(615坪) |
9.500円(31.700円) |
19.533.000円 |
|
| 育すう器 |
|
|
1.152.710円 |
円ガスブルダ-18基その他 |
| 給餌器 |
|
|
1.037.000円 |
|
| その他 |
|
|
1.035.000円 |
|
| 計 |
2.109m2 |
1.110円(36.900円) |
23.542.100円 |
|
これらの資本は構造改善事業による補助金35.9%を受けているので、上記の過剰投資による重圧は実質的にはかなり軽減せられることになる。
イ)ひなの原価計算
39年と40年では餌やひなの単価が異なり、外国ひなが割高であるが、最後の仕上げである育すう成績がよいので、生産原価は国産ひなで568円、外国ひなで594円で余り格差がない。
第5表 1羽当生産原価
| 費 目 |
39年(国産ひな) |
40年(外国ひな) |
金額
(円・銭) |
割合
(%) |
金額
(円・銭) |
割合
(%) |
| ひな購入費 |
113.65 |
19.5 |
170.58 |
28.7 |
| 飼料費 |
243.58 |
43.0 |
287.54 |
48.4 |
| 人件費 |
63.60 |
11.1 |
27.59 |
4.7 |
| 償却費 |
43.75 |
7.7 |
38.82 |
6.5 |
| 光熱費 |
15.89 |
2.8 |
23.35 |
3.9 |
| 衛生費 |
8.91 |
1.6 |
7.45 |
1.3 |
| 資本利子 |
51.10 |
9.0 |
22.67 |
3.8 |
| その他 |
27.12 |
5.3 |
15.59 |
2.7 |
| 計 |
567.64 |
100 |
593.95 |
100 |
備考 育成率国産ひな80.75%、外国ひな93.8%
第2図 育成率と原価変動の想定図
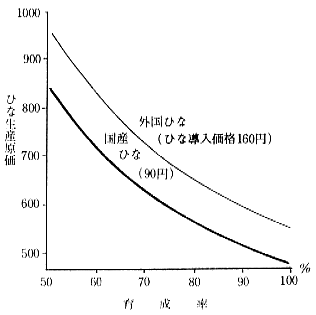
Ⅲ 共同育すうの効果
1. 共同育すうの有利性
東川町の共同育すうの効果を判定するには、なお時期が早過ぎるが、一般に常識的に考えられる有利性は次のようである。
①農家個々で育すう施設に固定資本を投ずる必要はない。
②農繁期における労力の競合をさけ得るし、育すう技術未熟や不完全整備による被害を防止できる。
③補充鶏を常時導入する体制にあるため空屋率が減少し、経営効率を高める。
これらの有利性は多数羽飼育になるほど高くなり、副業養鶏の段階では漠然としてくる。養鶏を本格的に経営するためには、成鶏部門に対して育すう部門の施設の投資割合が意外に多く40%位まで高まる。とっころが、一般には育すう施設投資を含む傾向が強く、そのために育すう成績不振に陥る事例が少なくないが、共同育すうの登場により、このような資金難にもとづく隘路を切り開くことができる。また補充鶏の任意入手が可能で、補充回数を増加すると次図の如く施設の遊休率を縮めることができて、これが養鶏収益に大きな影響を与える。例えば年の濁汰率が70%の時、年1回のみの補充では、37%位の施設遊休が生ずるが、2回補充では20%に減少する。
水田と労力の競合関係にある水田養鶏では1年間2~4回の補充が限度である。
第3図 補充回数と遊休率

2. ひな補充回数の増加
ひなの補充回数は、他の部門との労力の競合、施設の不備等で制限されるが、共同育すう組織が確立したのでこれらの障害が除去せられた。次ぎ図によれば、多数羽飼育に向かうほど補充回数は多くなるが、共同化以前にくらべ、共同化2年目では倍以上の補充回数になっている。
第4図 ひな補充回数の増加

3. 労働節減の効果
共同育すうが個別経営の省力管理に役立つことは明らかであるが、アンケ-ト調査によると、多数羽飼育になるほどその傾向が明らかで、65%の農家が労力の節減を認め、35%の農家は効果がない旨を述べている。また、節約された労力をどのように燃焼しているか、その使途を調べた所、次表の如く養鶏部門への還元が多い。
第6表 節減労力の使途
| |
雇傭の
減少 |
養鶏
拡大 |
養鶏
管理の
充実 |
圃場
作業の
補給 |
出稼 |
特筆する
のもがない |
計 |
| 戸数(戸) |
1 |
6 |
9 |
4 |
1 |
4 |
25 |
| 比率(%) |
4 |
24 |
36 |
16 |
4 |
16 |
100 |
Ⅳ むすび
東川町の共同育すう事業の、これまでの実態と問題点を述べてきたが、農業構造改善事業による大きなテコ入れで、ほぼその目的に向かって後展していると言えよう。然しはじめて事業にありがちな誤算や不測の事態の発生により予期の成績をあげ得なかった事も確かである。
共同育すう事業は地域の農家養鶏を発展させ、養鶏の主産地を形成するのに最も有力な原動力となるものであるから、これの成否は地域養鶏発展の鍵をにぎっているものと言える。この種の事業を進めるために留意すべき事項を次ぎに述べる。
1. 共同育すう事業と地域養鶏の場合
この事業開始に当り地域養鶏の現状、即ち飼育羽数、戸数、規模、技術水準、農協との結合、養鶏と営農の結合等の養鶏主産地として、将来の背景をよく分析し、それに見合った共同育すう計画をたてるべきで、もし共同育すう事業のみが独走することになると、地域養鶏との不均合によって生ずる犠牲が大きい。然し、共同育すう事業が養鶏団地育成の先駆者役割を果たさねばならない場合が多いから、地域養鶏の水準引き上げが急務である。
2. 農家養鶏経営の確立
副業養鶏の不安定層が減少し、水田と養鶏が固く密着した農家養鶏層が増加するような施策をとることが重要である。しかし、現状の水田農家における養鶏の存在意義は、単に余剰労力の年間活用のみに留まり堅い結びつきとは言えない。即ち水田養鶏に焦点をあわせた営農類型を作成する必要がある。
3. 共同育すう事業の経済運営の確立
大規模育成の偉力を発揮し、良質で安価で農家の喜ぶひなを配付し、しかも経済的に採算のとれる事業にまで発展しなければならない。もしこれと逆な立場になると、却って広範囲に悪影響をばらまく根元となる。
養鶏はその年の卵価等により人気が変動し、ひなの需要も増減するので、ひなの販売については、地域外にも販売の窓口を設け、余剰ひなを処分する体制も併せ考える。