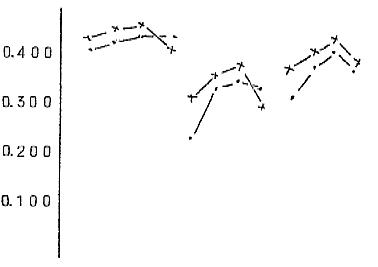
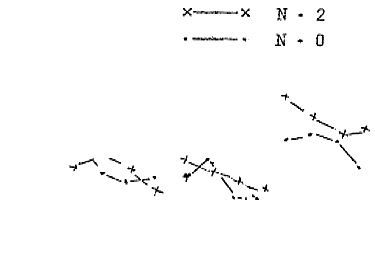
【指導参考事項】
|
天北地方における堆厩肥追肥用量試験 天北農業試験場天塩支場 (昭和39〜42年) |
・ 目 的
堆厩肥を草地に対して秋季に追肥する場合におけるその量的関係を知ろうとする。
・ 試験方法
1. 試験場所 天塩支場内低位泥炭地
2. 供試作物 A.採草型(チモシ−、アカクロ−バ)
B.放牧型(オ−チャ−ドグラス、ラジノクロ−バ、アルサイククロ−バ、ペレニアルライグラス)
3. 試験処理 主試験区堆厩肥(ton/10a) 副試験区窒素(kg/10a)
(分割区試験法2反復)
| 無堆厩肥(M0) 堆厩肥2ton(M2) 〃 4 (M4) 〃 6 (M6) |
0kg(N0) 2kg(N2) |
| 基肥N-4(硫安)P2O5-15(1/3過石表層2/3熔燐) └→N0区は施肥なし |
| 追肥K2O-10(硫加) N-2(硫安)処理区別により春季及び刈取毎 P2O5-5(過石)┐ >春季及び刈取毎 K2O-5 (硫加)┘ |
| 5. 収穫期 各年次共に採草3回、放牧型(5回)刈取 |
・ 主要成果の具体的デ−タ−
1番草に対する堆厩肥用量との関係(生草収量)
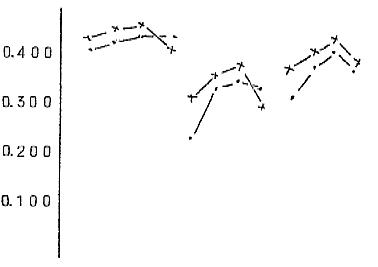 |
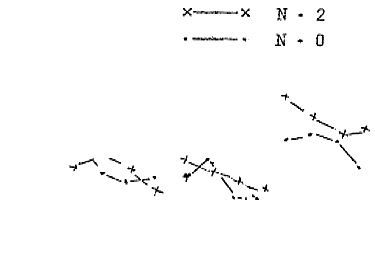 |
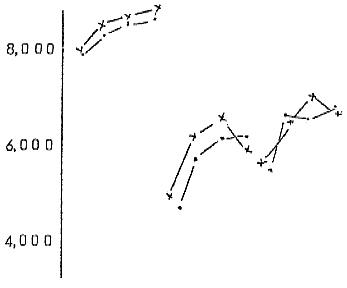 |
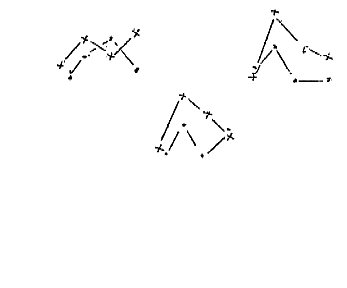 |
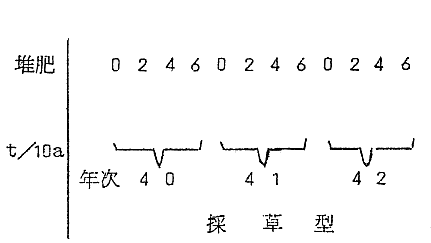 |
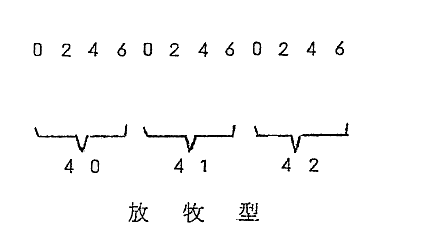 |
・ 奨励又は指導参考上の注意事項
1) 堆厩肥の撒布量は草種の組合の如何を問わず2t/10aが適量である。
2) マメ科の消失の点から考えて窒素は2kg/10a以内に施用すべきである。
3) 堆厩肥の撒布は出来るかぎり均一撒布が望ましい。
4) 越冬中の養分消失から考えると秋季よりは春季がよい。