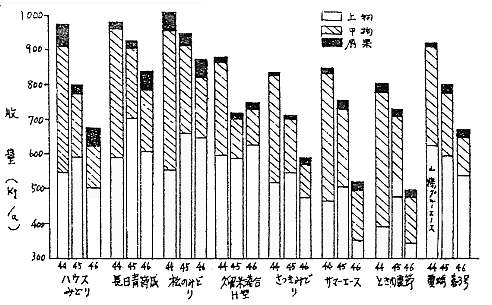
第1図 各品種の年次別収量
【普及奨励事項】
|
キュウリ促成栽培における品種ならびに地中加温に関する試験成績 (昭和44〜46年) 北農試作物第2部園芸作物第2研究室 担当者 小餅 昭二・田中 征勝 |
・ 目 的
本道にいけるハウス促成キュウリの品種生ならびに生育特性を調べ、有望な品種の選定と適栽培法を確立する。また、作季の延長と収量増大に対する地中加温効果を検討する。
・ 試験方法
| 供 試 | |||||||
| 品種数 | 播種期 | 定植期 | 栽植距離 | 施肥量 | 温風、地中加温期間 | ||
| 44年 | 24 | 3月5日 | 4月18日 | 90cm×40cm | 標準、5割増区 | 4月18〜5月29日(温風のみ) | |
| 45年 | 8 | 3月3日 | 4月17日 | 90×40・50 | 〃 〃 | 4月15日〜5月31日 | |
| 46年 | 8 | 2月24日、3月6日 | 4月10・20日 | 90×40 | 〃 〃 | 4月10日〜5月20日 | |
| 間 0.5m、高さ2.3mのパイプハウス1aを2棟使用 | |||||||
・ 試験成績の概要
1) 主枝と側枝の節成性との間には抑制栽培同様高い正の相関が認められた。更に節成性は促成と抑制との間でも相関が高く、一定の収量を確保するためにはある程度生枝節成性の高いことが必要である。
2) 初期収量の高い品種は総収量が高かった。また、初期収量に対する主枝節成性と着果率の寄与率は高かった。
3) 黒イボ系に比し、白イボ系は「夏埼落3号」を除きすべて収量が低かった。これは生枝節成性が一般に低いことと着果率が黒イボ系に比して劣ることが原因であった。以上の結果、品種の選定に当たっては初期収量の高い、言い換えると節成性が高くかつ着果率の高い品種が望ましい。
4) 品種は品質(外観)、収量性から従来ハウス促成栽培の基幹品種となっている黒イボ系の「松のみどり」が優れた。次いで品質は多少劣るが、節成性収量性の安定した「長日青節成」、節成性を安定させれば最も品質の良い「久留米落合H号」が有望である。更に、品質優れ、節成性、収量性も比較的安定した「夏埼落3号」は白イボ系の中では有望と認められた。
5) 栽植距離は50cmで株当り収量は増加するが、総収量では減収となるので慣行整枝法をとるときは40cmを適当とする。
6) 地中加温効果は、トマト同称キュウリにおいても地中加温により栄養生長が強められた。しかし収量については慣行は播種で15℃の設定温度では増収効果が小さかった。18℃の設定温度では一般に増収効果を示し、早まき区で効果が大きかった。以上両年の成績より慣行よりは播種期では地中加温の必要性が小さいと考えられる。
7) 地中加温により慣行よりは種期を前途させることが可能で初期収量の増大を計ることができる。地中加温の設定温度は18℃を目標とする。
・ 主要成果の具体的デ−タ−
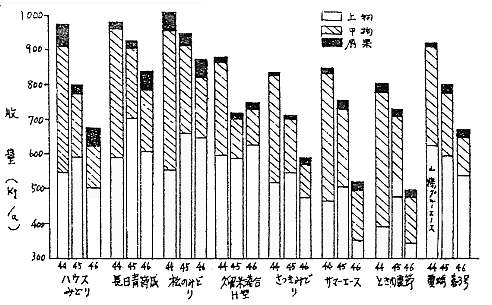
第1図 各品種の年次別収量
| 早まき区 | 慣行播種区 |
 |
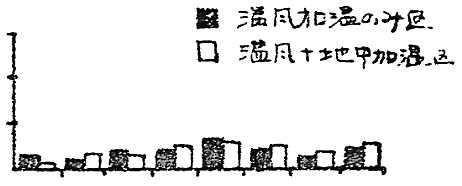 |
| 全収量 | |
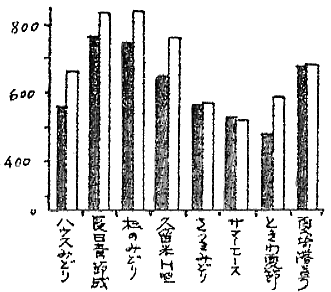 |
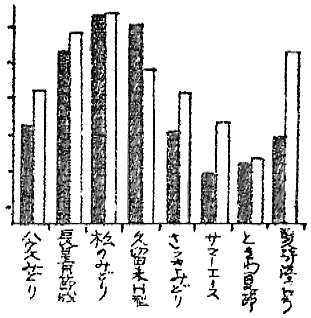 |
・ 普及指導上の注意事項
1. 促成栽培では白イボ系の収量が一般に低いため、市場価格との関係から品種の選定が必要である。
2. 地中加温の設定温度は18℃を目標とする。