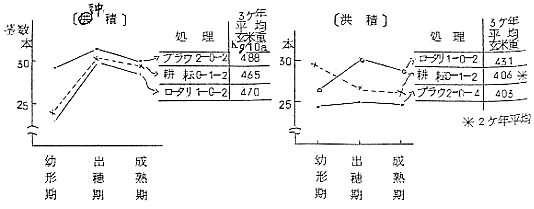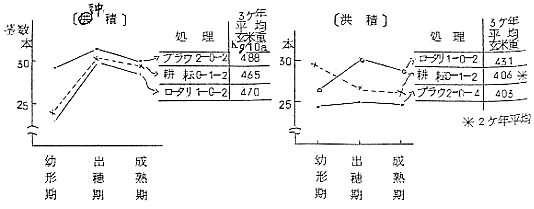【指導参考事項】
水田の耕起・砕土法に関する試験
(昭和44年〜46年) 道立中央農試 化学部 土壌改良科
|
・ 目 的
大型機械による耕起、砕土ならびにシロカキの違いが、土塊分布を中心とする物理性、養分供給ならびに水稲生育に及ぼす影響を、土壌の種類別に検討し、機械作業の適正な基準を策定するための基礎資料を得ようとする。
・試験方法
1. 土壌(雨竜町)
黄褐色土壌、強粘土型(沖)・灰褐色土壌、強粘土構造型(洪) |
2. 処理
耕起法:プラウ(14インチ)、ロ−タリ−(7インチ)、耕耘機
砕土法:灌水前砕土 0、1、2回
灌水後砕土 0、1、2、3回
シロカキ:レ−キ回数、2、3、4、5回 |
| 3. 1区面積:44、45年550〜650m2、46年1.000〜1.300m2 |
・ 試験成績の概要
1. 耕起法によって土壌乾燥に差がみられ、灌水直前の含水比でプラウ耕がロ−タリ耕より10〜20%低下した。
2. 灌水前の砕土では、沖積土では4cm以下の細かい土塊が多いが、洪積土は60〜80%までが4cm以上の大土塊で残る。
3. シロカキ後の土塊分布率は、灌水前に比べて、著しく細かくなり、0.5cm以下の部分が50〜80%を占め、4cm以上のものは10〜20%であった。
土壌間では、灌水前と同様に沖積が一段と粗らい。作業機別にみると、両土壌とも耕耘機>ロ−タリ>プラウの順に砕土率が高く、なおいずれも灌水後砕土が細かくなった。
4. 各種土塊の崩壊は、両土壌とも2cm以上の土塊は灌水後2ヶ月まで崩壊が続き、2cm以下の土塊は1ヶ月以内で殆ど崩壊する。
5. 灌水期間の減水深は、両試験とも6/下4〜5mm/日で両試験地間ならびに処理間の差はみとめられない。
6. 落水後の土壌乾燥は両土壌とも、灌水後の砕土、シロカキ作業回数の多いものが含水比は高く、キレツの発達も悪かった。このように灌水前後の作業内容の違いが秋の乾燥にも影響を残した。
7. 水稲の分けつからみると、沖積ではプラウ系列、洪積ではロ−タリ系列が良好で、なお、初期分けつは、灌水後砕土が少ない場合に良かった。
8. 収量は、生育と同様、沖積はプラウ耕、洪積はロ−タリ系列が夫々高い。なお両土壌ともに灌水後の砕土回数が少ない区が高収であったが、洪積のプラウ耕ではシロカキ回数が増すにつれて高収となるが、品質の低下がみられた。
9. 本試験から、土壌、機種ならびに作業の適切なところは以下のようになる。
| 土壌 |
耕起 |
灌水前砕土 |
灌水後砕土 |
シロカキレ−キ |
| 沖積 |
プラウ |
2回 |
0回 |
2回 |
| ロ−タリ |
1 |
0 |
2 |
| 洪水 |
プラウ |
2 |
0 |
4 |
| ロ−タリ |
1 |
0 |
2 |
・ 主要成果の具体的デ−タ−
図−1 土塊分布

図−2 土塊崩壊

図−3 生育並びに収量
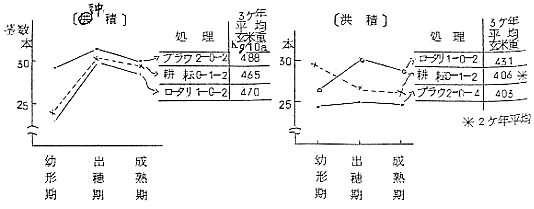
・ 普及指導注意事項
この試験の適応範囲は、全道一円とするが、土壌は沖積土の強粘質・乾田型水田土壌と洪積水田とする。