Ⅰ 現地実態調査
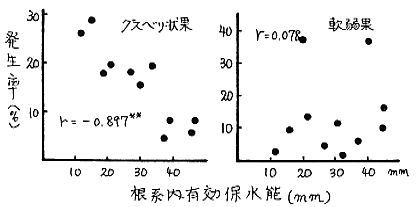
【指導参考事項】
| トマトトンネル栽培における異常発生の原因と対策 Ⅰ 現地実態調査並びに対策試験 Ⅱ 土壌水分条件並びにN施肥量が生育、収量、品質に及ぼす影響 Ⅲ 菌素質が生育、収量、品質に及ぼす影響 (昭和47〜51) (北海道立中央農業試験場 科学部) |
目的
トンネル栽培におけるトマト異常果の発生の原因を糾明し、その対策を明らかにすると共に、夏秋トマトの高品質、安定多収技術確立の資料とする。
試験研究方法
Ⅰ. 現地実態調査・対策試験:三笠市(褐色低地土及び暗色表尼疑似グラ仕)
1)栽培法比較試験 2)N施肥法試験 3)耕土改良試験 4)果房保護試験 5)苗交換試験 6)実態調査
Ⅱ. 土壌水分及びN施肥量試験:中央農業枠圃場(細粒質褐色低地土、夕張川沖積)
Ⅱ〜1試験 土壌水分条件(PF 2.6, 2.3, 2.0, 2.0→2.6等) 5処理 3反覆
圃場実施試験(無かん水, PF 2.6, PF 2.3) 3処理 3反覆
Ⅱ〜2試験 土壌水分試験(PF 2.6, 2.3, 2.0)3処理×N(11, 22, 44kg/10a)3処理 計9処理 3反覆
Ⅲ. 菌素質試験:中央農試枠圃場(細粒質褐色低地土)
育苗日数(40, 50, 55, 60, 70日苗)5処理 3反覆
結果の概要・要約
Ⅰ. 現地実態調査・対策試験
1)異常果はグスベリ状果と軟弱果にわけられ、形態上のみならず質的にも異常がみられ、日もちが悪い。
2)グスベリ状果は土壌水分環境(作土層の保水能)の劣悪化によって多発し、深耕によって、その発生率が著しく低下した。
Ⅱ. 土壌水分及びN施肥量試験
1)生育期間中の少水分条件ほどグスベリ状果が多発し、生育途中の水分条件の転換(湿→乾)によっても発生率が高まった。
2)多水分により栄養生長が旺盛になったものほど、着果数・平均−果重が増加し、収量が向上した。そのような収量向上条件下だはグスベリ状果が減少した。一方、軟弱果は、多水分多N条件で増加する傾向を示した。
3)グスベリ状果の発生は全体の栄養条件及び果実の肥大過程に関連し、軟弱果は果房間の養水分競合が関与しているように思われる。
Ⅲ. 菌素質試験
1)菌素質の形態的指標として葉/茎比の大きな苗(少日数苗)は栄養生長過多傾向を示し、尻ぐされ果が多発、葉/茎比の小さな苗(多日数苗)は栄養生長が著しく衰え、グスベリ状果が多発し、上位果房の着果数が減少し、収量を低下した。
以上の結果から軟弱果の発生要因にはなお不明の点が多いが、異常果の主体をなすグスベリ状果については、その原因がかなり明らかとなった。その対策としては
1)有機物施用により土壌の孔隙性を改良し、併せて深耕によって作土層全体の水分環境の改善を図る。
2)多水分条件(PF2.0)が生育収量・グスベリ状果抑制に望ましいが、軟弱果は増加傾向にあり、また、かん水施設の未普及を考慮に入れ、PF2.3〜2.0程度が妥当である。
3)異常果(グスベリ状果、軟弱果)は老化苗で多発するので、形態的指標としての葉/茎比3〜5(55〜70日苗)が望ましい。
4)N施肥法には問題も多いが、全量基肥では多水分条件40kg、中水分条件20kg/10aが適当である。
主要成果の具体的数字
Ⅰ 現地実態調査
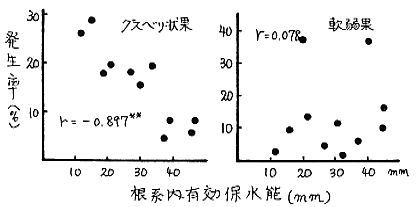
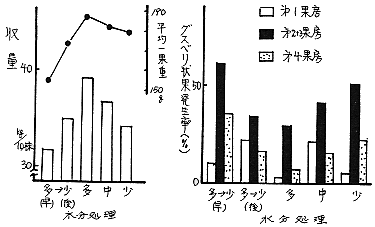
Ⅱ−2 土壌水分条件とN施肥量
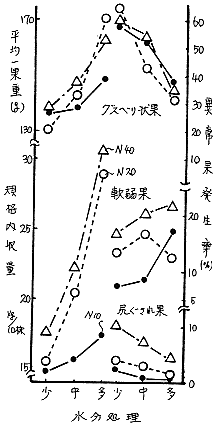
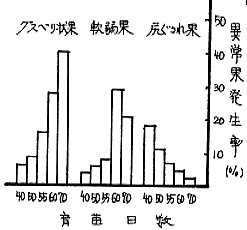
Ⅲ 苗素質(育苗日数)
収量調査結果(規格内収量kg/10株)
| 果房 | 40日苗 | 50日苗 | 55日苗 | 60日苗 | 70日苗 |
| 1 | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 9.7 | 9.1 |
| 1〜2 | 16.9 | 16.5 | 20.0 | 17.3 | 16.4 |
| 1〜3 | 21.9 | 22.4 | 26.1 | 23.6 | 20.7 |
| 1〜4 | 23.1 | 25.2 | 31.0 | 26.9 | 24.0 |
指導上の注意事項
1)収量向上、グスベリ状果発生率の低下には苗素質、N用量、水分条件(かん水量)の組合せをよく考慮して、良好な栄養生長を保つことが必要である。
2)全量基肥でN多量施用すると場合によって生育抑制が認められるので適正な水管理、暖効性Nの導入などにより、生育初期の濃度障害の回避を計ると共に、肥効持続を考えるべきである。
3)生育期間中のかん水条件は、多水分条件が望ましいが、生育期間中の急激な水分条件の転換(湿→乾)はグスベリ状果を多発させるので、無理のないかん水管理を考慮すべきである。