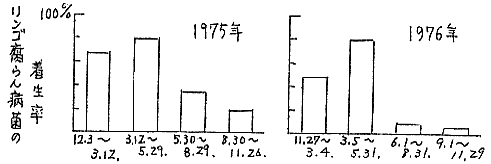
傷口の暴露期間
リンゴ腐らん病菌感染の季節的変動
散布時期試験
【指導参考事項】
|
1. 課題の分類 病害・果樹 2. 研究課題名 リンゴ腐らん病の防除時期について 3. 期間 昭和59〜53年 4. 担当 中央農試 5. 予算区分 道費 6. 協力分担 北後志・空知東部普及所 |
7. 目的
高率的な防除時期を検討する
8. 試験研究方法
1)発生生態に関する試験:各時期の選定痕から本病菌の検出を行い感染時期を調査する。また、休眠・生育両期のりんご樹の罹病性を比較する。
2)防除試験:各時期にメチルアミノベンツイミダゾ−ルカ−バメ−ト(MBC)とチオファネ−トメチルをほ場で散布し、防除効果を比較する。
9. 結果の要約
1)本病の感染は3〜5月に最も多く、次いで12〜3月が多い。一方、6〜11月までの間は比較的少ない。この感染の多い12〜5月までは、(ⅰ)この間に本病の侵入門戸となる剪定時の傷・凍寒害の被害部が生ずること、(ⅱ)りんご樹のゆ傷組織の形成が不良であるとともに、本病に罹病的であること、(ⅲ)この期間の後半は本病病微発現に好ましい条件であることなどから、本病の憂延に重要な時期と考えられる。
2)休眠期(晩秋1〜2回と発芽前)散布のみでも本病の発生を低減出来るが、これに加えて生育期間前半(発芽前から6月上〜中旬まで4〜5回)散布を行うと、通年やや勝る結果を得た。また、晩秋時の防除が特に重要であることが示された。
10. 主要成果の具体的数字
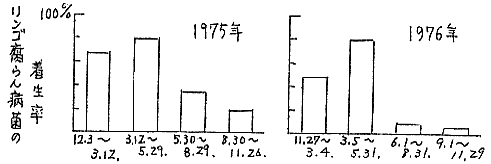
傷口の暴露期間
リンゴ腐らん病菌感染の季節的変動
散布時期試験
| 散布時期 | 枝腐らん発生数 | |||||||||||||||||
| 試験別(供試薬剤名) | ||||||||||||||||||
| 発 芽 前 |
生育期 | 収 穫 後 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| MBC | MBC | MBC | MBC、 チオファネ−トメチル |
チオファネ−トメチル | ||||||||||||||
| 一 年 目 計 |
二 年 目 |
三 年 目 |
合 計 |
一 年 目 |
二 年 目 |
合 計 |
一 年 目 |
二 年 目 |
合 計 |
一 年 目 |
二 年 目 |
合 計 |
一 年 目 |
二 年 目 |
合 計 |
|||
| 44 | 41 | 25 | 110 | 33 | 4 | 37 | 95 | 42 | 137 | |||||||||
| 44 | 42 | 86 | ||||||||||||||||
| X1000 |
90 | 100 | 37 | 234 | ||||||||||||||
| 40 (32) |
18 (23) |
58 (55) |
||||||||||||||||
無散布 |
24 | 0 | 24 | 106 | 26 | 130 | ||||||||||||
| 慣行散布 | 69 | 53 | 122 | |||||||||||||||
| 慣行散布 | 29 46。 |
48 55。 |
77 101。 |
|||||||||||||||
| 慣行散布 | 124 | 39 | 163 | |||||||||||||||
| 無散布又は慣行 | 94 | 195 | 150 | 439 | 35 | 14 | 49 | 136 | 40 | 176 | 51 | 84 | 135 | |||||
 は供試薬剤を1500倍、
は供試薬剤を1500倍、 は800倍で散布
は800倍で散布11. 今後の問題点
1)休眠期を完全防除出来るような散布方法および薬剤の検討
2)生育期に使用しうる有効薬剤の検索
12. 成果の取扱い
1)薬剤による本病防除は総合防除の一環として行う。
2)ベンツイミダゾ−ル系薬剤はリンゴ黒星病に耐性菌の出現を見ているので、生育期には当分の間使用しない。
3)休眠期散布薬剤としてはチオファネ−トメチルのほかに石灰硫黄合剤も有効である。