
図-1 1979年の7月中旬の気温
【指導参考事項】
寒地水稲機械移植栽培の冷温安定化に関する試験
障害型冷害に対する止葉抽出期葉身限界窒素濃度
窒素の施肥量が近年増加しつつあること、しかも、それが基肥の増加によってもたらされていることが、最近の
アンケート調査(斉藤、1979)に示されている。窒素多肥が障害型冷害の耐冷性を低下させることは実験的にも認められており、最近の稲作における窒素多肥化による耐冷性の低下が憂慮される。
窒素施肥の適生化を図るためには稲体の窒素栄養を診断することが重要である。これまでの研究で葉身の窒素濃度が収量構成要素と密接に関係することが明らかになっている(田中・1957、玖村・1957、木内ら・1960)。しかし、障害型冷害年次の収量と密接な関係にある不稔歩合と葉身窒素濃度との関係については、まだあまり研究されていない。
障害型冷害の場合、不稔発生に対する限界窒素濃度が診断の指標になる。限界窒素濃度がつかめれば、窒素濃度がそれ以下になるように施肥すれば良いことになる。そこで、本試験で止葉抽出期における葉身限界窒素濃度を提示する。
試験方法
1)冷温処置試験
1976年から1980年までの5ヶ年間に3品種を上川農試圃場(褐色低地土)で窒素の施肥量を変えて栽培した。1976年は「しおかり」および「ゆうなみ」、1977年は「しおかり」、1978年および1979年は「イシカリ」、1980年は「しおかり」を供試した。
窒素肥料は硫安を用い、各年共、10アール当り成分量で4kg、8kg、12kg、16kg、22kgを全量基肥とした。この他、基肥8kgに幼穂形成期に4kgを追肥した区を加え、計6水準とした。燐醸、加里は過燐酸石灰、塩化加里を用い、成分量でそれぞれ8kg、6kgを全量基肥とした。1区5㎡、1株3本、㎡当り25株植として5月下旬に移植した。
冷温処理は冷水かんがい装置(上川農試・1976)を用いておこなった。1976年、1977年、1979年は15℃、5日間、1978年、1980年は13℃、3日間処理した。水深は各年次共、地表より30cmに設定した。
その際、各試験区がほぼ同一ステージに処理されるよう全区を比較的生育が進む区(4kg,、8kg)と遅れる区(8+4kg、12kg、16kg、22kg)とにあらかじめに分けておき、処理開始日を2〜3日ずらせて別々に処理した。各年共、止葉抽出期(本試験では全基の約1割が葉耳間長がプラスに達した日とする)を冷温処理開始日とした。
冷温処理開始日に各区共、数10株の全基について、止葉より一枚下位の葉の葉耳と接している止葉の位置にマジックインクで印を付け、後日、処理開始日の葉耳間長が測定出来るようにした。
また、同じ日に数株を抜き取り、葉耳間長が-7.0〜-1.1cmの一次分けつの生葉身窒素濃度(以後、葉身N%と記す)を分析した。N%の分析はこの材料を含めて本試験では全てセミミクロケルダール法でおこなった。成熟期にヨードヨードカリ染色法で一次分けつの不稔歩合を調査し、葉身間長別に示した。1976年および1977年には収量ならびに収量構成要素を調査した。
2)実証試験

図-1 1979年の7月中旬の気温
試験結果
1)冷温処理試験
 |
 |
| 図-2 窒素施肥量が収量におよぼす影響 図中の数字はN施肥量(kg/10a) ( )は幼穂形成期追肥 |
|
図-2は1976年および1977年の収量を示したものである。
両年共、常温区では窒素の施肥量が多いほど多収であったが、冷温処理区では逆に窒素多肥区ほど減収した。
表-1にこの試験における冷温処理区の収量に対する㎡当り籾数と不稔歩合の標準偏回帰係数ならびに重相関係数を示した。標準偏回帰係数の比較から、冷温処理区の収量支配要因は不稔歩合であると言える。また、重相関係数が0.964および0.894であることから、これら2つの収量構成要素で収量の8割以上は説明することが出来る。
表-1 収量に対する籾数と不稔歩合の標準偏回帰係数ならびに重相関係数
| 年次 | 形 質 | 標準偏回帰係数 | 重相関係数 |
| 1976 | 籾数(粒/㎡) | 0.079 | 0.964 |
| 不稔歩合(sin-1√%) | -1.041 | ||
| 1977 | 籾数(粒/㎡) | 0.519 | 0.894 |
| 不稔歩合(sin-1√%) | -1.278 |

図-3 止葉期の稲体各部のN濃度の相関
注 ○ 処理開始日
● 処理中間日
× 処理終了日
図-3に稲体各部のN%を示した。それらの部位の中では葉身のN%が窒素の施肥量の変化に最も良く感応し、且つ、他部位のN%とも正の相関を示した。また、一次分けつの葉身N%と全葉身のN%との間には高い正の相関が認められた。したがって、一次分けつ、および全体の葉身はN%の測定部位として適していると言える。
図-4a〜fに各年の止葉抽出期の葉身N%と不稔歩合との関係と示した。
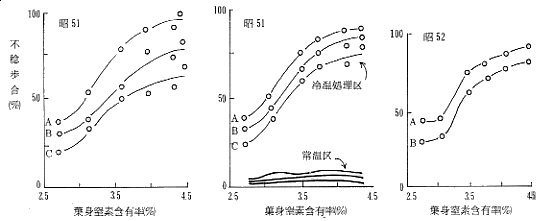 |
||
| 図-4-aゆうなみ(1976) | 図-4-bしおかり(1976) | 図-4-cしおかり(1977) |
 |
||
| 図-4-dしおかり(1980) | 図-4-eイシカリ(1978) | 図-4-fイシカリ(1979) |
| 図-4.a〜f 止葉抽出期の葉身%と不稔歩合 | ||
| 注 A:処理開始時葉耳間長-7.0〜-5.1cm B: 〃 -5.0〜-3.1〃 C: 〃 -3.0〜-1.1〃 |
||
不稔歩合はいずれも葉身N%の増加に伴って、S字曲線的に増加した。不稔歩合が急増し始める葉身N%は処理条件によって若干ことなるが、「ゆうなみ」では3.0%付近、「しおかり」では2.8〜3.2%、「イシカリ」では3.2〜3.5%であった。
2)実証試験
1979年の穂ばらみ期頃の冷温で、実際に不稔が発生したのは耐冷性弱の「ゆうなみ」のみで、他の2品種には認められなかった。「ゆうなみ」の止葉抽出期葉身N%と不稔歩合との関係曲線を図-5に示した。
不稔歩合は冷温処理試験の場合と同様、葉身N%の増加に伴ってS字曲線的に増加し、3.0%付近に屈曲点が認められた。

図-5 止葉抽出期の葉身N%と不稔歩合との関係
7月16日、葉耳間長-5.0〜1.0cm
品種「ゆうなみ」

図-6 止葉抽出期の葉身N%の実態
(鵡川町、美瑛町)

図-7 止葉期葉身窒素濃度と不稔歩合との関係
(士別地区農業改良普及所)

図-8 止葉期葉身窒素濃度と不稔歩合との関係
(北海道農業試験場、稲2研)
このように、3品種共、冷温処理試験で得られた結果が実証試験でも裏付けられたことから、止葉抽出期の葉身の限界N%は前記のごとく、耐冷性中の「ゆうなみ」で3.0%付近、中〜ヤヤ強の「しおかり」で2.8〜3.2%、ヤヤ強の「イシカリ」で3.2〜3.5%として大過ないと考えられる。
1978年におこなった止葉抽出期の葉身N%の実態調査では、10アール当り600kg以上の収量と確保した水田の約2割は限界濃度以下であった。この事実は、肥培管理次第では限界濃度以下で気象条件が良好な年次に10アール当り600kg以上の収量が得られることを示すものである。したがって、本試験で明らかにした限界濃度は実用的にもほぼ妥当な値であると思われる。一方、限界濃度を超えたものが約8割を占めたことは農家水田の障害型冷害に対する抵抗性が窒素の多肥化によってかなり低下していることを示唆している。
今後は更に、供試品種と増し、種々の環境条件のもとで試験を重ねて、上記の限界濃度の適応性を決定すべきである。また、栄養診断には簡易・迅速性が要望されることから、簡易診断法を検討することも今後の課題である。現在、緑色の色標を活用する方法を検討中である。
要 約
障害型冷害では、窒素多肥区ほど不稔歩合が増大し、減収が助長されることが確認された。
不稔発生に対する止葉抽出期の葉身N%は耐冷性中の「ゆうなみ」では3%付近、中〜ヤヤ強の「しおかり」では2.8〜3.2%、ヤヤ強の「イシカリ」では3.2〜3.5%であった。
障害型冷害を軽減するには、止葉抽出期の葉身N%を限界濃度以下に制御する肥培管理が必要である。10アール当り600kg以上の収量が見込まれる比較的多収田では、約8割が限界濃度を超えており、障害型冷害に対する抵抗性が窒素多肥のために低下していることが示唆された。