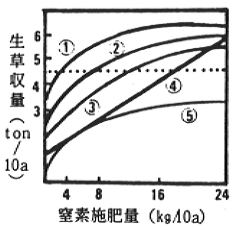
| 植生タイプ | 窒素施肥量 (kg/10a・年) |
| ①TY,RC.WC混播草地 | 4〜6 |
| ②TY,WC,30%混播草地 | 6〜8 |
| ③TY,WC,10%混播草地 | 10〜14 |
| ④TY単一的草地 | 14〜16 |
| ⑤荒廃草地 | - |
【指導参考事項】(昭和54〜61年)
チモシーを基幹とする採草地の効率的窒素施肥法
根釧農業試験場 土壌肥料科
目的
チモシーを基幹とする採草地を、その植生によって類型区分し、各類型ごとに窒素施肥適量を示すとともに、チモシー単播草地とマメ科牧草との混播草地に対する効率的な窒素施肥時期および施肥配分を明らかにする。
試験方法
1.草地の植生実態調査…根室地方の533圃場を対象。植生タイプの類型化と分布割合の調査。
2.植生タイプ別草地の窒素施肥反応…窒素用量試験。根室、釧路、十勝管内の現地および場内試験、窒素用量5段階×植生タイプ別草地。
3.チモシーの生育特性解明試験…チモシー単播草地供試。生育および養分吸収経過、分げつ発生の消長などを調査。供試品種=クンプウ、ノサップ、センポク、ホクシュウ。
4.窒素施肥時期に関する試験…早春の施肥時期3処理、1番草刈取り後の施肥時期3処理、および2番草刈取り後の施肥時期4処理。無窒素区(−N区)併置。
5.窒素施肥量に関する試験…①1番草に対して:秋のN施肥量3段階×秋と春の合計N施肥量
3段階、−N区。②2番草に対して:早春のN施肥量3段階×1番草刈取り後のN施肥量4段階、−N区。
6.窒素施肥配分に関する試験…施肥配分6処理(表2)×チモシー3品種(単播、混播)。
7.現地実証試験…未熟火山性土および厚層黒色火山性土の混播草地において、N施肥時期および施肥配分に関する試験を実施。
試験結果の概要
1.採草地における植生の実態調査から、草地を類型区分すると、5タイプに分類できた。このうち、マメ科率が10%程度と低い草地の出現頻度が最も多く42%を占めた。
2.N施肥量の増加に伴う増収効果は、草地の植生タイプによって異なっていた。また、N施肥量が同じ場合、マメ科率が高く維持され植生が良好な草地ほど多収であった(図1)。
3.このため、目標収量を生草で4.5t/10aとした場合、年間のN施肥適量は草地の植生タイプによって異なり、タイプ①(RC,WC30%以上)=4〜6kg/10a、タイプ②(WC20〜30%)=6〜8kg/10a、タイプ③(WC10%程度)=10〜14kg/10a、タイプ④(TY単−草地)=14〜16㎏/10aであった。タイプ⑤(荒廃草地)は、20kg/10aまで増肥しても目標収量に達しなかった(図1)。
4.上記のN適量を施肥することによって、タイプ①、②のマメ科率は維持された(表1)。また、タイプ④のようにNが多肥された草地でも、N03-N含有率が0.2%を上回ることはなかった。
5.チモシー草地の1番草収量は、早春の施肥時期が早いほど高まった(図2)。また前年の2番草刈取り後の施肥時期、施肥量にかかわらず、Nを秋と翌春の萌芽期に分施した区の収量や有穂茎数が、萌芽期に全量施肥した区のそれらを上回ることはなかった(図3)。
6.チモシー草地の2番草収量は、1番草刈取り後10日間程度経過し、チモシーの養分吸収が旺盛となる独立再生長期のN施肥によって、最も高まった(図4)。
7.チモシー草地の年間乾物収量を最も高めたNの施肥配分は、年間2回刈取り利用の場合、早春:1番草刈取り後:2番草刈取り後=2:1:0であった。これらの施肥配分は、年間収量に対する各番草収量の割合とほぼ対応していた(図5)。なお、クンプウのような極早生品種を基幹とする採草地では年間3回刈取り利用で、Nの施肥配分は、早春:1番草刈取り後:2番草刈取り後=3:2:1が適当であった(図5)。
8.チモシーとマメ科牧草の混播草地におけるNの効率的な施肥時期、施肥配分は、チモシー単播草地で認めた結果と同様であった(図6,7,8)。これは、チモシーが混播草地の乾物収量の大部分を占めたためである。
9.また、未熟火山性土および厚層黒色火山性土の混播草地で実施した現地試験においても、効率的なN施肥時期および施肥配分は、上述した場内(黒色火山性土)試験で得られた結果と同様であった(図6,8)。
10.以上の結果から、チモシーを基幹とする採草地(年間2回刈取り利用)の最も効率的なN施肥法は、草地の植生タイプごとに設定されたN施肥適量の2/3を萌芽期に、1/3を1番草刈取り後の独立再生長を始め期(根釧地方では1番草刈り取り後10日間程度経過した時期)に施肥することである。この結果は、未熟火山性土、黒色火山性土および厚層黒色火山性土のいずれにおいても適用可能である。
主要成果の具体的数字
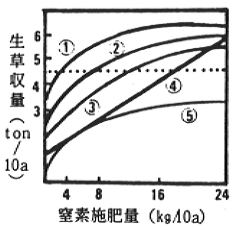 |
|
表1 窒素施肥量とマメ
科率の経年変化
| 草地 | N用量 | 58年 | 59年 |
| タ イ プ ① |
0 | 61.9 | 61.6 |
| 4 | 40.0 | 46.1 | |
| 8 | 23.7 | 15.2 | |
| 12 | 13.0 | 4.0 |
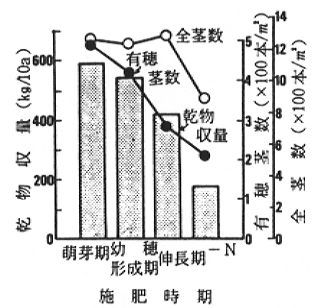
図2 早春の施肥時期が1番草収量、全茎数、有穂茎数に及ぼす影響
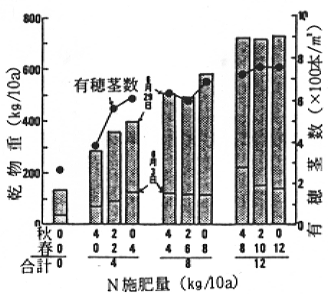
図3 茎葉部乾物重と有穂茎数

図4 1番草刈取り後の施肥時期が2番草収量に及ぼす影響
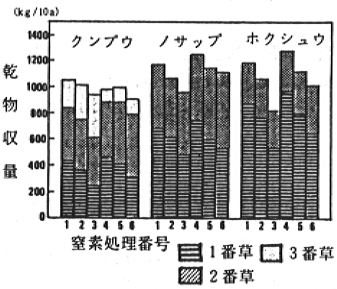
図5 窒素の施肥配分が年間乾物収量に及ぼす影響(単播草地)
表2 窒素の施肥配分
| 処理区 番号 |
窒素の施肥配分 |
| 早春:1番草後:2番草後 | |
| 1 | 3 : 2 : 1 |
| 2 | 2 : 2 : 2 |
| 3 | 2 : 2 : 3 |
| 4 | 4 : 2 : 0 |
| 5 | 3 : 3 : 0 |
| 6 | 2 : 4 : 0 |
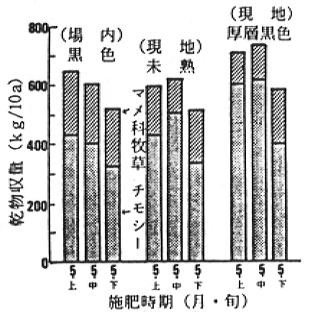
図6 早春の施肥時期が1番草収量に及ぼす影響
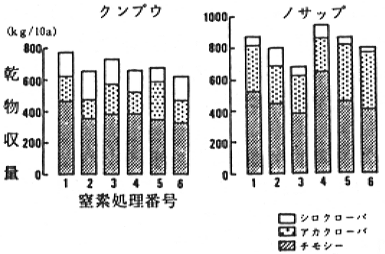
図7 窒素の施肥配分が年間乾物収量に及ぼす影響(3草種混播草地)
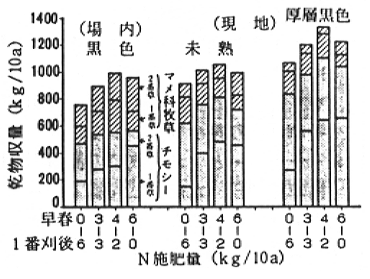
図8 窒素の施肥配分が年間乾物収量に及ぼす影響
普及指導上の注意事項
1.混播草地におけるマメ科牧草の維持には、本成績で述べた窒素施肥法のみならず、リン酸、カリ、苦土の十分な施肥が必要で、これらの施肥量は、施肥標準に準ずるものとする。また土壌pHを適正に維持するための石灰の施用も必要である。
2.とくに未熟火山性土は、その理化学的性質からみて酸性化しやすいため、草地のマメ科牧草の維持に留意する必要がある。