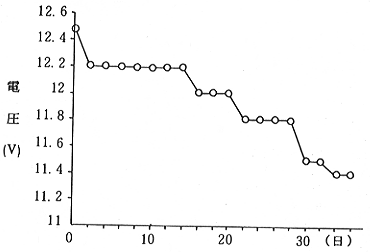
図(1)-② バッテリー電圧の推移
【指導参考事項】
|
1.課題の分類 家畜 肉牛・めん羊 管理 2.研究課題名 肉牛およびめん羊における新型電気牧柵の効果 3.期 間 昭和60年 5.担 当 新得畜試 肉牛科,滝川畜試 めん羊科 4.予算区分 受 託 6.協力分担関係 な し |
7.目 的
新型電気牧柵に対する肉牛およびめん羊の適応性と冬期積雪の影響を検討する。
8.試験方法
(1)電気放柵の設置方法
牧柵は外柵と内柵から成る。外柵は高張力線を使った固定柵で,3段張り(肉牛)と4段張り(めん羊)とした。内柵はポリワイヤーを使った移動可能な簡易電柵である。電牧器は直流型(肉牛)と交流型(めん羊)を用い,直流型の電源として自動車用12Vバッテリーを使用した。
(2)供試草地および家畜
肉牛では放牧用草地6.9haに,母牛12頭,子牛12頭,育成牛12頭を放牧した。めん羊では3.8haに母羊105頭,子羊155頭を放牧した。
(3)調査項目
行動調査,電気消費量,牧柵の雪害調査,草地の利用効率,アンケート調査
9.結果の概要・要約
(1)肉牛放牧における新型電気牧柵の効果
①電気牧柵に対する適応性では,入牧後2時間の観察の結果,時間経過と共に感電頭数は明らかに減少しており,放牧牛は電気牧柵に対して早い時間に順応していくことが分った。
②電気牧柵の電気消費量をバッテリー電圧の推移でみた結果,12.0V以上を維持した日数は20日間であった。バッテリーの保守管理の面から,安全を見込んで15〜20日ごとに充電するのが良いと考えられた。
③雪害については,牧柵線の脱落,切断あるいは支柱折れは認められなかった。積雪深は場所により0〜250㎝で全体に少なかった。
④草地の利用効率については,簡易電柵を使ったストリップ放牧区の方が,3牧区制輪換放牧区に比べて牧養力が16%高かった。
⑤雨あるいは下草の接触による電圧低下は少く,電気牧柵の能力を維持した。しかし、大型雑草や折れ枝,その他の接触に対して,定期的な点検と除去が電気牧柵の能力を維持する上で有効である。
⑥外柵設置資材費はアンケート調査から180〜398円/mであった。
⑦アンケート調査の結果,電気牧柵の利用によって脱柵や春先の補修作業の減少,放牧面積の節約などの効果が認められた。
⑧以上の結果,肉牛放牧における新型電気牧柵は,外柵については2〜3段張りにすることによって心理的柵として効果が発揮された。また,内柵を使って集約的な放牧が可能となることから,効果的システムと思われる。
(2)めん羊放牧における新型電気牧柵の効果
①放牧時におけるめん羊の感電頭数は入牧日の朝が母羊16頭,子羊18頭で最も多かったが,夕方になろと母羊,子羊それぞれ6頭に減少した。
②母羊8頭,子羊18頭を用いて個体ごとの感電回数を調査したところ,1頭あたりの感電回数は母羊1.7回,子羊2.2回で子羊が若干多かった。また,第1日目と第2日目の感電回数の比は2:1であった。
③放牧期間中の脱柵頭数は母羊6頭,子羊6頭であったが,母羊5頭は電棚でない出入り口からの脱柵と考えられ,子羊4頭は雷で通電中止中の脱柵であろ。放牧延頭数に対する脱柵頭数割合は0.3%であった。
④離乳子羊の放牧期における電気牧柵での脱柵は240頭中6頭で全体の2.5%であった。
⑤電牧線を夏期使用時のまま越冬させ,積雪による影響を調査した結果,線の脱落が124ケ所中5ケ所(4.0%),柱の折れが,固定支柱7本中5本(71.4%),保定支柱21本中2本(9.5%)であった。
⑥電気牧柵に用いたバッテリー消費電力は1日当り0.19kwであった。
⑦以上の結果、新型電気牧柵は外柵を4段張りにすることにより,めん羊の脱柵頭数が少なく,入牧後電気牧柵になれることにより感電が少なくなることから,めん羊に対して効果があるといえる。
積雪に対しては固定支柱の折れや線の脱落があることから,積雪地帯では線を弛め,牧柵を倒した状態て越冬させるほうが良いであろう。また,開始直後は感電頭数が多く,それによる事故や脱柵が考えられるので監視を行う必要があろう。
10.主要成果の具体的数字
表(1)-① 入牧から1時間における感電延頭数(狭い面積の場合)
| 牛の種類 | 時間経過 | 計 | |||||
| 0〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | ||
| ヘレフォード | |||||||
| 親(4頭) | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 |
| 子(4〃) | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 黒毛和種 | |||||||
| 親(2頭) | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 子(2〃) | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 育成(6〃) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 親牛(6頭) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 子牛(6〃) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 育成牛(〃) | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 全体(18頭) | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
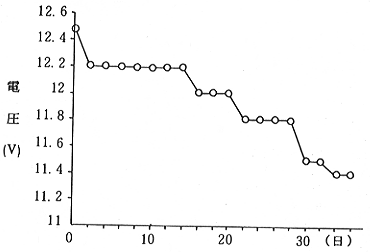
図(1)-② バッテリー電圧の推移
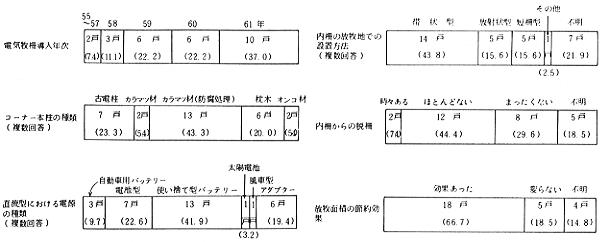
図(1)-⑦ アンケート調査結果
表(2)-① 群観察による感電頭数
| 期 | 調査時期 | 感電頭数 | ||
| 母羊 | 子羊 | 計 | ||
| 1 | 5月20日 朝 (移牧後) | 16 | 18 | 34 |
| 〃 夕 | 6 | 6 | 12 | |
| 5月23日 朝 (移牧前) | 4 | 7 | 11 | |
| 2 | 6月11日 朝 (移牧後) | 0 | 1 | 1 |
| 6月14日 夕 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 6月17日 朝 (移牧後) | 0 | 1 | 1 |
表(2)-⑤ 柱の折れ数と線の脱落数(外柵)
| 柱の種数 | 柱の折れ | 線の脱落 | ||||
| 調査数 | 折れ数 | 割合(%) | 調査数 | 折れ数 | 割合(%) | |
| 固定支柱 | 7 | 5 | 71.4 | 28 | 3 | 10.7 |
| バトン(保定支柱) | 21 | 2 | 9.5 | 84 | 2 | 2.4 |
11.今後の問題点
(1)新型電気牧柵システムを利用した放牧管理技術の検討
12.普及指導上の注意事項
(1)新型電気牧柵の能力を維持するためには,正しい施行方法に従って設置すること。
(2)積雪の影響が考えられる地域では,越冬前に電牧線を弛めて草地に倒す方式(耐雪方式)を採用する。
(3)電気牧柵に対する家畜の適応能力は高いが、未経験の家畜は適正な訓練をあらかじめ実施すること。
(4)電牧器の電源がバッテリーの場合,電気牧柵の設置条件などによって電気消費量が異なるので早目の充電,交換を心掛けること。
(5)電気牧柵システムは単に脱柵が少ない,補修が少ないなどのメリットに限定せず,放牧管理,草地管理の改善に役立てる工夫をすることが重要である。
(6)このシステムは乳牛にも応用できる。