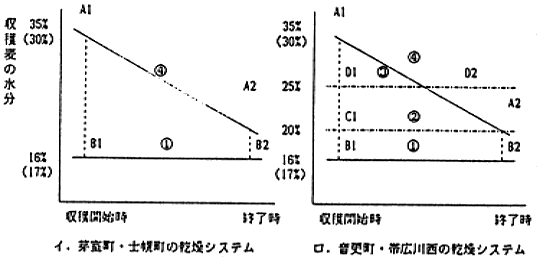
図 調査対象農協の乾燥図式
|
1.課題の分類 十勝農試 経営方式 畑作 2.研究課題名 小麦の乾燥・調製システムと経済性に関する調査成績 3.期 間 (昭60〜61年) 4.担 当 十勝農試経営科 4.予算区分 受託 5.協力分担 |
5.目 的
麦類の大型乾燥調製施設、予備乾燥施設及びコンバインの結合による利用シテムの違いが乾燥の利用効率と経済性などに如何なる影響を及ぼすかを明らかにし、小麦の収穫・乾燥効率の向上に資する。
6.試験研究方法
(1)小麦収穫・乾草工程において作業方式の異なる4地域(十勝管内の音更町、士幌町・芽室町・帯広川西)利用システムについて実態調査を行う。
(2)調査分析項目
①4地区タイプの小麦の乾燥効率の差
②サブ乾(予乾)タイプにおける麦作集団の運営方式と経済性の差
7.結果の概要・要約
(1)十勝地域の小麦の乾燥・調製方式について検討した。コンバイン収穫は農協の直接運営と麦作集団の運営に、乾燥・調製方式は農協乾燥施設一元方式とサブ(予乾)方式に類型化できる。農協の小麦面積が大きくなるに従い、コンバインの集団運営、さらには予乾方式の利用へと展開している。機械施設の平均的装備は、コンバイン1台当り60〜100ha、乾燥機(2.5/H)1トン当り15〜20haの小麦面積となっている。
(2)小麦の面積が2000ha以上の4地域を対象に小麦の乾燥・調製の実態を調査した。乾燥方式は農協一元方式が1地域・サブ乾(予乾)方式が3地域である。このうち、麦作集団がサブ乾施設を設置・運営する乾燥方式をみると、芽室町は集団及び農協の乾燥施設が生麦を仮乾燥(16〜17%)する。麦作集団は規模が大きく、乾燥機の乾減率(2.5/H)が高い。集団間の乾燥処理能力の差に対しては、農協の乾燥施設が調整的役割を果たすことになる。
他方、音更町、帯広川西は集団の予乾施設が一定の水分まで乾減し、この半乾麦を農協の乾燥施設が乾燥・調製する。この両地域の乾燥機は小型のラジアルビン型の乾燥機が主体であり、小麦の増加に対して乾燥機の追加導入など装備の変更が容易である。しかし、ラジアルビン型の乾燥機は乾減率が低く、小麦面積の大きな集団は収穫の遅れ等運営に問題を残す。
(3)サブ乾施設をとるこの3農協の乾燥・調製費用を農協一元方式と対比すると、いずれも低い水準となっている。従って、今後の小麦の面積拡大、10アール収量等小麦の収穫量増加に対してはサブ乾方式の拡充、新たな組織編成を示唆する.
(4)サブ乾(予乾)方式の麦作集団間のコンバイン収穫・乾燥費用を比較検討した。評価対象にした集団の規模と機械装備は、小麦面積75〜200ha、コンバイン1〜2台利用である。この集団のコンバインと乾燥費用を集団の規模と対応させると、費用が低い麦作集団は、コンバイン1台利用し小麦面積110ha規模、あるいは、コンバイン2台利用し小麦面積180ha以上の比較的大きな集団であり、集団の組織編成の規準となろう。
10.主要成果の具体的数字
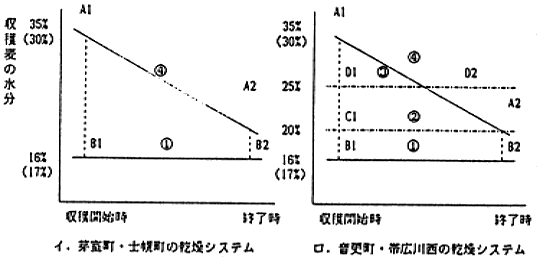
図 調査対象農協の乾燥図式
| 注1) | ①の線 | :仮乾燥の貯留水分 | ②の線 | :音更町のサブ施設から農協の受入水分 |
| ④ | :収穫時生麦の水分 | ③ | :帯広川西の 〃 |
| 2) | イのタイプ | :生麦を直接農協あるいは麦作集団の乾燥施設で受け、それを16〜17%の 仮乾燥水分までおとし、農協のサイロ、倉庫等で貯蔵する。 |
| ロのタイプ | :生麦を集団が自主運営するサブ乾施設で、農協受け入れ水分まで乾燥し 、農協はその半乾麦を16〜17%まで仮乾燥し、貯蔵する。 |
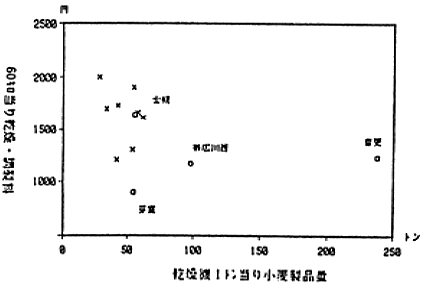
図 乾燥機当り処理量と乾燥・調製費用(59年)
注1.乾燥機は乾減率2.5%/Hの機械に限定した。従って、ラジアルビン・角型ビンの乾燥機は除いた。
2.資料は穀類共同乾燥調製状況集録(北海道)
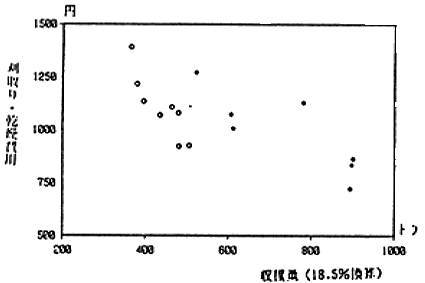
図 麦作集団の小麦収穫量と刈取り・乾燥費用
○−コンバイン1台の集団
●−コンバイン2台の集団
11.今後の問題点
小麦の乾燥方式を異にする(農協一元方式とサブ乾方式)方式間の乾燥費用の差異とその要因。
12.次年度の計画(成果の取扱い)
ここでは、十勝地域を対象に農協の乾燥施設と結びついた麦作集団の予乾施設の装備のあり方と経済性について評価した。従って、集団のみの完結方式についてはふれていないので留意を要する。