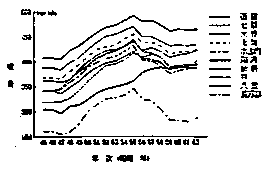
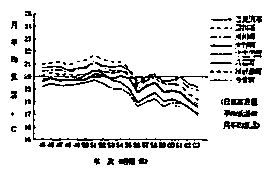
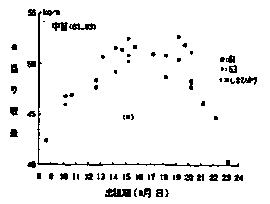
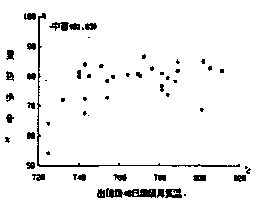
完了試験研究成績 (作成 1989年1月)
| 1.課題の分類 総合農業 作物生産 夏作物 稲(栽培)−V− 北海道 稲作 栽培 2.研究課題名 道南における近年の異常気象下の水稲作柄とその安定化対策 (道南における水稲の生育診断技術の確立) 3.予算区分 道単 4.研究期間 昭和61〜63年 5.担当 道南農試 作物科 6.協力分担 渡島南部、同中部、同北部、桧山南部、同北部各地区農業改良普及所 |
7.目的
道南における収量不安定要因について気象的な面からの解析を行うとともに、その改善策を見いだすために、品種と栽培条件の組み合わせ効果の評価を行い、適熟期品種を基本とした新品種の導入、既存品種の特産的位置付、初期生育促進技術の定着、稲作安定化のための栽培法などを検討しようした。
8.試験研究方法
【試験Ⅰ】
昭和30年代以降の収量と気温の年次変化を比較し作柄と気象要因の関係を検討。
【試験Ⅱ】
場内で低温年(61,63年)に「ともひかり」「上育397号」「ゆきひかり」「しまひかり」「渡育224号」「マツマエ」「巴まさり」の移植期の試験を行い、出穂期と登熟性および収量との関係、登熟気温と登熟性の関係などを検討した。61年:成苗、中苗、稚苗。63年:中苗、稚苗。
【試験Ⅲ】
昭和62,63年今金、八雲、厚沢部、知内、大野の5カ所で「ゆきひかり」「空育125」「巴まさり」の3品種を使い、側条施肥割合(0,30,50,100%)、追肥(幼形期、止葉期)、防風処理を組み合わせ、栽培技術効果の評価を行い、地域別の検討を行った。
9.結果の概要・要約
(1)道南の近年の水稲の作柄の低下は気象条件の悪化、とくに7月の気温の20℃以下への落ち込みが影響
しており、なかでも渡島、胆振、日高等の太平洋沿岸地域の水稲の作柄と密接に関係している。
(2)低温年では出穂期が早まるような栽培条件下(早植、成苗)においては晩生種の収量は比較的高かった
が、一般的な栽培法(中苗など)では大きく減収した。早生種は籾数不足の点で収量確保が困難であるが、
稚苗移植などでは比較的高収であった。
(3)低温年の防風効果は6月下旬での茎数増加、出穂期の促進について現地5カ所で認められ、穂数につい
ては今金、八雲、知内で多かった。側条施肥による茎数、穂数の増加効果は今金、知内で顕著であった。
(4)現地試験の結果から、栽培技術が出穂期と収量性に及ぼす影響力を数量化Ⅰ類のよって分析し計量化
した。出穂期に及ぼす栽培条件の影響力は、全体では年次>品種>地域>防風>側条施肥割合>追肥
の順であった。地域間では知内>八雲>今金>大野>厚沢部の順に出穂期は遅かった。
(5)籾数に及ぼす栽培条件の影響力は、全体では品種≧地域>追肥>年次>防風≧側条施肥割合の順
であった。地域間では八雲≧今金≧知内>厚沢部>大野の順であり、品種間では「巴まさり」≧「ゆきひ
かり」>「空育125号」の順であった。側条施肥では一定の傾向はなく、追肥ではとくに幼穂形成期追肥で
増加した。防風処理で増加した。
(6)登熟歩合に及ぼす栽培条件の影響力は、全体では地域>品種≧追肥≧側条施肥割合>年次>防風
の順であった。地域間では大野>厚沢部>今金≧八雲>知内の順で、品種間では「ゆきひかり」>「空育
125号」>「巴まさり」の順であった。側条施肥は施肥割合の高いほど高まった。幼穂形成期追肥で低下
した。防風処理は年次、地域で異なり、「巴まさり」では63年に高まった。
(7)収量に及ぼす栽培条件の影響力は全体では品種≧地域>側条施肥割合≧追肥>年次>防風の順で
あった。地域間では62年は八雲>今金>知内>大野>厚沢部の順、63年は厚沢部>今金=八雲>大
野>知内の順であり、品種間では「ゆきひかり」>「巴まさり」>「空育125号」の順であった。側条施肥効
果は62年減収、63年増収の傾向。追肥は両時期とも増収。防風処理では生育が進み過ぎ、不稔多発
で減収。
(8)北部では気象的にやや劣り、籾数多いが出穂が遅く登熟やや劣る。南部では厚沢部の気象と生育がよ
く、知内が劣った。側条施肥は初期生育旺盛化、穂数の早期確保ならびに登熟が向上し、とくに今金、厚
沢部で収量的にも効果が高かった。追肥は収量効果は高いが、登熟性の低下、長稈化など北部あるい
は知内で不安定要素が大きかった。防風処理は稈長がやや高くなるものの初期生育促進、穂数の早期
確保ならびに出穂、登熟、収量の面で北部および知内で顕著な効果があった。
(9)以上の結果を総合化し、栽培技術効果の地域別評価の総括表を作成した。近年の異常気象を考慮し
て、道南の稲作安定化のための栽培上の注意事項を整理して示した。
10.主要成果の具体的数字
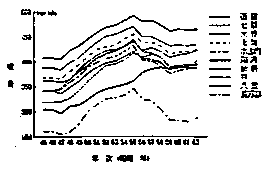 |
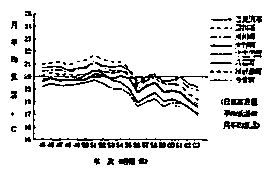 |
|
| 図1-a 前10年平均収量の年次変化(渡島) | 図4-a 市町村別7月平均気温の年次変化(5年平均) | |
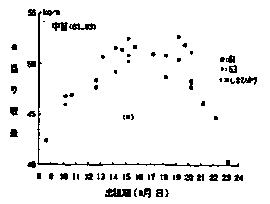 |
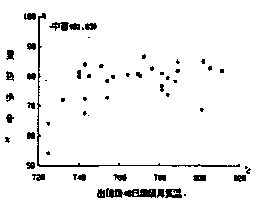 |
|
| 図7 品種の出穂期と収量の関係 | 図10 登熟気温と登熟歩合の関係 |
| 地域 | 気象 (高) |
出穂 (早) |
籾数 (多) |
登熟 (高) |
稈長 (短) |
収量 (多) |
品種 | 側条施肥 | 追肥 | 防風 | ||||||||||||||
| ゆ | K | 巴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 今金 | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | × | ▲ | ◎ | × | ○ | − | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 八雲 | × | × | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ▲ | ○ | △ | ▲ | △ | ◎ | ▲ | × | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | × | ◎ |
| 厚沢部 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | ▲ | ◎ | ◎ | △ | − | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | △ | × |
| 知内 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | − | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | × | ◎ |
| 大野 | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | ▲ |
11.成果の活用面と留意点
(1)晩生種とくに「巴まさり」については道南の中南部の全域にわたって必ずしも安定的とはいえないので、主
として気象条件の良いところで作付する。気象条件の不安定な、とくに渡島南部などでは今後も低温年に
おける減収が予想されるので、栽培環境を整える必要がある。晩生種を作付する場合は、成苗、あるいは
早植等の初期生育促進技術を必ず組み合わせるとともに、防風施設の導入を図ることが望ましい。
(2)早生種については道南の北部での作付はとくに問題はないが、これも中南部の全域において必ずしも安
定的とはいえないので、中南部での作付に当たっては、初期生育の旺盛化などにより構成要素を十分に確
保する必要があり、稚苗移植、側条施肥、栽植密度等を十分に検討し、栽培条件を整える必要がある。
(3)中生種の収量性は道南の中南部では、近年、比較的安定しているが、特定品種への作付の偏重は危
険であるため、水稲優良品種作付基準(水稲地帯別栽培指標)を厳しく守り、作付率の上限の35%を超えな
いようにする。
(4)初期生育促進、旺盛化技術の定着をはかるため、道南の北部および南部など、防風効果の高いところ
では、防風施設の積極的な導入が重要である。また、側条施肥についても初期生育の旺盛化、穂数の早
期確保の効果が高いため有効に活用する必要がある。
12.残された問題点とその対応
現地試験を年次を重ね、気象反応および側条施肥にともなう追肥の要否、時期を検討する。