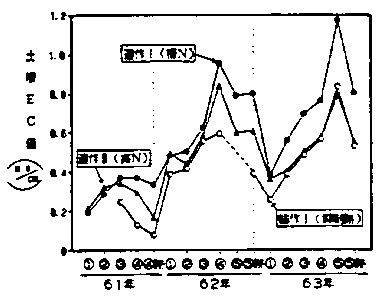
完了試験研究成績 (作成64年 1月)
| 1.課題の分類 野菜 野菜 栽培 スイートコーン ホウレンソウ 作付体系 北海道 2.研究課題名 施設野菜の新作付法に関する試験 (2)スイートコーンとホウレンソウの組合せについて 3.予算区分 道単 4.研究期間 昭和61年〜63年 5.担当 道南農試 園芸科 6.協力・分担関係 道南農試 土壌肥料科 |
7.目的
クリーニング効果が期待でき、かつ収益性のあるスイートコーンをハウス栽培に導入し、ホウレンソウとの組合による新作型を確立する。
8.試験研究方法
(1)試験区別
|
||||||||||||||||||||
(2)栽培法
①ハウス半促成スイートコーン
品種:ハニーバンダム9、は種3月下旬、定植4月下旬(移植栽培)、栽植密度500株/a
②ハウス抑制スイートコーン
品種:ハニーバンダム200、は種8月上旬、定植8月下旬(移植栽培)、栽植密度500株/a
③ホウレンソウ
品種:クレメント、ソロモン等、年4〜5作(春〜秋まき)、栽植密度80株/㎡目標
9.結果の概要・要約
(1)抑制スイートコーンは、11月上旬に収穫が可能であったが、規格内収量は30kg/aと少なかった。半促成ス
イートコーンは、7月上旬に収穫でき規格内収量も111kg/aと多収であった。スイートコーンのハウス栽培と
しては半促成が良いと考えられた。
(2)スイートコーンの養分吸収量は、半促成作型がN1.2、K2O1.3、P2O50.5、CaO0.4、MgO0.2kg/aで、抑制作
型では、N0.8、K2O0.9、P2O5・CaO・MgO0.2〜0.3kg/aであり、半促成作型で多かった。
(3)輪作Ⅰ(抑制跡)区のホウレンソウ収量は、春まき作型を除き他の作型で連作Ⅰ(標N)区より一作当たり
28kg/a多収で、特にこの傾向は夏まき作型で明らかであった。輪作Ⅱ(半促成)区のホウレンソウ収量は、
夏まき・晩夏まき作型で連作Ⅰ(標N)区に比べ一作当たり38kg/a多収であった。この両輪作区の増収効果
は経年的に大きくなる傾向があった。スイートコーンと組み合わせたホウレンソウは、連作(標N)した場合よ
り多収であり、特に夏まき作型で多収なので輪作体系を導入することが良いと考えられた。
(4)ホウレンソウ各作型における土壌EC値は、連作Ⅰ(標N)区に比べ、輪作区および連作Ⅱ(減N)区で低く
考えられた。
(5)以上により、夏作のホウレンソウを主体に考えた場合スイートコーンと組み合わせたホウレンソウは連作
区より多収であり、輪作体系が適切であると考えられた。作付法としては、半促成スイートコーン(3月下旬
は種、4月上旬定植、移植栽培)+ホウレンソウ2作(夏まき、晩夏まき)が適当であると考えられた。
10.主要成果の具体的数字
| 作型 | 土壌 残存 Nレベル |
収穫期 (月.日) |
収量(本・kg/a) | 乾物重 (kg/a) |
吸収量 (kg/a) |
|||
| 粗収量 | 規格内 | |||||||
| 本数 | 重量 | N | K2O | |||||
| 抑制 | 少 | 11.5 | 127.4 | 100 | 35.1 | 46.6 | 0.75 | 0.93 |
| 多 | 11.5 | 128.6 | 83 | 26.2 | 46.9 | 0.82 | 0.95 | |
| 平均 | 11.5 | 128.0 | 92 | 30.6 | 46.8 | 0.79 | 0.94 | |
| 半促成 | 多 | 7.5 | 160.6 | 313 | 111.1 | 59.6 | 1.18 | 1.30 |
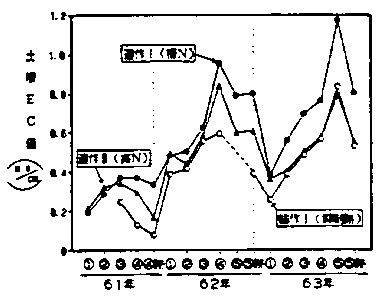 |
| 図1 ホウレンソウ作型別土壌EC値(発芽揃期サンプル) |
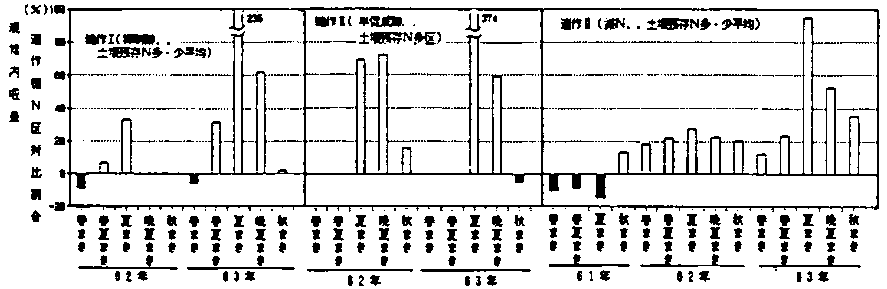 |
| 図2 ホウレンソウの各作型別連作 (標N)区対比規格内収量 |
| 土N 壌レ 残ベ 存ル |
作付法 | 3年間平均値 | 無機N (mg/ 100g) |
発芽数 (1m 当たり) |
アール当たり収量(株・kg/a) | 株数割合(%) | N 含有率 (%) |
|||||
| EC (ms/cm) |
pH (H2O) |
全株数 | 全重 | 規格内 重量 |
同左比 (%) |
規格外 | 病害 | |||||
| 少 | 連作Ⅰ(標N) | 0.50 | 6.29 | 28.6 | 50.0 | 7,015 | 134.2 | 112.1 | (100) | 34.2 | 2.1 | 4.7 |
| 連作Ⅱ(減N) | 0.43 | 6.45 | 14.1 | 52.0 | 6,749 | 147.7 | 128.0 | 114.0 | 25.2 | 3.6 | 4.7 | |
| 輪作Ⅰ(抑制跡) | 0.36 | 6.37 | 27.2 | 46.0 | 6,857 | 139.0 | 118.4 | 106.0 | 27.3 | 3.4 | 4.7 | |
| 多 | 連作Ⅰ(標N) | 0.63 | 5.90 | 50.7 | 55.0 | 7,235 | 111.7 | 90.3 | (100) | 37.6 | 2.2 | 4.7 |
| 連作Ⅱ(減N) | 0.52 | 6.13 | 15.9 | 53.0 | 7,514 | 141.6 | 124.5 | 138.0 | 24.8 | 2.3 | 4.8 | |
| 輪作Ⅰ(抑制跡) | 0.47 | 6.14 | 22.2 | 50.0 | 7,668 | 133.7 | 111.5 | 123.0 | 31.1 | 1.7 | 4.8 | |
| 多 | 連作Ⅰ(標N) | 0.78 | 6.17 | 50.7 | 82.0 | 7,233 | 94.9 | 70.1 | (100) | 44.4 | 3.5 | 4.7 |
| 連作Ⅱ(減N) | 0.60 | 6.46 | 15.9 | 66.0 | 7,032 | 113.3 | 98.4 | 140.0 | 29.4 | 3.9 | 4.8 | |
| 輪作Ⅰ(抑制跡) | 0.55 | 6.35 | 31.2 | 79.0 | 7,900 | 135.1 | 108.3 | 154.0 | 37.2 | 0.6 | 4.8 | |
11.成果の活用面と留意点
(1)ホウレンソウの連作が進み、土壌残存Nレベルが高い圃場では、スイートコーンを導入することは有効で
ある。なお、スイートコーンの茎葉は圃場外へ搬出すること。
(2)作付法としては、半促成スイートコーン(3月下旬は種、4月上旬定植、移植栽培)+ホウレンソウ2作(夏・
晩夏まき)が適当である。
(3)スイートコーンとの輪作でも、ホウレンソウに病害が発生する可能性があるので防除基準により発生を防
ぐこと。
12.残された問題点と留意点