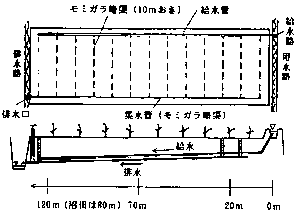
図1 給水管付加くし形暗渠(直結・自然流)
(沼田町、秩父別町)
|
1.課題の分類 総合農業 生産環境 3-1-3 水田農業 土壌管理 排水 北海道 水田農業 2.研究課題名 田畑輪換圃場における灌・排水機能の高度化による土壌・水管理技術の確立 3.予算区分 補助(地域水田農業確立) 4.研究期間 昭63〜平2年 5.担当 中央農試農芸化学部土壌改良科 農業機械部機械科、農業土木研究室 畑作部畑作第二科 6.協力・分担関係 空知支庁農業振興部計画課 |
7.目的
道央に広く分布する排水不良な強粘質転換圃場において、暗渠施設を活用した地下かんがいの適用条件を明らかにし、かんぱつ時には給水を、過湿時には迅速な排水を行い得る高度な土壌水分管理技術を確立する。
8.試験研究方法
1)モミガラ有材暗渠による地下かんがいの適用条件
(1)地下かんがい方法に関する予備試験(昭63年)
長沼町、秩父別町、岩見沢市(全て細粒灰色低地土)において、3種の方法により既存暗渠を一部手直しした施設を用いた地下からの給水を行い、地下水位の上昇程度をみた。
(2)適用圃場条件及ぴ土壌水分管理に関する試験(昭63〜平2年)
予備試験の結果、くし形暗渠が最も適応性が高いと判断し、以下それによって試験を行った。
A圃場:沼田町、細粒灰色低地上、面積30a、大豆(転換5年)、平2年7〜11月に3回給水。
B圃場:A圃場の隣・面積38a、小豆作付け、他はA圃場と同じで隣接圃場を対照区とした。
C園場:秩父別町、粗粒灰色低地土、面積47a、秋小麦(転換5年)、昭63年6月〜8月に3回給水
D圃場:C圃場の隣、地下水位がC圃場より低い点以外はC圃場と同じで、隣接圃場が対照区。
2)モミガラ組合せ暗渠の排水促進効果の確認(昭62年〜平1年)
地下かんがいにおける均一かつ迅速な水位制御の上で、最も望ましいと考えられるモミガラ組合せ暗渠の排水促進効果について、融雪水の排除状況、播種時の砕土性、作物の生育・収量から検討した。
長沼町(細粒灰色低地土)、施工区はモミガラ暗渠(10m間隔、標準形配線)にモミガラ心破(2mおき)を組み合わせた。対照区は隣接した圃場、土埋め戻し暗渠のみ、いずれも圃場を二分し、春播小麦と大豆を交互に栽培した。面積各区31a。
9.結果の概要・要約
1)地下かんがいの達成レベル
30〜40a程度の標準的転換畑において、給水管付加くし形暗渠を用い、用水路からの自然流下でほぼ1日以内に地表下20〜30㎝までほぼ均一に(±5〜10㎝のバラツキで、かつ、地表への水の噴出がない状態で)水位を上昇させ、作土層あるいは作土層直下部に水分を供給することが可能である。
2)地下かんがいの方法
暗渠の配線法と水の供給法の組み合わせにより数通りの方法があるが、以下の3種の方法で予備的試験を行った。
A法:給水管付加くし形暗渠(直結自然流)
B法:排水路せき止め直結形暗渠(逆流)
C法:標準形暗渠(直結逆流)(自然流下の給水法を自然流、圧で水を押し上げる給水法を逆流)
試験の結果、A法がi)現状の水田地帯への適応性が高い(既存暗渠を一部手直しすることにより可能)ii)給水効率が良く、水位上昇が均一、の2点に関して最も良好と思われた。したがって、本試験はA法によって行った。用水路水面と地表面の標高差は20cm程度で行った。
3)適応圃場条件
(1)常時地下水位は60〜100cm程度で、古い暗渠の水甲が機能していること。
(2)暗渠管埋設部(60〜80㎝)の現場透水係数は10-4〜10-5程度以下で、その上方の土層はある程度キレツが発達していること(概ね10-3〜10-4程度)。
以上の条件は、道央に広く分布する排水不良な強粘質土壌(灰色低地土、グライ土、灰色台地土、グライ台地土)転換畑のうち、転換後3年程度以上経った圃場の大部分が該当すると思われる。
4)モミガラ組合せ暗渠の排水促進効果
モミガラ組合せ暗渠の施工により、土埋め戻し暗渠よりも、融雪後から春播小麦の播種期にかけての土壌の水分の低下が促進され、砕土性が向上し、早播きが可能となり、播種期が若干拡大した。このことから、モミガラ組合せ暗渠は、土埋め戻し暗渠に比べ、融雪後の排水促進効果が高く、過湿時における迅速排水についても有効と考えられる。
10.主要成果の具体的数字
表1 試験地の概要と水位の上昇程度、給水量
| 試験地、土壌 | 圃場名 | 実施時期 | 直前の地 下水位cm |
最高水位 cm |
その時間 (hr) |
総給水量 (m3) |
面積 (a) |
転換 年数 |
作物 |
| 沼田町 | A | '90.7.16 | 82 | 20 | 22 | 119 | 31 | 5 | 大豆 |
| 細粒灰色低地土 | A | '90.11.21 | 57 | 13 | 4 | 48 | (同上) | - | |
| B | '90.7.16 | 103 | 33 | 10 | 176 | 38 | 5 | 小豆 | |
| 秩父別町 | C | '88.6.29 | 82 | 33 | 28 | 337 | 47 | 5 | 秋小麦 |
| 細粒灰色低地土 | D | '88.6.29 | 90 | 43 | 28 | 296 | 47 | 5 | (〃) |
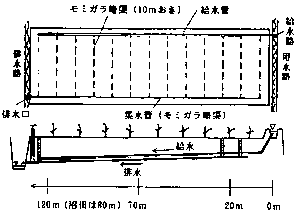
図1 給水管付加くし形暗渠(直結・自然流)
(沼田町、秩父別町)
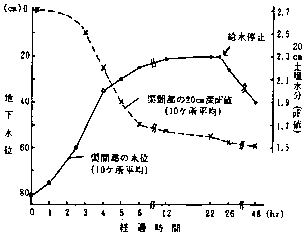
図2 地下水位の上昇と20cm深土壌水分の反応
(沼田A区、7.16〜18)
表2 融雪後の土壌条件
| 年次 期日 |
区 別 |
層位 (㎝) |
含水比 (%) |
三相分布(%) | ||
| 気相 | 液相 | 固相 | ||||
| 昭 和 62 年 4/6 |
施 工 |
0〜5 | 34.7 | 33.5 | 32.5 | 34.0 |
| 5〜10 | 39.1 | 24.0 | 39.1 | 36.9 | ||
| 10〜15 | 42.5 | 20.0 | 42.5 | 37.5 | ||
| 対 照 |
0〜5 | 48.2 | 19.0 | 42.5 | 38.5 | |
| 5〜10 | 47.0 | 15.0 | 47.0 | 38.0 | ||
| 10〜15 | 48.1 | 7.0 | 51.5 | 41.5 | ||
| 平 成 1 3/22 |
施 工 |
作土 | 35.5 | 13.5 | 41.7 | 44.8 |
| 心土 | 40.1 | 9.9 | 45.8 | 44.3 | ||
| 対 照 |
作土 | 39.0 | 2.0 | 50.4 | 47.6 | |
| 心土 | 47.3 | 2.6 | 54.2 | 43.2 | ||
表3 春播小麦播種床造成時の土壌水分と砕土性
| 年 次 |
期日 | ロ一タリ の組合せ |
耕転 ピッチ (cm) |
含水比(%) | 砕土率(%) | ||
| 施工 | 対照 | 施工 | 対照 | ||||
| 昭 62 |
4.21 | ダウン1 | 8.0 | 32.6 | 33.5 | 70.9 | 63.5 |
| 4.22 | 〃 2 | 8.0 | 29.2 | 30.6 | 73.1 | 69.9 | |
| 昭 63 |
4.12 | ダウン1 | 3.6 | 31.2 | 33.1 | 89.4 | |
| 4.15 | 〃 | 〃 | 31.9 | 89.9 | |||
| 4.12 | ダウン1 | 2.1 | 31.2 | 33.1 | 94.7 | ||
| 4.15 | 〃 | 〃 | 31.9 | 96.0 | |||
| 4.12 | アップ1 | 2.0 | 31.2 | 33.1 | 96.6 | ||
| 4.15 | 〃 | 〃 | 31.9 | 31.9 | 97.0 | ||
| 平 1 |
4.13 | ダウン2 | 6.1 | 33.0 | 35.6 | 75.0 | 63.0 |
| 4.13 | アップ1 | 4.9 | 33.0 | 77.7 | |||
| 4.16 | 〃 | 〃 | 33.8 | 66.0 | |||
表4 春播小麦の生育・収量
| 年 次 |
区別 | 播種期 (月日) |
出芽期 (月日) |
出芽 良否 |
出穂期 (月日) |
成熟期 (月日) |
稈長 (㎝) |
穂数 (本/㎡) |
子実重 kg/10a |
比較 (%) |
千粒重 (g) |
| 62 | 施工 | 4.21 | 5.9 | 中 | 6.23 | 8.4 | 88.2 | 712 | 220 | 99 | 30.0 |
| 対照 | 4.21 | 5.9 | 中 | 6.23 | 8.4 | 88.5 | 707 | 223 | 100 | 294 | |
| 63 | 施工 | 4.12 | 5.3 | や良〜中 | 6.26 | 8.8 | 87.2 | 557 | 456 | 113 | 38.3 |
| 対照 | 4.15 | 5.4 | 中 | 6.26 | 8.8 | 89.4 | 521 | 402 | 100 | 37.4 | |
| H1 | 施工 | 4.13 | 5.3 | 良 | 6.27 | 8.6 | 81.9 | 694 | 529 | 106 | 34.0 |
| 対照 | 4.16 | 5.4 | 良 | 6.28 | 8.6 | 80.3 | 611 | 501 | 100 | 32.1 |
11.成果の活用面と留意点
1)心土破砕や弾丸暗渠との併用が望ましい。
2)給水時の圧力が大きいと、地表への湧出があるので注意すること。用水路水面と地表面との標高差は30cm程度以内が望ましい。
3)水稲作では地表かんがいが原則である。
12.残された問題とその対応
1)泥炭地圃場における対応
2)大区画圃場への対応