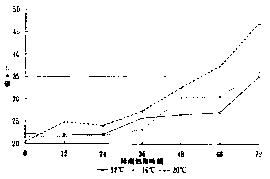
成績概要書(作成 平成7年1月)
|
1.課題の分類 2.研究課題名 菜豆(金時類)の色流れ粒の発生要因 (菜豆(金時類)の色流れ粒発生の要因解明と対策に関する試験) 3.予算区分 道単(豆基) 4.研究期間 平成3〜6年 5.担当 北海道立十勝農試・豆類第二科 6.協力・分拠関係 なし |
7.目的
菜豆(金時類)の色流れ粒発生の要因を解明し、その対策方法を検討する。
8.試験研究方法
(1)色流れ粒発生の実態調査
食糧検査事務所にて判定された色流れ粒と正常粒を色彩色差計にて測定し、色流れ粒の色の特徴を把握
する。
《色彩色差計:ミノルタカメラ社CK−221、測定方法:子実側部を単粒法にてL*a*b*表色系を測定》
(2)莢実の成熟と着色に関する調査
成熟期間近の「大正金時」個体をサンプリングし、莢実の各部位の水分と種皮色を調査し、莢実の成熟過程を
明らかにする。
(3)色流れ粒の発生要因解明(人工降雨下での色流れ粒発生再現試験)
金時類の莢実を気温、降水量等コントロールした人工降雨下で、子実の種皮包、莢実の部位別水分を経時的
に調査し、色流れに関わる種々の要因について検討する
降雨量:平均18㎜/hr
①降雨時の気温差による色流れ粒発生の差異について供試材料:「大正金時」の成熟
《莢気温条件:20℃、16℃、12℃》
②莢実の成熟程度の違いによる色流れ粒発生の差異供試材料:「大正金時」の莢実水分と外観より成熟度
を5段階に分類した莢実
《気温条件:20℃》
(4)色流れ粒発生回避のための播種期試験(十勝農試)「大正金時」を用い、播種期を5月下旬、6月上旬、中旬
とし、晩播による収量、品質への影響を調査する。
(5)色流れ粒発生回避のための播種適期の設定「大正金時」の生育日数推定式を用いて、金時類の栽培地域
における播種期を5月下旬〜6月下旬とした場合の播種適期を地帯別に検討する。
9.結果の概要・要約
・色流れ粒はL*値による判定が可能で、色流れ粒はほとんどL*値が35以上であった。
・降雨時の気潟が高いと色流れ粒の発生は速かった。
・莢実水分61〜70%(成熟度Ⅰ)で着色が始まり、莢実水分50%前後でL*値が35以下となった。
・莢実の成熟度0〜Ⅱでは色流れ粒は発生せず、成熱度Ⅲ〜Ⅴでは色流れ粒は発生した。・子実肥大が停止する莢実成熟度Ⅰ〜成熟度Ⅴになるには8〜10日程度かかり、色流れ粒発生の危険期間は色流れ粒発生の容易な成熟度Ⅲ〜Ⅴの莢実割合が増える成熱期前6日以降であった。
・年次によっては晩播で百粒重がやや小さくなり減収することがあり、子実の色がやや濃くなることがある。
・晩播により。早播に比べ成熟期での気温は低くなり、そのため色流れ粒の発生を回避できる可能性があった。
・十勝農試、北見農試のおける生育日数推定式は生育期間の日平均気温を独立変数としてY=6.02*X+206.13(r=-0.89**),Y=-7.98*X+239.93(r=-0.82**)で表せ、十勝および網走地方の現地試験においてあてはめが可能であった。
・十勝および網走地方の過去10年間(昭和59年〜平成5年)の気象から、金時類(北海金時を除く)では色流れ粒発生回避のための播種期は十勝中央および中央周辺では6月中旬、十勝山麓。、沿海および網走地方では6月上〜中旬が適当と推定された。
10.成果の具体的数字
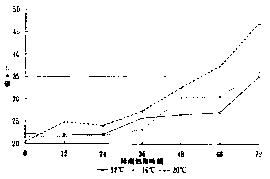
表1 金時類の莢実成熟度の分類
| 成熟度 | 外観 | 莢実水分 (%) |
莢実及び子実の外観 |
| 0 | 青莢 | 71〜 | 子実は肥大途中、子実は未着色。 |
| Ⅰ | 白莢 | 61〜70 | 莢殻は緑色が退色、子実の着色が始まる。 |
| Ⅱ | 黄莢 | 51〜60 | 莢殻が黄色になる。 |
| Ⅲ | - | 41〜50 | 子実の赤紫が濃い色を呈する。 |
| Ⅳ | - | 31〜40 | 外観は成熟莢とほぼ同様。やや子実水分が多い。 |
| Ⅴ | 成熟莢 | 〜30 | 子実、莢実ともに乾燥。 |
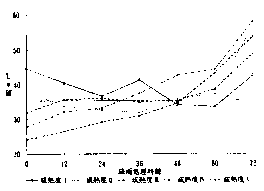
表2 十勝および網走地方における過去10年間(昭和59年〜平成5年)の平均気温と
生育日数推定式による成熟期の推定、旬別の30mm以上降水日数
| 場所 | 播種期(月日) | 推定成熟期(月日) | 旬 | 30mm以上 降水日数 (日) |
| 十勝農試 (十勝中央) |
5/25 6/ 5 6/15 |
9/ 1 9/ 9 9/18 |
8月下旬 9月上旬 9月中旬 |
5 7 4 |
| 本別 (十勝中央周辺) |
5/25 6/ 5 6/15 |
8/30 9/ 7 9/16 |
8月下旬 9月上旬 9月中旬 |
4 5 2 |
| 鹿追 (十勝山麓) |
5/25 6/ 5 6/15 |
9/ 5 9/13 9/23 |
9月上旬 9月中旬 9月下旬 |
6 2 4 |
| 忠類 (十勝沿海) |
5/25 6/ 5 6/15 |
9/ 8 9/18 9/27 |
9月上旬 9月中旬 9月下旬 |
9 6 5 |
| 北見農試 (網走内陸) |
5/25 6/ 5 6/15 |
9/ 4 9/11 9/21 |
9月上旬 9月中旬 9月下旬 |
2 1 3 |
| 斜里 (網走沿海) |
5/25 6/ 5 6/15 |
9/ 9 9/17 9/27 |
9月上旬 9月中旬 9月下旬 |
5 1 1 |
表3 色流れ粒発生回避のための播種期試験(十勝農試、平成3〜5年平均)
| 播種期 | 成熟期(月日) | 収量(㎏/10a) | 百粒重(9) | 品質(等級) | 成熟前10日間 平均気温(℃) |
| 5月下旬 | 9.10 | 245 | 74.5 | 3上 | 17.2 |
| 6月上旬 | 9.15 | 241 | 73.0 | 3中 | 16.5 |
| 6月中旬 | 9.22 | 233 | 70.2 | 3上 | 14.6 |
11.成果の活用面と留意点
・色流れ粒は成熟期前後の降水量と気温によって発生する。
・6月10〜15日までの晩播をすることにより色流れ粒の発生回避効果が高くなる。
・晩播は年次によっては百粒重が小さくなることがある。
・晩播は成熟期の遅れにより秋播小麦の栽培が不適となるので計画的作付に努める。
12.残された問題点とその対応
・降雨量と降雨時間による色流れ粒発生の機作の解明。
・成熟期前後の新しい収穫技術の開発。
・難色流れ粒品種の探索。
・晩生の良質多収品種の育成