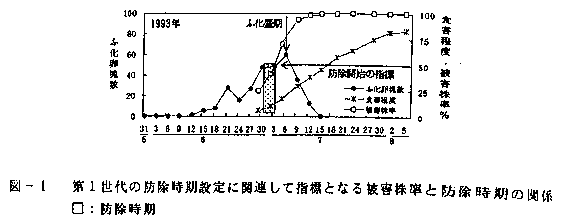
1995238
成績概要書 (作成平成8年1月)
|
課題の分類: 研究課題名:テンサイ主要病害虫に対するモニタリング手法の開発 2.ヨトウガ(発生予察地域活用技術確立事業)(環境保全型防除要否判断基準確立事業) 予算区分:植物貿易事業費 研究期間:平4〜7年度 担当科:北海道 病害虫防除所予察課 担当者:小野寺鶴将 奥山七郎 協力・分担関係:十勝農試研究部病虫科 北見農試研究部病虫科 |
1.目的
てん菜の主要害虫であるヨトウガの第1世代に対して、農業者自らが防除時期を決定できる縮易なモニタリング手法を関発し、適期防除を推進する。
2.方法
(1)てん菜ほ場におけるヨトウガの発生状況(平4〜7年)
(2)食害程度と収量の関係(平5年)
(3)簡易モニタリング手法の設定(平5〜7年)
(4)被害株率を用いた防除法の効果実証(平6〜7年)
3.結果の概要
(1)産卵期間は6月上旬より7月上旬頃までの約1ヶ月間にわたるが、産卵最盛期は年により1週間程度の変動が見られた。一方、ふ化最盛期は斉一で、各年とも産卵最盛期の約10日後であった。
(2)てん菜の根重は第1世代の食害程度に応じて減少した。被害許容水準として被害の軽い食害程度指数1(食害程度:25)を設定した。
(3)無防除ほ場における被害株率の上昇は非常に早かったが、食害程度は6月下旬頃より緩やかに増加した。判定の容易さと所要労力が軽いことから、モニタリング指標として被害株率が適当と考えた。
(4)被害株率50%の時点の食害程度が被害許容水準以下であったことから、この時点から防除を行った場合、以降の被害を被害許容水準以下に抑制できると考えられた。この防除時期はふ化最盛期にほぼ該当し、幼虫も大部分が若令期であった。また、この時期は慣行2回防除の第2回に相当するため、防除回数は1回削減できると考えられた。
(5)モニタリング値の査定誤差を比較的小さく納めるために必要な調査株数は50株程度であった。また、調査株の選定には従来から実施されている系統抽出法を適用できることが確認された。調査は5日間隔で行うのが望ましい。
(6)被害株率が30%および50%時点での1回散布の効果は慣行の2回散布と同等であり、しかも散布回数を1回削減できる有効な防除法と認められた。
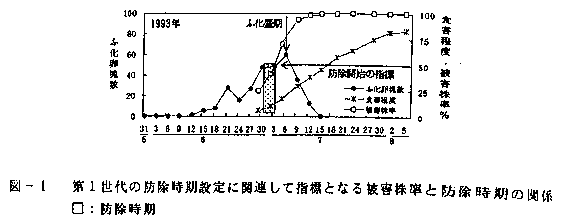
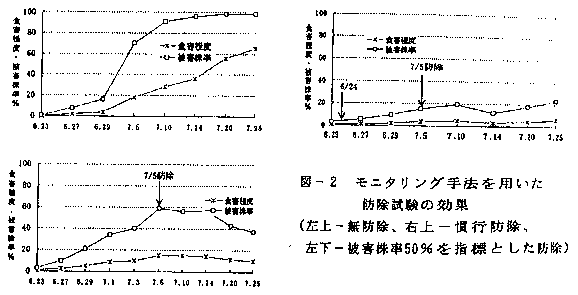
(1)第1世代の防除開始時期を決定するための簡易なモニタリング手法として被害株率50%が利用できる。
(2)簡易モニタリング手法を実行するための手順は以下のとおりである。
1)被害株率を被害発生初期(道央地帯で6月下旬)から5日間隔で調査する。
2)調査株は系統抽出法によって10株5箇所の計50株を選定する。
3)被害株率が50%に達した時点で防除を行う。
5.残された問題とその対応
(1)簡易モニタリング法の第2世代への適合性の検討。
(2)フェロモントラップを利用したより簡易なモニタリング法の確立。
(3)ヨトウガ以外の鱗翅目幼虫による被害が問題となる地域への適応の可否。