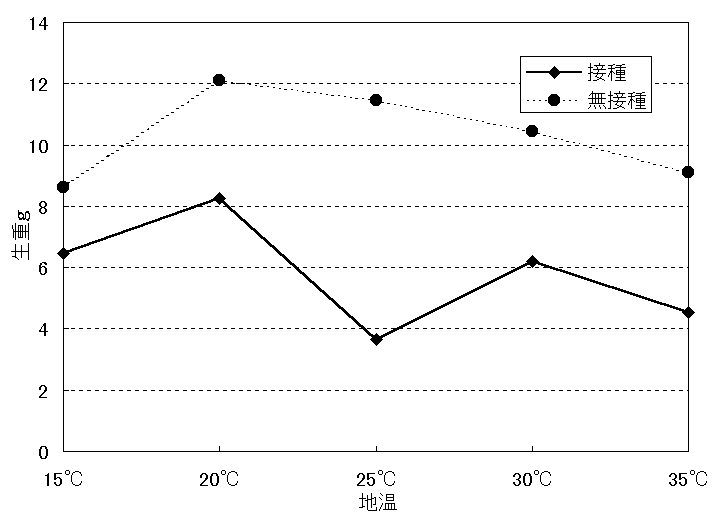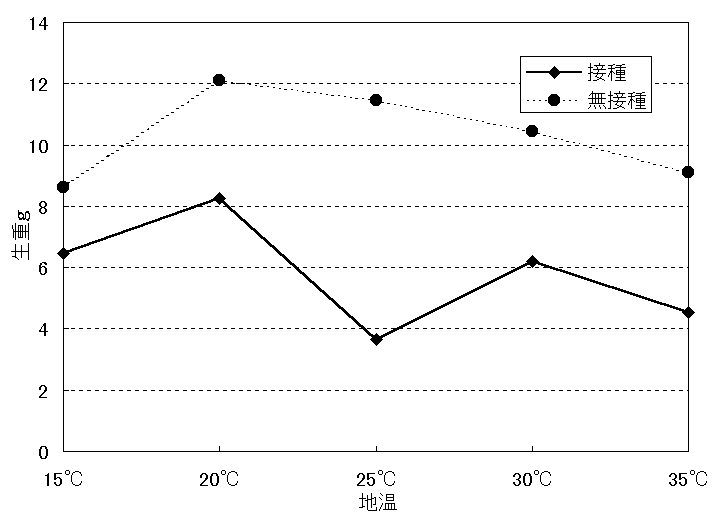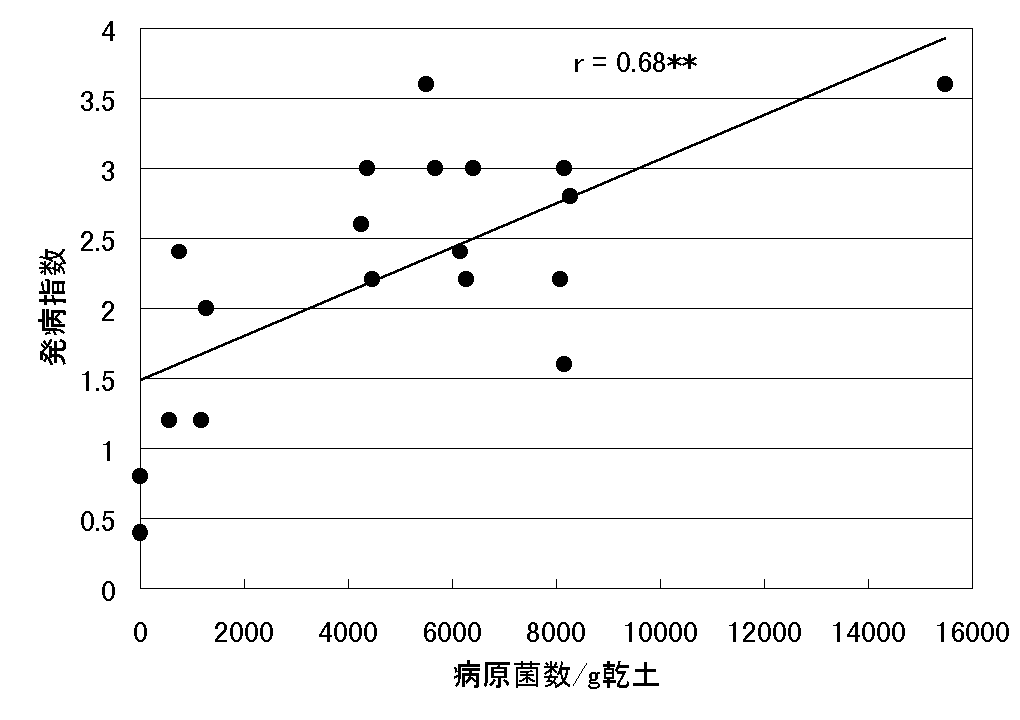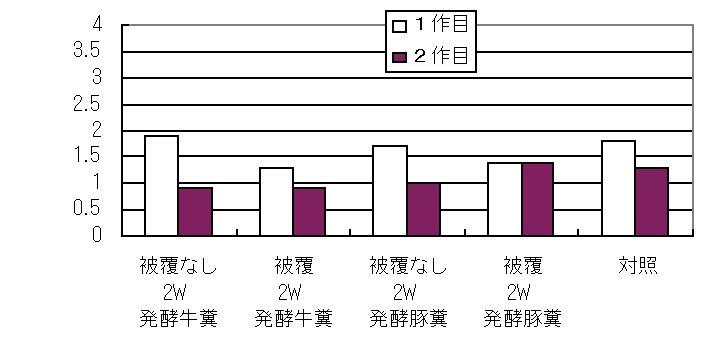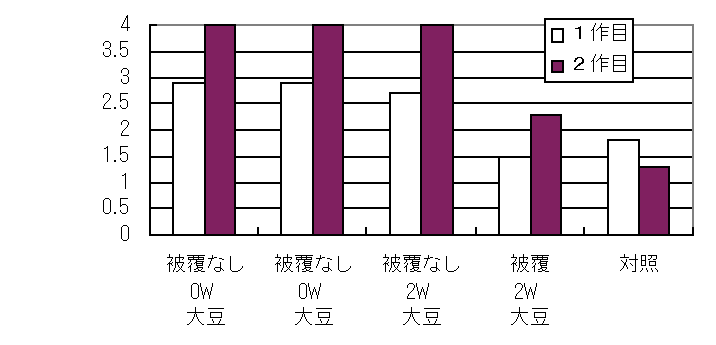成績概要書 (作成平成12年1月)
課題の分類
課題名:ねぎの根腐萎凋病の発生生態
(道南野菜の安定生産技術確立試験①軟白ネギの生産阻害要因の解明と対策)
予算区分:道費
研究期間:平9〜11年度
担当科:道南農試 研究部 病虫科
協力・分担関係: |
1.目的
根腐萎凋病の発生生態を明らかにし、防除対策に役立てる
2.方法
- 根腐萎凋病の発生地、面積、発病適温、寄生性の調査
- 根腐萎凋病の選択培地を開発および選択培地を用いたほ場診断
- 根腐萎凋病に対する品種反応および有機物、薬剤の影響
3.結果の概要
- ねぎの根腐萎凋病は1994年に発見され、1999年までに今金町、栗山町、八雲町、大野町、旭川市、門別町で発生している。殆どが施設栽培のねぎでの発生であり、栽培経歴の長い今金町では、周年利用型ハウスの約70%に発生している。
- 根腐萎凋病菌の生育適温は25℃前後であり、発病に適した温度も25℃前後であった。また、25℃以上であれば激しく発病すること、ねぎの生育は地温20℃を越えると低下することから、温度の高い夏に減収が甚だしい。
- 根腐萎凋病菌の土壌からの分離は変法駒田培地(K2HPO4:1g MgSO4・7H2O:0.5g KCl:0.5g Fe-EDTA:0.01g L-アスパラギン:2gガラクトース:20g 寒天:15g 蒸留水:1〜 45℃以下に冷えてから次の抗菌性物質を添加しpH6.0とする。ストレプトマイシン300ppm、PCNB1000ppm、クロラムフェニコール300ppm)が利用でき、菌密度を測定することができた。
- 変法駒田培地によって測定された病原菌数とねぎの発病には高い相関があり、次作のねぎの発病をある程度予測できた。また、土壌1g当たりの病原菌数が2000を越えると収量は大きく減る可能性がある。
- 根腐萎凋病菌は簡易軟白ねぎのハウス土壌においては、深耕を行わない限り、地表下30cmまで分布している。これはねぎの根系分布と一致した。
- 根腐萎凋病は、自然発病ではねぎにしか認められていないが、人工接種ではねぎ、たまねぎ、わけぎに発病が認められた。これはネギ萎凋病菌(Fusarium oxysporum f.sp.cepae)に一致するが、本病菌は乾腐症状を起こさないことから病原性は明らかに異なるため、新分化型と考えられた。
- 品種利用によって根腐萎凋病の発病を回避することは困難である。しかし、「冬扇2号」は比較的本病に強い傾向を示した。
- 有機物の施用によって根腐萎凋病の発病は軽減されなかった。また、大豆粕、魚粕などのC/N比の低い有機物は本病の発病を助長した。
- ベノミル、ヒドロキシイソキサゾール等の11薬剤の根部浸漬、土壌潅注によって本病の発病は軽減されなかった。
表1 現地発生ほ場における深さ別病原菌密度(乾土1g当たり)
|
土壌深(cm) |
今金1-1 |
今金1-2 |
今金2 |
今金3 |
栗山1-1 |
栗山1-2 |
|
0〜5 |
6870 |
10050 |
1410 |
2840 |
1870 |
3390 |
|
5〜10 |
7090 |
9950 |
1880 |
3170 |
2370 |
4410 |
|
10〜15 |
4540 |
6380 |
2000 |
2660 |
500 |
1700 |
|
15〜20 |
3590 |
3370 |
2590 |
1760 |
1120 |
3390 |
|
20〜25 |
120 |
2590 |
710 |
120 |
120 |
790 |
|
25〜30 |
0 |
120 |
710 |
0 |
0 |
910 |
|
30〜35 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
検出限界は生土1g当たり80
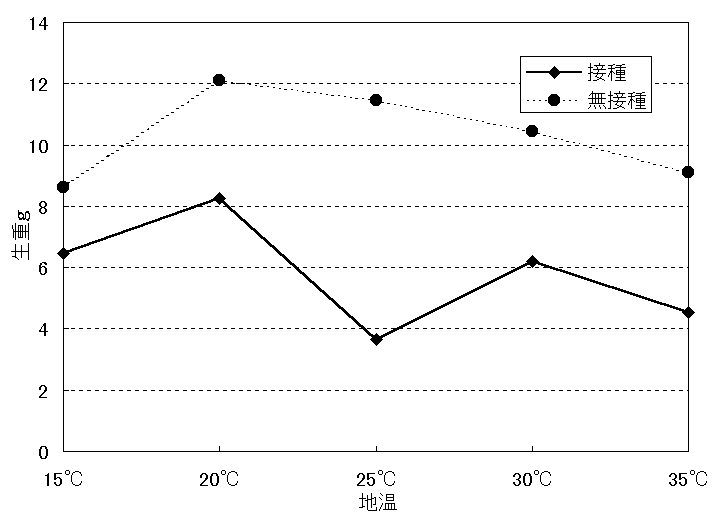
図1 地温によるねぎ生育量の違い
(根腐萎凋病菌接種および無接種土壌)
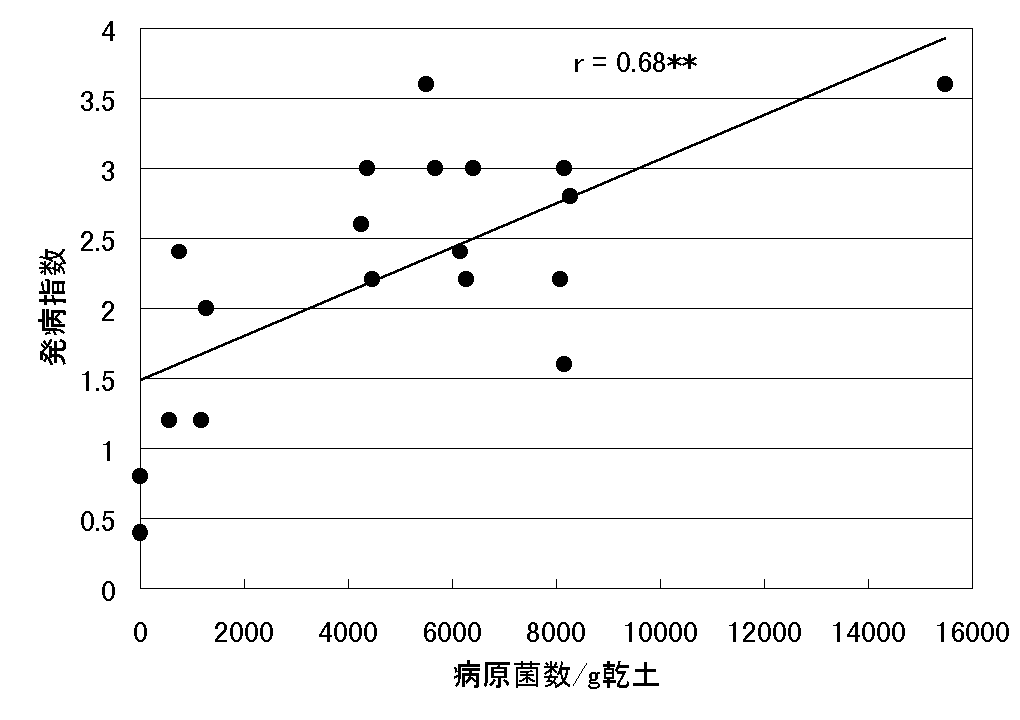
図2 現地ほ場における病原菌密度と発病の関係
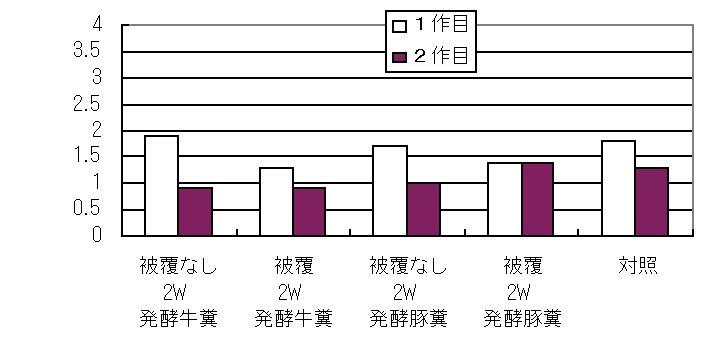
図3 十分に分解した家畜糞の施用効果
(根腐萎凋病菌接種土壌)
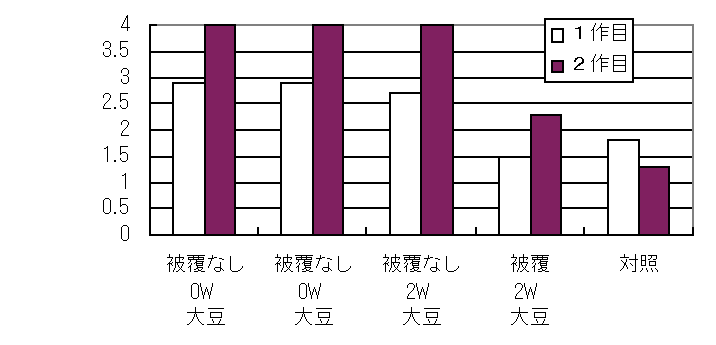
図4 C/N比の低い未分解有機物(大豆粕)の施用効果
(根腐萎凋病菌接種土壌)
* 有機物混和後日数
4.成果の活用面と留意点
1. 本成績は主に施設栽培におけるねぎの根腐萎凋病の被害軽減に活用する。
2. 防除対策としては、すでに報告した土壌消毒(還元消毒またはダゾメット剤30kg/10a)を行う。また、軽減策としては土壌塩類濃度(EC)の低下につとめる。
5.残された問題点とその対応
- 本病菌の感染、発病機構の解明
- 深い土層に対する土壌消毒技術の開発