近年、夏期に生産されるほうれんそうにおいて、切りそろえた根部切断面が黒色に変色する症状
「根部黒変症状」が発生している。本試験では、ほうれんそうの根部黒変症状の発生要因とともに
内部品質の変動を解析し本症状発生軽減のための対策技術確立をめざす。
- 発生実態調査(平成11-12年) ・アンケート調査及び土壌理化学性調査を富良野市で実施
- 発生要因解析試験(平成11-13年)
- 根部黒変症状の発生機作(平成13年) ・ポリフェノール濃度及びクロロゲン酸濃度の変動
根部黒変症状の評価は、根部切断面の黒変状況から指数化し、次式によって算出した。


・施肥試験(窒素、リン酸、塩基施用)・土壌水分(かん水)、遮光(遮光率50%)、根域制限試験
・収穫後の貯蔵温度試験 (5℃、10℃、20℃)・品種間差(品種比較試験)
- 根部黒変症状の発生は7月に集中し、発生多発時期は日照時間が少なく降水量が多かった。
- 発生圃場の液相率、易有効水分は高く土壌硬度は小さかったことから、土壌水分と根域が本症状の発生に関わっていると考えられた。
- 多肥条件(窒素、リン酸、塩基)により黒変程度は高くなり、乾物率およびビタミンCは低下した。また、根部の窒素及びリン酸含有率が黒変程度と正の相関関係にあった。
- 多かん水処理や遮光処理により黒変程度は高くなった(図1)。また、かん水処理に比べ遮光処理の影響が大きかった。
- 収穫後の貯蔵温度が高いほど黒変程度は高くなるので、収穫後速やかに予冷(5℃以下)することが根部黒変症状軽減に有効であった(図2)。
- 黒変程度には品種間差がみられ、夏期栽培の主要品種「トニック」は比較的発生しやすい品種であった。
- 黒変程度が高いほうれんそうは、根部のポリフェノール濃度・クロロゲン酸濃度が高かった。また、ポリフェノールに占めるクロロゲン酸の割合も高くなった(図3)。
- 草丈の伸長が速いものほど黒変程度が高かった(図4)。軟弱徒長化は本症状を助長した。
- 発生軽減(黒変程度10以下)のためには、乾物率を9%以上確保する必要がある。また、このことにより高品質ほうれんそう(ビタミンC指標値30mg/100g以上)生産が可能となる(図5)。
- 以上のことから、根部黒変症状の軽減対策を示した(図6)。

図1 かん水処理(pF)と遮光処理による黒変程度の変動

図2 黒変程度に対する貯蔵温度の影響
注)収穫3日後に調査
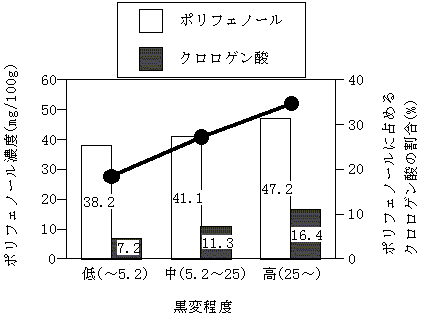
図3 黒変程度とポリフェノール濃度の関係(平成13年 場内)
サンプル点数:低 21点、中 44点、高 22点

図4 草丈伸長速度と黒変程度の関係(平成11-13年)

図5 乾物率と黒変程度、ビタミンC濃度の関係

図6 根部黒変症状の軽減対策
- 本試験の供試品種は、品種比較試験を除き「トニック」、「ふらのグリーン」である。
- 施肥量は、土壌診断を行い「北海道土壌診断基準と施肥対応(平成11年10月北海道農政部他)」を
参照して決定する。 - 品種の選定に当たっては、抽台性、収量性を考慮する。
- 予冷は、栽培期間中の他の軽減対策と組み合わせて実施する。
- 褐変抑制物質についての検討
- 根部黒変症状と萎ちょう病との関連性