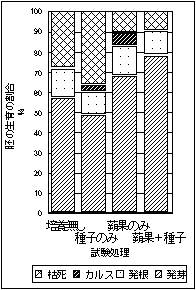

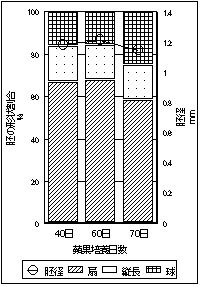
及ぼす影響
胚に及ぼす影響
及ぼす影響
成績概要書 (2003年1月作成)
| 研究課題:やまのいも育種技術の改善(やまのいも育種技術の確立と育種素材の開発) 担当部署:道立十勝農試 作物研究部 てん菜畑作園芸科、十勝農業協同組合連合会 協力分担: 予算区分:共同 研究期間:2000〜2002年度(平成12〜14年度) |
1.目的
やまのいも類の交雑育種において、労力の軽減と培養期間の短縮を目指し、交配および培養方法を検討し、効率的な育種技術を確立するとともに、品種育成のため育種素材を育成する。
2.方法
1)交配親株の栽培および交配条件の検討
(1)いちょういもにおける窒素施肥量の検討 試験処理:N施肥量3水準(2,4,6g/株)
(2)交配前後の温度条件の検討 栽培場所:平成12年2水準、平成14年3水準
2)未熟種子および胚の発育に及ぼす影響
(1)蒴果および種子培養の効果の検討
試験処理:培養なし、種子培養のみ、蒴果培養のみ、蒴果培養+種子培養
培養方法:それぞれの培地は;1/2MS培地+ショ糖7%+ゲランガム2%、pH5.7に調整
培養条件;温度25℃、照度約3000lx・16時間照明下で培養
(2)蒴果培養の開始時期の検討 試験処理:開始時期2水準(交配後20,30日)
(3)蒴果培養日数の検討 試験処理:培養日数3水準(40,60,70日間)
3)交雑実生の獲得と増殖
(1)交雑実生の獲得 供試材料:雌株;いちょういも(平成12年13系統、平成13年4系統、平成14年5系統)
(2)馴化・ポットによる栽培 試験年次:平成12年、平成13年 試験方法:胚培養後、バーミキュライトに植え付け馴化し、培養土を詰めたポットに定植した。
(3)圃場での栽培 試験年次:平成13年,平成14年 試験方法:1年間ポットで増殖を行った種イモを圃場に植え付けた。
3.成果の概要
1)交配用雌株(いちょういも)をポット栽培する場合、窒素施肥量は小花の大きさと蒴果形成率から4〜6g/株程度が良いとみられた。
2)いちょういもとながいもの交配時の温度管理は、夜温が25℃未満でも種子が十分に獲得できることから、最低気温は18℃以上に保ち、最高気温は34℃程度が必要である(表1)。
3)種子培養は省略しても、その後の胚の生育から培養の効果は十分に期待できる(図1)。
4)蒴果培養を開始する時期はその後の胚の生育から交配後30日程度が良いとみられた(図2)。
5)蒴果培養期間は胚の形状や大きさから40日以上で、蒴果および種子が褐変した時期に胚を摘出することが良いとみられた(図3)。
6)種子培養を省略することによって、交配からポット栽培までの期間を50日間短縮できる(図4)。ビニールハウスでポット栽培を行う場合は6月上旬までに幼苗を馴化・定植することにより翌年に圃場増殖出来うる種いもが得られる。
7)3ヶ年の交配、ポット栽培および圃場栽培によって交雑系統を得られた(表2)。
| 表1 交配前1週間の温度と蒴果および種子の獲得率 |
| 年次 | 処理 | 交配前1週間気温(℃) | 蒴果形成率(%) | 1蒴果種子数 | 種子獲得率(%) | ||
| 最低 | 平均 | 最高 | |||||
| 12年 | 夜間20℃ | 18.7 | 24.1 | 34.9 | 37.5 | 1.08 | 48.6 |
| 夜間25℃ | 25.2 | 29.1 | 33.9 | 47.8 | 0.94 | 50.0 | |
| 14年 | 最高34℃未満 | 19.0 | 24.3 | 33.1 | 53.6 | 0.16 | 9.9 |
| 最高34℃以上 | 21.2 | 26.4 | 35.8 | 39.3 | 0.94 | 35.2 | |
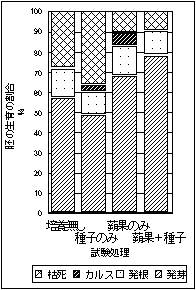 |
 |
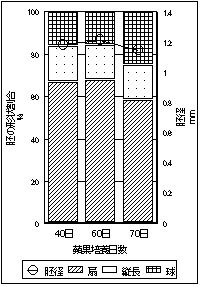 |
| 図1 培養処理が胚に 及ぼす影響 |
図2 蒴果培養開始日が 胚に及ぼす影響 |
図3 蒴果培養日数が胚に 及ぼす影響 |
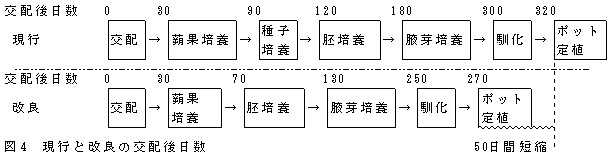
| 表2.平成14年 交雑系統の圃場栽培における収量 |
| 交配年 | 系統数 | 1系統当いも数 | 平均いも重(g) |
| 平成11年 | 32 | 4.6 | 132.6 |
| 平成12年 | 47 | 2.1 | 103.9 |
4.成果の活用面と留意点
本試験は雌株にいちょういも、雄株にながいもを用いた交雑に関する試験である。
5.残された問題とその対応
作出された交雑系統の特性評価。