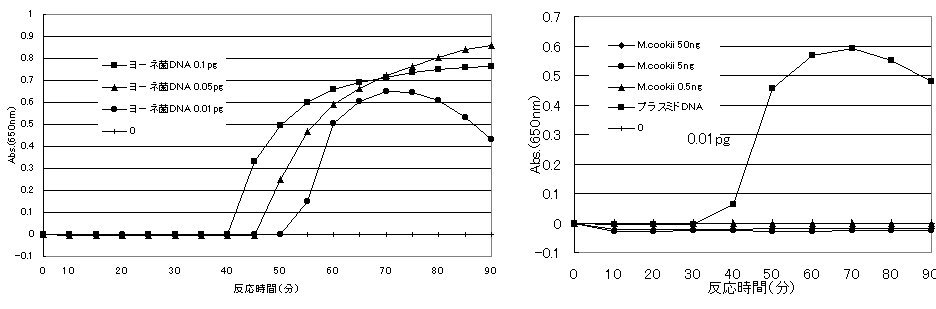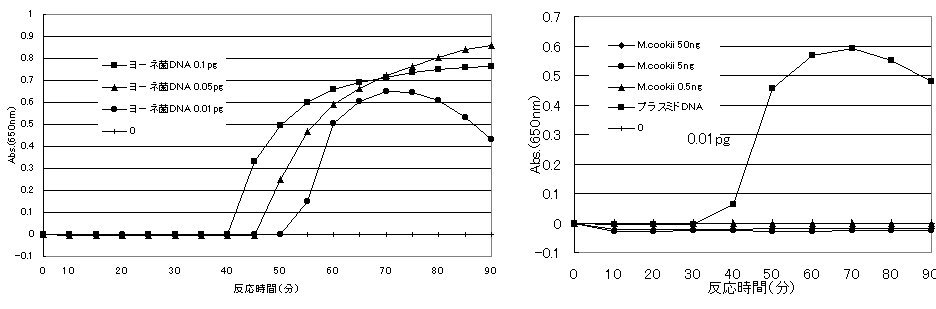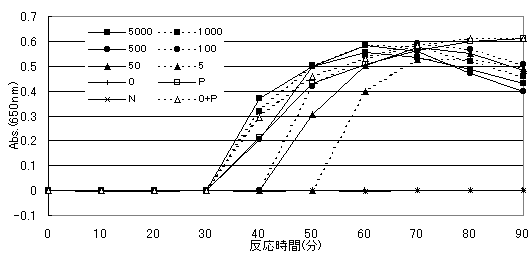成績概要書(2004年1月作成)
研究課題:LAMP法による牛糞便からのヨーネ菌遺伝子検出法の開発
(遺伝子増幅法による牛ヨーネ病迅速診断技術の確立)
担当部署:畜試 畜産工学部 遺伝子工学科、感染予防科
協力分担:(独)動物衛生研究所、栄研化学株式会社
予算区分:道費
研究期間:2001〜2003年度(平成13年〜15年度)
|
1.目的
牛ヨーネ病は、ヨーネ菌による下痢を特徴とする法定伝染病である。本病に対する有効な治療法はなく、唯一の対策は、感染牛を早期に発見して淘汰することである。現在、診断は主に糞便培養法とELISAが用いられているが、判定に長期間を要することや排菌数の少ない牛では陽性率が低いなどの欠点があり、迅速で高感度な診断法の開発が求められている。そこで、本病を早期に発見するために、LAMP法を用いて、牛糞便からヨーネ菌遺伝子を検出する方法を開発する。
2.方法
1)LAMP法によるヨーネ菌遺伝子検出法の開発
ヨーネ菌に対する特異的なLAMP用プライマーを作製して、検出効率の高い反応条件の検討を行った。
2)牛糞便からのヨーネ菌遺伝子検出法の検討
牛糞便からの核酸調製法およびDNA増幅反応阻害物質の抑制法について検討し、牛糞便からのLAMP法を用いたヨーネ菌遺伝子検出法の開発を行った。
3.成果の概要
1)−(1) ヨーネ菌特異的配列IS900、hspXおよびF57を増幅するLAMP用プライマーを合計173セット作製した中から、良好な反応を示すプライマーセットPrimer1およびPrimer2を選択した。
1)−(2) それぞれのプライマーセットを用いてLAMP法における反応の条件およびヨーネ菌の検出感度を検討したところ、Primer1は90分以内にヨーネ菌DNA1pgまで検出し、Primer2は120分以内に5pgまで検出した。
1)−(3) 9菌種42株のヨーネ菌類似菌を用いて特異性を検討したところ、Primer1は類似菌1種2株で反応がみられた。Primer2は全ての菌株で反応がみられなかったが、その後に報告された類似菌M.cookii
str2333において反応がみられた。
1)−(4) Primer2を改変して作製したPrimer3は、供試した全ての類似菌で反応がみられず、検出感度が反応時間90分間でヨーネ菌DNA0.01pgと高かった(図1)ことから、ヨーネ菌遺伝子検出に適しているLAMP用プライマーと考えられ、以下の検討に用いた。
2)−(1) ノンフェノールビーズ法と熱抽出法を比較したところ、熱抽出法と比べて、ノンフェノールビーズ法の核酸抽出効率が高かった。
2)−(2) 反応阻害物質の作用を抑制するAmpdirect○R添加の有無による検出率の違いを検討したところ、添加していない反応液は糞便培養法陽性7試料のうち5試料検出したのに対して、添加した反応液は全て検出した(表1)。
2)−(3) 培養したヨーネ菌を添加した牛糞便希釈液からヨーネ菌DNAが5cfu/mlまで検出できた(図2)。
2)−(4) 牛糞便166試料中、糞便培養法陽性9試料についてLAMP法は全て検出し、nested
PCR法は4試料を検出した。培養法陰性157試料については、LAMP法は26試料、nested
PCR法は8試料を検出した(表2)。
以上のとおり、ヨーネ菌に特異的なLAMP用プライマーを作製し、LAMP法による牛糞便からのヨーネ菌遺伝子検出の基礎的条件を確立した。
表1 Ampdirect○R添加の有無による検出率の相違 (検出数/反応回数)
| 試料 |
コロニー数 |
Ampdirect®
添加 |
無添加
(標準液) |
| A |
1 |
2/8 |
1/8 |
| B |
1 |
2/8 |
0/8 |
| C |
2 |
6/8 |
0/8 |
| D |
2 |
8/8 |
4/8 |
| E |
3 |
2/8 |
1/8 |
| F |
4 |
6/8 |
5/8 |
| G |
14 |
7/8 |
6/8 |
| H |
0 |
0/8 |
0/8 |
表2 LAMP法、糞便培養法およびnestedPCR法の比較
| 糞便培養法 |
LAMP法
(検出数) |
nestedPCR法
(検出数) |
| 陽性(9) |
9 |
4 |
| 陰性(157) |
26 |
8 |
( )は試料数
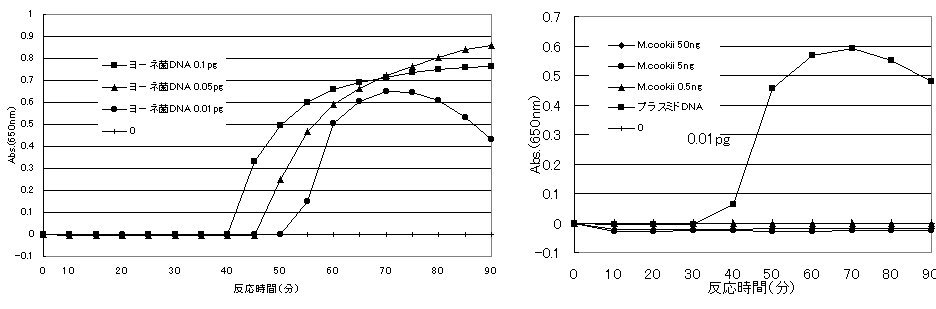
図1 Primer 3のヨーネ菌遺伝子検出感度(A)と特異性(B)
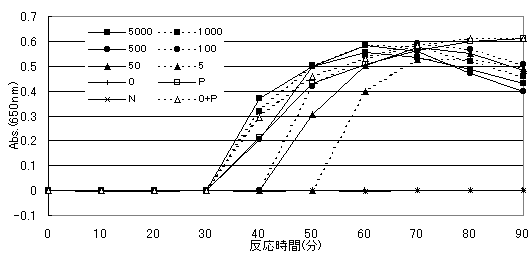
図2 牛糞便希釈液に添加したヨーネ菌の検出 (単位cfu/ml)
P:ヨーネ菌DNA200pg(4×104cfu) N:蒸留水
0+P:牛糞便由来DNAにヨーネ菌DNAを添加した反応系
4.成果の活用面と留意点
本技術は「ヨーネ菌検出用プライマーおよびこれを用いたヨーネ病の診断法」として特許出願中である。(特願2003-159573)
5.残された問題点とその対応
糞便材料を用いた本法の精度の検討、実用化に向けた多検体処理方法の検討が残されており、平成16年度からの試験研究課題の中で検討していく。
また、農水省の診断予防技術向上対策事業において、本法の試験調査が実施されることとなった。