成績概要書 (2006年1月作成)
|
研究課題:土壌消毒における蒸気消毒機の利用指針 担当部署:中央農業試験場 生産システム部 機械科、クリーン農業部 総合防除科 |
1. 目的
土壌条件別に土中温度の上昇過程および処理温度(60℃)および処理温度継続時間(10分)に達した土壌中の線虫および土壌病原菌の消長を明らかにし、消毒効果の不安定要因の特定とその対策および留意事項の提示を目的とした。
2. 試験方法
(1) 蒸気消毒機性能試験:供試機(ATA500)の燃料消費量、使用電力、使用水量およびシート敷設設置作業時間を検討した。
(2) ベンチ試験:3種類の土壌(砂土、砂壌土、壌土)を供試し、①キャンバスホースの距離別(深度40cm)、②土壌タイプ別(深度40cm)、③高水分土壌 (深度30cm) の温度上昇を検討
した。
【測定項目】外気温度、ハウス内温度、土中温度、土壌水分(含水率)および土壌三相
(3) 現地試験:A町(砂土)およびB町(砂壌土)ハウス農家において、処理温度および処理温度継続時間に達した土壌中の線虫および土壌病原菌の消長等の解明、消毒効果の不安定
要因の特定とその対策および留意事項を検討した。
【測定項目】外気温度、ハウス内温度、土中温度、土壌水分、土壌三相、総Fusarium菌数、サツマイモネコブセンチュウ数、交換性マンガン
(4) 経済性評価:A町の農家ハウスの実態解析調査を行い、蒸気消毒機の利用経費を検討した。
3. 結果の概要
(1) ロータリ砕土後の膨軟化した作土層の蒸気処理時の温度上昇は、粘土の含有量の多い土壌に比べ砂の含有量が多い土壌の方が速かった(図1)。土性タイプに関わらず、膨土化
した作土層下層部の土壌水分が約20%以上の場合、特に下層部の昇温が遅延し、土壌水分が23%〜24%(手で握ると形がつく程度の土壌)以上になると殺線虫および土壌殺菌の基
準温度である60℃まで上昇しなかった。
(2) 蒸気消毒終了の目安として温度測定する位置は、蒸気消毒機から最遠部、ハウスの際側の膨土層最深部であった。良好な土壌水分の土壌を対象とした蒸気消毒によるの処理
時間は、有機質土混じり砂を作土(土壌水分:約22.0%、ロータリハロー耕起深40cm)とした場合、おおむね20〜21時間程度(図2)、火山灰質砂を作土(土壌水分19.8%、ロータリハロー
耕起深25cm)とした場合、おおむね8〜9時間程度であった。
(3) 排水処理対策が不十分なハウスではハウスの周辺より雨水が地下浸透し、膨土層下部の土壌水分(25.6%〜28.5%)が上昇した場合は、土壌殺菌の基準温度である60℃まで上昇
しなかったことから、排水対策が必要である。(図3、4、5)。
(4) 設定温度60℃、設定温度維持継続時間10分における、サツマイモネコブ線虫およびFusarium菌の死滅が確認された(表1)。さらに、トマトの1年2期作の作型では、最短で1年2作目
までは褐色根腐病およびサツマイモネコブセンチュウに対する効果が持続するものと考えられる。
(5) 蒸気消毒機の初期投資として3890千円要するものの、光熱費は300m2あたり77千円/年であった(表2)。いったん、土壌病害による被害が発生すると、土壌病害の経済的な被害
は多大となることから(表3)、土壌病害の発生が認められるもしくは可能性の高いハウス経営において、蒸気消毒法の活用は有効と考える。
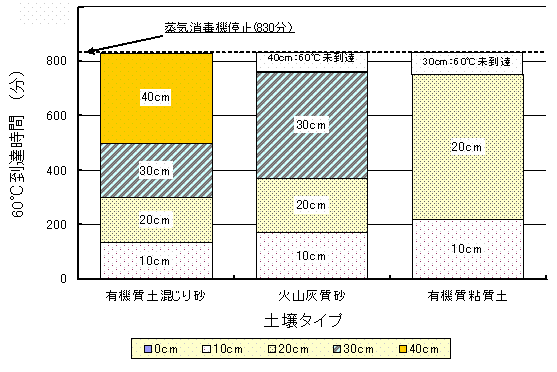
図1 土壌タイプ別の熱前線(60℃)
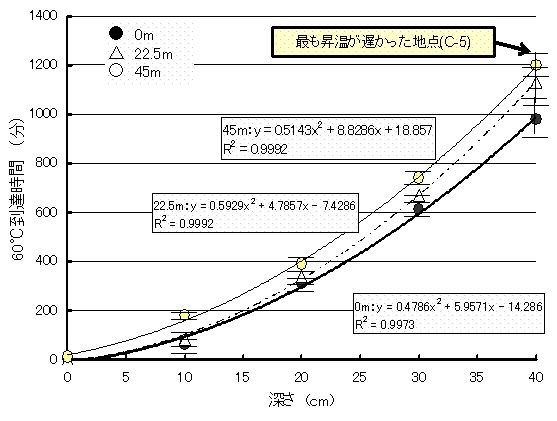
図2 距離別目標温度到達時間(A町、土壌水分16.2%(0cm)〜22.0%(40cm))
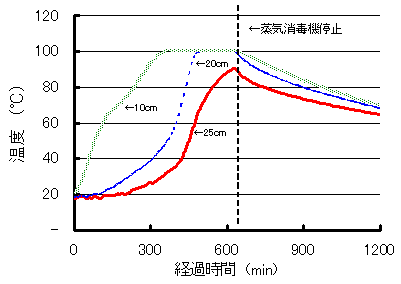
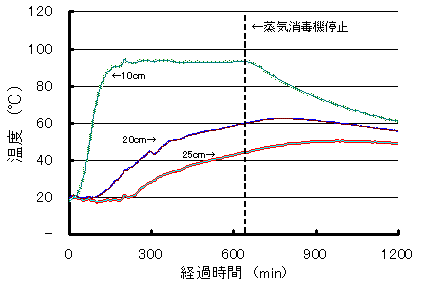
(土壌水分19.8%、B町) (土壌水分28.5%、B町)
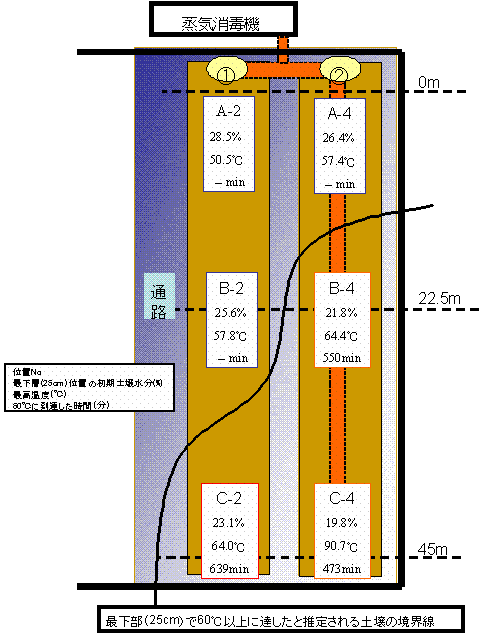
図5 滞水による膨土層25cm位置の
土壌水分、最高温度、60℃到達時間
表1 トマト栽培ハウス土壌における蒸気消毒の効果(消毒直後および2作目:A町)
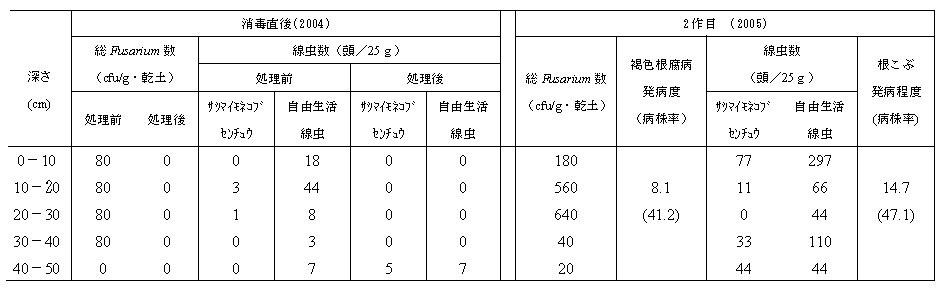
表2 蒸気消毒機の導入・利用費用
| 導入・利用費用 | 光熱費 | 使用量 | 費用 | ||
| 本体価格1) | 3635千円 | 燃料費4) | 1281L | 77091円 | |
| キャンパスホース等2) | 255千円 | 電気料金5) | 1.5KW | 406円 | |
| 計 | 4085千円 | 計 | 77467円 (77千円) |
||
| 減価償却費3) | 735千円/年 | ||||
表3 A町、A経営における土壌病害発生ハウスの収量
| 5年前 | 4年前 | 3年前 | ||||
| 1作目 | 2作目 | 1作目 | 2作目 | 1作目 | 2作目 | |
| 収量(kg/300㎡) | 2300 | 2300 | 1840 | 1610 | 0 | 2300 |
| 減収量(kg/300㎡)1) | 0 | 0 | 460 | 690 | 2300 | 0 |
| 減収率(%) | 0 | 02) | 20 | 30 | 100 | 0 |
| 被害額(円/300㎡)3) | 0 | 0 | 133400 | 200100 | 667000 | 0 |
4. 成果の活用面と留意点
(1) 蒸気消毒に当たっては消毒を要する土壌深さまで十分にロータリ砕土・膨軟にし、膨土層全体に蒸気が行き渡るようにする。
(2) 地下水位が高いか、ハウス内に雨水が浸入する場合は、ハウス周囲に側溝を掘るなど排水対策を施す。
(3) 蒸気消毒後、作付品目によってマンガン過剰症などによる生育障害が危惧されるハウスでは必要に応じて土壌診断を実施する。
(4) 蒸気消毒後の土壌は有機物が消耗しやすいので、完熟堆肥などの有機物の施用など地力の維持に努める。
(5) 蒸気消毒機の導入の際、生産部会等による共同所有等、機械所有のあり方に配慮する。
5. 残された問題点とその対応
(1) 簡易で省力的な断熱シートの設置法の検討
(2) 蒸気消毒機の自動停止タイマーの活用