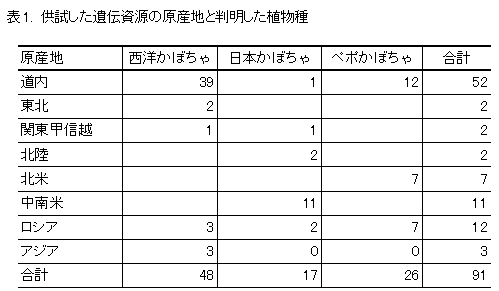
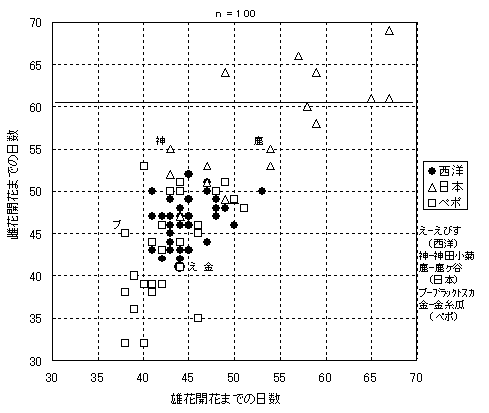
図1. 雄花開花までの日数と雌花開花までの日数の分布(2006年)
成績概要書(2007年1月作成)
| 研究課題:かぼちゃ遺伝資源の特性情報 (大豆遺伝資源の子実成分と主要作物遺伝資源の特性調査) 担当部署:中央農試 遺伝資源部 資源貯蔵科 |
1.目的
植物遺伝資源センターが収集した遺伝資源のうちかぼちゃについて、1次特性等を明らかにするとともに特性情報をデータベース化することにより、保存遺伝資源情報の充実を図り、遺伝資源の利活用のための資料とする。
2.方法
(1)供試材料:収集遺伝資源 91点
比較品種 11点(「えびす」,「こふき」,「神田小菊」,「ブラックトスカ」他)
(2)栽培概要:露地マルチ栽培 播種5月下旬〜6月下旬、定植6月上旬〜7月上旬
栽植距離 0.9m×4.0m、施肥量 N:P2O5:K2O=7:20:10(kg/10a)、全量基肥。
(親蔓+子蔓)2本整枝(株間0.9m)、放任(わい性タイプ)(株間0.9m)
(年次により一部の区は親蔓1本整枝、株間0.45m)。 1区1〜4株、反復なし。
(3) 調査項目:草姿、雄花開花始期、雌花開花始期、雌花着生節位、葉の大きさ、葉の形、葉柄の長さ、葉の斑紋、葉の形、蔓長、果実重量、果形、果皮色、果皮の状態、果肉の質、
食味等(農業生物資源研究所編 植物遺伝資源特性調査マニュアル野菜編に準拠)。
3.成果の概要
(1)収集遺伝資源91点について各種形質を調査し、茎葉および果実の形質から、植物種を西洋かぼちゃ48点、日本かぼちゃ17点、ペポかぼちゃ26点に分類した(表1)。
(2)雄花開花までの日数と雌花開花までの日数の分布を調べたところ、日本かぼちゃの中には8月中旬以降の短日条件下でないと雌花が着生開花せず、道内での栽培には不適と考え
られるものが7点あった(図1)。
(3)平均果実重量の階級別頻度分布をとると、各年次ともに1.5〜2.5kgのレンジを中心とする分布の山が見られ、これと離れて4.5kg以上のレンジに数点が分布した。1kg未満のレンジは
ペポかぼちゃが占めた(図2)。
(4)果肉の乾物率については、ペポかぼちゃは低いものが多く、西洋かぼちゃは比較的高かった。日本かぼちゃは両者の中間であった。
(5)西洋かぼちゃ48点の中から22点の硬外皮型遺伝資源(「まさかりかぼちゃ」)を見出した。これらの中には粉質で乾物率が高い遺伝資源が数点見られた。また硬外皮型ではないが、
肉質・食味に優れる遺伝資源が数点見られた。
(6)日本かぼちゃの中では、8点が雌花が安定的に着生・結実し、道内での栽培が可能と思われた。その中の2点は、果実が巨大であり肉質が繊維質でサラダ用等の用途に利用可能で
あると思われた。
また道外原産で食味が良好な遺伝資源が2点あった。
(7)ペポかぼちゃは遺伝資源として各形質の幅が非常に広く、小果のおもちゃかぼちゃ型からズッキーニ型、スキャロープ型、そうめん型、大果型等があった。草姿はわい性、わい性とつ
る性の中間、つる性の3タイプがあった。
(8)果実の外部形質および果肉の質・食味等から、植物種別に利用用途を想定し、12のグループに分類した(表2)。
(9)植物種別に、特長のある形質を有し利用が期待される有望な遺伝資源9点を抽出した(表3)。
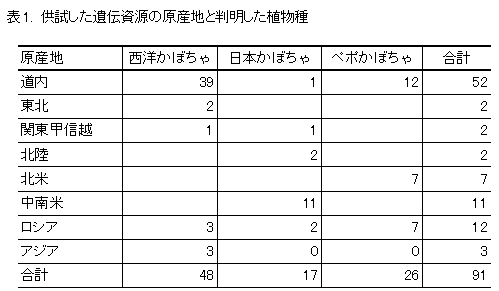 |
あああああ | 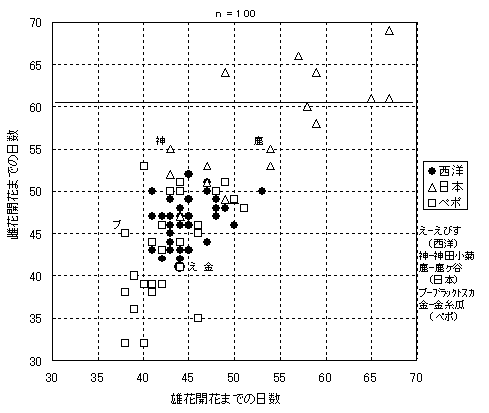 図1. 雄花開花までの日数と雌花開花までの日数の分布(2006年) |
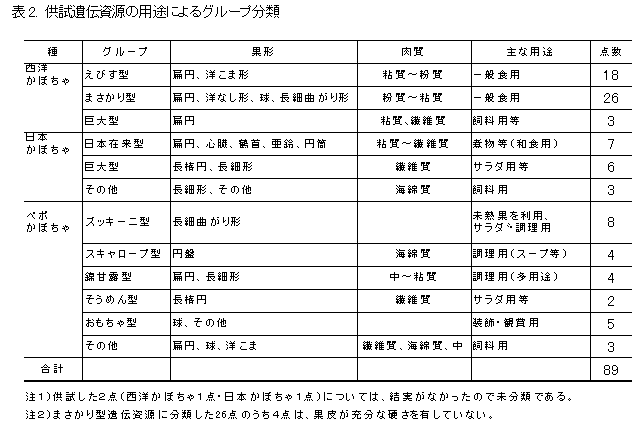 |
ああ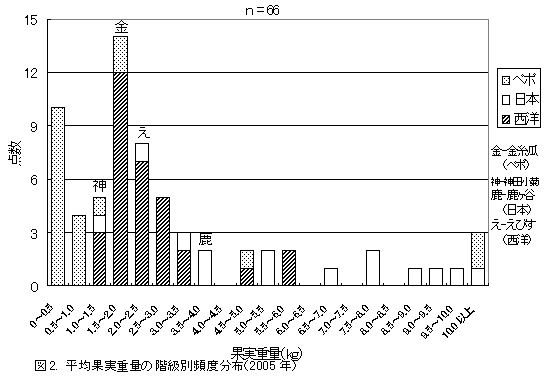 あ あ |
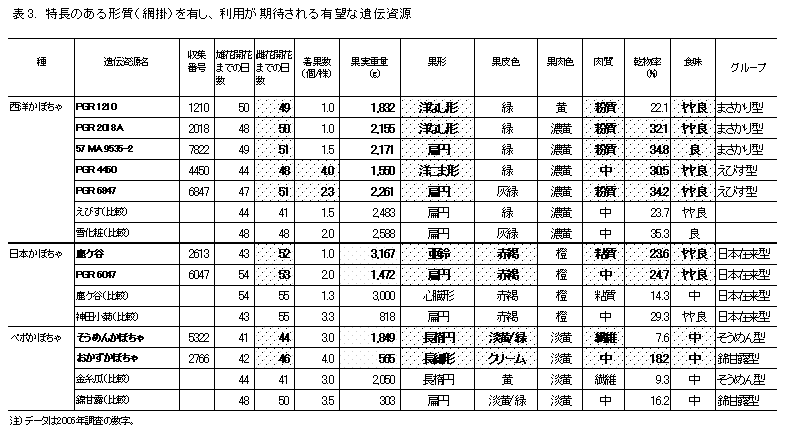
4.成果の活用面と留意点
1)本成績の個々の調査データは別途、データベースとして道内の野菜関係試験研究機関等に提供する。
2)利用にあたっては、いずれの遺伝資源も一定程度、形質の変異の幅(分離)を含有することに留意する。
5.残された問題点と留意点
1)短日花成性が強く、採種が困難な遺伝資源の増殖。