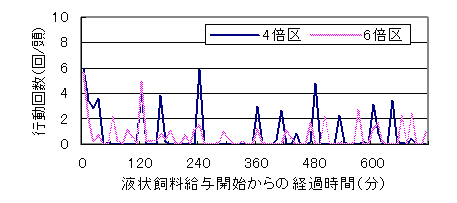
図1 液状飼料給与開始から12時間の採食行動の推移
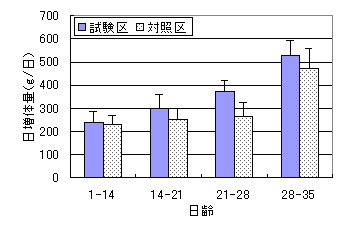
図2 液状飼料を給与した14日齢離乳子豚の日増体量
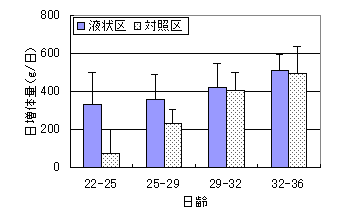
図3 液状飼料を給与した22日齢離乳子豚の日増体量
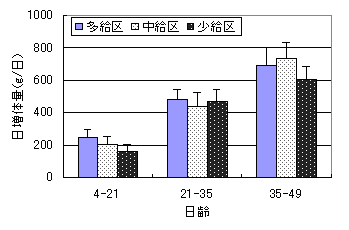
図4 液状飼料を給与した4日齢離乳子豚の日増体量
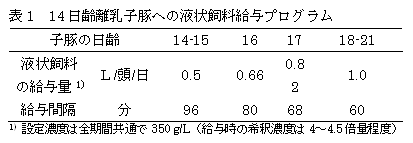
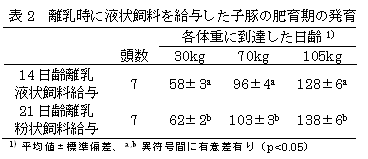
表3 22日齢離乳子豚への液状飼料給与プログラム
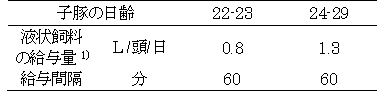
成績概要書(2007年1月作成)
|
課題分類: 担当部署:道立畜試 家畜生産部 中小家畜育種科 |
1.目 的
離乳直後の子豚では一時的な発育停滞がよく観察され、生産性を低下させる一因となっている。また人工哺育は、授乳母豚に事故が発生し、かつ里親が確保できない場合に実施されるが、代用乳を用いるためコストが高いという問題がある。そこで、粉状飼料を液状化して頻回給与することができる液状飼料給与装置を用いて、離乳後の発育停滞改善技術および安価な人工乳による人工哺育技術を検討した。
2.方 法
1) 液状飼料給与装置を用いた離乳後の発育停滞の改善技術
(1) 14日齢離乳子豚における液状飼料給与技術の検討
①給与濃度、②液状飼料の摂取量、③液状飼料給与による発育改善効果
(2) 22日齢離乳子豚への液状飼料給与効果の確認
2) 人工乳の液状化給与による2〜5日齢離乳子豚の育成技術
①液状飼料給与開始日齢、②4〜21日齢における液状飼料の摂取量
3.成果の概要
1)-(1)-① 14日齢離乳子豚では、希釈濃度を6倍量程度とするより4倍量程度として給与液量を低減する方が、液状飼料給与開始時の残食が少なく採食行動が活発となった(図1)。
1)-(1)-② 14日齢離乳子豚の液状飼料摂取量は、19日齢まで直線的に増加し(最大摂取量1.0 kg/頭/日)、14〜21日齢での日増体量は313±102 g/日であった。この結果をもとに、希釈
濃度を4倍量程度とした14日齢離乳子豚への給与プログラムを作成した(表1)。
1)-(1)-③ 14日齢で離乳して14日間液状飼料を給与した子豚は、21日齢で離乳して粉状飼料を給与した子豚と比べて14〜35日齢の日増体量が有意に高く、離乳後の発育停滞が認めら
れなかった(図2)。その結果、21日齢で離乳した子豚よりも30kg到達日齢が約4日、肥育終了時(105kg到達)の日齢が約10日短縮された(表2)。
1)-(2) 22日齢で離乳し液状飼料を給与した子豚は、同時期に離乳して粉状飼料を給与した子豚に比べ22〜25、25〜29日齢の日増体量が有意に高く(図3)、離乳後の発育停滞が認めら
れなかった。22日齢離乳子豚への液状飼料給与プログラムは、14日齢離乳子豚のプログラムを変更することで対応が可能であった(表3)。
2)-(1) 3〜4日齢で離乳した子豚では液状飼料への馴致に問題はなかったが、2日齢離乳子豚では採食開始までに時間がかかる傾向があった。
2)-(2) 4日齢離乳子豚において、液状飼料の最大給与量を1.5(多給区)、1.2(中給区)、0.9(少給区) L/頭/日とした3水準の中で、液状飼料の摂取量が最大1.5 L/頭/日であった場合に、
4〜21日齢での日増体量が246±49 g/日に達した(図4)。この結果をもとにして、希釈濃度を6倍量とした給与プログラムを作成した(表4)。人工乳を用いた液状飼料の給与によっ
て、4日齢で離乳を行っても21日齢の体重を6kg程度にまで高発育させることが可能であり、従来の代用乳を用いた人工哺育より低コストであった。
以上から、液状飼料給与装置による液状飼料の頻回給与は、14および22日齢で離乳した子豚の発育を改善し、また4日齢で離乳した子豚を21日齢で6kg程度に発育させることが可能であった。
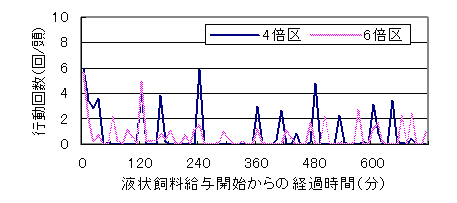 図1 液状飼料給与開始から12時間の採食行動の推移 |
ああああああ | 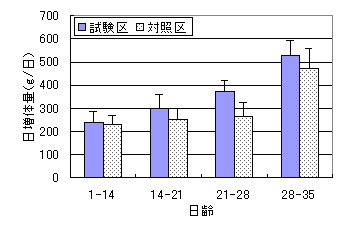 図2 液状飼料を給与した14日齢離乳子豚の日増体量
|
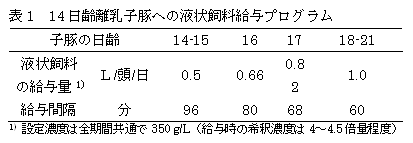
|
||
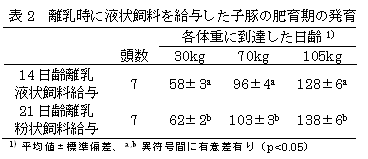
|
||
|
表3 22日齢離乳子豚への液状飼料給与プログラム |
4.成果の活用面と留意点
1)本試験で用いた装置には1回に給与する液状飼料の最低量が設けられており、本試験結果で作成した給与プログラムを適用するには、4日齢では15頭以上、14日齢および21日齢では
11頭以上を1群とするように留意する。また飼槽の頭口数は1群の頭数以上とする。
2)子豚の採食を促すには液状飼料の残食が無い状態が重要であり、そのために1日に3回は採食の状況を確認し、残食を確認した場合はすぐに廃棄すること。
3)本試験はSPF環境下で実施した。
5.残された問題とその対応
本装置により飼養した豚の肥育成績と枝肉成績の検討