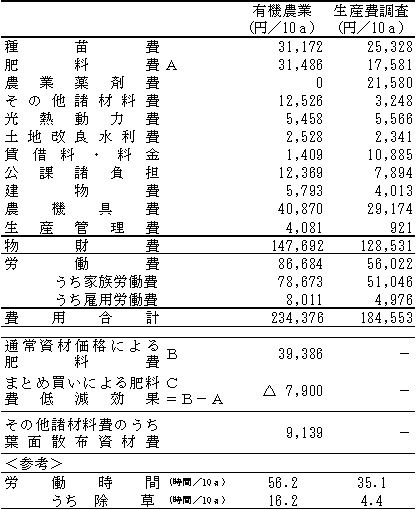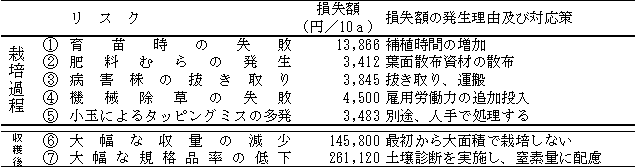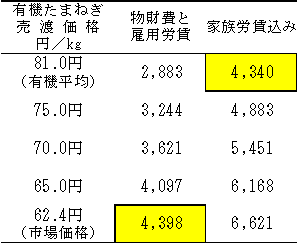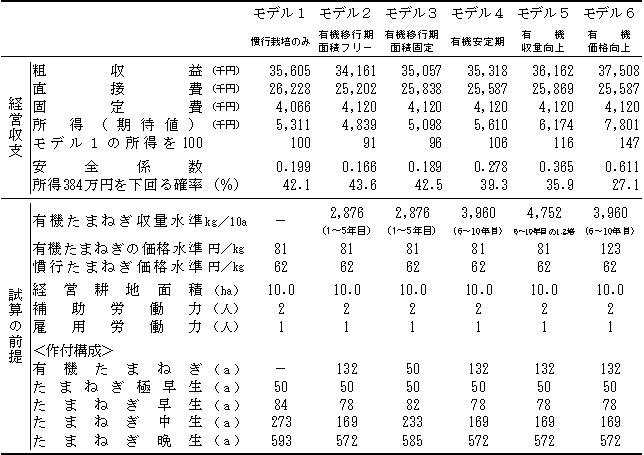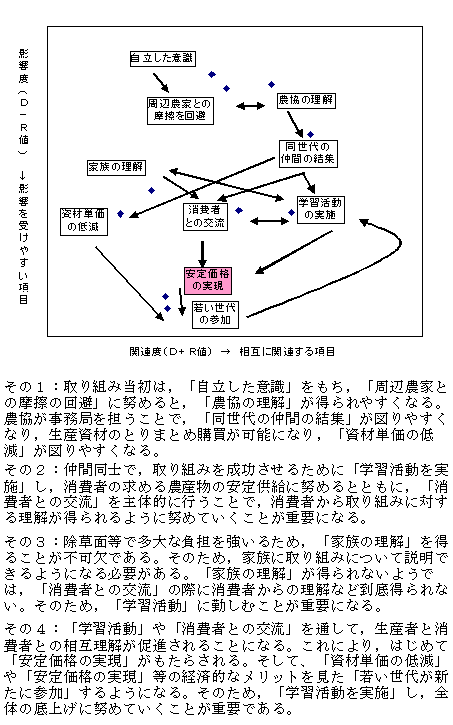成績概要書(2007年1月作成)
|
研究課題:たまねぎ有機農業の導入による経営安定化方策
(有機農業の経営的な成立要因の解明)
担当部署:中央農試 生産研究部 経営科
予算区分:道費(事業)
研究期間:2004年〜2006年度(平成16〜18年度)
|
1.目 的
消費者の安全志向の高まりを背景に、有機農業を試みる経営が増加する事態が予想される。そのため、経済的な視点から有機農業の成立条件を整理し、有機農業の導入による経営安定化方策を提案する。
2.方 法
1)たまねぎ有機農業の生産費調査と損益分岐点販売量の解明(網走管内A産地)
2)数理計画法による経営モデルの分析(確率的計画法によるリスク評価)
3)DEMATEL法(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory)による産地作りのポイントの整理
3.成果の概要
1)有機たまねぎの生産に要した費用から以下を指摘できる(表1)。①肥料費は、発酵鶏ふん等の有機物を多量に施用することから、上昇していた。ただし、農協を窓口に有機物を大量にまとめて購入することで、購入単価を低減させていた。②農業薬剤費は、化学合成農薬を使用しないため生じていなかった。ただし、植物活性を図る目的で葉面散布資材を使用するため、諸材料費が上昇している他、除草剤を使用しないことから、除草時間が増加していた。③農機具費は、収穫以降の衛生面に配慮し、有機専用のコンテナを保有するため上昇していた。④公課諸負担は、JASの認定・検査等に伴い上昇していた。⑤生産管理費は、研修会等の参加費用を反映して上昇していた。⑥労働費は、慣行栽培の4倍となる除草作業を始めとした労働時間の増加に伴い上昇していた。以上を反映して、たまねぎ有機農業の費用は、通常の水準を1.3倍程度上回っていた。
2)A産地では、技術の移行期でもある取り組み当初に多大な損失を被る事態に遭遇してきた(表2)。そのような経験を踏まえて、経営間で栽培技術の情報交換や土壌診断を実施し適切な施肥を行う等、有機農業に伴うリスクの軽減に努めるとともに、新たに取り組む経営に対して当初から大面積で栽培をしないように指導することで、リスクの緩和を図っていた。同時に、有機たまねぎの取引価格を市場価格よりも高水準に安定化させることで、収益の変動を縮小させていた。
3)有機たまねぎの平均的な価格水準(81.0円/kg)であるならば、4,340kg/10aの販売量を確保できると家族労賃を含む生産費を補填することが可能になる(表3)。一方、平均的な市場価格(62.4円/kg)では、4,398kg/10aの販売量を確保しないと、物財費と雇用労賃を購えないことが判明した。そのため、新たにたまねぎの有機農業に取り組む際には、価格下落のリスクを考慮して最低限4,400kg/10a以上の販売量を実現し、物財費と雇用労賃を補填するとともに、所得形成に向けて更なる収量と販売価格の向上に努める必要がある。その際、販売量の向上策として、消費者との交流を通じた規格の緩和を図ることで、製品歩留りを高めることが有効になる。
4)A産地の実態に基づく経営モデルの分析から以下を指摘できる(表4)。①有機農業の導入初期は、大幅な減収に直面することも多く、有機農業の導入による所得増加は実現しにくい。そのため、小面積の栽培に留めて技術の形成を図ることが、減収のリスクを緩和することになる。②経営内で技術を確立させ、生産性を安定させると、有機農業の導入による所得増効果が明瞭になり、経営の安定性が高まる。また、③更なる収量や販売価格の向上に努めることは、所得の増加と経営の安定化に貢献することになる。その際、市場価格の変動に影響されない取引関係を形成することが、経営の安定化をもたらす条件となる。
5)A産地では、有機農業に対して組織的に取り組むことで、資材価格の低減や安定価格の実現といった経済的な効果をもたらしていた。有機農業の導入による経営の安定化には、図1に示された経路に従い、産地形成による組織的な対応を採ることが有効である。
|
表1 有機農業の費用(たまねぎ) 単位:円/10a
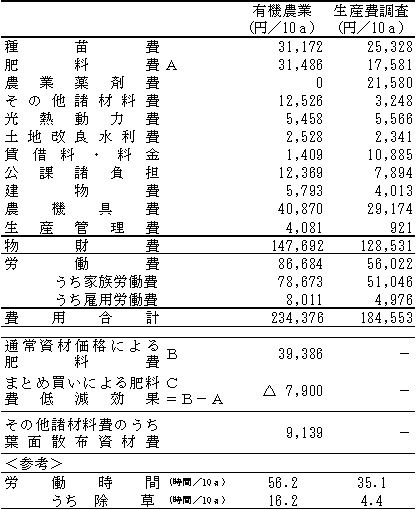
注1)生産費調査:たまねぎコスト削減検討会議の調査北見地区の値
注2)通常資材価格は、農業物価統計における有機物の価格に従った。
注3)生産費調査欄の労働時間は、実態調査の値を示している。
|
表2 有機農業のリスク(たまねぎ)
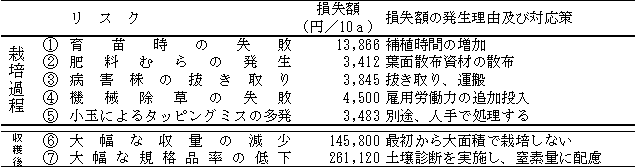
表3 価格水準ごとにみた損益分岐点となる販売量
単位:kg/10a
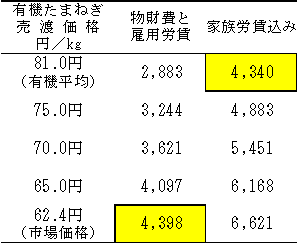
注1)有機たまねぎの平均販売価格:81.0円/kg
「北海道における有機農業の実態調査報告書」
注2)市場価格:62.4円/kg
(北海道農林水産統計年報(2000年〜04年平均))
注3)1kg出荷するのに要す費用:27円/kg
|
表4 たまねぎ有機農業導入の経営モデル
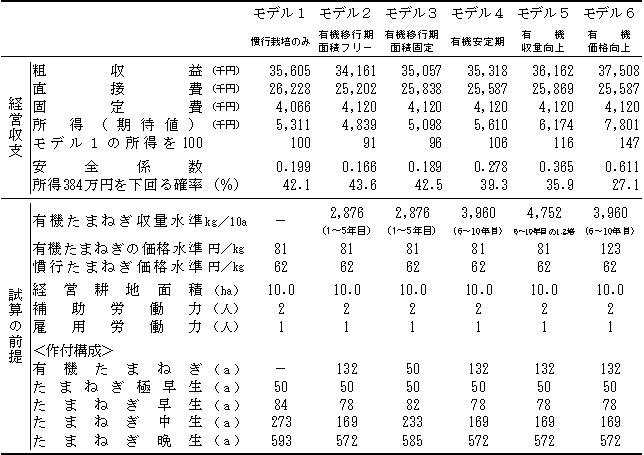
注1)試算は、micro-NAPS with WINE97(南石)を用いた。
注2)収益の変動(確率計算)は、A産地の実態に基づいた。
注3)所得は、期待値(平均値から試算)を示した。
注4)安全係数は、正規分布表のυの値を意味する。
注5)農業所得384万円は、「北海道農業経営基盤強化促進基本方針」による。 |
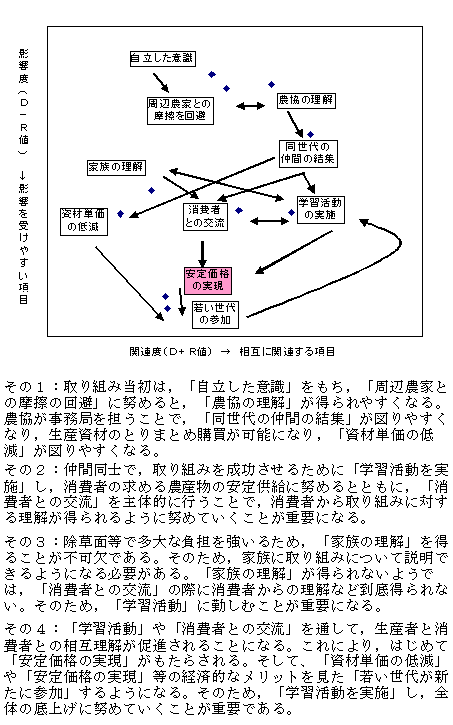
図1 有機農業の産地作りのポイント
注)プロットと矢印は、DEMATEL法により求められた。
|
4.成果の活用面と留意点
1)損益分岐点となる販売量は、網走管内A産地の実態に基づいて算出した。
2)たまねぎ経営における有機農業の導入場面で活用する。
3)環境保全型農業の産地作りの場面で役立てる。
5.残された問題とその対応
10ha未満の小規模経営を対象とした経営モデルは、新規課題で対応する。