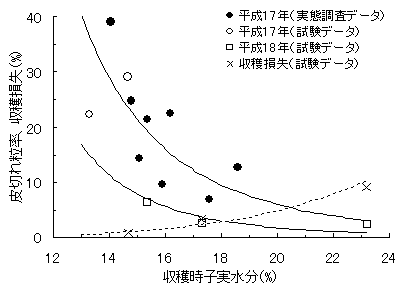
図1 黒大豆の収穫時子実水分と皮切れ粒率、
収穫損失の関係(晩生光黒)
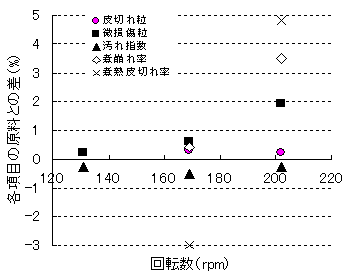
図3 横軸式研磨機の回転数と損傷粒発生程度、
汚れ指数の関係(H17 大正金時)
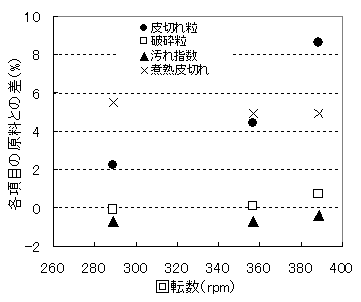
図2 横軸式研磨機の回転数と損傷粒発生程度、
汚れ指数の関係(H17 中生光黒)

図4 ヤスリ研磨した小豆の吸水性
(縦軸式研磨機、「エリモショウズ」)
成績概要書(2007年1月作成)
|
研究課題 : 豆類の損傷粒発生要因の解明と小豆の吸水性向上技術 |
1.目的
黒大豆、金時では煮豆用途で問題となる皮切れ粒の発生が多く、小豆では未吸水豆の低減が必要である。本試験では収穫時と調製工程における黒大豆および金時の損傷粒発生要因の解明とその対策、調製工程で利用される研磨機を利用した小豆の吸水性改善技術の開発を目的とした。
2.方法
1)黒大豆および金時の損傷粒発生要因の解明
試験内容:コンバイン収穫時の黒大豆子実水分と損傷粒との関係調査、調製施設における黒大豆の損傷粒発生調査、研磨機(横軸式:MK-KW、縦軸式:PF-91)の回転数と黒大豆お
よび金時の損傷粒発生程度の関係を調査した。
2)研磨による小豆の吸水性向上技術
試験内容:研磨機の種類(横軸式:MK-KW、縦軸式:PF-91)、回転数、研磨材の種類と損傷程度、汚れ除去程度、品質・加工適性(吸水特性、煮熟特性、官能評価、貯蔵性、実需評
価)を調査した。
3.成果の概要
1)黒大豆のコンバイン収穫において、収穫時の子実水分が低下すると皮切れ粒の発生が増加する傾向が認められた(図1)。年次間差や圃場間差、茎水分と汚粒との関係については
検討が不十分であるが、皮切れ粒の発生程度や収穫損失を考慮すると、黒大豆の損傷粒発生低減のためには子実水分が18〜20%になったら速やかに収穫することが重要である。
2)現地調査の結果、調製工程では黒大豆の皮切れ粒は磨き工程で発生することが明らかとなった。道内の多くの調製施設で利用されている横軸式研磨機では、回転数の増加により明
らかに皮切れ粒が多く発生した(図2)。汚れの除去程度と回転数に関係が認められなかったことから、横軸式研磨機による研磨ではメーカ推奨回転数より20%程度減速して使用する。
ただし、この条件でも皮切れ粒が発生する場合もあることから、黒大豆の損傷粒発生低減のためには、汚れ指数が1を超え落等の要因となる場合を除き、できる限り横軸式研磨機で
の研磨を行わないことが望ましい。
3)金時では、道内の多くの調製施設で利用されている横軸・縦軸式研磨機ともに研磨による皮切れ粒の発生は僅かであったが、回転数の増加により煮熟後の煮崩れ・皮切れが増加し
た(図3)。汚れ指数の低下程度と回転数に関係は認められなかった。これらのことから、金時類の研磨では研磨機の回転数はメーカ推奨回転で使用し、汚れ除去を目的に回転数を
増加させない。
4)縦軸式研磨機のロータに耐水研磨紙(ヤスリ)を貼って研磨することにより、汚れ除去と同時に小豆の吸水性を向上することができる。ヤスリ研磨により、小豆表面に微細な傷が形成
されることから、種瘤部のみならず種子表面から吸水する。このため、吸水時間が短縮し、煮ムラが小さくなる(図4)。未吸水小豆を対象にヤスリ研磨をすると、全ての粒が吸水するよ
うになり、未処理と比較して煮熟増加比が大きく、あん滓率が小さくなる。なお、ヤスリ研磨した小豆の表面傷が農産物検査で格下げ要因となることは無かった。ヤスリ研磨では、吸水
性や皮切れの発生等を考慮すると研磨紙の種類はJIS規格の100番程度、処理回数は3回程度が望ましい。
5)ヤスリ研磨した小豆の煮熟特性や貯蔵性、あんの食味官能評価が慣行の皮革研磨した小豆と比較して劣ることは無かった。実需評価でもヤスリ研磨した小豆は煮ムラが小さく、皮が
軟らかく、炊きやすいとの評価を得た(表1)。
以上の成果は豆類の低損傷化および調製工程における研磨機の効果的な活用法として有効である。
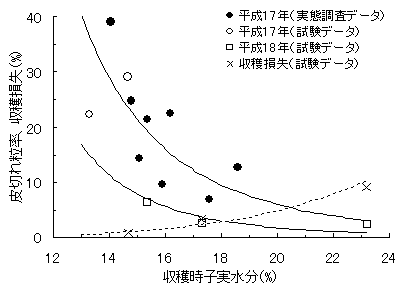 図1 黒大豆の収穫時子実水分と皮切れ粒率、 収穫損失の関係(晩生光黒)
|
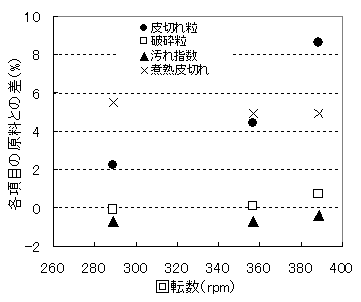 図2 横軸式研磨機の回転数と損傷粒発生程度、 汚れ指数の関係(H17 中生光黒)
|
表1 ヤスリ研磨した小豆の加工業者による製あん評価
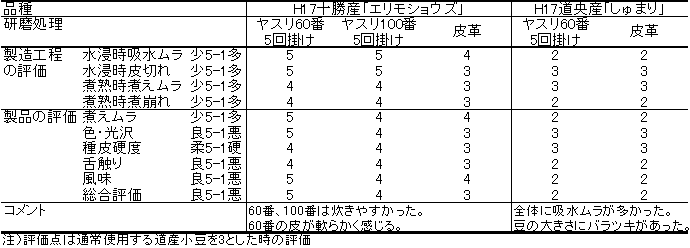
4.成果の活用面と留意点
1)研磨機に関する成果は横軸および縦軸式研磨機を利用する豆類乾燥調製施設等で活用する。
2)ヤスリ研磨した小豆は、煮熟後の皮切れが増加することがあるため、加工用途に応じて利用することが望ましい。
3)黒大豆の収穫に関しては「晩生光黒」を対象にして得られた結果である。
5.残された問題とその対応
1)黒大豆の皮切れ粒を発生させない研磨方式、研磨材の検討
2)黒大豆のコンバイン収穫適期判断基準の策定