| 研究課題:小豆における生育期別耐冷性の評価並びに遺伝資源の選定 (小豆の高度耐冷性育種素材の選定) (小豆の高度耐冷性品種の開発促進) 担当部署:十勝農試 作物研究部 小豆菜豆科 協力分担: 予算区分:道費(豆基) 研究期間:2002〜2007年度(平成14〜19年度) |
1.目的
小豆の低温による障害のうち、出芽直後からの長期低温少照による生育停止、枯死に対する耐冷性(以下、出芽直後からの耐冷性)について遺伝資源の選定及び基準品種の設定を行う。また、低温による開花・着莢障害に対する耐冷性(以下、開花・着莢障害耐冷性)について、極晩生遺伝資源から既存の耐冷性品種以上の遺伝資源を選定する。
2.方法
1)出芽直後からの耐冷性遺伝資源の選定(2002〜2004年)
(1)耐冷性評価方法の確立(2002、2003年)
「アカネダイナゴン」、「斑小粒系-1」等32点を供試し、低温遮光処理(夜10〜昼13℃、70%遮光)を4週間行った後、10日間の緑化処理(夜18〜昼28℃、自然日射)を行い、障害(枯死、カップリング)個体数、初生葉の葉色を調査する。
(2)耐冷性遺伝資源の選定(2002〜2004年)
年間32〜50点供試し、(1)の方法により、耐冷性遺伝資源を選定する。
2)開花・着莢障害耐冷性遺伝資源の選定(2002〜2007年)
(1)極晩生遺伝資源の短日処理条件及び耐冷性評価方法の検討(2002〜2004年)
短日感光性が異なると考えられる遺伝資源を供試し、短日処理期間、開始時期、処理日長を変えて、開花期がある程度揃い、健全な花が得られる条件を検討する。さらに、低温遮光処理(夜10〜昼15℃、50%遮光、7日間)後の開花数及び着莢数を調査する。
(2)耐冷性遺伝資源の選定(2005〜2007年)
(1)で開発された手法を用い、極晩生の遺伝資源等を年間約50点供試し、耐冷性遺伝資源を選定する。有望な遺伝資源の低温遮光処理後の受粉数を調査する。
3.成果の概要
1)出芽直後からの耐冷性について、4週間の低温遮光処理、引き続き10日間の緑化処理を行い、障害個体率及び初生葉の葉色を用いて、「アカネダイナゴン」を“強”、「斑小粒系-1」を“弱”の標準として相対的に耐冷性を評価する方法を確立した(図1)。
2)出芽直後からの耐冷性について「アカネダイナゴン」、「とよみ大納言」、「北海道在7」、「十育136号」の4点を“強”と評価した。さらに、3ケ年の累年結果より基準品種を暫定的に設定した(表1)。
3)極晩生の遺伝資源の開花・着莢障害耐冷性を検定するための短日処理方法を開発するとともに(図2)、低温遮光処理後の開花数、着莢率による評価基準を設定した。
4)極晩生の遺伝資源の中から、「斑小粒系-1」よりも開花・着莢障害耐冷性が強い遺伝資源として“強”の「Acc2265」1点、“やや強”の「Acc2266」等12点を選定した(表2)。「Acc2265」は、低温遮光処理後、正常に受粉する花の比率が高かった(図3)。
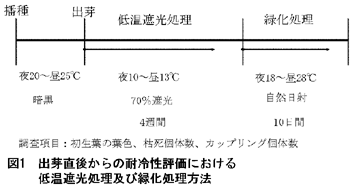
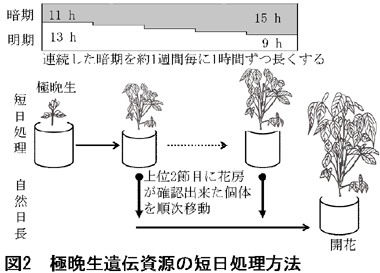
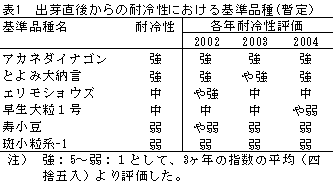 |
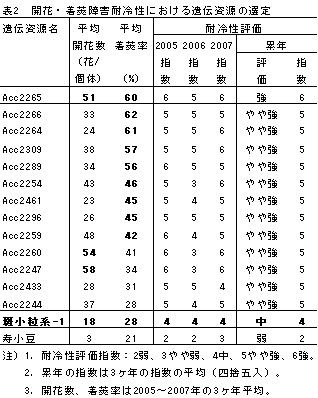 |
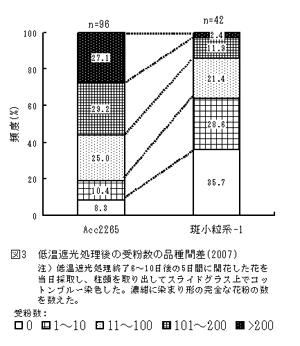 |
4.成果の活用面と留意点
1)開発した出芽直後からの耐冷性及び開花・着莢障害耐冷性の評価方法は、遺伝資源の選定、育種材料の選抜、特性検定に利用できる。
2)出芽直後からの耐冷性及び開花・着莢障害耐冷性遺伝資源が選定され、交配母本として利用できる。
5.残された問題とその対応
開花前の生育初期の低温による短茎化に対する耐冷性について、遺伝資源の評価手法の確立が必要であり、2008年度より始める新規課題「新規遺伝資源利用による小豆の高度耐冷性品種の開発強化」で検討する。