| 研究課題:たまねぎの直播栽培技術 (たまねぎコスト削減生産技術の実証と組立) 担当部署:北見農試 作物研究部 畑作園芸科、花・野菜技術センター 研究部 野菜科、花・野菜技術センター 技術体系化チーム 予算区分:受託 研究期間:2003〜2007年度(平成15〜19年度) |
たまねぎ直播栽培の実用化に向けた栽培技術確立のため、移植栽培と比較しながらその生産性を検証する。これにより、低価格が強く求められる加工・業務需要に対応できるような低コスト生産を実現するとともに、規模拡大や新規作付けを検討している生産者に対して、たまねぎ栽培導入に際しての新たな選択肢を提供する。
2.方 法
1.適品種の選定:16〜19年、極早生〜晩生品種まで12品種を供試
2.窒素施肥量の検討:16、17、19年、品種数7、窒素施用量7水準(0、5、10、12.5、15、20、30㎏/10a)
3.播種時期の検討:16〜19年、品種数10、播種日の設定:4月18日〜5月16日
4.栽植密度の検討:17〜19年、品種数4、栽植密度の設定:24690〜39216株/10a
5.べたがけ被覆の効果確認:18〜19年、品種数7
6.移植栽培との比較による直播栽培の生産性評価:16〜19年、品種数8、北見農試圃場において標準耕種法による両栽培試験区を比較
7.現地実証試験(網走管内):19年、試験実施場所数6
3.成果の概要
1)収量性及び品質の面から「北もみじ2000」等の中生品種が有望であった。「北もみじ2000」では、北見農試 及び花・野菜技術センターでの4ヶ年、計11試験の平均で規格内収量は5600㎏/10aとなり、春まき移植栽培の基準収量である5500㎏/10aを上回った(表1)。晩生品種ではさらに球肥大は進むが、地域や年次により内部品質が低下したり、倒伏期に至らない場合があった。
2)北見農試低地土圃場における窒素用量試験の結果では、施肥量は10〜12㎏/10aでも充分であった(図1)。直 播栽培における施肥量は移植栽培に準じ、土壌診断に基づく施肥対応を行う。
3)播種日が遅くなるほど収穫時の球重は低下した。4月下旬〜5月中旬の間では、播種が一日遅れるごとに収量 が約1.5%ずつ減少した(図2)。
4)播種は、4月中旬以降になり圃場が適正な土壌水分になった時点でできるだけ早く行い、4月中には終わらせることが望ましい。播種日が5月15日を過ぎると、倒伏に至らない株や腐敗球の発生が多くなる場合があったことから、播種限界は5月10日とする(図2)。
5)株間を狭くすることで栽植密度を高めた場合、平均球重は低下するものの収量は増加する。現在の移植栽培 における平均的な栽植株数である30000株/10aに対して、直播栽培では欠株による減収も見込んで栽植密度を 35000株/10a程度とする(図3)。
6)べたがけ資材の被覆により出芽期は3日程度早まるが、必ずしも増収にはつながらなかった(表2)。
7)現在、道内で多く作付けされているF1品種であれば、移植栽培と比較して直播栽培での変形球発生が多くなることはなかった。根切り時期は、品種の早晩に応じて移植栽培における基準を遵守する(表3)。
8)北見農試圃場における比較では、直播栽培での球肥大は移植栽培に優る場合もあるが、欠株や多雨年での肌腐れ症状等の影響により、4ヶ年平均での規格内収量は移植栽培に対して約20%の減収となった。しかし、「北 もみじ2000」の直播栽培区における総収量は6400㎏/10a、規格内収量は6000㎏/10aであり、産地への普及が可能な収量水準を達成することはできた(表3)。
9)網走管内の農家圃場6ヶ所での現地試験では、欠株率の平均は6.5%であり出芽は比較的良好であったが、全 般的に土壌が硬く締まる傾向があり、球肥大はやや劣った。2ヶ所の圃場で変形球が多発したこともあり、規格内収量の平均は4200㎏/10aとなり、基準収量である5500㎏/10aを下回る結果となった(データ省略)。
10)腐植含量が少ない砂質土壌や排水不良な粘質土壌では降雨の影響で土壌表面が硬化し、出芽率低下や初期 生育不良により低収となる場合があった(現地実証試験、表1の16年・花野及び18年・北見低地土)。直播栽培では移植栽培よりも土壌環境の影響を受けやすいことが想定され、腐植含量が多く、透・排水性に優れた圃場の選定が重要となる。
11)本試験での成果から、たまねぎの直播栽培技術体系を提案する(表4)。
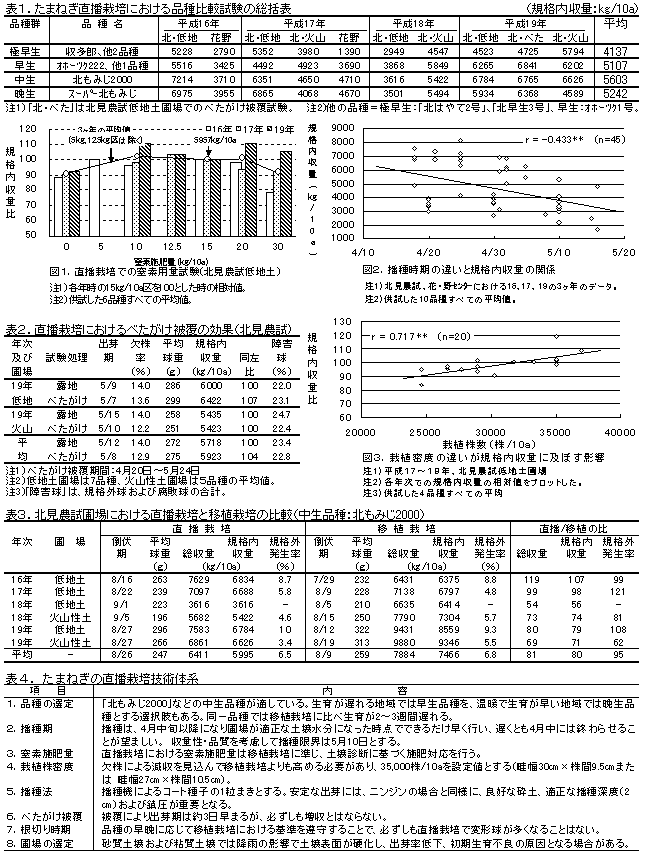
4.成果の活用面と留意点
1)たまねぎの直播栽培を導入するにあたっての技術資料とする。
2)本課題での直播栽培における除草剤(土壌処理剤)の登録拡大試験により、平19年にペンディメタリン乳剤が登録された。
3)たまねぎ直播栽培では、出芽が不安定となる砂質土壌及び粘質土壌での栽培をできる限り避ける。
4)直播栽培では、移植栽培に比べて生育が2〜3週間遅れるため、8月以降の病害虫防除に留意する。
5.残された問題点とその対応
1)現地事例で変形球が多く発生する要因の解明 2)本成果に基づく直播栽培技術の総合実証