| 研究課題:生体捕獲したエゾシカの一時飼育管理および産肉特性 (エゾシカ飼養の実態基礎調査) 担当部署:畜試 家畜研究部 中小家畜飼養科、釧路家保、根室家保、釧路農改セ、東京農大 協力分担:東京農大短期大、釧路短大、道立オホーツク食加技 予算区分:環境生活部事業(エゾシカ有効活用推進事業) 研究期間:2006〜2007年度(平成18〜19年度) |
生体捕獲からと畜・解体・肉販売まで行っている道内2カ所の飼育場においてエゾシカの一時飼育実態を調査するとともに、飼養試験およびシカ肉の特性調査を通して、エゾシカ一時飼育のための基礎資料とする。
2.方法
1)一時飼育実態調査(A飼育場;釧路支庁管内、導入実績1,178頭 B飼育場;根室支庁管内、導入実績293頭)
2)一時飼育における飼料摂取量と増体量の性別および年齢別差異
3)一時飼育エゾシカ肉の季節による成分変化と食味官能検査
4)一時飼育エゾシカ肉の加工特性
3.成果の概要
1)一時飼育実態調査
1)-(1) 両飼育場ともほぼ同型でシュート状の導入(出荷)施設を設置していた。フェンスは鹿用で高さ280cmであった。出荷スペースのフェンスには激突を避けるためにビニールシートを覆っていた。給餌施設は牛用を利用していたが、濃厚飼料用飼槽の前面には採食競合を防ぐため頭だけが入る幅の格子を取り付けていた(写真1、2)。
1)-(2)導入された個体の約6割は雌鹿であった。
1)-(3)濃厚飼料は両飼育場とも市販の圧ぺん大麦、圧ぺんメイズ、ビートパルプを給与していた。粗飼料には一部放牧草に加え、近郊農家から購入の乾草(ロール)、低水分ラップサイレージを用いていた。B飼育場ではでん粉粕を与えていた。
1)-(4)飼料給与量は、A飼育場が874gDM/日、B飼育場が1,120gDM/日であり、濃厚飼料の占める割合はそれぞれ9割および7割と高かった(図1、2)。A飼育場では裸地化が進み、小径木に樹皮食いが観察された。
1)-(5)A飼育場における飼育期間中の増体量は、1歳鹿が2歳以上より、雄鹿が雌より高かった(表1)。
1)-(6)輸送時および導入時にへい死した個体の死因は主に事故死、骨折であった。フェンスの下を約10cm埋設することで野犬の被害を防ぐことができた。飼育期間中で多かった死因は衰弱および骨折であった。
1)-(7)寄生虫検査では肝蛭および一般線虫の寄生が認められた。小型ピロプラズマはA飼育場で検出されたが、B飼育場では検出されなかった。
1)-(8)と畜体重に対する可食肉量の割合は雄雌間に差は示されなかった。しかし、飼育場間ではB飼育場が7ポイントほど高い値を示した。部分肉ではモモの割合が最も高かった(表2、図3)。
2)一時飼育における飼料摂取量と増体量の性別および年齢別差異
2)-(1)約8ヶ月間の飼育期間における増体量は性より年齢に大きく影響を受けた。したがって、肉量を重視する場合は2歳以上が、飼育で高い増体量を求める場合は1歳が有利と推察された。
3)一時飼育エゾシカの肉成分変化と食味官能検査
3)-(1)雄鹿の肉成分の季節変化では、粗タンパク質および粗灰分含量は季節に関わらず一定であった。粗脂肪含量は6月から9月にかけて穏やかに減少し10月に増加する傾向がみられたが、期間平均では2.0%と極めて少なかった。
3)-(2)食味官能検査では、「総合的な好ましさ」において雄雌および年齢間に有意差は見いだせなかった。
4)一時飼育エゾシカ肉の加工特性
4)-(1)総色素量は乳用種経産牛と大差なかった。また、脂肪の融点は43.8℃で乳用種経産牛より約6℃高かった。
【まとめ】
一時飼育における要点は、1)適正な飼料給与 2)圃場副産物等の利用による飼料費の節減 3)個体観察(元気,食欲、糞等)による異常の早期発見 4)給水施設の設置による肝蛭感染防止 5)エゾシカ衛生処理マニュアルの遵守(平成18年10月・北海道) 6)低品質部位(ウデ、スネ等)の加工技術開発 に整理される。
 |
←ビニールシート |  |
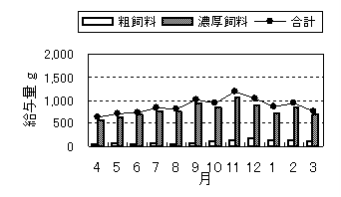
図1.A飼育場の飼料給与量
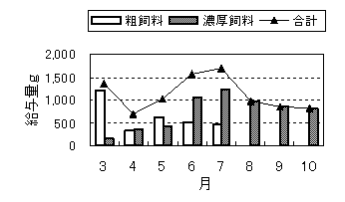
図2. B飼育場の飼料給与量
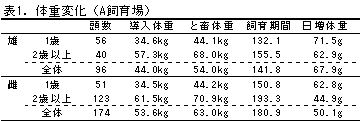
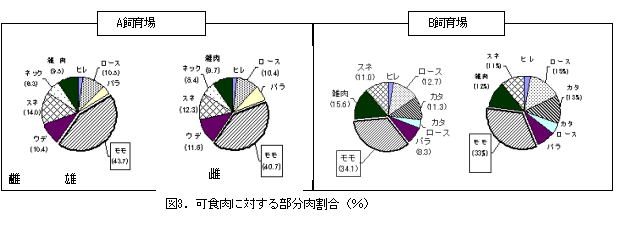
4.成果の活用と留意点
1)本成績は、現在稼働中のA飼育場およびB飼育場について調査したものであり、濃厚飼料主体の給与体系で飼育されている。
5.残された問題とその対応