| 研究課題:乳牛における周産期病低減のためのモニタリングと現地実証 (乳牛における周産期病低減の現地実証) 担当部署:畜試 技術体系化チーム(技術普及部、基盤研究部 病態生理科) 予算区分:農政部事業(革新的農業技術導入促進事業) 研究期間:2006〜2007年度(平成18〜19年度) |
農場ごとの乳牛の周産期病発症に係わる牛群モニタリング手法を検討するとともに、既存の予防法を的確に導入することによる周産期病低減効果を実証する。
2. 方 法
1) 腹囲形状のモニタリングによる周産期病の発生予測
2) 活動量のモニタリングによる乾乳牛の行動把握
3) 乾乳後期に給与する飼料の成分および物理性と周産期病発生との関係
4) 初乳比重のモニタリングと周産期病の発生
5) 飼槽の高さと飼料摂取量との関係
6) 乾乳期の飼養管理改善による周産期病低減効果の実証
3. 成果の概要
1)乳牛のルーメン膨満度を表す指標として腹囲形状(図1)を考案し、乾乳後期の腹囲形状とその後の周産期病発生との関係を5農場で調べたところ、各形状の間で周産期病発生率に差が見られ、 “ボックス形”の腹囲形状を呈する牛では周産期病の発生率が高かった(表1)。腹囲形状は周産期病の発生リスクをモニタリングする指標として有用であると考えられた。
2)周産期病の発生が少ないA農場において、乾乳牛に活動量計を装着し、区画移動に伴う1日の行動量、ならびに行動の日内変動パターンを検討したところ、周産期病を発症した牛では1日の行動パターンが一定しない傾向が見られ、正常牛に見られた規則的な行動ができない状況に陥っている可能性があることが示唆された(図2)。
3)乾乳後期にTMR方式で飼料を給与している5農場において、乾乳後期飼料の成分と物理性を調べたところ、飼料設計値と分析値の差が大きい農場、あるいは飼料片サイズの変動が大きい農場(B、I)が見られた。これらの農場では周産期病が多発していたことから、設計したとおり適正に飼料が調製されているかどうかを評価することは、周産期病を低減するための重要なモニタリング項目の一つであると考えられた(表2)。
4)分娩後の飼養管理が良好な農場では、初乳比重が高い母牛の周産期病発生率は低くなることから、初乳比重の高低による周産期病発生率の違いは分娩後の飼養管理が適切であるかどうかを評価する手段として有用である可能性が示唆された(表3)。
5)分娩予定の1〜2週前から、飼槽底面の高さを2水準(H群:45cmおよびL群:5cm)設定し、飼料摂取量を比較したところ、H群の平均摂取量はL群のそれに比べて多かったことから、飼槽底面の高さは飼料摂取量に影響することが示唆された(表4)。
6)周産期病の発生率が高い3農場(フリーストール飼養)において、乾乳期(前期・後期)および産褥期の群分け、休息スペース確保、ならびに飼料設計の見直し(分析値に基づきCP・TDN等の適正化、ミネラル添加)を中心に改善を実施したところ、周産期病の発生率低減が実証された(表5)。
以上の成績から、乾乳後期の腹囲形状はその後の周産期病発症リスクを予測するうえで有用なモニタリング項目となること、また、乾乳期の適切な牛群設定、乾乳後期から産褥期にかけてのグループに対して適切な飼料給与と十分な休息スペースを確保することにより、周産期病の低減が可能であることが示された。
| リンゴ形 洋梨形 ボックス形 | 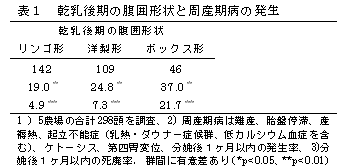 |
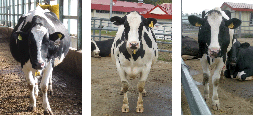 |
|
| 図1 ルーメン膨満度による腹囲形状のモニタリング |
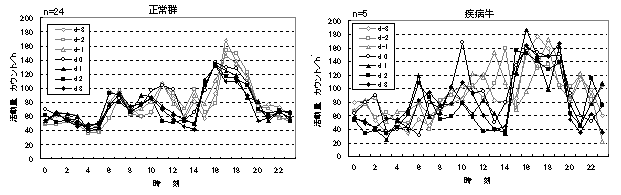
図2 周産期病の罹患の有無と乾乳期における乳牛の活動量の日内変動パターンとの関係
注)凡例のd0は乾乳前期群から後期群へ移動した日、d-1はその前日、d1はその翌日を示す.↓は給餌
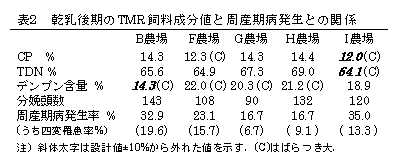
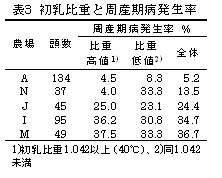
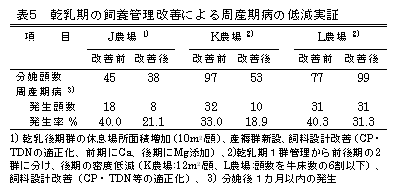
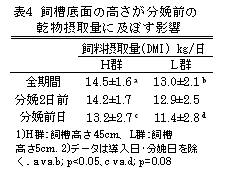
4.成果の活用面と留意点
1)腹囲形状は、周産期病の発生を予測する簡易な指標として生産現場で活用できる。
2) 周産期病の低減実証に用いた改善ポイントは現地での周産期病予防対策の参考になる。
5.残された問題とその対応
1) 牛の健康管理手法としての活動量評価法の開発
2) 周産期における適正な飼養密度ならびに給与飼料の物理性と周産期病発生との関係解明。