| 課題分類: 研究課題:ペレニアルライグラス新品種候補「天北5号」 担当部署:上川農試・天北支場・技術普及部 協力分担:北農研・寒地飼料作物育種研究チーム・イネ科牧草育種グループ、 根釧農試・研究部・作物科、畜試・環境草地部・草地飼料科 予算区分:道費 研究期間:1986〜2007年度 (昭和61〜平成19年度) |
越冬性、早春草勢、収量性に優れる採草・放牧兼用利用向けの中生品種を育成する。
2.方法
1) 育種方法
6栄養系の組合せによる合成品種法。
2) 育種経過
1986年から1987年に道内エコタイプの収集と特性評価を行い、44個体を選抜した。1988年には選抜した44個体を放任授粉・採種し、1991年から4年間44系統・2640個体からなる基礎集団からの個体選抜を実施し、出穂期が中生に属し、越冬性が優れる88個体を選抜した。
1994年に、88個体による放任授粉・採種を行い、1994年から1997年にその後代4928個体を供試して、越冬性、草勢、耐病性に優れ、出穂期が中生に区分される12母系に由来した49個体を選抜した。
1998年に、49栄養系の中で、枯死茎率が少ない6栄養系による多交配採種を温室内で行い、合成第1代種子を採種し、系統名「天系合98103」を付した。
1999年から3年間、生産力検定試験に供試するとともに、後代検定によって構成親栄養系の評価を行った。合成第2代種子に系統名「天北5号」を付し、2005年から地域適応性検定試験および各種特性検定試験を実施した。
「天北5号」の構成栄養系は、道内(滝川市)のエコタイプに由来する。
3.成果の概要
(1) 特性の概要(標準品種「ポコロ」(晩生)、比較品種「ファントム」(中生の晩)との比較)
1)出穂始は「ポコロ」より5〜8日、「ファントム」より4〜5日いずれも早く、早晩性は「中生の早」に属する。
2)兼用利用での乾物収量は、1番草は刈取時期が遅い「ポコロ」より少ないが「ファントム」よりやや多く、2番草以降の多回刈合計は「ポコロ」より多く、「ファントム」と同程度であることから、中生種としてはやや多収である。また、1番草収穫後の季節生産性は、「ポコロ」よりやや優れる。
3)多回利用での年間合計乾物収量は「ポコロ」、「ファントム」と同程度であり、季節生産性は「ポコロ」と比べ春はやや少なく、夏は同程度で、秋はやや多い。
4)越冬性は「ポコロ」、「ファントム」よりやや劣る場合があるが、実用上問題ないレベルを有する。
5)飼料成分は、兼用利用1番草の粗蛋白質(CP)含量が「ポコロ」より高く、多回利用時の水溶性糖類(WSC)含量が「ポコロ」、「ファントム」より高い。可消化養分総量(TDN)含量は「ポコロ」、「ファントム」と同程度である。
6)放牧条件下での採食性が「ポコロ」と比べやや良好であり、放牧適性は「ポコロ」よりやや優れる。
7)採種性は「ポコロ」および「ファントム」より非常に優れる。
8)葉腐病罹病程度は「ポコロ」より低く、斑点病および網斑病罹病程度は「ポコロ」と同程度である。
9)混播適性は「ポコロ」と同程度で良好である。
10)出穂期の形態的特性は、「ポコロ」と比べ、草丈および稈長は同程度かやや低く、穂長はやや短く、止葉の葉長はやや短く、葉幅はやや狭い。
(2)特記すべき特徴
「天北5号」は早晩性が中生の早に属し、現在北海道で栽培されている品種の中で出穂が最も早い。中生種としては兼用利用で採草1番草収量が多く、晩生の「ポコロ」と比べ夏以降の多回利用時の収量も多い。兼用利用1番草の粗蛋白質(CP)含量、多回利用時の水溶性糖類(WSC)含量が高く、放牧条件下における採食性も良好である。また、種子収量が多い。
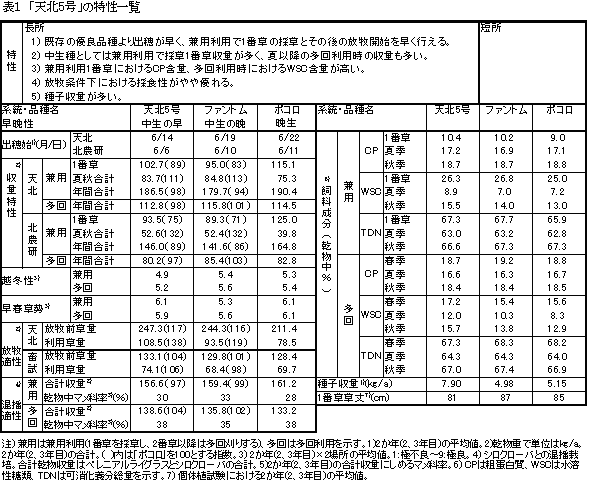
4.優良品種に採用しようとする理由
放牧地では、短草状態を維持して栄養価の高い放牧草を牛に過不足無く与えるため、スプリングフラッシュによって生じる余剰草と秋の草量不足を調整する兼用地の配置が必要となる。また、刈取り等による兼用地の管理・収穫作業は、冬期の貯蔵飼料の主力であるチモシーの収穫作業との競合を避ける必要がある。
「天北5号」の早晩性は、晩生の「ポコロ」より出穂が1週間程度早く、「中生の早」に分類される。このため「天北5号」を兼用地に導入すれば、1番草をチモシーの早生品種より早く収穫できる。1番草刈取後の放牧開始も早められることからスプリングフラッシュ後の放牧草不足を補うことができる。「天北5号」の収量性は既存の中生品種よりやや多く、既存品種と比べ兼用利用1番草の粗蛋白質(CP)含量、多回利用時の水溶性糖類(WSC)含量が高く、放牧条件下での採食性も良好であることから、北海道で生産される粗飼料を量から質へ転換させ、家畜生産性の向上にも有効である。
1999年に天北農試(現上川農試天北支場)で育成した「ポコロ」は、越冬性に優れ早春からの放牧が可能であることから農家の評価が高い。「ポコロ」と「天北5号」を組み合わせて利用することにより、放牧だけでなく、高品質な貯蔵粗飼料が確保でき、高栄養牧草ペレニアルライグラスを基幹草種とした放牧主体酪農の展開により、飼料自給率の向上に貢献できる。
5.成果の活用面と留意点
1) 適応地域および普及見込み面積:
道北、道央および道南。 6,000ha
2) 栽培上の留意点:
利用方法は1番草を採草し、その後放牧する兼用利用を主とする。
造成後2年目に倒伏が発生する場合があるので採草時は適期に刈り取る。
土壌凍結地帯での栽培は避ける。
6.残された問題とその対応