| 研究課題:ペレニアルライグラス放牧地における乳牛の数日滞牧型輪換放牧技術 (寒地中規模酪農における集約放牧技術の確立 ペレニアルライグラス新品種「ポコロ」を活用した放牧草地の維持管理・利用技術の開発) 担当部署:上川農業試験場天北支場 技術普及部 協力分担:北農研センター集約放牧研究チーム 予算区分:独法受託 研究期間:2003〜2007年度(平成15〜19年度) |
1.目的 放牧管理の省力化のため牧区面積を拡大し数日間滞牧した輪換放牧技術の確立を目指し、ペレニアルライグラス(PR)放牧地で滞牧日数の延長が採食量および草種構成に及ぼす影響を検討した。また、牧区内において採食場所が偏る要因を解析した。
2.方法
1) 数日滞牧型輪換放牧における放牧地の利用技術
(1)滞牧日数の異なる輪換放牧における採食量および草種構成
(2)入牧時草丈の異なる輪換放牧における採食量および草種構成
(3)再採食が牧草の生産量および永続性に及ぼす影響
(4)数日滞牧型輪換放牧実施農家における放牧草採食量
2) ゲートからの距離および水槽の位置が牧区内の採食場所に及ぼす影響
3) 植生および牧草の成分が牧区内の利用草量に及ぼす影響
3.成果の概要
1)-(1) PR草地に乳牛(乾乳牛・育成牛)を滞牧日数3日および1日とし輪換放牧しても採食量およびPRの草種構成割合の経年的推移に差はなかった(表1)。滞牧日数の経過に伴いバイト数に変動が見られたが、採食時間には大きな変化はなく採食量は低下しないと考えられた(表2)。
1)-(2) 滞牧日数を3日とし草丈15cmおよび20cmで放牧したが、草丈が異なっても採食量に大きな差はなく、PRの草種構成割合は同様な経年的推移を示した(表3)。
1)-(3) PRを草丈20または15cmで刈取り、さらに5日後に再び刈り取る処理を加えても年間乾物収量および草種構成に差はなく、滞牧期間中の再採食はPRの生産量に影響しないと考えられた(表4)。
1)-(4)数日滞牧型輪換放牧を実施した3農家の放牧草採食量は年平均8.5〜9.2㎏であったが、割当草量が多く、PRの冠部被度が高いと採食量が多くなる傾向が見られた(標準偏回帰係数;割当草量0.477 、PR冠部被度0.472、P<0.05 )。
2) 長辺約400mの放牧地でゲートからの距離と牧草利用率との関係を見ると、放牧圧の低いD農家(30頭×日/tDM)ではゲート付近の利用率が高く(67%)、適切な放牧圧のB農家(57頭×日/tDM)では各ブロック40%前後でほぼ均一に利用した。また、場内の放牧地で水槽の位置と採食場所の関係を見ると、水槽をゲート近くと420m地点の2箇所に設置した場合、牧区内を比較的均一に採食利用した(図1)。
3) 2農家の放牧地で植生と採食場所との関係をみるとPR草丈が低く、PR冠部被度の高い場所を好んで利用する傾向があったが(表5)、牧草成分と牧区内の利用量との関連は認められなかった。1農家の放牧地に石灰をCaO換算量で0.5t/haを3年間施用したが、石灰の多量施用と放牧草採食量向上との関連は明確でなかった。
PR放牧地では滞牧日数を3日程度にしても入牧時草丈が15〜20cmであれば放牧草採食量に大きな変化はなく、PR植生も維持できた。牧区内を均一に利用させる手段としてPRの割合、PRの草丈、放牧圧および水槽の設置位置が重要であった。
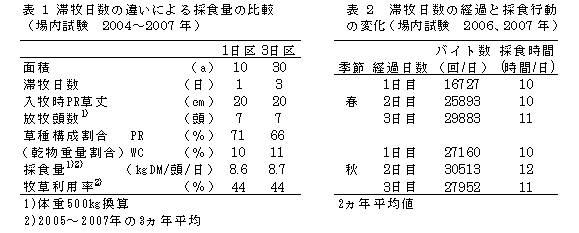
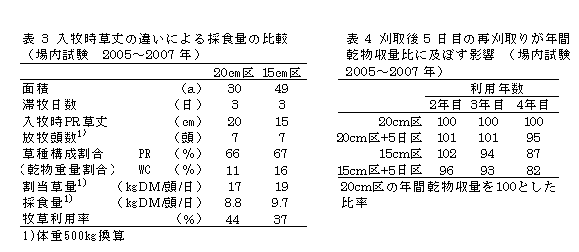
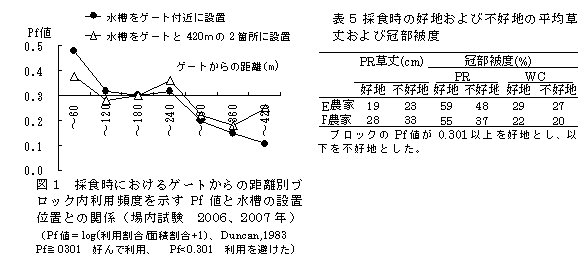
4.成果の活用面と留意点
1) 本成果はペレニアルライグラスを主体とした数日滞牧型の輪換放牧実施農家で活用できる。
2) 割当草量が十分あり、滞牧日数が2〜3日程度の輪換放牧を対象とする。
5.残された問題とその対応
1) 土壌pHの低い放牧地への石灰散布が放牧草採食量に及ぼす影響
2) 滞牧日数の延長が乳生産量に及ぼす影響