| 研究課題:養分循環に基づく乳牛放牧草地の施肥対応 (寒地中規模酪農における集約放牧技術の確立・環境保全型家畜ふん尿循環利用システム実証事業) 担当部署:根釧農試研究部 草地環境科・乳牛飼養科・作物科、 上川農試天北支場 技術普及部、北海道農研 集約放牧研究チーム 予算区分:独法受託、農政部事業(ふんプロ) 研究期間:2003〜2007年度(平成15〜19年度) |
1.目的
放牧草地の施肥は、放牧によって草地から減少する養分量を補給することを基本とする。これに基づいて、本試験では、メドウフェスク(MF)を中心に、チモシー(TY)、ペレニアルライグラス(PR)、オーチャードグラス(OG)のそれぞれを基幹とする乳牛の放牧草地を調査し、養分循環に基づく標準施肥量と土壌診断に基づく施肥対応を設定する。
2.方法
1) 道東MF放牧草地の標準施肥量
2) 道東チモシー放牧草地の土壌診断に基づく施肥対応事例
3) 乳牛放牧草地の標準施肥量における草種間差と地域間差
3.成果の概要
1) 放牧草地の施肥対応は、放牧によって草地から肥料として有効な養分が減少するので、その量(肥料換算養分の減少量)を施肥によって補給することを基本とする。本試験では、施肥量から放牧による肥料換算養分の減少量を差し引き、養分収支とした(図1)。
2) 道東のMF・シロクローバ(WC)混播草地をTY並の施肥量(N-P2O5-K2O=4.5-4.5-4.8g/m2)で管理すると、北海道施肥標準相当量(同7.2-9.6-13.2g/m2)で管理した牧区に対し、遜色ない被食量を得た(データ省略)。また、北海道施肥標準相当量の牧区では、リン酸とカリの収支、土壌の養分含量ともに明瞭な蓄積傾向を示したが、TY並の施肥量は、その傾向を緩和した(図2)。これにより、MF放牧草地にTYの標準施肥量を適用できると判断した。
3) 窒素の収支は、いずれの牧区でも負の値を示し、養分収奪が予想されたが、跡地土壌の培養窒素量には、3年間明瞭な低下傾向が認められなかった(図2)。これは混生するWCの窒素固定による効果であると判断し、その量を平均3-4g/m2程度と見なした。
4) 2)の結果を受け、道央のMFとPR、道北のPRとOGについても、同様に放牧による肥料換算養分の減少量を算出した。その結果、年間の肥料換算養分減少量には、草種間差、地域間差に一定の傾向が無く、年間被食量との間に有意な相関関係を得た(図3)。
5) そこで、得られた回帰式によって、年間被食量の水準別に肥料換算養分の減少量を求め(表1)、これに基づき、放牧草地における年間施肥量を、道内全域各土壌共通の値として設定した(表2)。本施肥量には幅が示してある。最初に平均的な施肥量で試行し、草量の充足度と土壌診断の結果に応じて、示された幅の中で調整を行い、次年度以降に草地ごとの標準量を設定することが望ましい。
6) 土壌診断に基づく施肥対応では、黒色火山性土の有効態リン酸含量100mg/100g以上、交換性カリ含量70mg/100g以上の場合に、それぞれ無リン酸、無カリ管理の可能性を認めた。その他の場合には、現行の施肥対応の妥当性が追認された(データ省略)。
7) カリの土壌診断基準値には、現行の土壌診断基準値にふん尿還元分(火山性土では6-7g/m2)を上乗せするため、以下の式で算出した値を用いる。
放牧草地用基準値(mg/100g)=現行基準値(mg/100g)+ふん尿還元分(g/m2)÷仮比重×2
以上の結果により、乳牛放牧草地における採食と排泄によって生じる養分循環に基づいて、標準施肥量(表2)と土壌診断に基づく施肥対応を設定した。
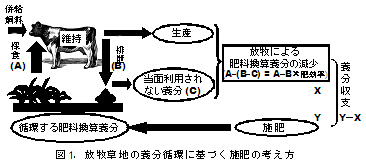
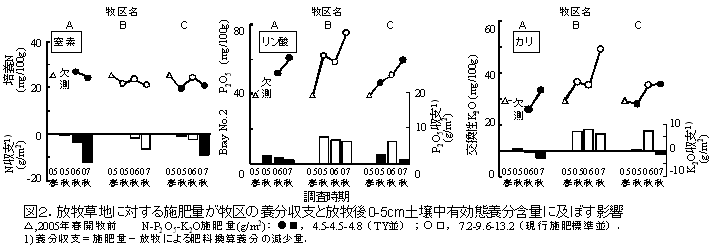
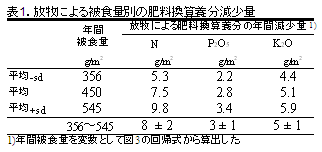 |
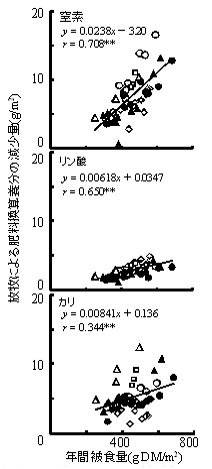 図3. 年間の被食量と放牧による肥料換算養分減少量との関係 図3. 年間の被食量と放牧による肥料換算養分減少量との関係〇,道東メドウフェスク; ●,道央メドウフェスク; △,道北ペレニアルライグラス; ▲,道央ペレニアルライグラス; ◇,道東チモシー; □,道オーチャードグラス. |
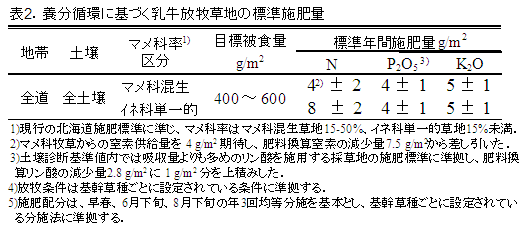 |
1) 初産以降の乳牛放牧専用草地における標準施肥量と土壌診断に基づく施肥対応として活用する。
2) 本施肥量は、併給飼料によってCP摂取量を調節する飼養管理と、小〜中牧区輪換・昼間〜昼夜放牧の条件で設定した。したがって、2-3時間の時間制限放牧のように、採食量と排泄量の比が大きく異なる放牧条件には適用できない。
3) 非火山性土のカリの土壌診断基準値算出に用いるふん尿還元分の値は、当面、火山性土の値6-7g/m2を準用する。
5.残された問題とその対応
非火山性土の放牧草地におけるカリの土壌診断基準値
牧区内における養分存在量の不均一性の評価とその対応