| 研究課題:めん用秋まき小麦「きたほなみ」の高品質安定栽培法 (新ランク区分に対応した小麦有望系統の高品質安定栽培法の確立) (道央地域における秋播小麦有望系統の高品質多収肥培管理技術の開発) (道東地域における秋播小麦有望系統の高品質多収肥培管理技術の開発) 担当部署:中央農試生産環境部栽培環境科・作物研究部畑作科、上川農試研究部畑作園芸科、 十勝農試生産研究部栽培環境科、北見農試作物研究部麦類科 協力分担:石狩、後志、空知、上川、留萌、網走、胆振、日高、十勝管内の農業改良普及センター 予算区分:受託(民間、ブランドニッポン) 研究期間:2003〜2007年度(平成15〜19年度) |
平成18年に北海道の優良品種となっためん用秋まき小麦「きたほなみ」について、高品質、安定生産を目的とした栽培技術(播種期、播種量、窒素施肥法)を確立する。
2.方法
1)供試品種:「きたほなみ」、「ホクシン」
2)試験地:中央農試、上川農試、十勝農試、北見農試、石狩3市村、後志2町村、空知9市町、上川2市町、留萌1町、網走2町、胆振1町、日高3町、十勝6市町において延べ39試験地。
3)試験年次(播種年):中央・十勝農試は2003〜2006年の4カ年、その他は2005〜2006年の2カ年。
4)試験処理:播種期(1〜6水準)、播種量(1〜3水準)、窒素施肥法(起生期以降の追肥処理1〜8水準)を適宜掛け合わせ、試験地当たり1〜37処理区を設置した。
5)検討項目:播種期、播種量および窒素施肥法が生育、収量、品質(主にタンパク、灰分、容積重、フォーリングナンバー、粉色)に及ぼす影響
3.成果の概要
1)「きたほなみ」は「ホクシン」に比べて以下の特徴が明らかとなった。①越冬前の生育量はやや小さいが、越冬性に大きな問題がない(表1)。そのため、越冬前主茎葉数の目標値は0.5葉少なく設定される(道央・道北:5.5葉以上、道東:5葉程度)。②穂数および一穂粒数が多く収穫指数(HI)が高いことから、子実重は2割程度多収である(表1)。③多収である反面、子実タンパクは0.8〜1.0ポイント程度低く、品質評価基準(9.7〜11.3%)の下限値を下回る事例が多いので、タンパクの改善が求められる(表1)。④タンパクは止葉期追肥で最も上昇効果が高い(図1)。⑤その他の品質は優れており、タンパクを基準値以内まで向上させても、その優位性は変わらない(データ省略)。⑥倒伏耐性は強く、穂数700本/㎡程度、窒素吸収量17〜18kg/10aまでは倒伏の発生が少ない(図2)。
2)道央・道北地域における「きたほなみ」の栽培法
播種適期は越冬前の主茎葉数が5.5〜6.5葉となる期間で、積算気温(3℃以上)では520〜640℃を確保する期間である(9月中旬前後)。播種適量は170粒/㎡、目標穂数は700本/㎡である(表2)。ただし、気象条件が厳しく穂数が十分確保できない地帯では255粒/㎡まで増やすことで収量は安定する。また、やむを得ず早播する場合には、倒伏を軽減するために播種量を100粒/㎡程度まで減らす(表2)。標準的な窒素施肥体系は、基肥-起生期-止葉期に各4-6-4kg/10aを施用する。ただし、収量水準が高く、あるいは養分吸収が阻害される圃場で、低タンパクが懸念される場合は、さらに幼穂形成期に追肥(上限4kgN/10a)もしくは開花後に尿素2%溶液の葉面散布(3回程度)を行う。
3)道東地域における「きたほなみ」の栽培法
播種適期は越冬前の主茎葉数が5葉前後となる積算気温(同上)470℃を確保する日を中心とした5日間程度である(9月中旬〜下旬)。播種適量は200粒/㎡で、目標穂数は700本/㎡であるが、やむを得ず播種が遅れる場合は255粒/㎡を上限として増やす。窒素施肥体系は、基肥-起生期-止葉期に4-A-4kg/10aを施用する(「ホクシン」では4-Akg/10a)。A値は表3に示す窒素追肥量で、追肥量が多い場合や倒伏しやすい圃場では幼穂形成期に分施する。ただし、収量水準が高いあるいは養分吸収が阻害される圃場で、低タンパクが懸念される場合は、さらに開花後の尿素2%溶液の葉面散布(3回程度)を行う。
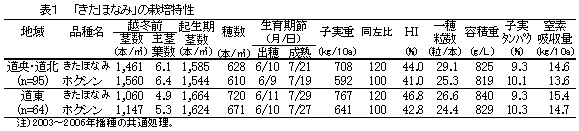
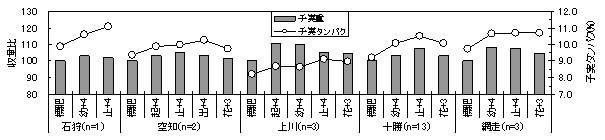
図1 追肥時期が子実重・タンパクに及ぼす影響(2005、2006年播種)
注)標肥の窒素施肥量は試験地によって異なり、基肥は3〜5.6kg/10a、起生期追肥量は2〜8kg/10a。起+4、幼+4、止+4、出+4、花+3は
それぞれ起生期、幼形期、止葉期、出穂期、開花後(葉面散布)に3または4kg/10aを追肥。
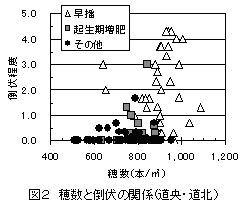
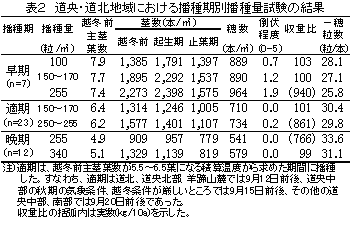
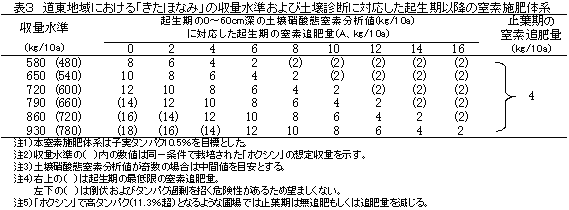
4.成果の活用面と留意点
1)本成果は、品質取引基準値(新ランク区分)の導入に対応した「きたほなみ」の基本的な栽培技術として利用する。
2)各地域の播種適期は、11月15日までに達する日平均気温(3℃以上)の積算値より算出した。
3)低タンパクが懸念される場合の目安は、「ホクシン」の子実タンパクが9.7%未満となりやすい圃場である。
5.残された問題とその対応
1)道央・道北地域における土壌診断による窒素施肥量の設定。
2)収量、タンパク制御のための土壌診断、生育診断、葉色診断を活用した窒素施肥法の高度化。