| 研究課題:金時類の茎折れリスク低減と土壌・作物栄養診断による高品質安定生産技術 ( 菜豆類(金時、虎豆)における土壌・栄養診断技術の開発と窒素施肥技術の実証 1.金時類の土壌および作物栄養診断技術の開発と実証 ) 担当部署:十勝農試生産研究部栽培環境科,十勝農試作物研究部小豆菜豆科 協力分担:中央農試基盤研究部農産品質科,十勝農業改良普及センター東部支所・東北部支所 予算区分:道費(豆基) 研究期間:2005〜2007年度(平成17〜19年度) |
茎折れリスクを低減するための栽培管理条件を明らかにし、土壌の窒素肥沃度や金時類の窒素栄養特性に対応した土壌・作物栄養診断技術を開発する。これら合理的な窒素施肥管理を行うことにより、環境負荷を低減し、金時類の高品質安定生産を図る。
2.方 法
1)茎折れ発生実態と発生要因の解析
①現地調査:十勝管内における発生実態調査
②場内試験:8品種系統、栽植密度2処理、窒素施肥3処理、播種時期2処理等
③調査項目:茎折れ個体率(自然発生・押し倒し処理)、個体生重、初生葉節径等
2)施肥条件による窒素吸収・品質特性
①試験処理:品種(大正金時・福良金時)×窒素施肥4-6処理
②土層内窒素利用率:15N-硝酸カルシウムを0-100cm土層内に20cm毎に埋設し、利用効率を調査
③品質特性:百粒重、成分含有率、煮熟特性(煮熟増加比・かたさ・皮切れ率等)
3)土壌診断および作物栄養診断技術の開発
①供試品種:大正金時、福良金時
②試験処理:前作が異なる圃場(十勝農試・本別町・浦幌町・鹿追町)×窒素施肥3-6処理
③調査項目:土壌無機態N(硝酸態N:以下NN)、熱水抽出性窒素(ACN)、葉柄の硝酸態N濃度、
窒素吸収量、収量等
3.成果の概要
1)茎折れの発生には品種間差異が認められ、「福良金時」で発生しやすい傾向にあった。また、茎折れが最も発生しやすい時期としては、開花2〜3週間後頃の急激に個体の生育量が増大する時期であることが示された(図1)。
2)茎折れは多肥または疎植条件で発生しやすい傾向にあった(図2)。有機物の過剰投入は、倒伏および成熟期の葉落ちの悪化につながることが示された。また、標植(16,700本/10a)かつ適正な窒素施用水準では、開花期頃の窒素追肥により茎折れの発生はほとんど助長されなかった。
3)重窒素を用いた窒素吸収試験の結果から、子実および豆殻(茎および莢)とも全窒素吸収量の85%程度が0〜40cmの土層に由来しており(図3)、金時類の土壌無機態窒素診断は0〜40cm土層で評価可能と考えられた。
4)追肥により子実タンパク含有率は上昇し、合計窒素施用量が同じ場合には、追肥(分施)によって百粒重の増加および皮切れ率の低下に結びついた。
5)子実収量は作物体の窒素含有量を説明変数とした回帰式により説明することが可能であり(図4)、その圃場における通常レベルの想定収量を得るために必要な窒素施肥量は、土壌の無機態窒素量(NN 0-40cm)および熱水抽出性窒素量(ACN 10cm土層相当量)から算出可能であった。
6)開花期における葉柄から水抽出した硝酸態窒素濃度は、窒素施肥量に応じて高くなる傾向にあり、初期生育における窒素栄養状態を反映していた(図5)。 開花期の葉柄硝酸態窒素濃度が概ね0.3%を超えている場合には、追肥は不要と判断された。
7)本試験で開発された土壌診断および作物栄養診断技術(図6)の活用により、生育過程の茎折れリスクを軽減し、高品質な金時類の安定生産(現行収量水準250kg/10a程度)が可能となる。
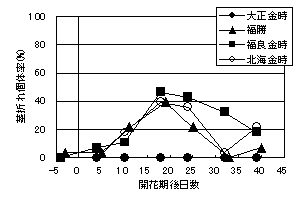
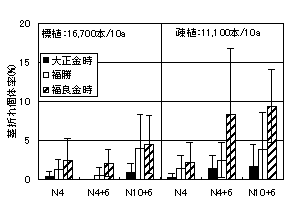
図1 押し倒し処理による茎折れ個体率の推移 図2 栽培条件と茎折れ個体率の関係
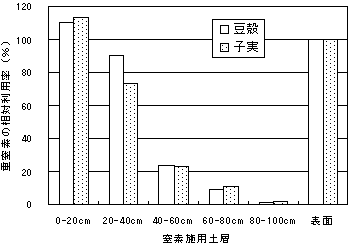 図3 金時の土層内窒素利用率 |
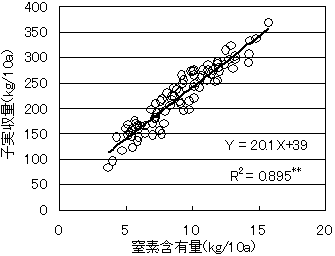 図4 窒素含有量と子実収量の関係(H17-19年現地) |
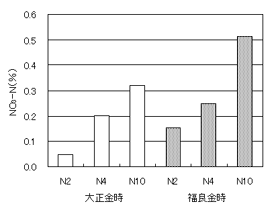
図5 開花期の葉柄中硝酸態窒素濃度
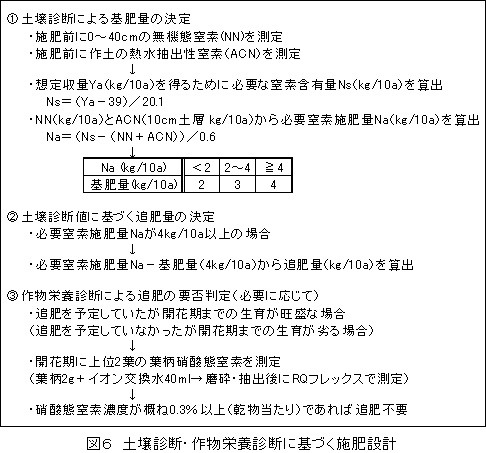
4.成果の活用面と留意点
1)本成果は、金時類の高品質安定生産と環境負荷の低減を目指した、施肥対応技術として活用できる。
2)本試験における土壌窒素診断では、根粒菌による窒素固定は考慮していない。
3)本試験は、収量レベル160〜320kg/10a、熱水抽出性窒素(ACN)2〜14mg/100gの圃場で行った。 また、泥炭土では試験を行っていない。
5.残された問題とその対応
1)根粒菌による窒素固定量の評価とその施肥対応。
2)現行収量水準を上回る安定多収技術の開発。