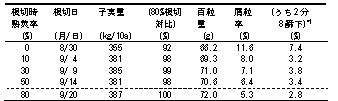| 研究課題:虎豆の窒素施肥改善および早期収穫体系による安定生産技術 (虎豆の安定生産のための窒素施肥技術の改善と実証) 担当部署:北見農試 生産研究部 栽培環境科, 作物研究部 畑作園芸科 協力分担:網走農業改良普及センター本所, JAきたみらい訓子府支所 予算区分:道費(豆基) 研究期間:2005〜2007年度(平成17〜19年度) |
虎豆の栽培面積がやや減少傾向にあることや農家間の収量差が大きいことから生産量増加や低収ほ場の底上げのための技術開発が求められている。また、早期出荷による消費拡大のために収穫をおよそ10日早める栽培法が実需・流通サイドから強く求められている。そこで、収量向上に最も効果的な窒素施肥体系を明らかにするとともに、早期供給が可能な栽培技術を確立する。
2.方 法
1)現地土壌・施肥実態調査:A町延べ114箇所の作土化学性, 同79戸の施肥量を調査
2)生育要因調査:A町25箇所(火山性土8, 台地土15, 低地土(下層泥炭)2)における作土化学性, 有効土層深さと収量(子実重)の関係を調査
3)窒素施肥試験(1)生育特性調査:播種〜根切時期の乾物生産量, 窒素吸収量, 収穫期の層位別の根の分布を調査(2)施肥反応調査:窒素施肥(追肥時期;手竹期6月下旬, 開花盛期7月下旬, 緩効性肥料;LPコート・シグモイド型LPS)の収量に及ぼす影響を調査
4)根切時期試験・播種期+べたがけ被覆試験:生育, 収量に及ぼす影響を調査
5)播種可能最早日の設定:遅霜の危険性が極めて小さい最早日に出芽期となる播種日を推定
6)播種期+べたがけ被覆+窒素施肥試験:組み合わせたときの収量に及ぼす影響を調査
7)早期収穫体系の組み立て:播種期・べたがけ被覆・根切時期および窒素施肥試験の結果と推定播種可能最早日から早期収穫体系を構築
3.成果の概要
1)A町における虎豆の窒素施肥量は平均6kg/10aで、北海道施肥ガイドによる高級菜豆の施肥標準量に比べ少なく、基肥重点の傾向が認められた。
2)虎豆の収量は作土の熱水抽出性窒素含量と有意な正の相関関係が認められ、窒素肥沃度を高める土壌管理の有効性が示唆された(図1)。また有効土層の深さも収量に影響すると推察された。
3)虎豆の窒素吸収量の増加は開花期以降で著しく、施肥量を上回る窒素を吸収することが示唆された(図2)。
4)収量は窒素施肥量が多いとき、また総量が同じ場合は開花盛期追肥のときに多くなる傾向にあり、窒素施肥量は基肥4+開花盛期8kg/10aが最適であった(表1)。また、緩効性肥料LPS40で追肥を代替した場合は手竹期追肥と同等以上の増収効果があると推測された。
5)根切時期を熟莢率30%としたとき、同80%と同等の収量および粒大が得られた(表2)。
6)早期播種では標準と比べて出芽期は5〜10日、成熟期は3〜9日早まった。べたがけ被覆と組み合わせるとさらに出芽および熟莢率30%の日が4日早まり、収量も標準播種を6〜7%上回った
(表3)。
7)虎豆の出芽に関する有効下限温度は7.1℃、有効積算温度は107.3℃であり、これらに基づき、平年の日平均気温およびべたがけ被覆の前進効果(-4日)からA町の播種可能最早日を推定した結果、平年播種日より約2週間早くなると見積もられた(データ省略)。
8)早期播種+べたがけ被覆における窒素追肥による増収効果は、標準播種と同様に開花盛期追肥で最も高く、開花盛期の追肥量の増加によりその効果はさらに高まった(表4)。
9)以上をまとめ、開花盛期の窒素追肥による虎豆の増収技術と早期播種・べたがけ被覆・早期根切による早期収穫体系を整理した(図3)。これにより収量の向上と収穫時期を約10日早める栽培が可能となる。
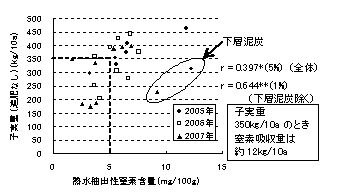 図1 作土の熱水抽出性窒素含量と 虎豆子実重(収量)の関係 |
表1 窒素施肥処理が収量に及ぼす影響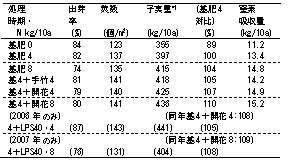 2006・2007年平均 開花=開花盛期 *1 子実重は水分15%換算値(以も同様) |
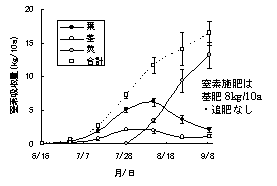 図2 虎豆の窒素吸収量の推移 |
表2 根切時期が収量および品質に及ぼす影響 2004〜2006年平均 窒素施肥は 基肥4kg/10a(追肥なし) |
|
表3 早期播種およびべたがけ被覆が |
表4 早期播種+べたがけ栽培における |
図3 虎豆の窒素施肥および早期収穫栽培体系
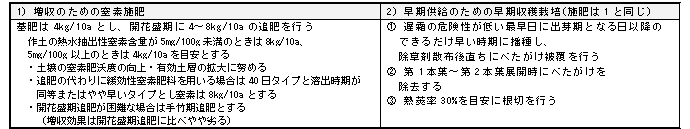
4.成果の活用面と留意点
1)本試験結果は北見地方で得られたものであるが、窒素施肥については他地域でも適用できる。
2)リン酸、加里の施用量は施肥標準に従う。
3)べたがけ被覆は雑草の生育を促進することがあるので、雑草管理には十分注意する。
4)早期播種+べたがけ被覆栽培では、根切後の温度が比較的高いので、雨害による品質低下を避けるため、茎および莢水分の低下後は速やかにニオ積みを行う。
5.残された問題とその対応
1)土壌の物理性・化学性の改善による虎豆の増収効果の実証