| 研究課題:北海道における有機性廃棄物によるカドミウム負荷の実態と土壌・作物へのリスク軽減策 (有機性廃棄物利用に伴うカドミウム負荷のリスク評価とその軽減対策技術の確立) (施設栽培における漁業系有機性資源の有効利用と施用基準) 担当部署:中央農試 環境保全部 農業環境科 道南農試 研究部 栽培環境科 上川農試 天北支場 技術普及部 協力分担: 予算区分:受託(独法)・道費 研究期間:2003〜2007年(平成15〜19年度) |
本道で発生する有機性廃棄物のカドミウム(Cd)濃度や利用実態に基づき、有機性廃棄物由来のCd負荷量を明らかにする。さらに、有機性廃棄物の施用に伴う土壌・作物へのCdリスクの軽減策を検討する。
2.方法
1)有機性廃棄物に由来したCd発生量
有機性廃棄物の分析、各種文献値および北海道バイオマス利活用マスタープランに基づいて、道内で発生する有機性廃棄物由来のCd発生量を推定し、負荷リスクを検討した。
2)有機性廃棄物の農地施用に伴うCd収支と負荷量の検討
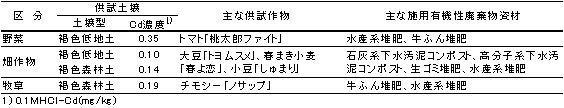
3)有機性廃棄物の施用に伴う土壌・作物へのCdリスク軽減策
有機性廃棄物Cd負荷と土壌Cd濃度の関係把握、土壌pH改善による作物Cd濃度低減策
3.成果の概要
1)北海道で年間に発生する有機性廃棄物由来のCd量8,059kgのうち、農業由来の約95%(2,033kg、主に家畜ふん尿)、非農業由来廃棄物の約21%(1,286kg、水産系およびし尿汚泥等)が農地に負荷されている(表1)。したがって、全耕地面積に対する農業由来の有機性廃棄物Cd負荷量は0.17、非農業由来は0.11g/10aと試算される。
2)Cdの平均濃度(mg/kg現物)は水産系のホタテウロが18.1と極めて高く、下水汚泥・事業生活ゴミは0.5以下であった(表2)。農業由来の稲わら・麦稈・乳牛ふん尿はいずれも低く、0.1を下回っていた。野菜は0.1未満(供試土壌0.1MHCl-Cdmg/kg:0.32〜0.3)、牧草も0.11以下(同:0.15)で、コーデックス基準や飼料の有害物質の指導基準より著しく低かった。
3)野菜畑におけるCd濃度の低い牛ふん堆肥区と対照区では、作物残さの搬出に伴いCd持出し量が負荷量を上回ったが、Cdを多く含む水産系堆肥区では土壌にCdが蓄積することが認められた(表3)。なお、トマトのCd濃度は0.02〜0.03(mg/kg現物)と低かった。
4)畑作物・牧草のCd濃度(mg/kg)は大豆子実が0.02〜0.03、小麦子実が0.05〜0.08、小豆子実が0.01未満、およびチモシーが0.02〜0.03と低く、処理間差は判然としなかった(表4、5)。これらの作物でも各種の有機性資材施用に伴いCd収支がプラスとなるため、Cd負荷量に対応して土壌蓄積するCdがやや高まる方向であった。
5)各種有機性廃棄物資材によるCd負荷量と土壌の0.1MHCl-Cdの増加量の間には正の相関が示され、Cd負荷量25g/10aあたり土壌の0.1MHCl-Cdは0.1mg/kg増加する回帰式が得られた(図1)。
6)作物のCd濃度は、炭カル施用による土壌pH上昇に従い低下する傾向が認められた(図2)。また、Cd濃度が低い堆肥でも20%程度低減した。
7)以上のように、本道で発生する有機性廃棄物由来Cdの農地への負荷量は農業由来と非農業由来を合わせて年間0.28g/10aである。有機性廃棄物の適正な施用量の範囲では、作物のCd濃度はコーデックス基準値を下回っており、また、作物のCd吸収を抑制するために土壌pHの管理が重要である。
表1 農地還元される有機性廃棄物由来Cd量、農地負荷量 表2 有機性廃棄物および作物のCd濃度
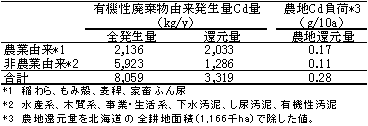
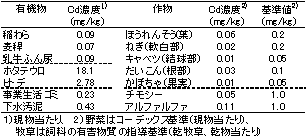
表3 野菜畑における有機性廃棄物施用に伴うCd収支と土壌およびトマト果実のCd濃度に及ぼす影響
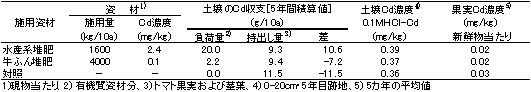
表4 普通畑における有機性廃棄物施用に伴うCd収支と土壌および大豆子実のCd濃度に及ぼす影響
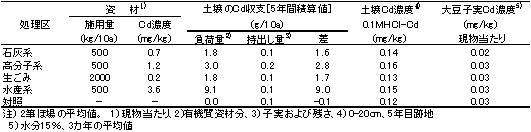
表5 草地における有機性廃棄物施用に伴うCd収支と土壌および牧草のCd濃度に及ぼす影響
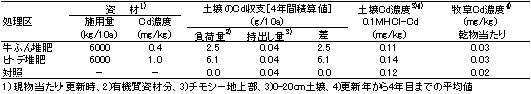
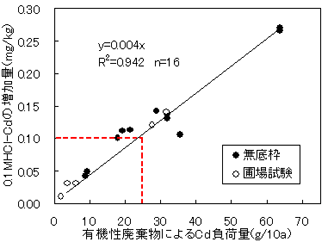 |
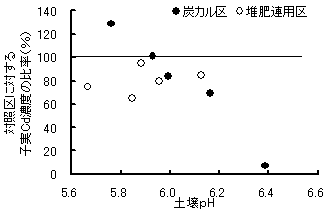 |
|
図1有機性廃棄物資材施用によるCd負荷量 と土壌(0-20cm)0.1MHCl-Cdの増加量の関係 |
図2 子実Cd濃度低下に及ぼす土壌pHの影響 注)0.1MHCl-Cd 0.49mg/kg、炭カル区:初年目のみ施用 供試作物 H15・16・19:大豆、17・18:小麦 |
1)農地における環境保全を考慮した有機物利用管理に活用できる。
2)土壌のCd蓄積リスクは有機性廃棄物施用に伴うCd負荷量に従い高まることから、Cd濃度の高い資材の施用には留意する。
5.残された問題とその対応
1)作物のCd汚染リスクが高い土壌における有機性廃棄物の利用法
2)Cdの作物吸収リスク軽減技術
3)畑土壌に蓄積したCdのファイトレメディエーション技術