| 課題分類: 研究課題:ばれいしょの種いも伝染性細菌病の簡易で高精度な保菌検定法 担当部署:中央農試 生産環境部 病虫科、(独)北農研 バレイショ栽培技術研究チーム 担当者名: 協力分担:(独)種苗管理センター北海道中央農場 予算区分:国費受託(高度化事業) 研究期間:2005〜2007年度(平成17〜19年度) |
ばれいしょの種いも伝染性細菌病(黒あし病・青枯病・輪腐病)の簡易で高精度な保菌検定法を開発する。
2.方法
1)増菌法:生育に好適な液体培地と培養条件(培養日数・振とうの有無)
2)ポリクローナル抗体の作成とそれを用いたELISAの検出精度の検討
3)種特異的プライマーの設計とそれを用いたPCRの検出精度の検討
4)増菌法とELISAおよびPCRを用いた保菌塊茎からの病原菌の検出
3.成果の概要
1)本試験で用いた検定菌株は黒あし病菌3種の23菌株、青枯病菌4菌株、輪腐病菌2菌株、軟腐病菌8菌株などの計41菌株であり、そのうちジャガイモ分離株が31株、本道産分離株が19菌株を占める。
2)黒あし病菌、青枯病菌および輪腐病菌5種の保菌種いもからの共通の増菌法として、基本培地にはKing'B液体培地が好適であった。検出のための培養条件としては黒あし病菌、青枯病菌は25℃、2日間、輪腐病菌では同、6日間以上の振とう培養が必要であった。
3)黒あし病菌3種、青枯病菌および輪腐病菌に対する種特異的なポリクローナル抗体を作成した。これらを用いた直接法ELISAによる識別を行った結果、一部の黒あし病菌間で非特異反応が見られたものの、それぞれの菌種の識別が可能であった。検出限界菌密度は黒あし病菌のうち、E. chrysanthemi(以下Echrと略記)、E. carotovora subsp. atroseptica(同Eca)およびE. c. subsp. carotovoraに(同Ecc)はそれぞれ104,106および104 生菌数/ml、青枯病菌と輪腐病菌は104と106生菌数/mlであった(表2)。
4)PCRによる検定では、黒あし病菌EchrについてはSmid et al.(1995)、Nassar et al.(1996)の方法、EcaについてはDe Boer and Ward(1995)の方法、輪腐病菌についてはLee et al.(1997)の方法が有効と考えられた。
5)黒あし病菌EccのITS領域の塩基配列を他の類縁病原菌と比較して、PCR用の種特異的プライマーを設計した(表1)。これを用いて本菌種の識別を試みた結果、少ない菌株数ではあるが高い特異性が期待された(図2)。
6)青枯病菌共通およびジャガイモに病原性を有する4系統に対してIto et al.(1998)の方法は、本菌共通および各系統の検出特異性が高かった。
7)これらPCRによる各病原菌の検出限界菌密度は輪腐病菌で101生菌数、その他の菌種で102生菌数と検出精度がいずれも高かった(表2)。
8)増菌法とELISAを組み合わせた検定法により種いもからの検出を試みた結果、黒あし病菌と青枯病菌は検出が可能であった。しかし、輪腐病菌では検出精度が低く、有効ではなかった(表3)。
9)増菌法とPCRを組み合わせた検定法により種いもからの検出を試みた結果、黒あし病菌3種、青枯病菌および輪腐病菌の検出が可能であった(表3)。ただし、輪腐病菌では増菌法の改良による検出精度の向上が必要と考えられる。
10)以上のことから、図3に示す、保菌検定マニュアルを作成した。
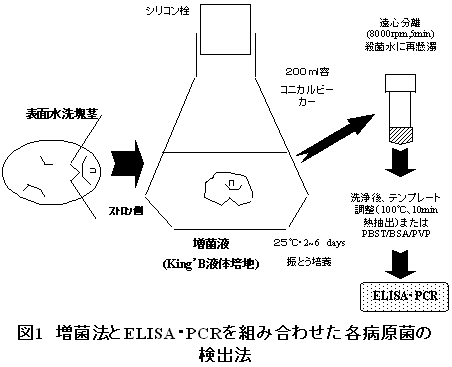
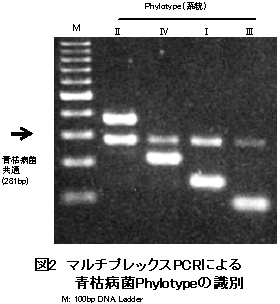
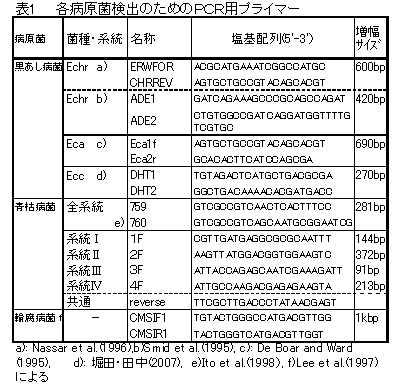
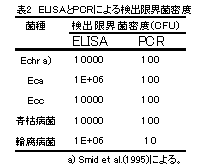

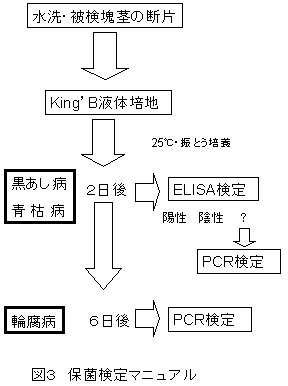
4.成果の活用面と留意点
1)本成果は種いも生産の場面における種いも伝染性細菌病の保菌検定法として活用する。
2)本試験で作製したポリクローナル抗体は配布が可能である。
5.残された問題点とその対応
1)輪腐病菌の選択的培養法
2)マルチプレックスPCRの可能性
3)外国産菌株での特異性と検出精度