| 研究課題名:アスパラガス立茎栽培における病害虫管理技術 (グリーンアスパラガス立茎栽培における病害虫管理技術の開発) (グリーンアスパラガスの新品種,新作型に対応した多収維持管理法) 担当部署:花・野菜技術センター 研究部 病虫科 中央農業試験場 環境保全部 クリーン農業科 協力・分担関係: 予算区分:道費 研究期間:2001〜2007年度(平成13〜19年度) |
アスパラガスの新しい栽培様式であるハウス立茎栽培およびアスパラガスで新たに問題となっている主要病害虫(斑点病、ネギアザミウマ、ジュウシホシクビナガハムシ)の管理技術を開発し、道産アスパラガスの安定生産に資する。
2.方 法
1)空知管内の立茎栽培地域において夏芽収穫中に発生する斑点病とネギアザミウマの実態調査を行った。
2)花・野菜技術センター内ハウスにおいて品種「ガインリム」、「バイトル」、「スーパーウェルカム」の3品種を定植し、ハウス被覆資材について農業用ポリオレフェンフィルムと近紫外線除去フィルム(UVC)の2種類を用い、品種や資材による病害虫の管理技術について検討した。
3)斑点病に対し適切な薬剤防除開始時期や防除回数について検討した。
4)ネギアザミウマに対し有効薬剤と効果的防除法について検討した。
5)ジュウシホシクビナガハムシについて、南空知及び胆振地方においてハウス立茎栽培での実態調査を行った。
6)ジュウシホシクビナガハムシの放虫試験による被害解析と春芽収穫終了後の幼虫に対する薬剤防除効果及び有効薬剤について検討した。
3.成果の概要
1)斑点病およびネギアザミウマは、立茎栽培では露地栽培と異なり夏芽収穫期から発生し、使用可能な防除薬剤が少ないことから対策が問題となっていた。
2)立茎栽培における斑点病に対しては、8月中旬頃からの発病が蔓延し始める時期にトリミングと薬剤散布により防除する。
3)UVCは被覆2年目までは斑点病の抑制効果が期待できる(表1)。
4)慣行の水平方向灌水に比較し点滴灌水で斑点病の抑制効果が期待できる。
5)斑点病は収穫終了時において少発生程度であれば翌年の春芽収量に影響はない。
6)ネギアザミウマは、立茎開始から寄生し、7月後半に増え始め栽培終了まで増加する。被害は、擬葉のかすり状食痕、若茎の傷や鱗片葉の褐変による商品価値の低下である。
7)ネギアザミウマに対しては、UVCと光反射資材の侵入抑制効果が高く有効であるが(図1)、光反射資材は汚れで効果が低下する。UVCは被覆3年目も効果がみられた。有効薬剤は、アセタミプリド水溶剤、クロチアニジン水溶剤、ついでスピノサド水和剤DFであり、7日間隔2回散布や、トリミング後の散布で効果が高まる。
8)立茎栽培でジュウシホシクビナガハムシ(以下、ハムシ)成虫は春芽収穫時から発見され、10月上旬まで認められた。新成虫は7月上旬から羽化し、8月中旬以降は新成虫が主体となった。幼虫は主に立茎開始の6月中旬以降10月上旬まで観察された。
9)ハムシ成虫による被害は立茎栽培では主に春芽の食害であり、3頭/10株以上になると食害率が10%を超えた。平成17年の放虫試験では、ハムシ幼虫が6月上中旬に約50頭/100側枝と多発して茎葉上部がほうき状となり、当年夏芽と翌年春芽の収量の減少を招いた(図2)。
10)春芽収穫終了後のハムシ幼虫に対する薬剤防除は、幼虫の食害による減収を防ぐとともに、次世代成虫の密度を低減させ若茎への食害を抑制する効果がある(図2)。
11)ハムシ幼虫に対して、収穫前日に使用できる薬剤では、ペルメトリン乳剤とアセタミプリド水溶剤の効果が高く、残効は10〜14日間認められた。
12)アスパラガス立茎栽培における主要な病害虫の管理技術を図3にまとめた。
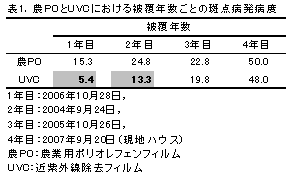
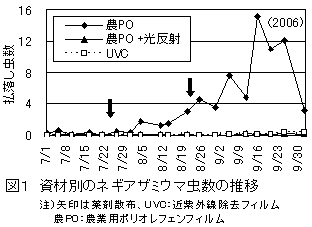
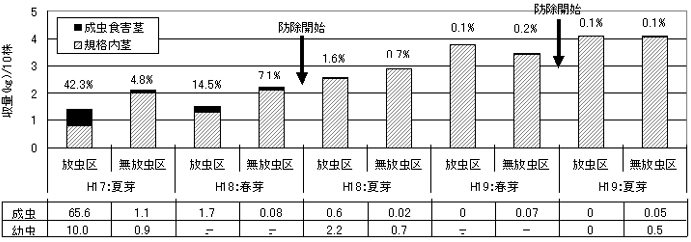
図2 ジュウシホシクビナガハムシの成幼虫密度とアスパラガスの収量
注)図内の数値は食害率。矢印は春芽収穫終了後の防除開始時期。
成虫頭数は10株あたり、幼虫頭数は100側枝あたりの収穫期間平均頭数。
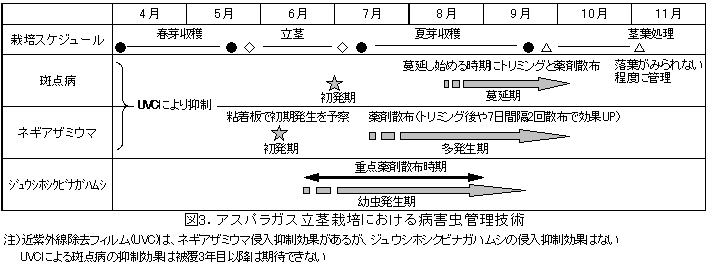
4.成果の活用面と留意点
1)アスパラガス立茎栽培における斑点病、ネギアザミウマおよびジュウシホシクビナガハムシの対策に利用する。
2)ジュウシホシクビナガハムシに対する薬剤防除は幼虫の発生に対応して行う。
3)近紫外線除去フィルムによる斑点病の抑制効果は、被覆3年目以降は期待できない。
5.残された問題とその対応
1)斑点病多発生条件での被害解析
2)ネギアザミウマの要防除水準の設定