| 研究課題:ダイズ茎疫病抵抗性の圃場検定法 (豆類高生産・安定供給のための耐病虫性複合有望系統の選抜強化 3)茎疫病抵抗性検定と高度抵抗性育種素材の作出) 担当部署:中央農試 遺伝資源部 資源利用科 協力分担: 予算区分:道費(豆基) 研究期間:2005〜2007年度(平成17〜19年度) |
ダイズ茎疫病(以下、茎疫病)は水媒伝染性の病害で、道央・上川の転換畑地帯を中心に発生が問題となっている。茎疫病菌Phytophthora sojaeはレースにより品種に対する病原性が異なるが、レース分化が激しいため、レース特異的に作用する真性抵抗性を利用した育種には限界がある。一方、レース非特異的に作用し、長期的効果が期待できる圃場抵抗性育種が近年注目されているが、日本ではその評価法は確立されていない。圃場抵抗性育種の資とするために、場内に造成した多湿圃場における茎疫病抵抗性検定法を確立する。
2.方法
1)茎疫病抵抗性検定圃場の造成
中央農試遺伝資源部内の水田(転換畑)に大豆と水稲を交互に作付け、夏期に1日おきに地表面から5cm程度湛水するよう給水することで多湿状態を維持した。また、検定圃場の土壌から茎疫病菌を分離し、培地挿芽接種法によりレース判定を行った。
2)茎疫病抵抗性圃場検定法確立のための処理条件および調査方法の検討
造成した圃場での抵抗性検定に最適な多湿処理期間、発病調査時期・項目について検討した。また、基準品種選定のために、10レース感受性(北海道で分離が報告された10レースに対する真性抵抗性を持たない)遺伝資源16点を圃場検定に供試した。
3)真性抵抗性を持つ品種の検定圃場における茎疫病抵抗性
北海道の栽培品種・レース判別品種計17点を圃場検定に供試した。
3.成果の概要
1)中央農試遺伝資源部内の水田(転換畑)に、大豆・水稲交互作と多湿処理により安定的に茎疫病が発生する検定圃場を造成した(表1)。検定圃場の土壌から分離した菌株(3レース3菌株)に対して10レース感受性遺伝資源5点が真性抵抗性を持たないことを確認した(データ省略)。また、検定圃場から「はや銀1」(既知の10レース全てに真性抵抗性)を侵す新しいレースが分離された。
2)検定圃場の多湿処理期間は、20日間では短く、7月20日頃からの40日間が必要であったため、処理終了後で成熟期前の9月上旬が最適な発病調査時期と考えられた(図1)。発病調査は、調査が簡便で発病度と高い相関がある枯死個体率を指標とした。
3)供試した10レース感受性遺伝資源16点は、検定圃場における枯死個体率が連続的な分布を示し、品種間差が認められた(図2)。このうち、枯死個体率の年次変動が少なく来歴や熟期の異なる6点を検定圃場における茎疫病抵抗性評価基準品種として選定した。
4)2カ年のデータから、当検定法による抵抗性評価には4反復の供試が必要だと判断した。これらの結果から、茎疫病抵抗性圃場検定の実施要領を作成した(表1)。
5)真性抵抗性を持つ17品種の検定圃場における枯死個体率の品種間の順位には年次変動が少なく、本検定法による茎疫病抵抗性の評価が可能と考えられた(図3)。また、検定圃場での抵抗性と真性抵抗性との間に関連性の見られない品種が認められたことから、本検定法では圃場抵抗性を含めて抵抗性を評価していると考えられる。
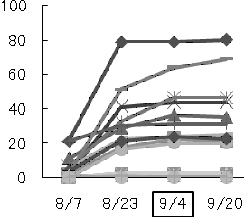 図1検定圃場における 枯死個体率の推移(H19) 10レース感受性遺伝資源16点・ 8反復の平均値を示した。 |
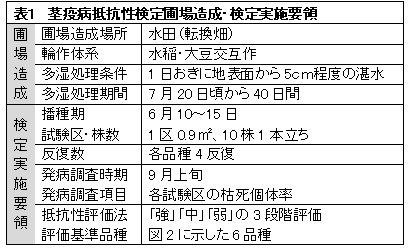 |
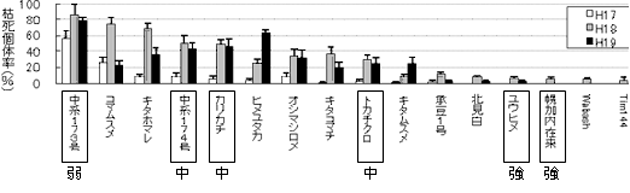
図2 10レース感受性遺伝資源の検定圃場における枯死個体率
8反復の平均と標準誤差を示し、選定した抵抗性評価基準品種を枠で示した。
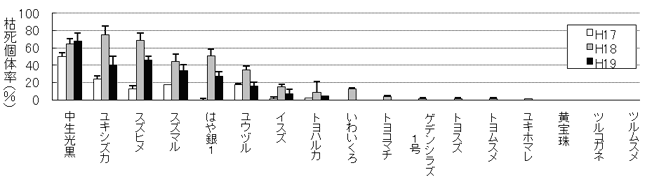
図3 真性抵抗性を持つ品種の検定圃場における枯死個体率 8反復の平均と標準誤差を示した。
平成17年度は「はや銀1」は未調査、「トヨハルカ」は「十育237号」として4反復供試した結果を示した。
4.成果の活用面と留意点
1)開発した圃場検定法は圃場抵抗性を含めた茎疫病抵抗性の選抜・評価に利用できる。
2)真性抵抗性を持つが圃場での発病が多い品種を供試して、検定圃場のレース変遷を把握する必要がある。
3)抵抗性「弱」品種の確認が目的の場合は2反復での供試が可能である。
5.残された問題とその対応
1)検定圃場を用いた圃場抵抗性の作用機構・遺伝様式の解明
2)圃場検定抵抗性評価の現地実証