| 課題分類: 研究課題:ピーマンの主要病害虫に対する生物農薬の適用性 (ハウス野菜の病害虫に対する生物農薬の適応性検定) (ハウス野菜に対する生物農薬を活用した減化学農薬防除体系) 担当部署:花・野菜技術センター 研究部 病虫科 担当者名: 協力分担: 予算区分:農政部事業(クリーン) 研究期間:2005〜2007年度(平成17〜19年度) |
施設栽培では収穫が長期に渡る作物も多く、減農薬栽培技術、特に生物農薬を導入した防除体系確立への要望は多い。北海道におけるピーマン栽培はハウス長期穫りが主体であるが、道ではこれまでピーマンの病害虫について取り組んでおらず、生物農薬の適用性や活用方法について不明な点が多い。このため主要病害虫の問題点、生物農薬の適用性を明らかにすることを目的とした。
2.方法
1)主要病害虫の発生調査:場内ハウスにおいて定期的に調査し、一部被害解析を行った。
2)灰色かび病の発生条件を検討した。
3)うどんこ病に対するバチルス・ズブチリス水和剤の適用性を検討した。
4)主要害虫に対する天敵農薬および微生物農薬の適用性を検討した。
3.成果の概要
1)灰色かび病による果実発病は収穫初期と収穫終盤に、枝発病は収穫期間を通して常に認められたが、発生量は少なく収量に影響しなかった(表1)ことから、通常のハウス栽培条件下では本病に対する薬剤防除の必要性は低いと考えられた。
2)ハウス内が長時間高湿度条件に晒された場合に灰色かび病の発病が高まったことから、本病の多発を防ぐには多湿にならないハウス管理が重要であると考えられた。
3)2005年に道内でピーマンうどんこ病の発生が初確認された。通常初発期は8月で蔓延は9月中下旬と考えられた。また本病により黄化・落葉すると減収する傾向にあった(図1)。
4)バチルス・ズブチリス水和剤(インプレッション水和剤500倍散布、ボトピカ水和剤2000倍散布)はうどんこ病に対して防除効果が認められたが最終的な黄化・落葉を防ぐことができなかったことから、蔓延期以降の利用は困難で、発病初期の防除に適用できると考えられた(図2)。なお、インプレッション水和剤500倍散布で果実の汚れがあったものの、商品価値への影響は低いと判断し、実用上問題ではないと考えられた。
5)主要害虫は、アザミウマ類とアブラムシ類で、次いでヨトウガ、ハダニ類であった。
6)アザミウマに対するタイリクヒメハナカメムシ剤は、アザミウマの侵入が多い8月は効果がないが、侵入抑制効果がある近紫外線除去フィルム(UVC)と併用すると、アザミウマを低密度にでき、減化学農薬ができた(図3)。放飼は、発生初期(粘着板に誘殺)に行うと良い。
7)アブラムシに対するコレマンアブラバチ剤は、UVCで侵入抑制しタイリクやバンカープラント法を併用した場合、アブラムシは低密度になるが、マミーは少なく、タイリクやバンカープラントの天敵等の影響が考えられ効果は判然としなかった。
8)微生物農薬のアザミウマ類に対するボーベリア・バシアーナ剤の効果は低かった。アブラムシ類に対するバーティシリウム・レカニ剤は、湿度条件を満たすことが必要で、本試験では高い効果は得られなかった。
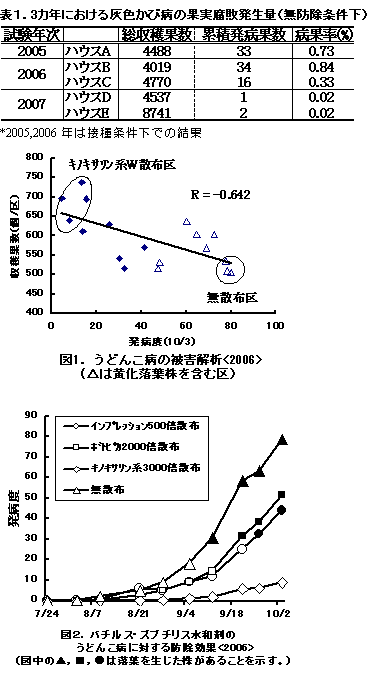
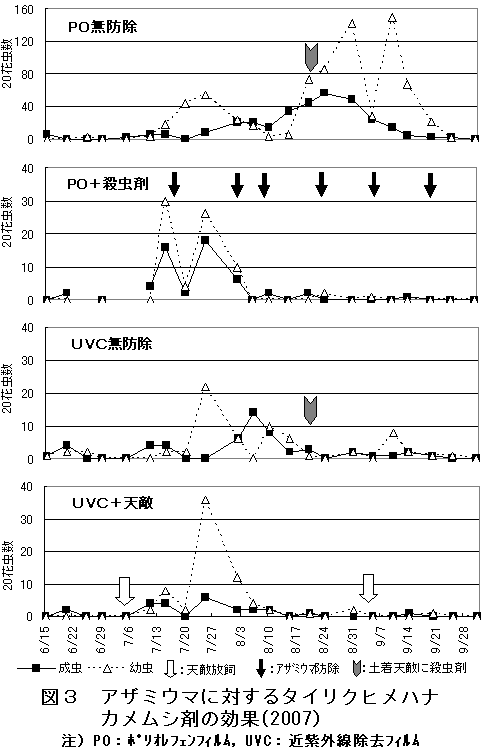
4.成果の活用面と留意点
1)本成績はハウス長期どりピーマンに活用する。
2)生物資材の基本的な取り扱い方についてはメーカー等の情報を参考とする。
5.残された問題とその対応
1)うどんこ病体系防除の実証・確立
2)他の生物資材の適用性や他害虫への対応