| 研究課題:水稲品種「おぼろづき」の食味評価と石狩・空知南部地域における栽培特性 (予算課題名:多様な米ニーズに対応する品種改良並びに栽培技術の早期確立泥炭地における低アミロース品種の活用技術の確立) 担当部署:中央農試 生産研究部 水田・転作科、基盤研究部 農産品質科 上川農試 研究部 水稲科 協力分担:なし 予算区分:受託 研究期間:2004〜2007年度(平成16年〜19年度) |
低アミロース品種「おぼろづき」の品質・食味特性と変動性を解析し、求められる品質目標を提案する。また、本品種の栽培特性を検討し、石狩および空知南部のような泥炭地を中心とした比較的低タンパク米生産が困難な地域における良食味米生産のための栽培指標を提案する。
2.方法
<圃場試験>
1)中央農試岩見沢試験地 試験年次:2004-2007年 供試圃場:泥炭土
窒素施肥処理:少肥(2004:全層0-側条4kg/10a,2005-2007:全2-側4)、中肥(2004:全4-側4,2005-2007:全6-側4)、多肥(2004:全8-側4,2005-2007:全10-側4)
他に栽植密度の増加、浅耕代かき、側条比率、粒厚選別に関する試験
2)北村農業試験圃 試験年次:2004-2006年 供試圃場:泥炭土、処理:窒素施肥(全3.2-側2.8kg/10a、全5.2-側3.2)×栽植密度(22株/m2,35株/m2)
3)当別町農家圃場 試験年次:2005-2007年 供試圃場:泥炭土、グライ低地土、灰色低地土
<人工気象室試験>
試験年次:2004-2006年 供試品種:おぼろづき、ほしのゆめ、ななつぼし、彩、あやひめ
試験規模:1/5000aワグネルポット 温度処理:出穂期以降の温度を以下のように処理した、極高温区(昼/夜:34/28℃)、高温区(30/24)、中温区(26/20)、低温区(22/16)
<炊飯米の物性評価試験>
供試サンプル:岩見沢試験地および現地農家産「おぼろづき」および主要な北海道産米等
調査項目:炊飯米外観特性値、炊飯米物性、炊飯後の炊飯米糊化度
3.成果の概要
1)アミロース含有率が低いことにより、食味評価で重要な「口当たり」「粘り」「柔らかさ」など食感の項目において他の一般うるち品種に比べ、「おぼろづき」は明らかに高く評価された。
2)炊飯後の物性や澱粉糊化度の経時変化および官能試験の結果から、「おぼろづき」は他の品種に比べて、炊飯後の硬化、老化程度が緩慢であり、冷めてもその高い食味が維持された(図1)。
3)「おぼろづき」のアミロース含有率は、出穂後30日間の平均気温1℃あたり1%程度低下した(人工気象室試験)。また、農試の奨励品種決定圃場の気象データから得られた回帰式はy=-0.9447X+34.669、(X=出穂後30日間平均気温、Y=アミロース含有率)であった(図2)。
4)「おぼろづき」の食味は、タンパク質含有率8%未満、アミロース含有率12%以上、16%未満で基準となる「ほしのゆめ」(4カ年平均,タンパク質含有率7.2%、アミロース含有率20.2%)より明らかに優った(図3)。
5)「おぼろづき」の総籾数や不稔歩合等は他の主要品種と類似していたが、千粒重は明らかに軽く、精玄米収量は劣り、タンパク含有率は高い傾向にあった(表1)。
6)良食味米生産を目指した「おぼろづき」の栽培において、総籾数32千粒/m2?33千粒/m2、窒素吸収量9?10kg/10a程度、精玄米収量470kg/10a(篩目1.90mm)を暫定的な目安とし(図4)、そのための生育推移は、幼穂形成期茎数:600本/m2、出穂期茎数:650本/m2、穂数:630本/m2であった(データ省略)。
7)グレーダーの篩目の拡大により精玄米の歩留まりが著しく低下した。篩目1.85mm?1.95mmのタンパク質含有率、アミロース含有率、食味官能評価についての影響は小さく(表2)、1.85mmにすることで精玄米収量は40kg/10a程度増加した。ただし,外観品質が劣る場合もあるため、その際には色彩選別の併用を検討すべきである。
8)以上の知見をもとに、「おぼろづき」における産米品質目標と石狩・空知南部地域における栽培指標(暫定)を提案した(表3)。
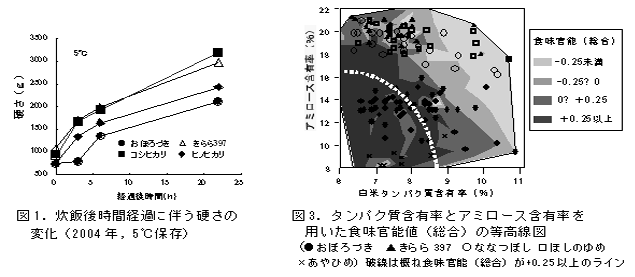
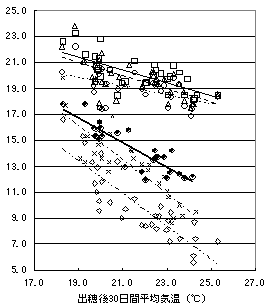 図2.奨励品種決定試験における登熟温度 とアミロース含有率の関係 (●おぼろづき △きらら397 ○ななつぼし □ほしのゆめ ×彩 ◇あやひめ) |
表1.生育および収量構成要素の品種比較(2004-2006年、岩見沢試験地)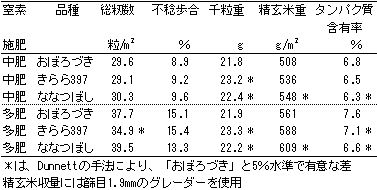 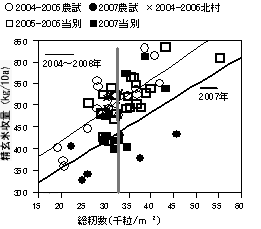 図4.総籾数と精玄米収量の関係 (篩目は1.90mm) |
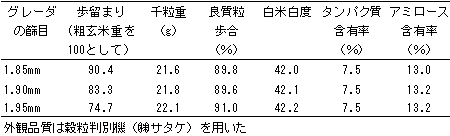
4.成果の活用面と留意点 1)「おぼろづき」の品質向上と安定生産のために活用する。 2)本試験結果は、主に空知南部および石狩の泥炭土で得られたデータである。 3)施肥量については、現行の施肥標準に準拠する。 5.残された問題とその対応 1)土壌および気象変動を考慮した低アミロース品種の栽培指針の作成 |
表3.品質目標と石狩・空知南部 地域における栽培指標(暫定) 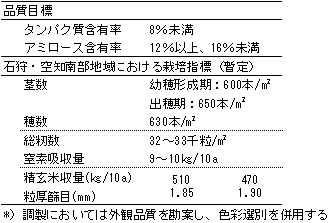 |