| 研究課題:たまねぎ畑の減肥・後作緑肥導入による窒素負荷低減対策の実証 (後作緑肥導入によるたまねぎ畑の窒素負荷軽減対策の実証) 担当部署:北見農試 技術体系化チーム 協力分担:網走農業改良普及センター本所, 同 遠軽支所湧別分室 予算区分:農政部事業(革新) 研究期間:2006〜2007年度(平成18〜19年度) |
北見地域のたまねぎ畑の栽培実態から、窒素負荷からみた課題を明らかにするとともに、現地たまねぎ畑において減肥対応と後作緑肥の栽培による窒素負荷の低減効果を実証する。
2.方 法
1)現地実態調査(1)対象:北見地域のたまねぎ生産者411戸(2)調査項目:有機物施用量, 化学肥料施肥量, 輪作および後作緑肥栽培の実態および各種意識
2)たまねぎ施肥試験(1)試験地域:北見地域4箇所(褐色低地土)(2)品種:北はやて2号またはオホーツク222(3)窒素施肥処理:2水準(慣行, 減肥;過去10年の有機物施用履歴を勘案して決定, 対慣行-2〜-7kg/10a)
3)緑肥施肥試験(1)種類:えん麦, ライ麦(2)窒素施肥処理:2〜3水準(0, 2.1, 4.2kg/10a)
4)窒素負荷低減効果検証(1)作付・施肥別窒素負荷量の推定(2)低減対策導入時の経済性評価
3.成果の概要
1)北見地域のたまねぎ生産者を対象とした栽培実態アンケート調査
(1)総窒素施用量のうち化学肥料による窒素施肥量は平均12kg/10aで、近年減少傾向にある。しかし、施用有機物に由来する窒素量が多い場合でも施肥量を低減する傾向はみられなかった(表1)。たい肥を連用する生産者の割合は8割以上と高いため(データ省略)、連用による窒素放出分を考慮すると、残存窒素量が許容量を超える場合も多いと推察された。
(2)後作緑肥の栽培は全生産者の51%が取り組んでいた。緑肥に対する窒素施肥は38%が行っておらず、栽培の目的として少数ながら「硝酸性窒素汚染防止」の回答があった(データ省略)。
2)たまねぎへの減肥および後作緑肥の導入に関する現地実証
(1)窒素施肥を長期の有機物施用履歴を勘案して減肥した場合、たまねぎの収量は減肥量が2〜4kg/10a程度の場合は慣行と比べ同等程度であったが、それ以上の場合は減収した(図1)。この減収については生育初期の窒素供給が不足したことも要因の1つと推察された。
(2)後作緑肥播種後の積算気温が高いほど緑肥による土壌からの窒素収奪量は多い傾向にあった。窒素を施用した場合の緑肥による土壌からの窒素収奪量は、概ね無窒素施用の場合を下回った。また、えん麦はライ麦よりも高い土壌からの窒素収奪効果があった(図2)。
(3)たまねぎ畑における窒素収支は、たい肥の施用量に大きく影響を受けることから、硝酸性窒素による地下水汚染のリスクを小さくするためには、施用有機物に由来する窒素分を減肥することが重要である(データ省略)。
(4)たまねぎへの窒素施肥に有機物施用履歴を勘案した場合、現地4箇所2箇年の平均では慣行に比べ4.5kg/10a減肥となり、減益となったものの窒素負荷量は4.3kg/10a低減した(表2)。しかし減肥量4kg/10a以下の場合の平均収益は慣行を上回った(データ省略)。
(5)たまねぎへの総窒素施用量を土壌診断に基づいて決定し、「総窒素施用量が12kg/10a(北海道施肥ガイド・窒素肥沃度水準Ⅲ)のときに粗生産額が慣行施肥と同等に維持できた」
| 表1 現地実態調査における有機物施用量と 化学肥料による窒素施肥量の関係 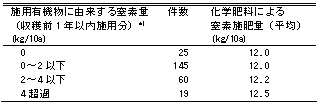 調査は2006年実施 *北海道施肥ガイドによる減肥可能量に相当 |
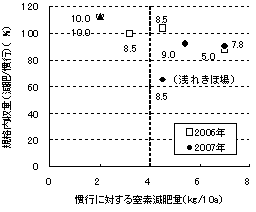 図1 たまねぎへの窒素減肥量と規格内収量の関係 (▲(2007年の1点)は総収量について表示) 図中の数字は減肥区の窒素施肥量(㎏/10a) |
| 表2 たまねぎへの減肥・後作緑肥導入による 経済性と窒素負荷低減効果 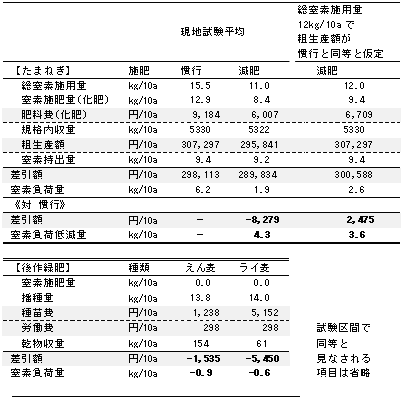 |
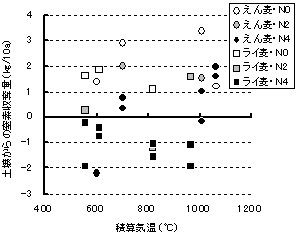 図2 積算気温と後作緑肥による 土壌からの窒素収奪量の関係 (作物による土壌からの窒素収奪量=窒素吸収量−窒素施肥量) |
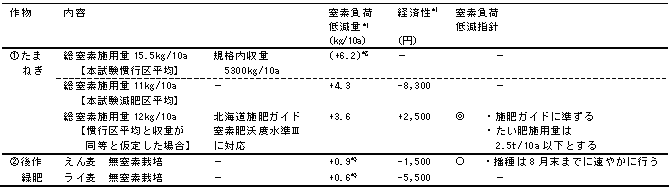
現地試験のたい肥施用量は平均2.6t/10a *1 ①たまねぎは本試験の慣行区, ②後作緑肥は緑肥なしに対する評価
*2 総窒素施用量から持出量を差し引いた実数 *3 すき込まれた窒素の土壌中への放出割合は59%で計算
4.成果の活用面と留意点
1)北見地域のたまねぎ畑における窒素負荷低減のための減肥、後作緑肥導入時の参考とする。
2)窒素負荷量と経済性の関係は本試験結果に基づいたものであり、地域や気象、土壌等により異なる場合がある。
5.残された問題とその対応
1)有機物施用履歴に基づいたたまねぎへの窒素施肥技術の開発
2)土壌条件(窒素肥沃度, 硬度, 土性等)に対応した後作緑肥の導入基準の策定