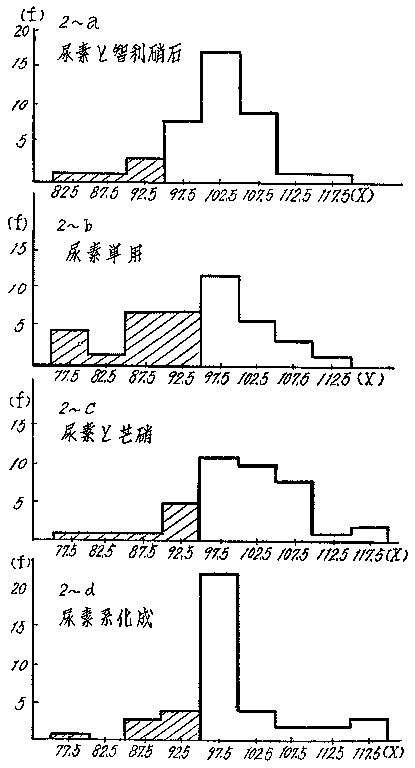
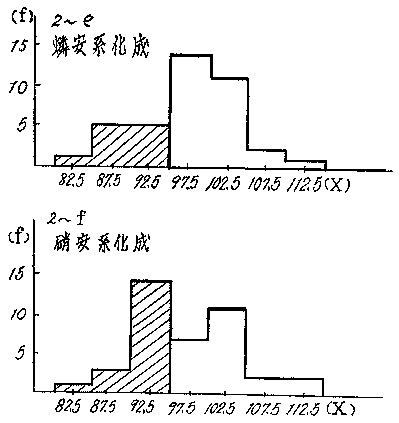
【指導上の参考事項】
| てん菜に対する尿素並びに複合肥料について
北海道農業試験場 作物部 |
Ⅰ まえがき
従来、甜菜栽培用のN質肥料としては6:4あるいは5:5の比率をもって智利硝石と硫安の併用が一般的に行われてきたが、国内に智利硝石の算出がなく、その全量を外国からの輸入にたよらなければならないため、これが確保と配分に手数と困難を伴うと共に他肥料との配合ならびに価格の割高等にも問題があった。
一方酷なⅡおいては智利硝石に比較して割安でしかも使用に便利なN質肥料が多量に生産されている。よって智利硝石を使用することによって起こる諸種の問題を回避すると同時に国内産肥料の利用を図り甜菜栽培をより有利に展開する目的で数年前より諸種の肥料試験を実施してきた結果、尿素の使用、あるいは他のN質肥料を原料として製造された複合肥料の施用によっても智利硝石を使用した場合と大差ない効果を期待することができることを認めたので、関係機関相協力して最終的な結論を得ようと企画し試験を実施した。以下はその成績の概要である。なお詳細は支庁および改良普及所に別途配付の本成績を参考せられたい。
A 試験実施場所
試験実施場所はつぎの41ヶ所である。
Ⅰ 農業試験場関係
北農試琴似本場、渡島、北見、十勝、根室、天北、宗谷各支場、紋別重粘地研究室、大正火山灰地研究室、上川支場士別畑作試験課
Ⅱ 製糖会社関係
日甜~中士別、磯分内
ホクレン~東藻琴、斜里
台糖~八雲、伊達紋別、大滝
芝糖~端野、上湧別
Ⅲ 改良関係(普及所名)
北檜山、早来、静内、狩太、留寿都、広島、美深、長沼、美瑛、豊富、幌延、北見、白糠、東藻琴、幕別、大樹、士幌、池田、十勝清水、足寄、女満別、壮瞥
B 供試肥料
燐酸と加里肥料ならびに硝安系化成肥料以外は各実施場所同一製品を使用した。すなわち尿素、配合2号、尿素化成は東洋高圧、燐安系化成は神島化学硝安系化成は住友ならび
に日産化学工業株式会社において製造したものであり、燐酸、加里肥料はそれぞれの現地において購入したものを用いた。なお含有成分は尿素N46%(複合)化成肥料は3種ともN-
10P2O513-K2O5%、配合2号は5-13-5%であり、芒消は理論値32.37%のものである。なお、智利硝石は現地において購入したものであるが、これは同一品と見做しても差し支えないものと
思考される。
C 施肥設計ならびに試験区別
根釧、宗谷、天北地域はB表、その他の地域はそれぞれA表の施肥設計によった。試験区別(7)の硝安系化成肥料は尿素系、燐安系化成肥料の対照肥料として組み入れたものであ
る。
(A)
| 10a当要素量(kg) | 10a当施肥量(kg) | |||||||||
| 窒素 | 燐酸 | 加里 | 配合2号 | 智利硝石 | 尿素 | 化成 | 芒硝 | 過石 | 硫化 | |
| 1 標準肥料 | 11250 | 14625 | 5615 | 112500 | 35156 | - | - | - | - | - |
| 2 尿素と智利硝石 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 85156 | 12228 | - | - | 73127 | 11250 |
| 3 尿素単用 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | 24457 | - | - | 〃 | 〃 |
| 4 尿素単用(芒硝) | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | 24457 | - | 29404 | 〃 | 〃 |
| 5 尿素系化成肥料 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | 112500 | - | - | |
| 6 燐安系化成肥料 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | - | - | ||
| 7 硝安系化成肥料 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | - | - | ||
| 8 無窒素 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | 73125 | 11250 | ||
(B)
| 10a当要素量(kg) | 10a当施肥量(kg) | |||||||||
| 窒素 | 燐酸 | 加里 | 配合2号 | 智利硝石 | 尿素 | 化成 | 芒硝 | 過石 | 硫化 | |
| 1 標準肥料 | 7000 | 9750 | 3750 | 75000 | 23438 | - | - | - | - | - |
| 2 尿素と智利硝石 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 23438 | 8152 | - | - | 48750 | 7500 |
| 3 尿素単用 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | 16304 | - | - | 〃 | 〃 |
| 4 尿素単用(芒硝) | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | 16304 | - | 19531 | 〃 | 〃 |
| 5 尿素系化成肥料 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | 75000 | - | - | - |
| 6 燐安系化成肥料 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | 〃 | - | - | - |
| 7 硝安系化成肥料 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | 〃 | - | - | - |
| 8 無窒素 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | - | - | 48750 | 7500 |
D 複合肥料の粒度分布とpH
本試験に供試した複合肥料の粒度分布とpHを参考までに示すと次の通りである。
| (尿素系) | (燐安系) | (硝安系) | (配合2号) | |
| 4mm> | 8.7 | 4.9 | 0.1 | 3.0 |
| 2~4mm | 64.1 | 65.7 | 52.1 | 23.1 |
| 1~2mm | 25.0 | 23.5 | 37.3 | 66.2 |
| 1mm> | 2.0 | 5.9 | 10.5 | 7.7 |
| pH(H2O) | 4.13 | 4.20 | 3.85 | 27.0 |
Ⅱ 概評
甜菜に対する尿素ならびに尿素系、燐安系両複合肥料の施用効果について験知するため、道内41ヶ所において圃場試験を実施した。その結果連絡と試験実施上の不備、或いは圃場の異質性その他のことによって全ヶ所に必ずしも完全なる試験成績を得ることの出来なかった憾はあるが、反面広く試験を実施したことによって甜菜に対するこれら肥料の効果の概要については明らかにし得たものと思考される得られた。
試験成績から標準肥料の菜根収量を100とした各処理区の収量指数を一括して表示すると表Cの通りであり、それを又収量指数(75~80)、(80~85)、(105~110)というように5%宛を1区分とする階層に分けるとD表の如き度数分布が得られ、更にそれに基づく度数分布柱状図形(ヒストグラフ)を作成すると第2図a~fの如くなる。
(C)
| 処理区分 試験所別 |
尿素 智利硝石 |
尿素単用 | 尿素 芒硝 |
尿素系化成 | 燐安系化成 | 硝安系化成 | 無窒素 | |
| 琴似本場 | 農試 | A 104.8 | 106.8 | 103.4 | 99.2 | 98.6 | 99.2 | - |
| B 109.1 | 105.9 | 115.1 | ||||||
| 火山灰地研究室 | 103.6 | 91.4 | 108.9 | 110.7 | 99.3 | 90.1 | 40.7 | |
| 重粘地研究室 | 89.9 | 79.7 | 74.9 | 108.0 | 103.8 | 101.0 | - | |
| 十勝支場 | 103.8 | 96.9 | 102.5 | 102.4 | 100.7 | 102.0 | 94.0 | |
| 北見 | 111.8 | 91.5 | 96.0 | 96.5 | 100.2 | 97.6 | 93.4 | |
| 根室 | 103.9 | 90.6 | 99.8 | 95.3 | 105.2 | 98.0 | 93.1 | |
| 宗谷 | 100.6 | 103.3 | 106.4 | 100.3 | 97.5 | 102.9 | 65.9 | |
| 天北 | 102.1 | 103.5 | 107.3 | 95.4 | 100.0 | 92.9 | 75.6 | |
| 渡島 | 116.4 | 99.4 | 106.9 | 98.1 | 97.3 | 97.3 | 72.9 | |
| 士別畑作試験課 | 101.6 | 85.6 | 97.9 | 100.8 | 96.8 | 105.4 | 39.8 | |
| 日甜、磯分内 | 製糖 会社 |
109.4 | 75.0 | 104.9 | 86.2 | 86.8 | 89.6 | 86.2 |
| 〃 、 士別 | 108.3 | 91.7 | 104.7 | 96.8 | 105.5 | 109.3 | 70.2 | |
| ホクレン、斜里 | 98.3 | 89.9 | 99.7 | 86.8 | 89.5 | 92.6 | 70.6 | |
| 〃 、東藻琴 | 108.0 | 95.9 | 101.5 | 97.6 | 104.1 | 102.7 | 70.0 | |
| 台糖、伊達 | 104.4 | 103.5 | 98.5 | 97.1 | 103.2 | 99.4 | 82.7 | |
| 〃 、大滝 | 103.5 | 101.1 | 98.4 | 99.8 | 98.7 | 102.3 | 84.7 | |
| 〃 、八雲 | 107.7 | 87.1 | 97.6 | 77.4 | 98.6 | 91.3 | 73.2 | |
| 芝糖、上湧別 | 96.3 | 95.4 | 104.9 | 117.4 | 80.2 | 88.4 | 44.7 | |
| 〃 、端野 | 90.4 | 87.9 | 99.1 | 96.8 | 87.5 | 87.7 | 86.8 | |
| 白糠 | 改良課 | 104.4 | 97.2 | 99.7 | 119.4 | - | - | 97.2 |
| 女満別 | 102.4 | 95.3 | 103.8 | 99.5 | 95.3 | 101.0 | 78.3 | |
| 東藻琴 | 96.6 | 95.5 | 89.8 | 93.5 | 93.3 | 93.1 | 92.1 | |
| 北見 | 109.3 | 79.4 | 84.2 | 99.6 | 94.5 | 100.6 | 67.3 | |
| 幌延 | 105.5 | 109.2 | 117.0 | 117.0 | 103.9 | 112.1 | 78.0 | |
| 美深 | 107.1 | 101.5 | 106.3 | 112.8 | 100.3 | 103.9 | 89.1 | |
| 豊富 | 101.6 | 110.8 | 109.4 | 108.9 | 42.7 | 113.6 | 58.1 | |
| 北檜山 | 101.6 | 100.4 | 98.4 | 95.8 | 102.4 | 94.7 | 51.7 | |
| 大樹 | 96.0 | 95.6 | 109.2 | 101.1 | 96.4 | 91.2 | 58.8 | |
| 静内 | 97.6 | 88.4 | 93.2 | 96.6 | 92.6 | 90.2 | 82.5 | |
| 留寿都 | 105.2 | 91.6 | 100.8 | 97.7 | 98.1 | 104.6 | 82.9 | |
| 狩太 | 93.7 | 88.8 | 92.2 | 87.4 | 89.7 | 92.6 | 80.3 | |
| 幕別 | 100.9 | 90.4 | 109.1 | 97.2 | 86.1 | 96.8 | 73.4 | |
| 足寄 | 96.7 | 97.3 | 95.8 | 97.1 | 95.0 | 94.4 | 76.6 | |
| 士幌 | 101.3 | 77.7 | 94.6 | 98.0 | 98.5 | 95.6 | 75.0 | |
| 池田 | 104.0 | 89.4 | 98.6 | 97.4 | 103.0 | 101.0 | 83.8 | |
| 清水 | 94.1 | 97.0 | 99.4 | 92.6 | 94.8 | 82.0 | 74.9 | |
| 広島 | 96.0 | 94.9 | 92.2 | 97.9 | 95.4 | 94.9 | 74.2 | |
| 壮瞥 | 103.8 | 95.8 | 109.2 | 99.5 | 97.9 | - | 64.8 | |
| 長沼 | 97.9 | 99.6 | 105.8 | 93.3 | 90.4 | 103.1 | 78.2 | |
| 早来 | 101.5 | 110.0 | 112.5 | 92.5 | 101.1 | - | 101.5 | |
| 美瑛 A | 85.0 | 84.5 | 93.1 | 95.3 | - | 94.4 | 76.0 | |
| 〃 B | 97.1 | 83.9 | 108.0 | 97.1 | - | 81.7 | 87.6 | |
| 〃 C | 87.8 | 121.5 | 140.2 | 102.8 | - | 123.4 | 83.2 | |
(D表) 度数分布表(琴似本場の尿素関係は、B、美瑛はAを採用した。燐安系は63、硝安系は38場所分で尿素系は41場所である。)
| 階級 | 階級値(X) | 尿素と智利硝石 | 尿素単用 | 尿素と芒硝 | 尿素系化成 | 燐安系化成 | 硝安系化成 |
| 度数(f) | 度数 | 度数 | 度数 | 度数 | 度数 | ||
| 75~80 | 77.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80~85 | 82.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 85~90 | 87.5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 90~95 | 92.5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 |
| 95~100 | 97.5 | 8 | 12 | 11 | 22 | 14 | 7 |
| 100~105 | 102.5 | 17 | 6 | 10 | 4 | 11 | 11 |
| 105~110 | 107.5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 110~115 | 112.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 115~120 | 117.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - |
1. 尿素関係
各試験実施場所の成績、或いはそれを要約した前表図2a~cによって明かな如く、尿素単用区が土壌別では火山性土、洪積重粘土、地域的には道東、道北といった一般に立地条件が不良と考えられる場所において発芽障害、生育の遅延、その他のことによってその収量が劣るを示した意外は2~3の例外はあるが大体において智利硝石、芒硝との併用、単用いずれによっても標準肥料に比し殆ど遜色のない効果を期待出来ることを認めたのであるが、しかし一般に尿素の施用によって発芽が可成り阻害され欠株が多かったことと、単用に比較しNa塩の補給源として芒硝を併用したものが大体において良結果を収めているので、甜菜栽培用のN質肥料として尿素を使用する場合、発芽阻害の回避とNa並びに微量要素の併用等について今後大いに考えていかなければならないものと思考される。
尿素を基肥として使用する場合、いわゆる発芽障害が起こり易いことについては多くの人によって広く経験されているが、その原因については尿素の分解過程におこるアンモニア化に伴う局部的なアンモニアの集積と土壌のアルカリ反応、それに伴う障害の発生が考えられる。従って尿素施用による発芽障害は特に土壌が砂質で有機物に乏しく微生物的活力が貧弱にして土壌の緩衝能力の低い処と、低温乾燥の起こりやすい処において助長されるであろうことは容易に想像されることであり、又施用量が多く種子と比較的接触しやすい「肌肥的」施肥の場合に多く認められるであろう。よって土壌、気象条件の不良な処においては勿論、その他の地帯においても他作物に比し比較的多量のN施用を必要とする甜菜作に尿素を施用する場合には1部全面施肥や1部条肥といった施肥法について検討を加える必要があり、又条肥する場合には可能な限り十分土壌と混和するよう努めることが肝要である。
次に単用区に比し芒硝併用区が4~5ヶ所を除いてはいずれも良結果を収めて芒硝併用の効果が顕著に認められた。P.M.Harmerらはいろいろの作物を栽培してNa塩に対する性質について研究した結果、加里の豊富な場合においても甜菜に対してはNa塩施用の効果が大であったと報告し、J.J.Lehrは甜菜葉面積を増大すると述べている。従来甜菜栽培用のN質肥料として智利硝石を使用してきたが、これはNの形体がNO3-Nであるばかりでなく、多量のNa塩を含有しているということも大きな理由として挙げられる。更に微量要素、Mgの如き特殊成分の併用等についても当然考慮すべきであるが、ここではこの問題に対する議論は省略したい。
以上要約すると、施用量の増加に伴ってその施肥法を考え、又Na塩並に必要微量要素等の併用を行えば充分甜菜用N質肥料として尿素の使用は可能であり、従来の標準肥料に比し同等乃至はやや優る結果を期待できるということになる。しかし実際使用農家の安全を期すため現状においては比較的立地条件の恵まれていると考えられる地帯を中心に使用し今後の試験研究の結果と併行して漸次使用地帯を拡大せしめるのが妥当の如く思考される。
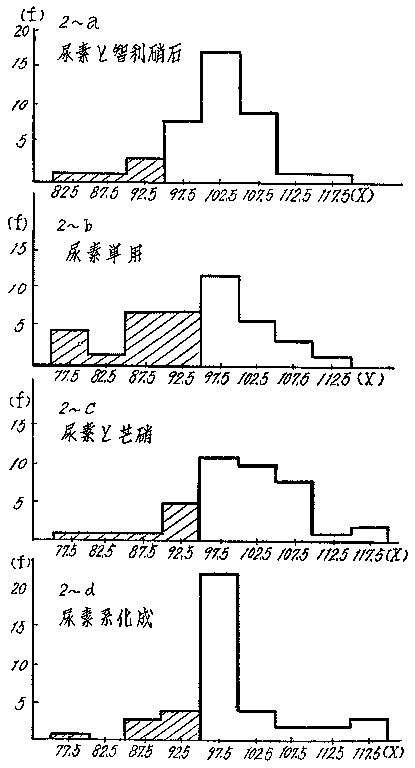 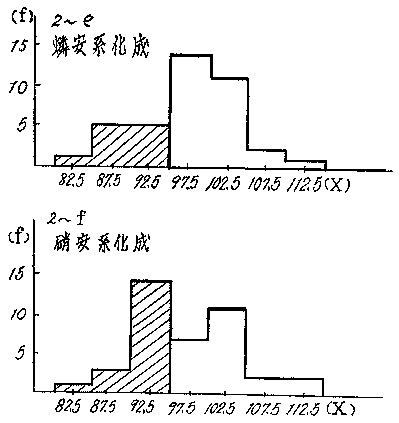 |
2. 複合肥料関係
尿素系化成肥料は日甜磯分内、ホクレン斜里、台糖八雲、改良課狩太、清水、長沼、燐安系化成肥料は日甜磯分内、ホクレン斜里、芝糖上湧別、端野、改良課静内、狩太、幕別、長沼といった殆ど火山性土壌地帯と考えられる場所において肥効が1部劣ったが、試験実施場所の約2/3に該当する場所においては標準肥料の収量100に対し95~105%の収量指数を示して殆ど遜色のない収量を収めると共に既に試験段階を終えて市販使用されている硝安系化成肥料より全体としてはやや優るが如き結果を示し、懸念された初期成育の遅延並に不良といった現象は概して認められなかった。
以上の如く両化肥料とも1部の地帯においてその肥効が劣った以外は大体において標準肥料、硝安系化成肥料に比し大差ない結果を示して充分甜菜複合肥料として使用し得ることを認められたのであるが、尿素系化成肥料は尿素単用の場合に比し、その程度は可成り軽減されているとはいえ、比較的発芽障害による欠株が多く認められると共に、化成肥料区は一般にT/R Ratioが高きを示した場合が多い。尿素系化肥料を施用した場合、比較的欠株の多く認められたことの原因については先に論述した尿素の項と同様と考えられるので省略するが、一般に化成肥料のT/R Ratioが高きを示したことについては、尿素系化成肥料については分解遅延の影響ということもある程度関与しているかもしれないが、それにも増して炭安(アンモニア化成をうけると尿素は重炭安の形になる。)並に燐安は粉状にあって硫安や硝安に比較して土壌吸着能と吸着強度が大であるのに加えてそれが粒状化されているため一層Nの損失が寡く後半に至っても尚Nの供給が多かったためと解せられる。従ってこのことは相対的な肥効の持続性と利用率の大なるを示しているとみることが出来るが、しかし甜菜栽培にとって過度の肥効の持続性はかえって負に働くことが多いので場合によっては幾分施用量を減ずるとか、物理性の改善を図るが如き対策が必要であろう。勿論以上述べたN以外の問題も幾分関係しているであろうことは容易に推考し得ることであるがNの問題に比すれば、影響の度合いは可成り軽度のものと思考される。
而して物理性の改善成分比率の適正化による肥効の増進、施用量、施肥法との関連における肥効並に登熟状態の関係、その他諸種の問題について改善と試験研究を重ねていかなければならないが、物理性の改善と成分比率の適正化については既にメーカーに対し要望してあるので実際市販されるものについては或る程度改善された物が出来ると思われるし、又施用量、施肥法との関連における肥効並に登熟状態、その他検討を必要とする事項については今後試験を実施して明らかにしたいと考えている。更に1部の場所において肥効が劣っているが、原因については明確を欠く点が多いので、これらの点についても引き続き試験を実施して解明する必要があろう。