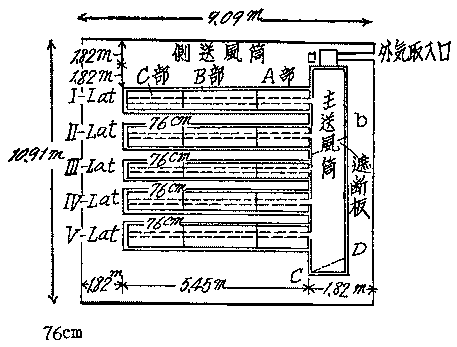
第1図 送風筒配置図
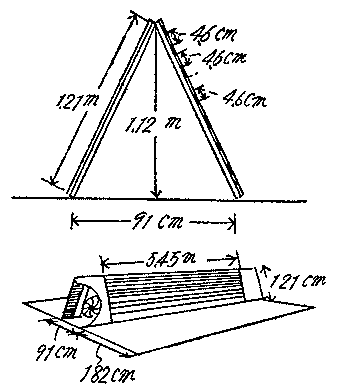
第5図 Aフレームの縦断面図
【指導上の参考事項】
| 牧草送風乾燥に関する試験成績について
北海道農業試験場畜産部 |
Ⅰ 目的
北海道における乾草調製は天日乾燥法に全面的に依存しているが、地域によっては牧草刈取期の気象条件が必ずしも好適しない場合がある。かかる地帯の乾草調製はきわめて困難であるばかりでなく、飼料価値の少ないものを生産しているのが現状である。またその他の地域でも年により刈取期の雨天は乾草調製をはなはだ困難にしている。このことは日本のおかれている多雨多湿型気象条件に由来するものとは考えられるが送風乾燥法による乾草調製技術はこの点を十分補い得るものと思われる。さらに最近酪農振興にともないルーサンの作付が拡大されているが、これが乾草調製には従来多くの労力を要し、三角架乾燥法によるなどして多くの労力を要し、利用面における隘路はその作付拡大を抑制する大きな要因の一つともなっていた。かかる調製上の難点は送風乾燥法により容易に解決し得ると考えられる。
本試験は以上の理由から北海道における酪農振興の基礎を確立する上にきわめて有意義と考え計画された。
Ⅱ 試験経過
1. 試験担当
北海道農業試場畜産部 飼料作物第1研究室
牧野研究室
業務科
北海道立農業試験場 農機具試験室
2. 送風施設の概要
(1) 送風施設
ⅰ) 側方主送風筒型(Side main dust System)
(イ) 送風筒の配置 第1図のとおり
(ロ) 送風筒の大きさ 第2.3図のとおり
主送風筒
断面積 0.99㎡(3.8尺×2.85尺)
側送風筒
A部 0.226㎡(1.35尺×1.8尺)
B部 0.201㎡(1.35尺×1.6尺)
C部 0.172㎡(1.35尺×1.4尺)
本数 6
(ハ) 送風量 61982m3/sec(13133.37cfm)
(ニ) フアン シロツコフアン(直径457.2mm 回転数 750rpm)
(ホ) 使用動力 10馬力モーター
(ヘ) 堆積床の面積 99.2㎡(5間×6間)
ⅱ) Aフレーム型(A-Frame System)
(イ) Aフレームの配置 第4図のとおり
(ロ) 送風施設の大さ 大5図のとおり
(ハ) 送風量 5.13838m3/sec(10887.71cfm)
(ニ) フアン 柳井式中型送風機(MS1号)
直径 720mm 回転数 1485rpm
(ホ) 使用動力 3馬力モーター
(ヘ) 堆積床の面積
ⅲ) スラツト床型(Slatted-floor System)
A 関東東山農試式(1953~1957年)
(イ) スラツト床の配置 第6図のとおり
(ロ) スラツト床の大きさ 3.64m×1.82m×0.9m(間口×奥行×高さ)
(ハ) 送風量 0.98m3/sec(2076.6cfm)
(ニ) フアン 富士式送風機
直径 600mm 回転数 1400rpm
(ホ) 使用動力 1馬力モーター 1450rpm
(ヘ) 堆積床の面積 6.6㎡
B 柳井式(1959年)
(イ) スラツト床の配置 第7.8図のとおり
(ロ) スラツト床の大きさ 第9.10.11図のとおり 2.73m×3.64m×1.82m(間口×奥行×高さ)
(ハ) 送風量 2.5288m3/sec(5358.27cfm)
(ニ) フアン 柳井式小型送風機(S2号)
直径 577mm 胴翼 20枚 回転翼 10枚 回転数
(ホ) 使用動力 1馬力モーター 1450rpm
(ヘ) 堆積床の面積 9.9㎡
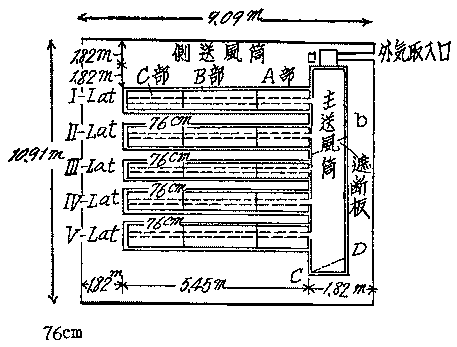 第1図 送風筒配置図 |
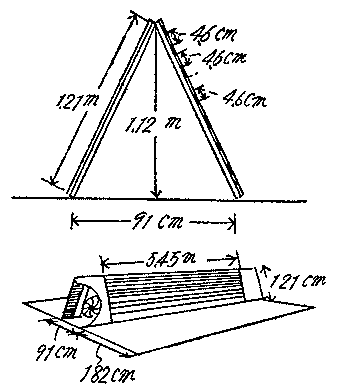 第5図 Aフレームの縦断面図 |
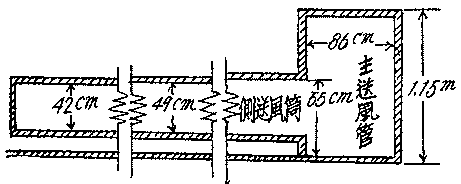 第2図 送風筒縦断面図
|
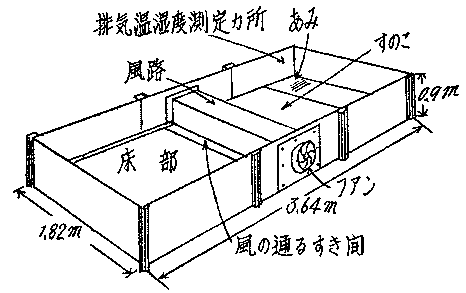 第6図 関東東山農試式スラツト床型空気は風路から “すのこ”の下部に入り、“すのこ”の上に 堆積された牧草をとおり上に抜ける。 |
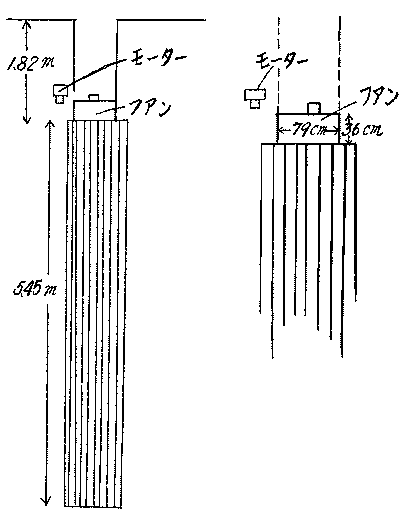 第4図 フレーム配置図 Aフレームフアンの取付位置 |
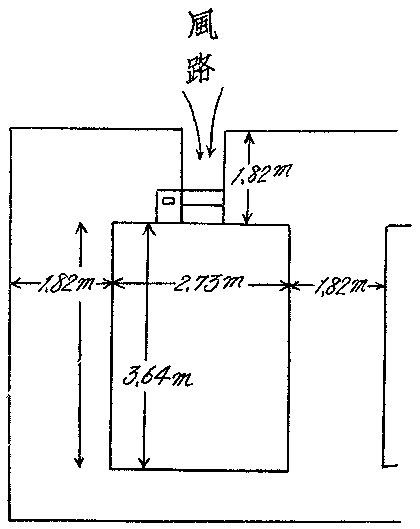 第7図 スラツト床型配置図(柳井式) |
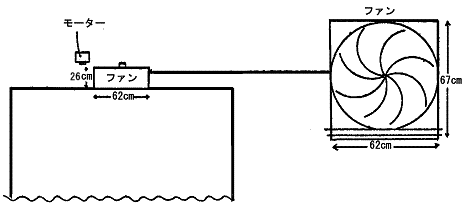
第8図 スラツト床型、ファンの取付位置
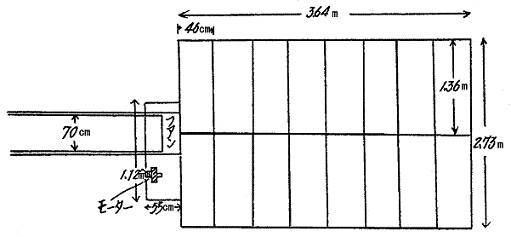
第9図 スラツト床平面図
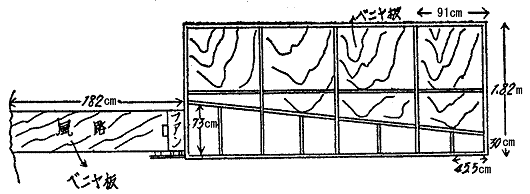
第10図 スラツト床側面図

第11図 スラツト床断面図
Ⅲ 試験の結果留意すべき点
(1) 送風乾燥施設設置上の一般的注意事項
1) 乾燥施設は通常乾草を収納する畜舎二階に設置することが望ましく、その大きさは設置場所の坪数によって決まるが、乾草すべき牧草量、原動機その他の事項も考慮する必要
がある。
2) 送風中に堆積乾草からでる湿った空気が再び送風機に入って循環しないように、送風機はできうれば乾燥室外に取り付けることが望ましく、乾燥室と同一室内に取り付ける場合は、
これをベニヤ板などで遮断するようにする。
3) 送風機は北側よりむしろ西側、南側に取り付ける方が望ましく、乾燥室の床、送風筒などからの空気もれがないようにする。
(2) 乾燥施設
1) 乾燥施設としては、スラツト床型、筒型法(ダクトシステム)のほかAフレーム型が実用的である。
2) 送風機
(イ) 大別してプロペラ型と多翼型の種類があるが一般にプロペラ型が安価で好都合である。
(ロ) 送風量は正確にはさらに精密な試験調査を必要とするが、一応乾草中に含まれる水分1kg当り0.005~0.009m3/secの風量を送るようにする。
(3) 送風乾燥実施上の注意事項
(ⅰ) 圃場予乾
1) 適正な時期に刈りとられた牧草は、刈取り時における牧草の水分含量は大体70~80%くらいであるが、圃場で予乾して納屋に入れられる時の最適水分含量は大体40~45%とされて
いる。この程度の水分含量では、葉は凋れるが砕けて損耗を招くようなことがなく緑色を保っている。手でしぼって汁液が容易に茎からでる程度ならば、この乾草は水分が多すぎるの
であるから、さらに天日に乾燥をつづける必要がある。
2) 晴天に恵まれれば朝方に刈られた牧草は昼過ぎには凋れはじめるから2日目の朝には反転され午後には収納できる程度となる。圃場乾燥の促進にはヘイコンディショナーの使用
が有効で、刈取り後、ヘイコンディショナー作業を引き続き行うような作業計画が望ましい。
3) 一般に牧草の刈取り日は天候、牧草の種類、収量、土地の乾き具合その他の要因を考慮に決められるが、牧草が圃場で乾燥し過ぎると緑色は失われ葉は砕けて損耗し易く、水
分含量が多すぎると送風によって除かるべき水分が多くなり、乾燥に要する時間を長引かせるばかりでなく収納量をも減少する。
(ⅱ) 収納
1) 納屋への乾草積み込みはなるべく水平になるように入れて、常に均一の厚さを保つようにする。また積み込み時に乾草を踏圧すれば、空気の滲透を不良とし、乾燥効果を低下せ
しめる。
2) またスラツト床型などで、壁に接するまで十分乾草を積み込む場合は、この部分の茎葉は壁に支えられて堆積密度が小さくなり、さらに壁が多少なりとも振動するので壁に沿って空
間ができ、乾燥が速く進行するから周囲は若干高く堆積するか、または密に堆積する必要がある。
3) 一般に乾草積み込みの厚さは2m前後が普通であるが、乾燥後にはさらに積み込んでその厚さをこともできる。
(ⅲ) 送風
1) 送風筒が十分乾草でおおわれれば直ちに送風を開始する。大体収納時の乾草含水率が50%以上であれば、収納翌朝からの送風を行う場合、夜間中に醗酵による発熱を伴う場合
が多い。とくにマメ科牧草ではこの危険が多いから、水分含量の高い材料を用いる場合は収納中または直後からの送風が必要である。
2) 送風は天候、牧草の状態を考慮に行われるが大体5~7日は要する。雨天、夜間その他外気湿度のきわめて高い場合の送風は、乾燥効果を減ずるから、発熱の危険がない場合
はかかる気象条件下の送風は避ける方が経済的である。
3) 送風中は随時乾草堆積の温度を点検することが望ましく、これにより発熱徴候の有無を調べ得る。送風は乾草堆積中に湿り気の部分がみあたらなくなった時期にフアンを3~4時
間停止し、その後に温かい箇所または加熱の徴候があるか否かを調べながら行うようにする。もしも湿気が堆積乾草の上部から上がっている場合は再び送風を開始する。このよう
な点検は温度の上昇が止み、十分乾燥が終わるまでくりかえす必要がある。最後に2~3日フアンを停止した後最終的に放熱せしめるため再び短時間内の送風を行って仕上げる。
4) 乾草堆積の温度上昇は送風によりこれを冷却上昇を防止しうる効果がある。収納直後にこの危険のある場合は、降雨時でも送風の必要がある。低含水率乾草の送風は、外気か
らの吸湿があるから注意を要する。かかる吸湿現象は、乾草堆積から排出された湿った空気が、収納舎の排気状態が不良なため循環しておこることもある。
5) 晴天時の日中湿度は50~60%であるが、この程度の空気では12~15%ぐらいまで乾燥せしめうるが、雨天時の空気湿度は80%ぐらいあるからこの程度では18~20%ぐらいまでしか乾
燥せしめえない。これは空気の湿度と乾草の含水率との間に平衡関係があるためで(平衡含水率という。)、20%程度以下の乾草に80%以上の空気を送り込むと乾草は逆に平衡含水
率近くまで吸湿しいわゆる「戻り」の現象をおこすことがある。一般的には外気湿度85%以上になると、乾燥速度きわめて遅く、十分その効果を期待しえない。
送風期間中を通じて外気湿度は75%以下が好適のようである。
Ⅳ 要約
1) 北海道では赤クロバーとチモシーまたは赤クロバーとオーチャードグラスとの混播による乾草生産が行われる。これら混播牧草地のマメ科、イネ科の植生割合が20:80%程度であれ
ば、夏季晴天時に刈取りを行う場合、圃場で2日間予乾後にはおおむね30%前後の水分含量に低下する。かような場合の送風乾燥の経済効果については多少検討の余地があるか
も知れない。
2) マメ科とくにアルファルファは従来乾草調製の困難な牧草とされていたが、送風乾燥法は葉部折損脱落を防止し、品質良好な乾草をうるのに最も適合した方法と認められる。
3) 赤クロバー採種における利用性については、北海道における主要採種地は収穫期の降雨に起因する豊凶差がきわめて大であるが、かかる不良気象条件による被害を軽減する
一方法として考慮されてよい。
4) 送風乾草を天日乾燥と比較する場合、その価値を過大評価することは危険である。湿度の多い時期や地帯においては需用の送風のみでなく熱源を利用し関係湿度を低下する方
法を施用する必要がある。しかし秋季の気象条件は利用の可能性も考えられるから、2番、3番をもって乾草を調製する工夫も検討するべきで、同時に2番草を如何に多収穫とするか
について栽培技術上の検討が併せて行われることが望ましい。
5) 本試験では10月中旬の送風によっても乾草調製を行いえたが、冷涼気象条件下においても成果を期待できる点で、地域によっては乾草調製期間を延長しうるばかりでなく、また労
力的には天日乾草法に比しはるかに節減されるはずである。
6) 本試験ではチョッピングした場合の送風乾燥は未解決である。また風量水分比の範囲は更に精密な試験を経て決めるべきであろう。その他加照送風の場合など多くの問題が未解
決で残されている。したがって今後も試験を継続してこれらの問題は解明される必要がある。
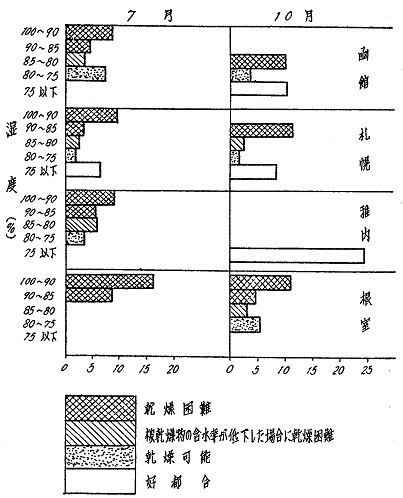 第1図 湿度別時間数 |
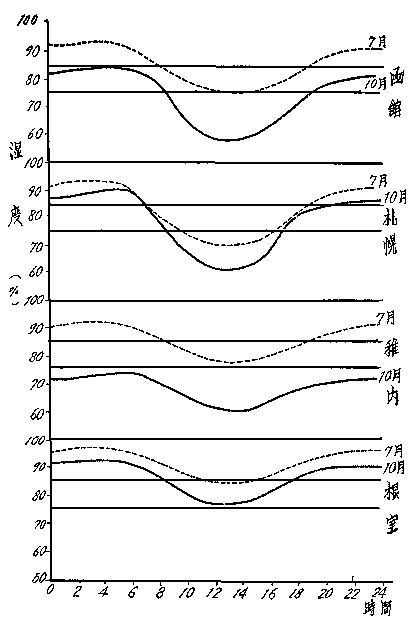 第2図 湿度の日変化 |