10輪咲で90~100cm
30輪咲で110~130cm
(7月20日頃より)
(7月24~5日頃より)
(7月末~8月始めより)
斑点の分布
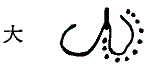
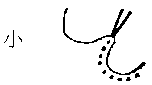


70~75%分布
60%に分布
全面に分布
【普及奨励事項】
| ホノオ(花ゆり交配1号)およびハゴロモ(花ゆり交配2号)について
道立農試種芸部 |
Ⅰ 来歴
1 交配材料
♀ あかひらと
北大農学部附属農場花卉園のもの。
♂ おくきんぶせん
北大農学部附属農場花卉園に「かばすかし」の名称のもとに保存されていたもので、花粉採取個体は札幌市南11条西13丁目杉原氏の庭さきに栽植されていたもの。
2 育成経過
食用を主目的とする新品種育成のため昭和26年交配した24組合せのうち、あかひらと×かばすかし の実生個体から鑑賞用として選抜育成されたものである。この組合せの実生は
日本で始めてのものであって、大きな特徴は、在来のおにゆり、こおにゆりにくらべると、花が濃紅色で美しく、開花期は早く、作りやすいことなどで、今後国外、国内向けの花壇用品種
として有望視されるものである。
Ⅱ 特性概要
1 花百合交配1号
1) 球根: 球~扁球型で純白色、まれに外周の鱗片頂端部がわずかに黄色をおびることがある。鱗片は擬宝珠~広卵形、厚さは普通、鱗片の抱合、球のしまりはよい。
球根の形状は「あかひらと」に似ているが鱗片の厚さ、抱合、球のしまりは「あかひらと」にくらべ劣る。
球根の肥大は良好で、鱗片繁殖後3作で球周20~25cm、球重90~130g(鱗片の大きさ5~6×3~4cm)に達する。
2) 茎: かたく、多角形、暗紫~紫褐色をおび、いわゆる黒軸高さは100cm前後、(1輪咲35~40cm前後、6~7燐咲70~80cm、10~12燐咲90~100cm)に達する。
種球の小さい場合(1~3輪咲)は地下茎は匍匐する傾向が強い。珠芽は着生しないが木子は4~5個着生する。
3) 葉: 披針形、大きさは茎の中央部のもので9.0~10.5×0.9~1.0cm、葉脉は3~4本、濃緑色で光沢はなく茎への着生はやや斜め上向で、時に捻れることがあり、やや密である。
葉数は1輪咲で50枚、6~7輪咲で70~80枚、10輪咲で90~100枚である。
4) 花: 開花期は7月下旬で花期は15~20日間、蕾は紡錘形(8.5×2cm位)でわずかに彎曲し、全面に白毛があり、先端は紫黒色を呈する。花は燃えるような朱紅色で、わずかに芳
香があり、大きさは10~10.5cmで、斜め下向きに咲き、花被片は強く反転し、やや撚れる場合が多い。
斑点は2~2.2×1mm前後、紫黒色で多く花被片の基部より70~75%の範囲に分布する。雄蘂は6本、花 の長さは6cm前後、朱赤~朱紅色であるが開花直後、基部は淡色であるが
漸次濃色に変化する。花粉は茶色でおおい。雌蘂は1本で5.8cm前後、柱頭は紫赤色、花柱は朱赤~朱紅色を呈し、花糸とおなじような変化をする。
花序は総状花序、花梗はかたく、紫黒~紫緑色で長いものは8cm前後に達する。7~8輪以上の花序では花梗が分枝して2花着生するものがみられる。
花数は多く、鱗片繁殖3作目で20輪前後になる。
5) 耐病性: ウイルスには強いようであるが、Bo-trytisには侵れる場合があるので銅剤の散布が必要である。枯葉期は9月中下旬、草勢は強く栽培は容易である。
2 花百合交配2号
1) 球根: 腰高の球~扁球型で角張った外観を呈す。純白色、大玉になっても分球は少ない。鱗片は短ざく型で厚くなく、抱合、球のしまりは普通である。
球根の肥大は極く良好で鱗片繁殖後3作で球周25~30cm、球重180~230g(鱗片の大きさ7.5~9.5×2.0~3.3cm)に達する。
2) 茎: かたく、多角形で頂端部2~3葉あたりが淡紫褐色を呈し、また基部がわずかに紫褐色をおびることもあるが青軸である。頂端帯色部にはわずかに白毛がある。
高さは100~120cm(1輪咲40~45cm、5輪咲70~75cm、30輪咲120cm前後)に達する。小玉のばあいには地下茎は葡匐する傾向が強い。
球芽はつかないが木子は4~5個着生する。
3) 葉: 披針形、大きさは茎の中央部のもので8.1~12.5×1.1~1.4cm、葉脉は5本、緑色、やや光沢があり、茎への着生は水平~やや斜め上向、やや密で葉裏の茎への接着部は紫
褐色をおび、頂部の葉、とくに裏側には白毛がややある。葉数は1輪咲で45~55枚、5輪咲で80~95枚、30輪咲で110~130枚である。
4) 花: 開花期は7月下旬~8月上旬で花期は15~20日間におよぶ。蕾は棍棒状に近い防錘型(7.3×2cm)で、白毛が密生し、頂端部は紫黒色を呈する。
花色は朱紅色で芳香がわずかにあり、大きさは11cm前後、斜め下向きに咲き、花被片の反転はかるく、撚れることもないので花姿は整っている。
斑点は紫黒色、2.5×1mm以下のものがおおいが花被片の基部より60%位の範囲に分布し、反転部より先端に分布しないので目立たない。雄蘂は6本、花糸の長さは5cm前後、朱赤
~朱紅色、花粉は茶色でおおい。花序は総状花序、花梗はかたく、淡紫色で長いものは9.5~10.5cmで白毛がややある。10輪以上の花序では花梗が分枝して2花着生するものが多
い。花数は多く、鱗片繁殖3作目で30輪前後になる。満開期の草姿は清楚でノーブルである。
5) 耐病性: ウイルスには特に強いようであるが、Botrytisには侵されるばあいがあるので、銅剤の散布が必要である。枯葉期は9月下旬、草勢は強いので栽培は容易である。
主要特性につき両親と比較表示するとつぎのとおりである。
| 交配1号 | 交配2号 | あかひらと | おくきんぶせん | |
| 草勢 | 強 | 強 | やや強 | 強 |
| 草丈 | 1輪咲で35~40cm 10輪咲で90~100cm |
1輪咲で40~45cm 30輪咲で110~130cm |
10輪咲で100~120cm | 2~3輪咲で30~35cm |
| 開花期 | 7月下旬 (7月20日頃より) |
7月下~8月上旬 (7月24~5日頃より) |
8月上旬 (7月末~8月始めより) |
7月上旬 |
| 花の大きさ | 10~10.5cm | 11cm前後 | 7.5~8cm | 13~13.5cm |
| 花色 | 朱紅色 | 朱紅色 | 赤橙色 | 橙紅~橙黄色 |
| 花の向き | 斜め下向咲 | 斜め下向咲 | 下向咲 | 受咲 |
| 花被片の反転並びに 斑点の分布 |
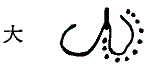 |
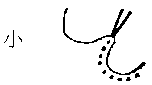 |
 |
 |
| 斑点 | 多、紫黒色 70~75%分布 |
多、紫黒色 60%に分布 |
多、紫黒色 全面に分布 |
小、淡黒色 |
| 球根の形 | 球~扁球形 | 腰高の球~扁球形 | 球~扁球形 | 鈍円錘形 |
| 大きさ | 中 | 大 | 中 | 小 |
| 色 | 純白 | 純白 | 純白 | 白、燐片先端帯黄色 |
| 珠芽 | なし | なし | なし | なし |
| 木子の着生 | 中~少 | 中~少 | 中~少 | 少 |
| 地下茎の葡匐 | 中 | 中 | 大 | なし |