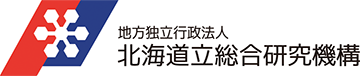経営部年次報告 はしがき
昭和60年度
基幹作目の生産調整や複合作物における産地間競争の激化など、北海道農業をめぐる情勢は誠に厳しいものがある。農家並びに農業関連機関においては、このような厳しい情勢を切り拓く、足腰の強い北海道農業の確立をめざして、経営・技術改善がなされている。
当部がたずさわる農業経営研究が、これらの経営改善の努力に役立ち得るためには、研究成果の敏速な提供が必要と考え、この度、中間的な成果を含めた研究成果の年次報告を公表することにした。印刷費節減の企画から、一部共同研究を単純に合本したため、編集上での未整備もあるが、農家や農業関連機関の活動に、いささかなりとも役立てば幸である。
昭和61年8月1日
北海道立中央農業試験場経営部 経営部長 今野行男
昭和61年度
ポスト三期の水田農業対策事業は、転作の強化、転作奨励金の減額と6年後の打ち切りなど、ほぼ全貌が明らかになりつつある。
このような厳しい営農環境にあっても、これにめげず、経営転換による柔軟で足腰の強い地域農業の確立が必要である。
このような地域農業の確立に、いささかなりともお役に立てばと思い、中間的な成果も含めた当経営部の研究年次報告をお届けする。
昭和62年3月20日
北海道立中央農業試験場経営部 経営部長 今野行男
平成3年度
ダンケル・ガット事務局長が1992年4月中旬と期限を切ったガット・ウルグァイラウンドの最終決着を間近に控え、北海道農業も大きな転機、言い換えると「大きな曲がり角」を迎えようとしている。しかし、この「曲がり角」と言う言葉は、以前にどこかで聞いた事がある。調べてみると、昭和36年に制定された「農業基本法」の基礎資料となった「農業の基本問題と基本対策」の中で初めて登場した言葉である。以来、この「曲がり角」と言う言葉は、今日まで至るところで繰り返し強調されてきた。一体全体北海道農業はどれくらい曲がり角を回れば良いのであろうか。渦巻状にのたうち回りながら、次第に消滅しつつあるのではないかと恐れているのは、筆者だけの思い過ごしであろうか。
農業を大切にして貰いたいという筆者の思いは、つぎの一文に凝縮される。
「公共の繁栄は樹に類する。農業は根であり、人口は幹であり、工業は枝であり、商業は葉である。いうまでもなく樹木が育つのは根によってである。根が痛めば、葉は落ちるし、枝は萎れるし、樹は枯れる。樹の枯れるのを避けようとするならば、根にこそ対策を講じなければならない」
この一文は、「基本問題と基本対策」のまえがきで、小倉武一氏がフランス革命の立憲王政派の政治家ミラボー伯爵の言葉を孫引きしたものであり、それをさらに筆者が曽孫引きをさせて頂いた。要するに農業を粗末にするとそれは人間否定につながり、遂には工業も駄目になることを言いたかったからである。
道立中央農試経営部の研究結果が、北海道農業再生のためにいささかでもお役にたてれば、幸いである。
平成4年3月23日北海道中央農業試験場 経営部長 長尾正克
平成4年度
―故中紙輝一氏を偲んで―
私が十勝農試に勤務していた時代に、親しくお付き合いを頂いていた帯広市豊西町在住の作家で酪農家でもある中紙輝一氏が昨年69歳でご逝去された。
訃報を聞いて、彼が当時の私に語ってくれた話を突然思いだした。
彼いわく、「自分が農業を営んでいるのは、生業(なりわい)としてですよ。企業的に経営しようと思ったことは一度もありません。そして、国民に食料を供給するためや地域のために農業をやっているのでありません。自分のために農業をやっているのです。」
当時、私は農業雑誌に「これからの農業経営は企業的でなければならない」としきりに強調していたことに対する農家としての批判であったかと思う。しかし、私にはその意味が当時はまだ良く理解できなかった。
中紙さんの酪農の技術水準は管内でもトップにあったと思うが、彼の技術体系は少々変わっていた。基本技術を踏まえた上で、飼養管理労働時間は極めて少ない飼養管理体系を作り上げていた。執筆時間の余裕を生み出すため、放牧の採用と粗飼料の給与を1日1回としていた。それにもかかわらず頭当乳量は管内でトップクラスであり、搾乳牛の故障も少なかった。研究熱心であり、複式簿記も採用していた中紙牧場は、まさに私が描いていた企業的経営のイメージそのものであった。
しかし、中紙氏が独自に作り上げた飼養管理体系は、当時の常識、言い換えれば指導機関の指導とはかなり異なるものであった。基本技術を踏まえつつ彼独自の営農哲学で乳牛と折り合いをつけたのである。いわば、職人の名人芸を想わせる。
農業経営が生業であるならば、果して後継者は確保できるのであろうか思っていたら、彼の一人息子である麦平君が北大工学部を卒業後、エンジニアの夢を捨てて自主的に経営を引き継いだ。彼は、ややしばらく父の指導にしたがっていたが、経営を全面に引き継いだ時点で父のやり方を改めて麦平流の管理方式をつくりあげた。無放牧・粗飼料3回給与であった。結果は、試行錯誤の連続であったが、彼はこれにめげずその後無放牧体系で乳量・乳質ともに管内でトップ水準の酪農家に成長した。
自ら生業であると主張する農家ほど、経営革新や技術革新の担い手になっている現状を、どの様に理解したら良いのであろうか。営農それ自体に人生哲学が投影されているのである。決して生活費を得るためだけの農業ではないのであろう。
担い手問題に頭を悩ませていた私に、天国からメッセージを頂いたと思っている。
平成5年3月10日
北海道立中央農業試験場 経営部長 長尾正克
平成5年度
-農協運動の原点を考える-
かたずを飲んで見守っていたガット・ウルグァイラウンド交渉も平成5年12月に各国の合意が成立し、平成6年4月15日に各国代表が合意文書に署名したことによって、これまでのガットに代わる新しい世界貿易機関(WTO)の設立協定文書が確定したことになる。各国は1月1日発効を目指して合意受け入れのための批准手続きに入る。合意内容は「総関税化」の基本理念を受け入れたことによって、農業部門にとっては文字どおり「総自由化」になっている。
コメに関しては高率のミニマムアクセス(最低輸入義務量)と引換に部分自由化ということで6年間の猶予期間をもらい、その後関税化のコースを辿ることになろうが、その時は当然のこととして食管制度を改革し、これまでの全量管理から部分管理に移行せざるを得ない。そうなれば全量管理であるが故に採用できた一律減反・一律出荷制限という農業者の統制政策も採用しにくくなる。農業者自らが消費者や実儒者と直接結びついても、それを止める手だてが無くなる。
加えるに農水省は新しい担い手像として認定農業者制度をつくり、その事業展開の法的根拠として農業経営基盤強化促進法を制定した。この政策は明らかにエリート農業者確保のための農業者選別政策に外ならない。
このような農水省の動きは、食管制度の双子の兄弟と言われてきた農協組織に大きな影響を与えずにはおかない。そもそも食管制度は、戦時における食糧の強制調達(供出)のための制度であり、 そのため農家を効率的に統制するため農協の末端集落組織としての農事組合あるいは農家組合のムラ機能(イエ連合体としての)を利用して農政意図の徹底を図ってきた。集落の常会参加者はイエの代表であり、したがって農村に残存している封建制の遺物のイエ制度を農政が陰で強力に支援してきたため、そのことが農村社会のイメージを暗くして、嫁日照り問題を招いてきたものと思われる。その後、食管制度が供出機能から価格支持機能を持つことによって、農家保護的機能の側面が強まったが、これによってイエ制度に根ざした集落統制機能は補強され、減反転作政策でも大いにその機能が発揮された。総自由化時代の農政として登場してきた「新農政プラン」では、意図的に「農家」という言葉が消えている。イエ連合のムラ社会に依存してきたこれまでの農政浸透システムを変えるというのであろうか。
これまでは曲がりなりにも農業者の生活を支えてきたのが食管制度であり、その実質的な業務執行主体が農協であったわけで、従って農業者も保護してくれる限りにおいて渋々統制に服してきたが、今後は如何なものであろうか。食管制度が崩壊すると、農事組合などの集落のインターフェース機能が失われてくるとなると、農協は農業者への求心力を失って、食管制度と同じ運命を辿るのであろうか。多様な性格を持つ農業者を農家という画一の呼び名でくくって良いのであろうか。農協組織のリストラも含めて、ここのところが大問題である。認定農業者となって農業者の企業的感覚が高揚すればするほどこれまで農協に委託してきた販売権、購買権、資金調達・運用権、共済加入権に対する差別化要求が厳しくなり、協同原則(平等原則)は、発揮しにくくなるはずである。
どうやら我々経営研究者も、ガット・ウルグァイラウンド合意を契機に、農業経営環境に対する研究の基本的な枠組みの見直しが迫られている。つまり、農協も含めてこれまでの農業支援システムを与件としてカヤの外に置く訳には行かなくなっている。我々農業経営研究者は、今こそ与件改変にまで踏み込んだ研究成果が期待されているのである。
平成6年3月北海道立中央農業試験場 経営部長 長尾正克
平成6年度
-地方自治体経営研究者の研究理念-
日頃、農業者に対して経営理念の確立を訴え続けている自治体農業試験場の経営研究者は、自らどのような研究理念を確立しているかをここで問題にしたい。
自治体経営研究者の研究理念に直接影響を与えるのは言うまでもなく農政理念である。しかし、自治体経営研究者にとって農政理念は、実は二つあって、その一つは農水省農政である国土農政であり、もう一つは地域住民の声を反映した自治体農政である。国土農政のみを重視し、自治体農政の主体性を認知しないで国土農政に自治体農政を従属化させることは、明らかに地方自治の本旨を否定することになるのではなかろうか。
そもそも国土行政と地方自治とは、本来的に必ずしも調和的ではない。特に、最近では都市(工業)と農村(農業)との対立、端的に言えば東京と北海道との対立が益々激しくなり、工業の立場を優先する国土農政が自由貿易を掲げて地域農業の安楽死を迫りつつある。いわば国が工業製品を売るために、地域(農業)をスケープゴート(生け贄)にしようとしているのである。
地方政府である自治体が、地域の生殺与奪権を持つ国土農政を与件として無抵抗に受諾し、その徹底化を図ることは自らの存在そのものすら否定することになりはしないだろうか。そうであれば、都道府県議会や市町村議会は一体何のために存在しているのであろうか。
国土行政が地域住民の合意が得られない場合は、地方政府と地方議会は、国土行政のフィードバックを迫り、そして、その実現を働きかける義務があるのではなかろうか。
このまま国土農政の農業イジメに地方自治体までもが加担すると、北海道の農村はたちどころに崩壊してしまうことは目に見えそうである。
私が言いたいことはガット・ウルグァイラウンド合意を破棄しろと言うのではない。国際条約は尊重しなければならないが、ガット合意自体は農業そのものの廃棄まではうたっていない。要は、国際競争で生き残れない商業的農業は止めなさいと言っているだけなのである。だが、農水省農政では、農村の担い手は考慮せず、食糧生産の担い手として僅かな認定農家だけしか農業者として認めていない。
ここにおいて初めて、われわれ地方自治体農業試験研究機関の経営研究者の研究理念が明確になるのである。一方では立地条件を生かした国際競争に耐えうる農業経営の展開支援研究と、他方では、地域の自然環境を守り、そして地域社会を守るためのデカップリング政策を実現させるための研究がそれである。
大蔵省では、日本でのデカップリング政策は国民的合意を得ていないといっているので、国民的合意を得るための研究蓄積を積み重ねることが、当面最も望まれているのではなかろうか。その他方の側面である日本型デカップリング研究を重視することが、国立農業試験場の経営研究者と立場の異なるところでもあろう。
平成7年3月北海道立中央農業試験場 経営部長 長尾正克
平成7年度
-国民経済路線とデカップリング-
ガット合意がなされた時、正直な感想を述べれば北海道の農業関係機関の人達は、私と同様に目も眩むような憤りを覚えたことと思う。農業依存度の大きい北海道では、農畜産物の自由化が即、価格低下につながり、北海道の農村が農家の多少の自助努力では如何ともし難く、立ち行かなくなる恐れが十分予想されたからである。 それゆえ、わが経営研究部門としても、農家を取り巻く経営環境の悪化は、農業依存度が高いばかりでなく、条件不利地が多いこともあって、北海道農業崩壊の危険性を証明することに全力を挙げて取り組みつつある。このような厳しい環境の中で、経営の自助努力による「このときほどチャンス」といった類の千に一つの、あるいは万に一つの可能性を説くことはあまりにむなしく、潔しとしなかったからである。 デカップリングについては、農林水産省では大蔵省が国民的合意が得られていないと言っているというばかりで、デカップリング実施のための前提作業である農地の経済的土地分級事業すら進めようとはしていない。一体全体、デカップリングに対していつ、どこで国民的合意を問うたのであろうか。 これまで日本の農政は、農村に対する配慮があり、農業基本法もその延長線上にあった。農村に対するかくのごとき仕打ちは、日本経済の政策路線が変化したのであろうか。 いうまでもなく、世界の資本主義経済の路線においては、二つの潮流があり、一つは「米英型資本主義」であり、もう一つは「ライン型資本主義」である。ライン型資本主義はドイツで最も発達を遂げた資本主義であり、ライン河にちなんでこう呼ばれている。市場至上主義を唱えて企業の利潤追求行動に対する規制を撤廃し、全面自由化を迫る米英型に対して、ライン型は、別に「社会資本主義」とも呼ばれるように、企業活動において収益ばかりでなく、社会への利益還元や社会的責任をも重視し、労働者の利益や社会福祉制度との調和を目指す資本主義といってよいであろう。日本は、これまで米英型とライン型の中間かややライン型寄りの資本主義を歩んできたが、ガット合意後は米英型資本主義に席巻されつつある。そのため慌ててコンツェルンに対する規制を緩和し、民族資本を擁護しつつ、米英型資本主義に近づこうとしているように思われる。 ドイツも労働者を大切にし、福祉に力を入れてきたため製品コストがアップしつつあり、経営合理化のためなりふり構わず労働者の首を切る米英型資本主義に押されつつあるのが現状である。 しかし、ドイツでは経済政策というものは国民生活に貢献するものであるという信念は揺らいでいないのである。都市住民にとって農村の存在は必要不可欠というのがライン型資本主義の中で認知された結果が、デカップリングなのである。 これに対して日本は、農産物は比較劣位にあるので切り捨てて、得意の工業製品で勝負し、その過程で生ずる産業廃棄物は、過疎になった農村地域に埋め立てることに決めているのであれば、事態は深刻である。 日本の経済システムの特徴である「終身雇用制」や「不平等拡大防止規制」を高く評価しているロンドン大学のロナルド・ローア教授は、「最近、日本の知識層に広がっている規制緩和などの『市場至上主義』が、日本経済の再生につながるかどうか疑問である」と問題を提起している。日本国民は、本当に貧富の差が激しく、したがって犯罪も多いアメリカ型の社会の到来を待ち望んでいるのであろうか。日本型デカップリング政策の登場が待望される。
平成8年3月北海道立中央農業試験場 経営部長 長 尾 正 克
平成8年度
-私の農業経営学研究34年の軌跡-
私が道立の農業経営研究に従事する期間がいよいよ短くなったので、私なりの反省点をいくつか披露したい。若手研究者にいささかでも参考になれば幸いである。 まず第一は、担い手の経済的性格の問題である。現状の担い手は、経営(生産)と家計(生活)とが一体化した家族経営であることは疑いのない事実である。したがって、家族経営の経営目標は、当然のこととして、経営と家計の二重構造になるはずである。
つまり、経営(生産)…農業粗収益-農業経営費=農業所得
家計(生活)…農業所得-家計費 =農家経済余剰、ということである。
これまでの農業経営学では、農家の経営目標として経営サイドの農業所得だけに注目し、家計、つまり、生活に対する目標を無視してきたきらいがある。しかし、現実の農家の経営目標は、農業所得だけではなく、家計のあり方、すなわち家族生活のあり方、究極的には家族の生き方まで大きな影響を与えているのではなかろうか。そうであれば、当然のこととして生涯時間の生産と生活に対する配分も問題になろう。したがって、農家の経営目標は所得最大化のために生き方を変えるというよりも、所得と生き方を同時的に考慮するか、あるいは、むしろ生き方を達成するための手段として所得をみるのが本来的ではなかろうか。そうなると、経営目標は家計、つまり、生き方を中心に統一的に追求されなければならない。しかるに、私が行ってきたこれまでの経営研究では、所得の追求に偏りがちであった。そのため、農業経営における家族労働の役割分担とその地位、家族制(相続も含む)の変貌、農村共同体の変化等の解明、経営者能力の向上、嫁不足・後継者不足・高齢化対策、さらには兼業を含む多面的経営の育成対策等に有効な提言を示すことができなかった。農業経営学から生活を切り捨ててきた報いである。
第二に、私は、長い間、家族経営は資本主義経済の発展に伴って必ず崩壊し、資本制企業に移行する仮の姿だと思っていた。しかし、いつまでたっても資本制企業に移行しないばかりか、世界的にみても家族経営は、その質的内容に差はあるものの、根強く農業生産の担い手の主流からはずれていない。一方では、社会主義国では農業が崩壊している。その理由は何か。商品化された労働では、農業は成り立たないのであろうか。私は、生産と生活が一体化した農家の経営行動そのものが人間の生命活動であり、生命生産である農業そのものでもあるからだと思い至った。地域の共同体を前提とした家族経営こそ、農業の本来的担い手であると信じている。資本主義経済(市場経済)は、工業の論理に基づく経済システムではなかろうか。農業の工業化を信じ、限りなく一人当たりの飼養頭数や経営面積の拡大、あるいは、限りない単位当たり収量または頭当泌乳量の増大をもって、農業経営の発展と勘違いした私の愚かさにただ恥じ入るばかりである。農家が人間としての生き方を追求する上で、それに貢献する技術開発こそ、生産力の発展といえる。部分ではなく総体なのである。
第三は、誰の立場に立って、経営研究をするのかと言う問題である。長い間、農業経営とは、国民経済と私経済の相互交渉の場という磯辺先生の言葉を信じてきた。ところが、国民経済の立場(わが国農政)から、北海道農業と言えどもWTO体制のもとでは保護することはできないので、国際競争の中で自力で生き残れという政策を示されて、ハタと気づいた。このままでは、まず最初に都府県とは異なり兼業に逃げ込めない北海道農業が先に崩壊してしまう。農家は農村生活者の立場から、断固として短期視点の国民経済に反撃しなければ、生き残りの方策はない。農業に依存してきた地域の住民も同様である。私を含めて公立農業試験場の経営研究者は、農家の立場に立つことを改めて決意し、地域を救うための対策を構築しなければならない。その場合の農業は、地域自立の農業である。地方分権が確立していない今日では、国民経済の立場に立つということは財界の立場に立つということと同様である。
残念ながら私には、現役として残された時間はほとんど無い。若手経営研究者の今後の活躍に期待するだけである。もちろん、私も、立場は変わるが、引き続き北海道農業の応援団として、私なりの研究を続けていきたい。
平成9年8月北海道立中央農業試験場 経営部長 長 尾 正 克
平成9年度
本年の春季農耕開始期は天候に恵まれ農作業が順調に進み、6月にはやや低温傾向で推移したものの、現時点の各作物の作況はほぼ平年並みとなっている。中央農試の位置する稲作地域においても水稲の生育は順調であるが、農家の方は、出来秋にはその生産した米を如何に販売するか、米価格はどうなるか、不安を抱えたなかでの農作業管理となっていよう。
1997年産の自主流通米取引は、道産米の価格が基準価格の値幅制限の下限に張り付いた状況のままほぼ終わり、農家の受け取り額は仮渡金の13,000円/俵を維持できるかどうかとなっている。
自主流通米価格の急落や生産調整対応への不公平感に対処するため、農林水産省では昨年11月に「新たな米政策」を発表した。この対策によっても、米の需給緩和の状況で道産米価格の低落傾向が予想されるもとでは、「稲作経営安定対策」に伴う補填金を加えて流通経費を差し引いた、1998年産米の農家手取額は13,000円弱/俵と算出される。この米価格は米生産費を下回り、水稲生産の費用を償なうことができず、稲作経営に深刻な影響を与える。ことに、稲作専業農家における米価格の低落傾向は大きな農業所得の減少となり、農業所得で家計費を充足できる専業農家の存立条件を欠くことになる。
また、備蓄米調整から1998年産道産米の政府買い入れ数量がゼロとの状況で、米の生産から販売に至る全量が市場経済へゆだねられることになり、「売れる米づくり」を柱に各地域で町村・JAの枠を越えた広域産地形成の取り組みが発足している。昨年、道産米の良食味品種「ほしのゆめ」がデビューのとき「きらら397の二の舞にならないように」と言われたように、消費者から信頼を得る安定した食味の米生産と集荷には、良食味品種の地帯別作付基準や栽培基準の遵守が求められる。このため、米広域産地の生産・集荷・販売に至る戦略は一様ではなく、各産地の特質を活かした取り組みが必要となろう。
新しい経済の仕組みとして「共生」がキーワードとなっている。この行動原理では、「いかに安く」でなく、「いかに公正な価格で買うか」が基準と言われる。米の需給緩和の状況といえ、現行の米価格は農家生産者のコスト低減の限界を超えている。営農集団の再編などによるコスト低減、クリーン栽培、食味改善の技術を積み重ねるとともに、消費者からの信頼や連携が課題となり、米を作れば良いとの時代は終わったのである。
農試では「開かれた農業試験場」として、地域ニーズに対応し、農業者・JA・町村などと提携した地域密着型の研究を進めつつある。道産米のあり方が問われるなかで、地域の稲作振興や広域米産地形成に向けて、今、地域と提携した研究を検討中である。
平成10年7月北海道立中央農業試験場 経営部長 山本 毅
平成10年度
道立農試の経営研究分野では、これまでにも増して技術研究分野とのプロジェクト研究への参加が求められている。これは一つに、技術開発の出口において実証的な技術効果の検証とともに経済効果の評価が必要であり、殊に農業生産が過剰段階では、経済効果を伴わない技術は実用化を欠くことがあげられる。二つに国立の地域農試がキーテクノロジーを主体として推進している開発技術の体系化プロジェクト研究・地域総合研究に結びついて、道立農試においても地域基幹研究のプロジェクト課題が位置づけられていることである。
これらのプロジェクト研究の参加を通じて経営研究に対しては、①慣行技術の限界や評価対象技術の事前評価と、②開発技術の体系化や定着条件の解明、経営経済効果などの事後評価が期待されているが、同時に、いくつかの課題を内括している。
技術研究分野から求められる技術の経営経済評価の多くは、新たな開発技術を経営に導入した場合の収益性改善効果を指標として示すことであるが、開発技術の性格・内容は一様でなく、経営経済評価の定量的手法としてルーチン化は難しい。このため、新たな技術導入を慣行技術との比較にとどまる部分技術の評価といえども、技術導入対象の地域条件や経営構造との関連で明らかにすることが必要であり、経営研究分野のみでの経営経済評価の課題数をこなすには限界がある。
また、プロジェクト研究においては、事前評価と技術研究が同時にスタートであり、技術評価・成果が地域ニーズを欠いたり、実用化技術に至らない技術開発の中間段階であっても経営経済的評価の事後評価がしばしば求められる。
技術の経営経済的評価は古くて新しい課題と言われているが、これまでの経営研究の蓄積を踏まえて「農業技術の経営評価マニュアル(農林水産省農業研究センター、平成7年10月)」の手引書が作成されている。このマニュアルでは、公立研究機関で取り組む地域基幹研究の的確な推進や、公立研究機関では、経営研究者が少なく技術研究者でも利用できる手法を提示したと言われるが、経営評価の内容は経営研究担当者向けに作成した域をでていないと思われる。
農研センターの小室次長が、かつて北陸農試時代に研究ノート、「農業技術の経営的評価と評価基準について(農業経営通信 NO141、1984.9)」のなかで、プロジェクト研究における部分技術の評価基準の指標として、①要素評価指標(生産要素の効率:部分技術の特性に基づく部分技術効果の判定)、②部分評価指標(生産性)、③総合評価指標(収益性)の三段階のレベルで技術効果を判断・評価する手法を提案されている。この評価指標のなかで、①と②のレベルは、技術研究研究者が評価することが可能であり、これに③の収益性視点からの経営評価を加えることで技術開発の実効性はより高まると期待できる。このためにも、前述の「農業技術の経営評価マニュアル」を基礎に、技術の評価基準の指標と関連づけた評価手法のマニュアル作成が、経営研究者に課せられていると言えよう。
平成11年7月北海道立中央農業試験場 経営部長 山本 毅