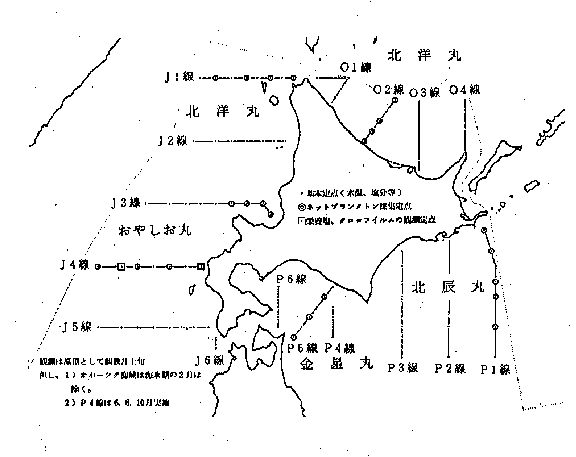定期海洋観測と海況速報
水産資源は”海”という環境の中にあるので、資源調査をするにしても、まず、周りの環境調査をする必要があり、海の中がどうなっているのか、その構造と変化を知ることは陸上の気象観測と同様に重要なことなのです。
事実、長期的かつ大きな変動を繰り返えす浮魚類などの資源が変動したとき、「なにか海況が変わったのか」「水温は平年と変わってるのか」と漁業者からよく聞かれます。これには、長い間のデーターの蓄積がないと的確にお答えすることができないわけで、海洋観測は、漁業資源を扱う試験研究機関として基本的にやらなければならない重要な調査研究分野です。
中央水試には海洋部という専門部門があり、他の各水試・試験調査船と分担協力して海洋状況把握のため定期的な海洋観測を行っています。
事実、長期的かつ大きな変動を繰り返えす浮魚類などの資源が変動したとき、「なにか海況が変わったのか」「水温は平年と変わってるのか」と漁業者からよく聞かれます。これには、長い間のデーターの蓄積がないと的確にお答えすることができないわけで、海洋観測は、漁業資源を扱う試験研究機関として基本的にやらなければならない重要な調査研究分野です。
中央水試には海洋部という専門部門があり、他の各水試・試験調査船と分担協力して海洋状況把握のため定期的な海洋観測を行っています。
この海洋部の大きな事業として「北海道周辺海域漁場環境調査」があり、(1)北海道周辺の海洋構造の把握とその変動、(2)海洋の生産力についての調査研究という二大テーマを持っています。これに取り組むための1つの方法として、定期海洋観測を行っており、前図のように4隻の試験調査船が本道周辺の広大な海域を分担しながら実施しております。これだけ広い海洋観測網は現在大学や水産研究所、他県の水試では行われておらず、それだけ北海道の水試として誇り得るべきものなのです。
しかし、気象予報のアメダス調査点のように海にも調査点がたくさんあればよいのですが、全道周辺の海といっても広く、観測点がまだまだ少ないという問題点もあります。
こういう観測は、非常に長い地道なデータの積み重ねが必要です。そういった中から新しい現象の発見もあるのです。しかし、どだい「海洋」という陸上とは全く異なった環境の状況を知ろうということなのですから、まず「観測」自体が大変な難しさをもっています。そして要求される調査精度は、海水の塩分濃度では、海水1キログラム中、1/100グラム単位まで測定しなければならず、魚を育む多種多様のプランクトンなどでは1/100ミリメートル前後という非常に微細な生き物も相手にします。さらにプランクトンを育む栄養塩類の変動を見るには、海水1キログラム中の1/1,000,000グラムという極く微量成分の高度な分析技術が必要となります。
しかし、気象予報のアメダス調査点のように海にも調査点がたくさんあればよいのですが、全道周辺の海といっても広く、観測点がまだまだ少ないという問題点もあります。
こういう観測は、非常に長い地道なデータの積み重ねが必要です。そういった中から新しい現象の発見もあるのです。しかし、どだい「海洋」という陸上とは全く異なった環境の状況を知ろうということなのですから、まず「観測」自体が大変な難しさをもっています。そして要求される調査精度は、海水の塩分濃度では、海水1キログラム中、1/100グラム単位まで測定しなければならず、魚を育む多種多様のプランクトンなどでは1/100ミリメートル前後という非常に微細な生き物も相手にします。さらにプランクトンを育む栄養塩類の変動を見るには、海水1キログラム中の1/1,000,000グラムという極く微量成分の高度な分析技術が必要となります。
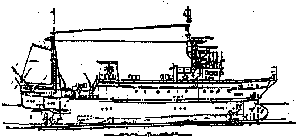
まず、海況速報をご覧になっていただき、おおまかにでも海の現況がどうなっているのかを知る目安にしてほしいものと願っています。また、海況と資源をつなぐ重要な接点の一つである動物プランクトン量のデータや、それを育むもととなる栄養塩のデータは今までは水温情報に比べるとはるかに少なかったのですが、これからようやくデータが蓄積されていくという段階で、今後の調査結果を息長く見守っていただきたいものと思います。(中央水試)