ページ内目次
Q&A? コンブの成長についておしえてください。
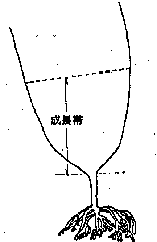
コンブには成長帯(主に葉の基部から数十センチの範囲)と呼ぶところがあり、この部分の細胞分裂によって成長します。葉の基部付近に小さな穴を空けて定期的に観察しますと、その穴が上方へ移動することによって、コンブの成長を知ることができます。
コンブは一般的に早春から初夏にかけて最も伸びますので、この時期に先に述べたような方法で測定された結果をご紹介します。
対馬暖流域に生育するリシリコンブは一日あたり2.51センチほど伸長します。これに比べると寒流域に成育するマコンブは一日当たり5.32センチ、ミツイシコンブは8.15センチ、そしてナガコンブは13センチと前二者よりも早く成長します。
しかし、これらの値はそれぞれ異なった環境条件のもとで測定されたものですから、絶対的な比較はできません。といいますのは、コンブの成長は温度・照度・栄養塩類の濃度・海水の流れなど、生育する場の環境条件に大きく左右されるからです。

しかし、この温度範囲での成長は、ホソメコンブが最も良く、次いでリシリコンブ・ナガコンブ・マコンブ・オニコンブと続き、種による成長の差が認められています。
なお、栽培漁業総合センターでは、現在各種のコンブの交雑によって、成長や品質の良いコンブをつくる試験に取り組んでいるところです。(釧路水試)
トピックス
磯焼け地帯のウニ除去と海藻の発生
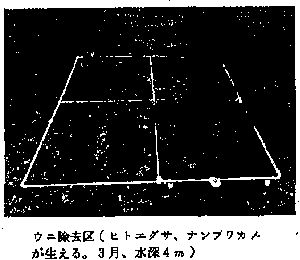
- 我々は、磯焼け現象の発生原因として「海の貧栄養」を考えています。日本海の栄養補給は、太平洋のように栄養豊富な親潮による水平的な栄養補給でなく、冬期間水面が冷やされ、冷やされた水は重たいので底に潜り、その力が原動力になり、海底の栄養豊富な海水を上昇させる、この垂直混合による栄養補給をします。ですから日本海はなぜ「海の貧栄養」かというと、近年海面が大きく冷やされず大きな垂直混合が起こっていないのではなかろうかと考えています。その結果として冬期間の海水温の上昇が昭和30年以降観測されています。
- 日本海のウニ類は4月から7月の産卵前と10月から12月の水温の下がるまで海藻類をよく食べます。冬期間の水温の低い時期にはほとんど餌を食べません。その時期はコンブ、ワカメなどの海藻類の芽生えの時期にあたります。しかし、冬期間でも水温が高いとウニ類は餌を食べ海藻類の芽を食べてしまいます。そこで中央水試では(2)のウ二が海藻類の芽生えをどの程度食べ、海藻群落の形成を阻んでいるか調べるため、寿都町でウニを取り除いて海藻の生え具合いを調査しています。10月、11月にウニを除去した区域では、3月にはワカメ、スジメを中心ににかなりの量の海藻が水深5mの地点まで生えています。ウニ(キタムラサキウニ)が海藻群落形成阻害に関係していることがわかってきました。また、コンブの発生はまだほとんど見られません。
