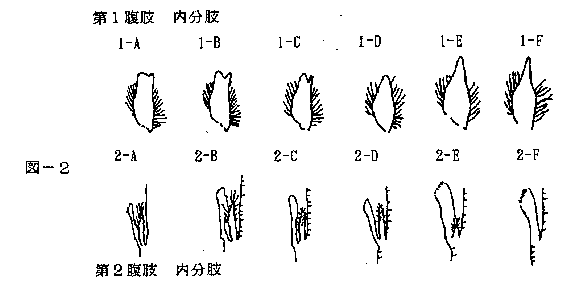エビ類の性転換と雌雄の見分け方について
北海道周辺海域で漁獲される主なエビ類は、ホッコクアカエビ、トヤマエビ、ホッカイエビ、モロトゲアカエビ、ヒゴロモエビであり、これらの総漁獲量は平成元年で約4,000トンになっています。
このうち、約7割がホッコクアカエビ(通称ナンバンエビ)であり、北海道の漁獲量は、本州日本海沿岸(鳥取~青森)で漁獲されるナンバンエビの総漁獲量をはるかに上回っています。
また、エビ類を対象とする漁業は、日本海側の主要な漁業のひとつでもあります。しかしながら、近年では、エビ類資源(主にナンバンエビ)の減少が危慎されています。
さて、これら5種のエビ類はすべてタラバエビ科に属し、雄から雌へ性転換することが知られています。この性転換は雄として機能した直後から始まり、生殖巣の雄性部分(精巣)が消失して行くとともに、雌性部分(卵巣)が成熟し始めます。日本海産のホッコクアカエビでは、大部分が満5才で雄として交尾を終え、5才の中ば頃から性の転換が始まり卵巣が成熟し始めます。この時期の平均体長は約100ミリメートルです。また、5才では性転 換せずに6才で転換する個体も一部あるようです。大部分は満6才で初めて産卵し、腹肢(腹)に卵を付着させた抱卵雌となります。雌に守られた卵は約10ヵ月後にふ出(ふ化)します。このようにホッコクアカエビでは稚エビ(未成熟)、雄性転換、抱卵雌、無抱卵雌というような生活をおくります。また、日本海産のものでは性転換後、抱卵雌と無抱卵雌を繰り返し、1年おきに産卵することになります。
そこで、これらの成長段階をどこで見分けるのか、つまりエビの雌雄の判別はどの様に行うのかについて日本海産のホッコクアカエビを例に整理してみました。
このうち、約7割がホッコクアカエビ(通称ナンバンエビ)であり、北海道の漁獲量は、本州日本海沿岸(鳥取~青森)で漁獲されるナンバンエビの総漁獲量をはるかに上回っています。
また、エビ類を対象とする漁業は、日本海側の主要な漁業のひとつでもあります。しかしながら、近年では、エビ類資源(主にナンバンエビ)の減少が危慎されています。
さて、これら5種のエビ類はすべてタラバエビ科に属し、雄から雌へ性転換することが知られています。この性転換は雄として機能した直後から始まり、生殖巣の雄性部分(精巣)が消失して行くとともに、雌性部分(卵巣)が成熟し始めます。日本海産のホッコクアカエビでは、大部分が満5才で雄として交尾を終え、5才の中ば頃から性の転換が始まり卵巣が成熟し始めます。この時期の平均体長は約100ミリメートルです。また、5才では性転 換せずに6才で転換する個体も一部あるようです。大部分は満6才で初めて産卵し、腹肢(腹)に卵を付着させた抱卵雌となります。雌に守られた卵は約10ヵ月後にふ出(ふ化)します。このようにホッコクアカエビでは稚エビ(未成熟)、雄性転換、抱卵雌、無抱卵雌というような生活をおくります。また、日本海産のものでは性転換後、抱卵雌と無抱卵雌を繰り返し、1年おきに産卵することになります。
そこで、これらの成長段階をどこで見分けるのか、つまりエビの雌雄の判別はどの様に行うのかについて日本海産のホッコクアカエビを例に整理してみました。
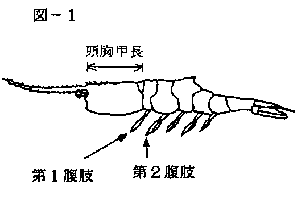
この内分肢の形状の変化を図2に示しました。腹肢の先端(葉のような形をした部分)を指でつまみ外側に開くようにすると、その葉のような形をした部分の付け根に内分肢を見ることができます。
まず、雄の場合、第1腹肢内分肢の形が1-Aまたは1-Bのようになっています。第2腹肢内分肢では2-Aまたは2-Bのような形になっています。
これが性転換個体では、第1腹肢内分肢の形が1-C、1-Dへと変化してきます。第2腹肢内分肢では2-C、2-Dの形状に変化します。
性転換後は、雄となり卵を抱いているため内分肢を見なくとも雌であることはわかります。その後、卵をふ化させた後は、すぐには産卵せずに約1年間無抱卵の状態で過ごしますが、このときの第1腹肢内分肢の形状は1-E、1-F、第2腹肢内分肢の形状は2-E、2-Fとなっています。
卵巣の成熟状態は、性転換後や無抱卵個体の場合、エビの頭(頭胸甲長)の部分の色(卵巣の色)が青緑色に変わってくることで観察することが出来ます。
機会がありましたら、第1、2腹肢内分岐による雄、雌、性転換の判別を行ってみるのも良いでしょう。肉眼では第1腹肢内分岐による判別の方が分かりやすいと思います。
ちょっとためになる話
ホッコクアカエビには、ほかのエビにはみられないほど強い甘味があります。
この甘味は、水に溶けやすいたん白質が肉質に多く含まれていて、これが強い粘りをだすことと関係しています。この粘りは他のエビと比べ非常に高く、これが味を増します。しかし、煮てしまうとこのたん白質は固まり、とろみがなくなってしまい、甘味が少なくなります。
この甘味は、水に溶けやすいたん白質が肉質に多く含まれていて、これが強い粘りをだすことと関係しています。この粘りは他のエビと比べ非常に高く、これが味を増します。しかし、煮てしまうとこのたん白質は固まり、とろみがなくなってしまい、甘味が少なくなります。