クロガシラカレイの人工受精卵の放流
クロガシラカレイは北海道沿岸の重要なカレイ資源として古くから増殖対象種として注目され、能取湖、サロマ湖、根室沿岸、留萌沿岸などで人工受精卵の放流が取り組まれています。とりわけ、能取湖では昭和20年から水産孵化場が中心となって、湖内に生息するクロガシラカレイの生態調査を行うとともに、人工受精に積極的に取り組み、資源増大を目指してきました。その技術は漁業者に受け継がれ、現在でも毎年4~5月になると採卵用親魚の捕獲から、人工受精、卵の盆付け作業、ふ化盆の設置まですべて漁業者自らの手で行われています。しかし人工受精卵の放流については、カレイ類をはじめとしてまだその効果が十分に解明されていません。最近、湖内のカレイ漁獲量の減少や漁獲個体の小型化(低年齢化?)などがあり、人工受精卵の放流はこの方法でよいのか、あるいは、人工受精卵はどれくらいのふ化率があり、どれくらいが漁業資源に戻るのかを調査して欲しいなどの疑問や要望が寄せられるようになりました。そこで網走水試では、まず人工受精卵の放流実態を調査するとともた、ふ化実験を行い、水温や塩分とふ化率との関係を求めることにしました。
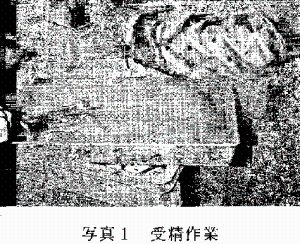
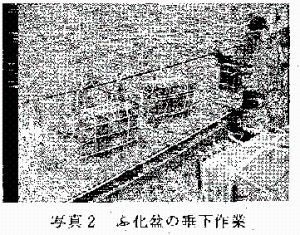
さて、実態調査ではこの垂下ロープにメモリーパック式水温塩分計(ACT-8000)を設置するとともに、ふ化盆設置後の卵の発育状況、付着卵数などを調べるために、4日に1度ずつふ化盆を回収しました。これらは現在、東京農業大学の協力を得ながら、顕微鏡観察を続けているところです。

塩分によるふ化実験では水温5度の滅菌海水を7区の塩分に設定し、水温実験と同様にして行いました(図)。それによれば、塩分0ではふ化はみられませんが、塩分5で11パーセントものふ化率がありました。最も高いふ化率は塩分20の実験区で82パーセントでした。クロガシラカレイの産卵期である4~5月の能取湖沿岸域には塩分25前後の低塩分水が分布しており、天然の状態でもふ化時期には低塩分水に覆われていると考えられます。しかし、高いふ化率とその後の生き残りの関係はまだわかっていませんので、受精卵を低塩分水の分布する場所に放流するのは危険性があります。また、ふ化実験では塩分25と30のふ化率が低くなっていますが、これは実験の際、卵の収容密度を揃えることができず、他の実験区より高密度になったことが関係していると考えられます。今後は、密度とふ化率との関係も含めて調査を進めていきます。
(網走水試漁業資源部 横山信一)
